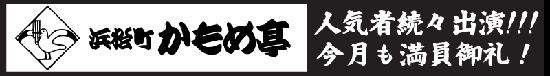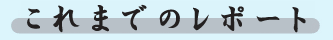
第31回かもめ亭レポート
文化放送主催の『浜松町かもめ亭』第31回公演が6月26日(金)、文化放送12階にある「メディアプラスホール」で開かれました。今回の番組は「二代目林家三平襲名記念公演」と銘打ち、いっ平改め二代目三平師匠の襲名を寿ぎ、兄である正蔵師匠をはじめ、いわば「林家だらけの会」となりました。その内容は・・・
『初天神』 林家はな平
『星野屋』 林家たけ平
『鼓ケ瀧』 林家正蔵
仲入り
襲名披露口上 林家正蔵・林家三平
ギター漫談 林家ペー
『濱野矩随』 林家三平
という出演順。

<林家はな平さん>
天神に 何を祈るや 親心
先ずは林家正蔵師匠門下の前座さん・はな平さんが「浜松町かもめ亭」初登場。
宮崎駿アニメに出てきそうな「ぬいぐるみ系キャラクター」で、高座に現れただけでお客さんを和ませる、得がたい特性を持った前座さんです。私は『寺内貫太郎一家』を再演する際は、是非、はな平さんに二代目貫太郎を演じてほしいと思うほどデスゾ。
さて、はな平さん「小児は白き糸の如し」と定番マクラを振ると“血は水より濃く、結局、親と子はソックリなのよ落語”『初天神』へ。この所、よく寄席の高座でも掛けています。おそらく柳家さん喬師匠系の演出ですが、マクラの小噺から子供の調子が大変に明るくなり、お陰で全体の調子も常に高く、噺がトントン進む印象を受けました。
また、息子を嫌々初天神へ連れて行った親父が、「子供ってのは何時までも、そんな(親の思うような)子供じゃねェ」と、こまっしゃくれた口をきく息子相手にムキになって怒る様子も、上野の西郷隆盛像がモコモコと動き出したみたいで実に楽しい。
親子の会話のほか、親父と飴屋・団子屋の遣り取りもちゃんと間が取れていて、〜この屋台主2人が何となくボヤッとしてるのも親子と好対照でオモチロイ<へwへ>〜前座さんらしからぬ安定感を発揮。親父が蜜を嘗め尽くした団子を、団子屋の蜜壷にポチャンと放り込む件まで、ホッコリと御座を固めてくれました。

<林家たけ平さん>
花が女か男が蝶か 騙し騙され 夜が更ける
続いては、正蔵師匠門下の二ツ目さん、スラッとした容姿のたけ平さんが登場。
「人間、年齢を取ると笑わなくなります。特に男性。でも、こういう所では笑いましょうね。“こんな若い奴の噺でなんか笑わねェ”なんて意地を張らないで」〜「こないだも“オレはまだ若い。カルピスは水で割らずにそのまんま飲む”って人がいました。“体に悪いですよ”ったら“オレは障害原液だ”って・・」と座を賑やかしてから、サッと“騙したつもりで騙される、それが男女の恋じゃもの落語”『星野屋』へ。
如何にも落語らしい、一寸シニカルに男女間の不信を扱った名作ですが、前半、笑いが少ないせいか意外と演者の少ないネタ。たけ平さん、敢えて挑戦!という印象です。
大商家・星野屋の旦那が妾のお花に20両の手切れを渡し、「別れてくれ」と言い出します。お花が理由を聞けば、「商いに失敗して店が潰れる。面目なさに自殺する」との答え。この時、お花がつい「旦那と私はいつも一緒じゃあありませんか、相撲見物、芝居見物、落語見物、死ぬのも一緒に」と言っちゃった事から、「ならば夜が更けてから心中に」と、乗り気でないお花を他所に心中話が進んでしまいます。
そして夜更けの吾妻橋上。ためらうお花を残して星野屋の旦那は川へドッボ〜ン!川面を覗き込むお花の耳に聞こえたのは屋根船で誰やらが歌う一中節の『紙治』。「さりとは狭いご料簡」、この歌詞を聞いてお花の気持ちは「死ぬの止〜めた」に一決します。たけ平さんは同じような展開の『辰巳の辻占』に登場する女性もですが、ノンシャランとドライな商売女を軽く演じるのが似合って可笑しい!
一人、自宅に戻ったお花を訪ねてきたのが、お花と星野屋の旦那を取り持った重吉という中年男。何かと思えば、星野屋の旦那の幽霊が枕元に現れ、「お花は一緒に死ぬと云っておきながら逃げた酷い女。これから化けて出るが、その時は、お花を世話したお前の所にも必ず寄って出るから」との事。ここは怪談噺でグッと締める所で、「序盤の別れ話・中盤の可笑しな心中・後半の怪談・終盤のどんでん返し」と『星野屋』は多彩な話術が要求される高度な落語なのでありマス。因みに私が伺った中では、怪談噺の件は六代目の春風亭柳橋先生に一長がありました。
閑話休題。「もう化けて出たのかい!」と慌てるお花。重吉に「髪を下ろして尼になれば許して旦那が浮かんでくれるかも」と唆され、隣の部屋で緑の黒髪をプッツリ切って姉さん被り。切り髪を重吉に差し出します。これを見た重吉、「浮かんでくれまさぁねぇ旦那」と屋外に声を掛けると、部屋に入ってきたのは星野屋の旦那!ここがいわばクライマックス!実は、お花の心根を計ろうと重吉の仕組んだ狂言心中で、もしお花が旦那と一緒に飛び込めば直ぐに助けて、新たに出す店を任せるつもりだった・・・そう聞いて、「そんならもう一度吾妻橋へ」とシャラッと言う辺りもたけ平さんの持ち味で可笑しうございます。このお花もさるもの達者なもので、「そんなこったろうと思ったよ。お前さんのまみえの下に光ってるのは何だい?目かい?見えない目なら代わりに銀紙でも貼っときな。その髪は鬘だよ」と姉さん被りを取ると黒髪は元のまま。この辺りのお花の威勢の良さと口の利き方、私には何故か亡くなった漫才の内海好江師匠みたいに感じられました。たけ平さんと好江師匠って顔が似てるのかな?
アッと驚いた重吉と旦那。しかし、「さっき、旦那が渡した手切れの20両は贋金。使えば直ぐに手が後ろに回る」と重吉が言うので、「どこまで人を騙しやがって」と中っ腹のお花が金を叩き返します。金を受け取ってニッコリ笑った重吉、「赤子の手を捻るようなもんでござんすねェ。お前ェのまみえの下に光ってるのはなんだ。目か?見えない目なら変わりに銀紙でも貼っておけ。贋金なんぞ使えば、星野屋の旦那が先にお縄になっちまわァ。この小判は本物だ!」。そう言われたお花が「おっかさん、本物の小判だってさ」と半泣きで云うと、今度はお花のお袋さんがニマッと笑って、「そんなこったろうと思って3枚くすねておいた」とオチが付きますが、このお袋さんのケタケタとした可笑しさも、たけ平さんの仁に適ってマス。下手すると、妙にリアルな騙しあいになって後味の悪くなるネタですが、たけ平さんの運びには「金がらみの恋なんてこんなもの」というシニカルな軽さがあって、仲々面白うございました。重畳、重畳!

<林家正蔵師匠>山の宿 三神と見る 炭火かな
仲入り前は林家正蔵師匠が『浜松町かもめ亭』3度目の登場。
「弟の襲名という事ですが、襲名後の呼び名に困って一門で会議をしました。矢張り師匠の名前ですから“三平”と呼びつけには出来ません。結局、全員一致で弟の事をこれからは“オイ!”と呼ぶ事にしました」。そう軽くジャブをかましてから、まず正蔵師自身が落語家になった頃の話へ。
自分は志ん朝師匠に憧れ、「古典落語が演りたい」と落語家になったけれど、父・先代三平師匠に入門したら古典を稽古してくれない。そのため、見習い期間が終わって前座として寄席に入った時も、同期中一人だけ古典が出来ず、帰宅して「僕は古典落語が出来ません」と悔し涙にくれていた。するとその様子を見た先代三平師答えて曰く「大丈夫、お父さんも出来ない」。こんな自虐的体験漫談で笑わせながら、先代三平師匠のおおらかな、そして輝くような可笑しさをふと偲ばせてくれました。
そこから、「落語家は言葉が大切です。昔から日本には俳句や和歌といった、短い表現で言葉の力を鍛えてくれるものがありますが・・・」と、“慢心のなる慢心は誰もする。ならぬ慢心せぬが名人”落語『鼓ケ瀧』へ。「浜松町かもめ亭」では以前、三遊亭圓窓師匠が演じられた講釈ネタですが、正蔵師匠も菊千代師匠から稽古を受け、その後、運びに色々と手を入れられ、現在は得意ネタにされています。
上方の名所・鼓ケ瀧の前に立った歌読みの法師。通りかかった樵にも励まされ、多くの歌人が詠んだ鼓ケ瀧を題材に名歌を詠もうと苦心します。正蔵師の場合、この歌法師が如何にも若々しく、また樵がはな平さんみたいにホッコリとユーモラスなのも特徴。
「伝え聞く 鼓ケ瀧に来てみれば 沢辺に咲きし蒲公英(タンポポ)の花」。蒲公英の一名を「鼓草」という所から読んだ歌に満足した法師、瀧前の松の寝方でウツラウツラして、気が付けば辺りは真っ暗。慌てて宿を探しますが道に踏み迷い、狼の遠吠えも聞こえる不安さ。前半、殆ど笑いのない、損な噺ですが、この辺り、敢えて情景描写でなく、辺りが真っ暗になる緊張感が出せるようになっております。
暗い道の奥、漸く辿り着いた一軒の山家には爺さん・婆さん・孫娘の3人が暮らしていました。正蔵師は初演当時、「この3人をアニメ『妖怪人間ベム』のベム・ベラ・ベロみたいに演出して不気味さを出したい!」と言ってましたが、その後、やや方向転換。現在は妙に不気味で可笑しなキャラ3人となっています。この3人、法師の作った歌を聞くや、次々に「手直しをしてしんぜましょうぞ、旅の御方」と言いだします。
一度はムッとしかけた法師ですが、「面白い」と「手直し」を受けます。すると先ず爺が「“伝え聞く”では当たり前過ぎよう。“音に聞く”と直されよ、旅の御方」。続いて婆が「“鼓ケ瀧に来てみれば”では面白くない。“鼓ケ瀧をうち見れば”とすれば、“うち見る”と“鼓を打つ”が縁語になって面白かろう、旅の御方」。最後に孫娘までが「“沢辺に咲きし”ではのうて“川辺に咲きし”と直されよ、旅の御方」と続けます。この間、直される度に法師(実は西行法師の若き日という設定)が驚き、「直されて素晴らしい歌になったものの、自分が詠んだのは“鼓ケ瀧”と“蒲公英の花”しか無の凝っていない」と悲嘆にくれ、歌詠みとして打ちのめされて行く辺り、正蔵師の持って生まれた愛嬌と、3人の「旅の御方」という声音の繰り返しの面白さで、ドッドと笑いが起きるのは今回も寄席も違いがありません。
悲嘆にくれた西行法師が樵に起こされてフッと気づけば、そこは瀧の前。
樵曰く「ここで歌を詠んだ者はみな同じ夢を見る。しかし、手直しを受けたのは偉い。大抵は“素人に何が分かる”と怒った途端に目が覚めてしまう。あんたは良い歌詠みになりますぞ。オラが思うに、山家の3人は“和歌三神”が姿を変えて現れたものではないかな」。この言葉に西行法師、「夢とはいえ、和歌三神に数々の御無礼。罰が当たりはせぬか」と悔いると、再び樵曰く「ここは鼓ケ瀧、撥は当たらねェだ」とオチがつくまで、瀧の音も爽やかに響く、名人誕生外伝として楽しませて戴きました。

<二代目林家三平襲名口上>
鶯の 子は子なりけり 枝に鳴く
仲入り後は「二代目林家三平襲名披露口上」から。正蔵師匠と、いっ平改め二代目林家三平師匠、兄弟2人だけのシンプルな口上です。
正蔵師が先ず「政界では“世襲制は如何なものか?”と議論されている真っ最中の襲名で、目指すは鳩山兄弟です」と空気を和ませてから、先代三平師匠が二代目三平師匠を余り溺愛するので兄乍ら一寸嫉妬して「どうしてそんなに可愛がるんだ?」と訊いたら、先代が「45歳の時の子供で、長く一緒にいてやれない分、可愛がってやるんだ」と答えた言葉に納得した話へ。様々なエピソードを色々な方からうかがう旅に、「先代三平師匠という方は親として師匠として実に優れた方だった」と私は感心しております。
さらに正蔵師は続けて、「兄が言うのも何ですが、弟は苦労人です。9歳で父と別れ、入門したこん平師匠も現在は闘病中。義理の兄だった小朝師匠もあんな事になって・・・当人は不安だと思います。しかし、父は兄弟それぞれに才能を分けてくれました。弟には明るさがあります。高座に出できた時、私が60ワットなら、弟は120ワットの明るさがあります。また父同様、可笑しさの中にペーソスも持っています。オフクロからは生真面目さと頑固さを、危険な魅力は泰葉から受け継ぎました(客席大爆笑)。いつかは手を組んで(鳩山兄弟のように)連立を・・・私も“頼もしいライバルの誕生”と感じています」と口上を納めました。親代わりの口上というだけでなく、三平師匠の襲名で、正蔵師もまた噺家さんとして成長された、という印象を私は受けましたね。
続いて、三平師匠も「弟の(鳩山)邦夫でございます」と軽く笑わせてから〜一寸分かりにくかったけど(苦笑)〜、「“いっ平”という三文字の名前でなく、“正蔵”のように二文字の名前になりたかったんです。もし、“三平”で上手く行かなかったら、別の二文字名前に改名を致します。二代目“泰葉”を襲名します」と爆笑させました。
最後に正蔵師匠の音頭で、目出度く三本締めを執り行い、披露口上を納めました。

<林家ペー師匠>
ミュージシャン マイケル・ジャクソンより 林家ペーの方が好き!(字余り)
口上に続いては先代三平師匠の高弟ペー師匠が永久不滅の真っピンク衣装で登場!
今回の三平襲名披露興行で久しぶりに寄席の高座にも立たれましたが、今回はかもめ亭松本尚久プロデューサーの頼みで、グレート義太夫氏から貰ったというギターを抱えて、涙の出るほど懐かしい「ギター漫談」を披露という大おまけ付き!
「いっ平の三平襲名は感慨一入です。こんなに小さい頃から(殆ど足首サイズ)知ってましたから。小さいって、寝てましたからね」と、二代目三平師に触れたかと思うと、この日の朝亡くなったマイケル・ジャクソンに触れて、「ボクの尊敬する50人のうちの1人です。同じ“ミュージッシャン”として、彼の葬儀に参列しようと思いましたけど、ギャラ3万円の仕事が入ったので、そっちを選びました」とか、「最近の芸能人はジャニーズとか、みんな本名ですが“林家ペー”は本名じゃありません。本名は妻夫木聡といいます」(これって先代三平師匠の「今日は加山雄三です」を継承したギャグなんでしょうか?)、「ギター漫談を演れって言われましたけど、それって久しぶりです。マッカーサーが帰国して以来かな?」といった具合に、誰よりも下らなくて、支離滅裂で、絶対に可笑しい「ペー世界」突入! モハメド・アリとアントニオ猪木の決戦のネタなど、懐かしネタ満載で、オチも昔ながらの『水戸黄門』の東野英次郎さんの真似!ときて、寄席ファンには涙のチョチョ切れるほど嬉しい高座に大満足!

<林家三平師匠>
先代の背中は背中 真っ直ぐな道で寂しくても我が道は我が道
最後は本日の主役、『浜松町かもめ亭』初登場でトリになった二代目三平師匠。
「ペー師匠って会う度に同じギャグ言うんですもん。“君は品が良くて相がいい。合わせて貧相”こればっかり」と笑わせてから、2008年9月12日・東京ドームでの始球式で始まったプレイベントから寄席での襲名披露興行の話を次々とくり広げます。中では矢張り、相撲の貴乃花親方に「兄弟仲良くして下さいね」と言われて唖然とした!って話が最高に可笑しうございますゾ。そして、昨年、新橋演舞場で演じた『勧進帳』の話、立川談志家元が根岸の先代三平師匠宅を訪ねて来たのを、マネージャーさんが「バンダナを巻いた変質者が家の前にいます」と間違えた話など、次々に繰り出しますが、こうしたマクラの間は先代三平師匠のように客席に語りかけていました。
そこから一転、「襲名披露興行中は『紀州』など地噺ばかりでしたが、今日は本格的な古典を」と“名人に二代あり。藍より出でて藍より青く”落語『濱野矩随』へ。真打昇進の際、元義兄・小朝師に稽古を受けた噺ですが、今回は前もって三平師匠自身から松本プロデューサーに「『濱野』を演ります!」と連絡があった決意の一席です。
江戸の宝暦年間、腰元彫りの名人・濱野矩安は酒好きが祟って早逝。財産は酒で使い果たし、残った妻と息子は大変な貧乏。しかも、彫り師として後を継いだ息子・矩随は親父と大違いで、何を彫っても頓珍漢のヘボ。親父の作品を一手に扱っていた若狭屋だけが、先代の恩義に報いて、矩随の駄作・失敗作を金一分で買い取ってくれるだけ。
所がある日、矩随が「三本足の馬」という大失敗作を持ち込んだ所、たまたま期限が悪く酒も入っていた若狭屋が激怒して、「生きてお父さんの箔を剥がすり、死んじまえ!」と矩随を罵倒します。
「地噺」ではないけれど、説明文の多い展開ですが、若狭屋が芝居っ気の濃い描き方、一方、若い矩随は果敢なく頼りなげ、という対照は明確。矩随の頼りなげな所は、或る意味、「爆笑王」の二代目を継いだ三平師匠と重なり、真打昇進時には感じられなかった切ないリアリティを醸し出します。今回の襲名興行中、「世襲襲名」に対してシニカルな内容の『真夜中の襲名』(終盤にちゃんと「世襲襲名者」への救いが用意されていますけど)を三遊亭白鳥師匠が演じて観客を驚かせたエピソードを思い出しました。
若狭屋の言葉に矩随は死を決意して悄然と帰宅。若狭屋がくれた手切れの金を差し出し、「明日から友達と伊勢詣に行くから、暫くはこれで食いつないで下さい」と母に告げますが、そこは親子。「騙す事は出来ないよ」と若狭屋の罵倒と死の決意を聞き出します。この母の「騙すことは出来ないよ」に不思議な色香があったのは出色でした。
しかし、母は矩随を慰める訳ではなく、「いっそのこと死んでおくれ」と突き放し、「その代わり、この世の名残として観音様を私に彫っておくれ」と言いつけます。
元より親孝行の矩随は一心不乱。七日七晩、不眠不休で観音様を彫り続けます。眠気が差すと隣の部屋から母の神仏に祈る声が聞こえてくる、という辺りは小朝師匠の演出でしょうか、非常にドラマティックでした。
矩随の彫り上げた観音様を見た母は、その出来栄えに「おっ母さんの最期の頼みだ。これを持って若狭屋さんへ行き、20両で売ってきておくれ」と命じ、水盃をして送り出します。矩随は「自分の彫った品にそんな値のつく筈がない」と思いながらも若狭屋へ。「こないだは酔っていて悪い事をした。神さんにも“あんな正直な事を云っちゃいけないよ”と叱られたよ」と謝った若狭屋は、矩随の差し出した観音様を手に取ります。
「一寸お高いのですが20両」と、値段を矩随から聞いても、「矩安先生の作品がまだあったのか!これなら50両でも買うよ」と若狭屋は絶賛します。この時、若狭屋の言葉を聞いた矩随が「有難うございます!」と叫んで平伏すのですが、今回の三平師匠の高座ではここが白眉!同時に「『濱野矩随』という噺は、この“有難うございました”を言えるかどうかが魅力を左右するネタなんだ」と私は初めて感じました。実はこれまでにも何人かの方の『濱野矩随』を伺いましたが、正直、「この噺、何処に共感すればいいの?」と私は思っていたのでありマス。「“きっと誰かが見ていてくれる、待っていてくれる”と信じて自分の道を行くしかない」という、日本人が芸事・職事に寄せてきた思いが三平師匠の「有難うございました」にはありました。
その後、母と水盃をして別れた事の意味を若狭屋に言われて悟った矩随が扱けつ転びつ自宅へ戻り、自害していた母の亡骸の前で怒るように泣く件も、真情溢れる場面でした。「明鏡止水の名人芸」等とは申しませんが、高座を見ながら「先代三平師匠は、確かに兄弟それぞれに才能を分け与えてくれた」と、私が感激していたのは事実。そこから、矩随が親勝りの名人となって、かつての失敗作まで数百両で売れる、という笑いでしめくくり、「『濱野』を演ります」という気概を示してくれまた。
という訳で、第31回『浜松町かもめ亭〜二代目林家三平襲名記念公演』。似た者親子同士の『初天神』に始まり、騙しあいの『星野屋』をちょいと色変わりの彩りに、慢心を戒め初心の大切さを描く『鼓ケ瀧』。兄が弟を思う襲名披露口上。兄弟を暖かく見守るペー師匠の漫談を挟み、名人親子誕生の『濱野矩随』と、先代三平師を真似ず受け継ぐ一門の気概を示して、お客様にはお楽しみを戴けた次第・・・・・という訳で、次回、7月のかもめ亭も、御多数ご来場あらん事を。
高座講釈:石井徹也(放送作家)
今回の高座は、近日、落語音源ダウンロードサイト『落語の蔵』で配信予定です。どうぞご期待下さい。
|