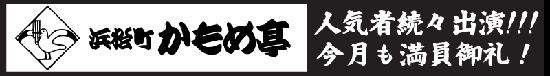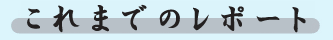
第37回かもめ亭レポート
文化放送主催『浜松町かもめ亭』第37回公演が12月5日(土)、文化放送12階の「メディアプラスホール」で開かれました。
「立川志遊真打昇進披露」と題した今回の番組は
『小町』 立川春太
『鮫講釈』 立川談春
『崇徳院』 立川龍志
仲入り
立川志遊真打昇進披露口上
『ねずみ』 立川志遊
といった内容。かもめ亭恒例の「立川流一門会」の変形開催となっておりマス。

<立川春太さん>
優男 負けるな先輩 ここにあり
今回の開口一番は立川談春門下の前座さん・春太さんが登場。ヒョロッとした、三代目桂三木助師匠をやさ男にしたみたいなタイプ。私にとっては大学の落語研究会の後輩初の立川流入門者でもあります。お約束のマクラを振ると“百夜通いし恋路の闇 果ては道灌となりにけるかも落語”『小町』へ。お馴染み『道灌』の序盤部分ですが、最近は寄席でも余り聞かなくなりました。百人一首の衰退と共に、小野小町と深草少将の恋ってものが世間で知られなくなったからかな。
春太さん、如何にも軽い調子ですが、隠居さんに向かって悪口をいい、「普段からいってるから口癖になってます」と平然としたり、「(小野)小町っちゃん、自転車屋の娘」「(十二単を)ドテラの重ね着」などとうそぶく熊さんが、若く飄々とした職人に聞こえるのはなかなか結構。隠居が「羊羹を薄く切るてぇと、こういう男(熊さん)は料簡を見るからな」とボヤくのが分かる気がす可笑しさあり。トントンスイスイと運んでの御座固め、ご苦労様。

<立川談春師匠>
船底を ガリガリ齧らない 談春の鮫
続いては、春太さんの師匠、年末or年始かもめ亭恒例出演の立川談春師匠が登場。
「真打昇進披露といっても(つい最近あった)立川雲水の真打昇進披露は“演れるもんなら演ってみろ”といった内容で立川流ってのは異空間なんだな〜。」「出て、いきなり(言葉を)“噛む”というのは(我ながら)珍しい。開演が2時半という段階で、今日は芸を期待しちゃいけない」「新宿末廣亭の四派合同の余一会に出て、“何か名人らしい一席を”と思ったら、柳亭市馬さんに“寄席というのは寝ていても演れる落語をすところだ”と言われたけど、落語家って何処で命懸けの芸を演るんだ!」と、マジなのか、怒ってるのか分からないような、でも実は本題に繋がるマクラ(笑)から、「船の旅は悲しい、戸田川、平和島」と競艇ファンらしい言葉を繋いで“パンパン叩くのは朝鮮半島の洗濯と講釈師くらいなもんだ落語”『鮫講釈』へ。
元々は上方落語の『兵庫渡海鱶魅入』、略して『兵庫船』という旅ネタ。東京でも先代桂小南師匠がよく演ってらっしゃいましたし、講釈好きの立川談志家元や故・三遊亭圓楽師匠も若い頃から得意にしておりましたが、いつの間にか題名が変わって『鮫講釈』の方が通りがよくなっちたようですね。
江戸っ子二人を乗せた海路の渡し船が海の真ん中でぴたりと止まる。船のまわりを鮫の背鰭・尾鰭がグルグルと回りだします。海中の鮫連中が「船中旅人の誰か一人に魅入れたので船がピタリと停まった」と説明しながらも、船頭は「こりゃ鮫の大寄せだ」と暢気なもの。このまま、魅入れられた者が自ら海に入らないと、船がひっくり返されて全員鮫の餌食とは厄介な話ですが、「おれたちゃ鮫と顔なじみだから皆殺しになっても、船頭だけと無傷」と船頭だけが甚だ無責任なのは、『ロード・ジム』の日本版みたいなものでありマス。旅人たちが手持ちの品を海に流すと、一人だけ、グルグルッと品物が海に飲み込まれたのが旅の講釈師。
覚悟を決めながらも、「芸人は業が深い」と講釈師、「この世の名残に最後の一席」と講釈を始めます。「待ってました!」「鮫も待ってる!」というギャグは談志家元系の味わい。確か、上方には無かったなぁ。
一瀉千里、疾風怒濤に読み始めた講釈は『居候講釈(五目講釈)』などと同様、何でもござれ。いわば「講釈チャンチャカチャン」。一度だけ、今の桂文字助師匠が『三河戦記』の一段を丸っこかし語ったので驚いたことがありましたが、今回の談春師は『忠臣二度目の清書』に始まり、張り扇をパンパン叩きながら、『三河戦記・内藤三左衛門』『大岡政談』『次郎長伝』『源平盛衰記・那須与一扇の的』『義士銘々伝・堀部安兵衛高田馬場』『源平盛衰記・一の谷青葉の笛』『義経記』『先代萩』『桜田門外の雪』『お富与三郎』『垂乳根』etc,etc.と、講釈・落語・浪曲ネタを取り混ぜてのオンパレードは家元写しの面白さ。最近、『五目講釈』を演る若手が増えてきましたが、こういう「水道講釈」的なリズムの楽しさは矢張り家元直系だけのものですね。
この講釈が読まれるうち、何故か船が動き出して、船中は大喜び。一方、収まらないのが海中の鮫連中。ここで談春師が鮫の泳ぐ形するのですが、妙にかわいくて可笑しいのよ(笑)。一番笑っちゃいました。「パンパン叩くからカマボコやかと思った」のオチまで快調に読み通して、龍志師匠に高座を譲りました。

<立川龍志師匠>
家元の 甘酸っぱさを 今日ぞ知る
という訳で、立川流屈指の人格者として知られるベテラン・立川龍志師匠が『浜松町かもめ亭』に初登場。二ツ目の金魚家錦魚時代から、人情噺で先代中村勘三郎丈を泣かせたこともあるくらい、巧さでは評判の師匠で、かもめ亭お馴染みの立川こはるさんや、談春師匠も敬愛している大先輩です。
「寄席に来る人は良い人が多いのですが、まともな人が少ない」と笑わせてから、半年前に脚の手術を受けた話へ。「手術をしたのが前座の医者で」と、「患者一人殺して一人前の医者になる」という「藪医者の治療の恐ろしさ」をひとくさり。実施意には怖い話なのですが、淡々と喋られるので、クスクスッと可笑しいのは流石。
そこから“瀬をはやみ いわにせかるる 恋煩い落語”『崇徳院』へ。戦後の東京落語界では三代目桂三木助師匠の十八番であり、今も、ちょっとそっぽの良い若手(春太さんみたいな人ね)が必ずといってよいほど一度は口演するネタです。
若旦那が謎の病気で、その原因が分からない。「出入りの熊さんになら喋る」というのてせ呼ばれた熊さん、「どうしても言わねぇようなら石ィ抱かせて」と拷問まがいの
手口を口にしますが、この熊さんが何となく談志家元に似て聞こえるのが妙。
とはいえ、「病の家元」みたいにやせ衰えた若旦那の有様に、手を尽くして原因を聞きだします。原因は清水の観音様で出会った名も知らぬ美令嬢。「せをはやみ いわにせかるる たきかわの」と崇徳上皇の上の句だけが書かれた短冊を手渡され、それきり分かれてしまった彼女への恋煩い。これが不思議といえば不思議で、崇徳上皇という方は歴史研究者によっては「日本歴史上最大の魔王」と呼ぶ人もいるくらいの「祟り主」なのですが、落語だと恋の手引きもするのですねェ。
親旦那に原因を告げるや、「その娘さんを探して来たら、今、熊さんの住んでいる三軒長屋をやる!」と言われて熊さんは唯一の手掛かりである「せをはやみ いわにせかるる たきかわの」の歌を叫びながら、人の集まる江戸中の髪結床と湯屋を探し回り、湯のぼせと剃刀負けでヘロヘロになってしまいます。
最終的に熊さんは運良く、これも恋煩いに陥っていたお嬢さん方の探索者(町内の頭)と巡り合い二人で「オレの御店に来い」と取っ組み合いをするうち、髪結床の鏡を割り、「割れても末に買わんとぞ思う」と崇徳院の御歌もじりのオチに至るのでありマス。
若旦那から原因を聞きだす件、熊さんが江戸中を「せおはやみ」と叫んで歩く件と、笑い所の多い噺ですから、クドく演じようと思えば演じられるのですが、龍志師はギャグを見事なまでに押しません。本当に、粋な江戸落語らしい展開でスイスイと噺を進めて行きますから、馬鹿馬鹿しい中に、若旦那の恋煩いの甘酸っぱさが漂います。
そういえば、談志家元が実は「『若草物語』みたいな、甘い、可愛らしい映画が一番好き!」と著書で語られていますが、そういうロマンティシズムが立川流の噺家さんにはどこか伝わっているんですね。

<志遊真打昇進披露口上>
取り敢えず 異空間には ならず済み
仲入リ後はまず、「立川志遊真打昇進披露口上」。談春師のマクラのように異空間というか、破天荒な口上になると思いのほか、談春師は志遊師匠の経歴を紹介しながら、「私のようにバクチにウツツを抜かさず、龍志師匠のようにオンナにウツツを抜かさずながら、結核で闘病一年。いまどき結核を発病するなんて珍しい人で」と、まあ近年の口上では普通の可笑しさ。続く龍志師も立川流屈指の人格者らしく、「闘病などで真打昇進が遅くなったからってどうってことはありません。病理学的に言いますと、結核は沢山の人に移した方が勝ちです。志遊さんは大変に賢くて真面目で失礼の無い人で、万引きなんかもしませし、盗撮もしません。覚醒剤は金が無いから買えないし、いわば小沢・鳩山の民主党のように頭脳明晰で、大変に行儀の良い芸ですが、惜しいことに落語が明晰でないという」と淡々たる爆笑口上から、三本締めでの御祝いとなりました。

<立川志遊師匠>
病み上がり けれども芸は右肩上がり
主任はもちろん志遊師匠。「六月六日付けで真打に昇進しまして、今日十二月五日が真打披露の一番最後になります。今日はちょっとカクカクしてます」と、『オーメン』の少年みたいな日に真打昇進をした話から、「今日は色々と学びました。“口上は人選が大切”」とジャブをかまし、「真打昇進して周囲が“師匠”と呼んでくれるようになりましたが、入院していた病院で落語会をしたときは“立川さんどうぞ”と言われてしまいました」とマクラを繋げて、“魂を込めれば木っ端でも動き出すというのは奇蹟か単なる妄想か落語”『ねずみ』へと入りました。
『崇徳院』同様、これも三代目桂三木助師匠が浪曲ネタから落語化した十八番物。以後、入船亭扇橋師匠、七代目春風亭柳橋師匠といった三木助一門や、先代春風亭柳朝師匠、昨年亡くなった三遊亭圓楽師匠たちから中堅・若手の師匠たちに受け継がれ、寄席の主任で聞くことも多いネタてす。最近も三代目三木助師には孫弟子に当たる八代目春風亭柳橋師匠が新宿末廣亭での真打披露興行の初日に演じていらっしゃいました。
龍志師の仰られた通り、確かに真面目で失礼の無い、やや老成した雰囲気の口調で杜の都・仙台の入り口での宿の客引きの少年と旅人の出会いを語りだします。この旅人は名人・左甚五郎ですが志遊師は如何にも職認体の雰囲気を醸し出しているのが特色。少年に指図された通り、甚五郎が仙台城下一番の小さくて汚い宿「ねずみ屋」にたどり着くと、出迎えた主は腰が抜けて立てない有り様。川の水で足を洗うにも履き替えの下駄が片方しかなく、「ピョンピョンと飛んでください」と主に言われ、「屋号をねずみ屋からうさぎ屋に変えた方がよい」と苦笑する表情はなかなか堂に入ったもの。
ここで甚五郎は宿の主から、★自分たち親子は元々前にある仙台一大きな旅『虎屋』の持ち主だった。★三年前の七夕の晩、客同士の県下に巻き込まれて主の腰が抜けてしまった。★その後、後妻と番頭が結託して親子を『虎屋』から追い出した。そのため、元は『虎屋』の物置だった場所を『ねずみ屋』にして宿を細々と始めた。★元は物置でねずみが暮らしていたのを乗っ取ったようなものだから、ねずみに遠慮して『ねずみ屋』と屋号をつけた。といった話を聞きだします。
志遊師はひとつのセリフに対する相手役のリアクション数が普通の噺家さんより多いのか特徴かな。また、主の述懐口調は講釈的で、甚五郎のリアクションは人情噺的、という二つの口調がクロスする辺りはユニークですね。
この親子のために甚五郎は精魂込めて一匹のねずみを彫り上げると、「坊やいいかい、今は辛いだろう、大変だろうが、阿父っつぉんを助けておやり。今にきっと良いことがある」と述べて立ち去ります。その甚五郎を涙で見送る宿の親子・・・そこからカットパックして、近隣の田舎者二人が『ねずみ屋』の前に立つという演出は初耳。ここで田舎者二人の目の前で、木から彫ったねずみが動き出すという、名人の奇蹟が起きる訳ですが、二人の田舎者のうち二人目が甚五郎ねずみに噛まれる、ってのも独特です。
このねずみが評判となって『ねずみ屋』は大繁盛、反対に『虎屋』は客が激減してつぶれる寸前。そこで甚五郎に恨みを持つ仙台随一の彫物師・飯田丹下に頼んで、虎の彫り物を彫ってもらい、虎屋の屋根に据えると(これも普通の演出だと二回の手すりのとこですけど)ねずみがピタッと動かなくなる。
その報せを聞いて甚五郎が再び仙台に乗り込み、動かなくなったねずみに語りかけると、ねずみが「ありゃあ虎ですか!あたしは猫かと思った」というオチになります。
ストーリーに起伏の多い反面、ややもすると「作りすぎ」になりやすいこのネタですが、志遊師の“失礼の無い口調”が恬淡とした落語らしさを生み出してくれました。
という訳で、第37回『浜松町かもめ亭』。「恋煩いで死んだ深草の少将」を語った立川春太さんの『小町』に始まり、鮫の魅入れを人生最後の一席に掛けた思いが払った立川談春師の『鮫講釈』、立川龍志師が若旦那恋煩いの結実を粋に描いた『崇徳院』、左甚五郎の精魂がも木製のねずみに命を与えた『ねずみ』と、真打昇進披露らしい「人の思いの深さ」でお客様にタップリとお楽しみを戴けた次第・・・・・という訳で、次回のかもめ亭も、御多数ご来場あらん事を。
高座講釈:石井徹也(放送作家)
|