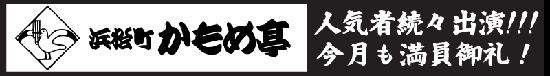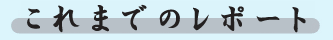
第52回かもめ亭 2012年1月レポート
文化放送主催第52回『浜松町かもめ亭』が1月31日(火)、文化放送12階の「メディアプラスホール」で開かれました。
今回の番組は「五周年記念特別公演」と命名された三ケ月連続公演の第一回目です!
番組は
『平林』 立川こはる
『片棒』 金原亭馬治
『抜け雀』 桃月庵白酒
仲入り
『御血脈』 春風亭百栄
『干物箱』 柳家小満ん
といった内容。

<立川こはるさん>
開口一番は『かもめ亭』の娘看板・立川談春師匠門下の前座・こはるさん。「とうとう大台、私も三十歳。かもめ亭は五周年。私も五年間、前座です」と挨拶して(女性の年齢公表は噺家さんでも珍しい)、直ぐに“忘却とはは天が人間に与えたもうた最大の恩恵である落語”『平林』」へ。
丁稚の定吉が「平林さん」へ宛てた手紙を届けようとしますが、親代々の無筆で、しかも酷い健忘症のため、宛名を忘れて四苦八苦するという展開。こはるさんの主人公・定吉は御当人そのまま、責任感が強く、何とかして「ひらばやし」という読み方を思い出そうとするのが特徴。そのため、あちこちで訊いてみますが、みんな知ったかぶりで「字には色気が必要」等と言いだすおかしな人ばかり。ついに「定吉も「(教えてくれた)おじいさんは本当にこの読み方で良いと思っているのか?」「そんな大変な(名前の)人じゃないよ」と疑問を呈するに至るというのが可笑しうございました。
という雰囲気で、御座固め、御苦労さまです。

<金原亭馬治さん>
続いては、既に何度か『かもめ亭』に出演している金原馬生師匠門下の二ツ目・金原亭馬治さん。「初体験をしまして」というから何かと思ったら、胃カメラ。一寸した行き違いから、二日連続で胃カメラによる検査を受けるハメになった顛末を面白く語ると“親に似た息子は三人のうち誰?落語”『片棒』へ。
最近は柳家さん喬師匠か、馬治さんが御稽古をして戴いたという春風亭一朝師匠の演出が多いのですが、以前は柳家小ゑん師匠が独特のギャグで沸かせていたネタです(25年も前ですけれど)。ケチな大旦那が大事な身代を守るため、自分の葬式をどう執り行うか、その方法で三人息子の中から相続人を選ぼうとする一席。今の時代では、相続法 律上、成田太噺ですが、兎に角、左所の二人は「金を湯水のように使う豪勢な葬式」「祭のような破天荒な葬式」と大旦那を呆れ返らせます。特に息子の一人がいう「一遍しか死ねないんだ。折角死ぬんだから、葬式は盛大に」というセリフは可笑しさの中に妙な実感があります。また、大旦那そっくりの形をした山車の人形が動く形が独特で、大抵は前後と左右に動くのですが、馬治さんのは真横に傾くのが奇妙で可笑しい。最後に登場する三番目の息子が一転して、金を徹頭徹尾ケチッた葬式を提案して、「死して屍晒す者無し」と言いだす辺り、『大江戸捜査網』とは懐かしいギャグでありました。

<桃月庵白酒師匠>
仲入り前は「ふくよかな野獣」というべき桃月庵白酒師匠の登場。容貌に関するマクラから「この後、登場する百栄さんは“残り物、余っちゃいないから”と言われても仕方ない容貌でと、相変わらず情け無用の強烈なジャブをかましてから“古今亭の爆笑演目は白酒師匠によって守られる落語”『抜け雀』へ。
寄席の主任や落語会でも、よく掛けている演目ですが、今回は初めて聞くセリフや、地の文だった所が会話になっているなど、新たな改訂が施されたヴァージョンアップ版。配信されるでしょうから、敢えて内容は書きません。「聞いた者勝ち」です。
兎に角、主人公の宿屋亭主とかみさんのキャラクターの可笑しさ、夫婦関係、人物造型の素晴らしさは驚くばかり。そこに、芸術家的傲慢を味付けにしたシニカルな絵師親子が絡む遣り取りの精妙至極な面白さ、絵師親子のシニカルさが噺に師匠である五街道雲助師風の陰影を醸し出す辺り、正に抱腹絶倒&出来栄え十二分で、「ここが良い、ここが面白い」と書ききれません。五代目志ん生師匠以降、『火焔太鼓』と『抜け雀』に関しては「可笑しさでは白酒師匠に敵う者なし」という出来が更にグレードアップしています。昨年後半、一寸休火山状態でしたが、今年に入って、また噴火したみたい(「落語界の桜島」と言いたい体型だし)。初めて聞いたギャグでいうと「(衝立を持たせて)携帯は電源を切れ」「(鳥籠が)網にしか見えません。雀が焼き鳥になりまんか」には大爆笑です。

<春風亭百栄師匠>
仲入り後は「“残り物、余っちゃいないから”と言われても仕方ない容貌」の持ち主・春風亭百栄師匠の登場。「回復力が弱まってきました」と老人みた
いな話から、このところ、良くふっている「ヒポクラデスの言葉」というマクラへ。「原因も無いのによく倒れる人は、死ぬかもしれない」なんて本当にヒポクラテスが言ったのかどうかは知りませんが(私はヒポクラデスと聞くと伊藤蘭の顔が浮かんでしまう世代)、更に「昔は数人の医師が執刀を連携する公開手術があったそうで、“お次の先生がまだ(手術室に)入っていないそうで、つなぎを(寄席じゃあるまいし)”なんてラリフを百栄師匠にマジめな顔で言われると、物凄く可笑しい。大爆笑です。
そこから釈迦の話に移り、「お釈迦様は八万四千の法問を説いたそうです」という話をへて、“地獄の沙汰も血脈の御印次第落語”『お血脈』へ。
最近は寄席だと前半の『仏教伝来』や『義光寺の由来』で切ってしまう事も多い演目ですが、百栄師匠は大抵、ちゃんと最後まで演じられます。『かもめ亭』では、柳家小せん師匠が二ツ目時代に見事な口演を聞かせてくれました。信州・義光寺に納められた「御血脈の御印」の法力で、悪人も善人になってしまうため、地獄が過疎化してしまう。そこで閻魔大王の命を受けた石川五右衛門が「御血脈の御印」を盗みに入る、という展開。今回の百栄師匠は割と抑え気味の口調でサラサラと噺を運んでゆきますが、飄々とした分奇異がまた独特で、騒がしくなりがちなこの噺を楽しませてくれました。終盤、五右衛門が出てきてから、「ダーッ!」と見得をする辺りも、普段は割とクサ目に、激しく演じるのですが、今回はスッとしています。トリ前を意識されたのかな。とすれば、噺家さんとしては真に優れた心がけですぞ。

<柳家小満ん師匠>
本日のトリは、現在絶好調続きのベテラン、柳家小満ん師匠の登場。「遊びの本場、吉原のお噺を」と振られると、「吉原も、明治に入ると日本堤の土手がまずなくなり、衣紋坂もなくなりまして、乗り物も駕籠から人力俥へと替ります」とマクラを続けて、“猫の恋、猫の鳴き真似したりけり落語”『干物箱』へ。小満ん師匠の最初の師・八代目桂文楽師匠の十八番です。
親旦那から二階に軟禁状態にされている若旦那が、何とか吉原の花魁の所へ行こうと、時分の声色が得意な貸本屋の善公を身代わりに二階へ送り込むが・・・というお噺。「綱っ引き」「五十間」といった用語も小満ん師匠ならではの風趣が漂います。物凄い貧乏くらしで「忍者屋敷だね」と若旦那に言われるボロ家の主。「借金取りには犬をけしかける」という了見ですから、「大名(格子)の表に、唐子人形の(模様の)裏地の御召し羽織」につられて、若旦那の計略に加担。二階に上がったまでは良かったものの、そこで発見した花魁からの手紙に時分の悪口が次々と書かれているのを見て騒ぎだし、遂に親旦那に露見するという・・・この親旦那が二階の騒ぎに「何をガタガタしてんだい!」という調子は正に八代目文楽師匠そのもので、何ともなつかしく、また粋な興を感じさせて戴いた一席でした。
という訳で第52回浜松町かもめ亭〜五周年記念特別公演」の第一ケ月目は無事、お客様に御堪能を戴けた次第・・・・・次回のかもめ亭も、何卒御多数ご来場あらん事を。
高座講釈:石井徹也(放送作家)
|