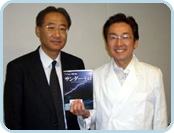キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。3連休だよね。みんな、どっか行っちゃってるかなぁ。今日のテーマは雷。なぜこの季節に雷なのか?夏になるとゲリラ豪雨という言葉を聞くと思うんだけれど、ここ何年か限られた地域ですごい雨が降ったり、雷が落ちたりしてる。雷って、僕らが思ってる以上にけっこう怖いものだということなんです。お知らせの後、サイコーの登場です。
今週のサイコーは、株式会社サンコーシヤの伊藤眞義さんです。こんばんは。

- こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。伊藤さんは、ダイヤモンド社から『サンダーテロ』という本を出版されてます。サンダーテロって怖い言葉ですけれど、直訳すると“雷の恐怖”ということですよね。雷の対策を考えるのがお仕事?

- はい、そうです。
この本は出たばかりですよね。オールカラーで、雷に関するいろいろな知識が読んでいるうちに分かってしまうという非常に読みやすい本ですね。ちびっ子にもたぶん読めると思うんですが、巻末の伊藤さんの紹介を見たら、サンダーバード大学卒業!

- ハハハハ。
何ですか、サンダーバード大学って?

- アメリカにある大学院ですが(笑)。
やっぱり雷とかを教えているわけですか?

- そういうことは関係ありません。
サンダーつながり。

- サンダーつながりですねぇ。偶然でございますけれど。
サンダーにはずっと興味があるんですか?

- そうですね。
サンダーバード大学って何を習う大学ですか?

- 経営学ですね。ビジネススクールです。
直訳すると“雷鳥大学”。僕は富山の出身なので、富山県の鳥はサンダーバード、雷鳥なんです。

- そうですね。
もう冬になって来ましたが、雷って夏場のものですよね。

- そうですね。太平洋側では夏場に多く発生しますけれども…。
東京では。

- はい。日本海側ですと、冬に多く発生するんです。
冬に多いんですか?

- はい。
冬に雷が落ちてくるんですか!?

- そうです。
聞いたことないですよ。

- そうですか。富山では“鰤起し(ブリオコシ)”と言いまして、富山湾にブリが入ってくる頃に、雷がよく発生するんです。
寒ブリの季節に?

- ええ。
えぇ〜!

- これからシーズンだと思います。
分かりました。で、雷はイメージからすると当たったら怖いし痛いし、場合によっては死んじゃうし…。空から電気が落ちてくるようなものですよねぇ。何で空から自然に電気が発生して落ちてくるか? まず、そこから伺いたいんですが。

- なるほど。雷が発生するにはある一定の条件があります。夏場ですと、夏の太陽で地表や海面が温められて、その湿った空気がずーっと上空に上がっていく。それを上昇気流と言って、どんどんどんどん上がっていくわけです。これで入道雲とか積乱雲ができる。
はい。

- 夏場だとそういう現象が起きるのですが、冬場でも先ほど申しましたように、日本海側で寒冷前線、寒気団が入ってきますと、冷たい空気は重いから日本海側の温かい湿った空気を上に押し上げる。そういうことによって上昇気流が起きるわけです。
ええ。

- その上昇気流の中でどういうことが起きているかというと、湿った空気だからどんどん上がって雲になる。水蒸気が水滴になり、どんどん上空に行くと氷点下の気温になりますから、マイナス10度とか20度のところで完全に氷の粒になる。
もともと温かかった空気が上のほうで…。

- 上のほうに行くと氷になる。アラレやヒョウができるわけです。
はい。

- ある程度氷が大きくなると、当然重力で下に落ちてこようとします。
それが雪とかになるわけですよね。

- まぁそうですね。ただ上昇気流が発生してますから、落ちようと思っても、また上に吹き上げられることになり、対流が起きるわけです。
下りようとする氷と、下から上がろうとする水蒸気がケンカするということですか?

- そうですね。当然冷たくなってますから、氷の粒がいっぱいあって、氷の粒同士がぶつかり合うわけです。
はい。

- そうすると静電気が発生する。
へぇ〜。水分ですよね。水分と水分がぶつかっても静電気が発生するんですか?

- 水分同士ではないと思います。氷の粒ですから。
粒々と粒々がぶつかる、固形物がぶつかると静電気が発生する?

- 基本的には、そういうことになりますね。
へぇ〜。

- 冬場にセーターに触れてバチバチッと来るような現象ですね。
あの冬場の静電気のイメージが、空の上で起きているということですか?

- そうです。
でも、それだって別に「いてぇ!」というぐらいじゃないですか。

- そうですね。雷は氷の大きな粒と小さな粒が分かれるんですが、大きな粒が下のほうに溜まってマイナスの電気を帯びるわけです。小さな軽い氷の粒は、上のほうでプラスの電気がどんどん溜まっていく。
雲の層があったら上のほうにはプラスの電気が、下のほうにはマイナスの電気がある。

- そういうことです。
その雲の幅は何キロぐらいですか?

- まぁ大きさはいろいろありますが、数キロもあるし数百メートルのものもあると思います。それが、雲の一番下にマイナスが溜まり始めますと、地上にはプラスの電気がだんだん溜まってくることになっているんですね。
へぇ〜。何でですか?

- 何でですかねぇ。そういうことになっている(笑)。
ルール?

- そうなんです。そうしますと、どんどんどんどんマイナスの電気が増えてプラスの電気が溜まってくると、空気の壁を破ってバチッと放電する。これが、いわゆる落雷ということになるわけです。
へぇ〜! そうですか。みんなイメージして! イメージ大事よ。 それで、大なり小なりの雷がありますよね。その大きさは、やっぱり雲の大きさによって変わってくるわけですか?

- 必ずしもそうでもないと思いますが、エネルギーもいろいろな特徴がありまして、冬場の日本海の雷は、エネルギーが非常に大きいと言われています。
冬場の日本海側の雷はエネルギーが大きい!?

- はい。
じゃあ、夏場によく雷で事故が起きて山に救急隊員が行ったりするけれど、冬のほうが怖いということですか?

- そうですね、そういうことになります。まぁどちらも怖いですけれど。
いま日本海側では“リアルサンダーテロ”のシーズンだということですね。

- はい。
へぇ〜。実際に雷に打たれちゃったことはあります?

- さすがに私が打たれると困りますから、そういうことはないように気を付けてます。
雷も選んでいるんですね、こういう重鎮に当てちゃいけないと。

- いえいえ(笑)。
無防備な僕らは雷に打たれる可能性はあるわけですよね。

- そうですね。雷はあまり大したことはないと思われている方が多いですけれど、実際には非常に怖いとお考えいただいたほうがいいと思います。
よく子どもの頃は、雷の音が聞こえたら金属のものをすばやくはずすとか、傘をさしてたら閉じるようにと習いました。雷対策として落ちやすい人とか、性格はあるんですかねぇ。

- それはあまりない。
性格は関係ない?

- ただ身に付けている貴金属、腕時計とかネックレスをはずす必要は全くない。
えっ、何ではずさなくていいんですか?

- はい。雷は基本的に高いところや、とんがったところに落ちやすいので、金属を身に付けているから落ちるということはまずないと思います。
じゃあ、ちびっ子だったら逆に落ちにくいということですか?

- 落ちにくいですね。ただ自分より高いところに、――例えばテニスラケットを振り上げたり、大人の場合はゴルフクラブを振り上げたり、釣竿を立てて持ったりすると、自分より高いところにとんがったものができますから、そこに落雷する危険性はあると思います。
ということは、例えば雷が落ちてくる瞬間にゴルフでテークバックとかフィニッシュしていると雷が落ちちゃう可能性があるということですか?

- ありますね。非常に危険だと思います。
おしゃれでとんがり帽子をかぶっている人は?

- そうですねぇ、帽子は…。まぁとんがっているものは落ちやすいです。周りにもっと高いものがあれば、そんなに危険はないかとは思いますが。
周りにもっと高いものがあれば。じゃあ、原っぱでとんがり帽子をかぶっちゃいけないんですね。

- そうですね。
へぇ〜。いま思ったんですが、ゴロゴロの音源はどこから聞こえてくるんですか? 何でゴロゴロの音なんですか?

- これは先ほどちょっと申し上げましたが、地面と雲の中で放電するのが落雷と言うんですが、雲の中でもプラスとマイナスの電気が通ってますから放電するわけです。雲の中で放電した時にゴロゴロという音が聞こえる。
へぇ〜! 雲の中でくすぶっているのがゴロゴロで、それが飛び出したらゴロゴロという音じゃないんですね。

- 地面にはドカーンという音がしますね。
ドカーンが来たら大変なことになるわけですね。

- そうです。
気を付けなくちゃ。すごい勉強になった。もうこんな時間。伊藤さん、あっという間ですが、この番組短いですよね。もっとしゃべりたいと思いませんか?

- いえいえ(笑)。
いや、もっとしゃべってください、来週。

- そうですか、またぜひ!よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のサイコーは、株式会社サンコーシヤの伊藤眞義さんでした。ありがとうございました。

- はい、どうもありがとうございました。
いまだに「雷に遭遇したらベルトをはずそう」とかいろいろ言われているけれど、サイコーに聞いたら決してそうじゃないと。なるべく低く身をかがめることが大事だと分かりました。それじゃ、また来週も夕方5時半に会いましょう。バイバ〜イ!