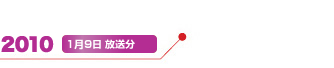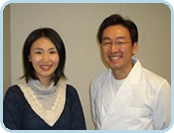キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。
9日になりました。冬休みも終わったと思うけれど、今学期は2ヵ月もすれば「もう次は春休み」となるから、がんばって乗り越えていきましょうね。
さぁ今回も“食べる”を科学しちゃいますよ。テーマは、みんなの大好きなお寿司のネタ。イカかな? エビかな? それともあの赤いやつかな〜? お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
今週のサイコーも先週に続きまして、日本科学未来館の五十嵐海央さんです。こんばんは。

- こんばんは。
海央さんのミオは「海」に浅田真央ちゃんの「央」だから、海の中央で生まれたんですか?

- 海の中央で生まれたわけではありません(笑)。
どうしてこういう名前が付けられたんですか?

- 太平洋の真ん中のような広い心を持った人になって欲しいと、親が願いを込めたらしいです。
子どもの頃、「ハワイ」とかいわれませんでした?

- それはなかったですね(笑)。
そうですか。そんな海にちなんだ話を今日は伺おうと思います。日本科学未来館といいますと3月22日まで『‘おいしく、食べる’の科学展』の真っ最中で、五十嵐さんはその中でいろいろな案内をしてくれるお姉さんの一人でもあります。

- はい。
で、今日のテーマはみんな好きかな〜? マグロ。だいたい、ちびっ子たちは、お寿司でタマゴとかカッパ巻きで始めるじゃないですか。最初にチャレンジする魚介類はマグロだと思うんですよ。


- 私もそうでしたねぇ。
ですよね。うちの子もそうだったんですよ。マグロはみんな大好きだと思うんですが、マグロが好きな国民は日本が一番だといいますよね。

- 日本人はマグロ大好きですね。
世界のマグロの9割ぐらいは日本人が食しているという話もあるぐらいで。

-
それはすごいですよね。
このマグロだけど、よくニュースの映像で浜松町から大江戸線で2駅行った築地に水揚げされてカチンカチンに凍ってます。さて、今日はクイズがあります。「家庭の冷蔵庫の冷凍室はマイナス18度。マグロを凍らせる温度はマイナス何度か?」。 このクイズ、みんな分かるかな? マグロはカチンカチンに凍ってくるけど、五十嵐さん、ズバリ何度で凍ってるんですか?


- はい。マイナス60度で凍らせます。
さかなクン的には「ギョ、ギョ、ギョギョギョギョッ!」という感じですかねぇ。

- すごい低い温度ですよね。
家庭用の冷凍庫じゃ、まず出ない温度ですよね。

- はい。特別な冷凍の技術が必要になります。
しかも、築地に入ってくる時に、あんなコチンコチンということは、海の上でああいう風な形に凍ってるってことですよね。

- はい、そうですね。マグロは日本の周りの海だけではなくて、世界中のもっと遠い所まで捕りに行っています。
はい。

- その水揚げしたマグロを船の上で急速に冷凍させて、日本までカチカチの状態で運んでるんですね。
急速に冷凍させる必要があるということですか?

- はい、そうなんです。
なぜですか?

- 物を凍らせる時、お家の冷凍庫でもみなさん凍らせたことがあると思うんですが、だんだんゆっくりと凍っていくのですけれど、ゼロ度からマイナス5度までの間が特にゆっくりと、ちょっとずつ凍っていく。
はい。

- この時に食べ物の中にある水分が氷の粒になるんですが、ゆっくり凍っていくと、大きい氷の粒になってしまうんです。
ふ〜ん。

- そうすると氷の粒が細胞をこわしてしまって、解凍した時においしくないマグロになってしまいます。
へぇ〜。じゃあ、家庭用の冷凍庫に、例えば買ってきたお肉を入れた場合、マイナス18度まで固まるかもしれないけれど、その固まっていく過程は比較的ゆっくりですよね。

- そうですね。なので、お家の冷凍庫でも冷蔵庫に比べれば長く保存できるんですが、おいしく食べ切るには数週間ぐらいで食べたほうがいいですね。
そうなのか…。お肉とか冷凍して1年後に食べても、風味は落ちているということですね。

- そうですね。だけどマイナス60度だと、風味も損なわずに凍らすことができます。
だけど去年、松方弘樹さんが釣った巨大マグロみたいなものは、急には凍りませんよね。

- そうですね。大人のマグロといわれる、だいたい50キロぐらいのマグロを丸ごと凍らせるのに、どれぐらいかかると思いますか?
50キロぐらいですか? 一般的な大人のマグロ?

- はい。
急速冷凍?

- はい、マイナス60度で。
芯までということですよね。

- そうですね。
う〜ん。じゃあ、急速で5時間ぐらい?

- 足りないです。
足りない!?

-
だいたい、丸一日から二日かかるそうです。
24時間から48時間かかるんですか!?

- はい。
全然急速冷凍じゃないですね。

- それでも、家庭の冷凍庫で冷やすよりは、もっと早く芯まで凍らせることができるんです。
そうすると風味を損なわずに保存がきくということですか?

-
はい、そうです。
それを船の上でやってる?

- はい。
へぇ〜。どの船にもそういう装置が付いてるんですか?

-
遠くの海までマグロを捕りに行くような船には付いているので、捕ってすぐに内臓とかエラを取って、冷たい冷気を吹き付けて凍らせる。新鮮なまま凍らせて日本まで運んで来てるんですね。
この技術は何年ぐらい前からやっているんですか?

- 大体40〜50年ぐらい前から、おいしいマグロのお刺身が冷凍の技術によって食べられるようになったといわれています。
けっこう前ですねぇ。

- そうですね。
高度経済成長期ぐらいから始めているということですか?

- はい。マイナス60度で凍らせるとおいしさを保てると分かってきたのが、それぐらいだそうです。
マイナス60度という根拠は何ですか?

- 根拠! 根拠は何でしょう?
何となく、ですかねぇ。だいたい、それよりも高い温度で、マイナス30度とか40度だったらイマイチで、60度にたどり着いて「やっぱりウマイ」ということになったんですかねぇ。

- そうですね。ひとつがマグロの肉の中に、ミオグロビンというのがあるんです。
ミオグロビン。

-
はい。これが空気に触れてしまうとどんどん酸化して、マグロの赤身が黒っぽくなってしまいおいしくなくなってしまう。
古くなるとマグロが黒くなる。はい。

- これがお家の冷凍庫のマイナス18度ぐらいだと、ちょっとずつ進んでいってしまう。だけど、マイナス60度まで冷やせば、それを止めることができることが分かっているそうです。
ミオグロビンが現れるのを?

- そうです。空気に触れて酸化していくのを止めることができる。
へぇ〜。未来館で、マグロの冷凍は一応「食品の保存」というテーマ、くくりでありますよね。

- はい。
食品の保存で、古くは塩漬けや天日にかけて乾燥させるとか展示されてますよね。僕が驚いたのは、缶詰。缶詰って100年以上、何百年も前からあったんですって?

- 缶詰の前にびん詰めが考えられたんですが、ナポレオンの時代だそうです。
その時代から、びんに詰めて保存するという技術があったわけですよね。

- そうですね。その時は食べ物を持って他の所まで兵隊さんが移動していくのに、なるべく食べ物を長く保存させるにはどうしたらいいか、という知恵を募って、びん詰めという技術ができたそうです。
それが進化して缶詰になった。

- はい。
今も缶詰って重宝されてますものね。

-
そうですよねぇ。
日本の場合は、あまりそういうのが進んでなかったという展示もありますよね。

- 日本はどちらかというと、乾かして乾燥させたりするような技術が昔からありましたから。
そうですよね。それも非常に興味深い展示だったんですが、未来館と連動して去年から足かけ2年、6週にわたって特集を組んできました。

- ありがとうございます。
未来館であと2ヵ月半この科学展をやってますが、五十嵐さんとしておすすめの見どころがあったら教えてください。

- 私の個人的なおすすめは、保存食のマグロのコーナーのちょっと奥にあります宇宙食のコーナーです。ちょうど今、日本人の宇宙飛行士の野口聡一さんも宇宙に行ってますが、保存技術が発達したことによって、いろんな所まで行って食事ができるようになったことをぜひみなさんにも感じていただきたいですね。
そうですよね。そうか、保存のプロセスで最後は宇宙に、という話ですものね。宇宙のコーナーは、実は行ったキッズが見逃しているかもしれないけど…、天井に面白い映像が出ていることを忘れちゃいけないですよね。

-
そうですね。天井に、実際に宇宙飛行士が食べてる食事の風景が出てます。
古くは毛利衛さんの映像から。

-
当館の館長です。
はい。未来館へ行かれたら、ぜひ『‘おいしく、食べる’の科学展』観てくださいね。ということで、なごり惜しいなぁ、未来館の話が終わっちゃうのは。

-
フフフ。
今回のサイコーは、日本科学未来館の五十嵐海央さんでした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
そういえば、一昨年ぐらいにこのシークレットラボの公開イベントで液体窒素というマイナス196度に一瞬手を入れて「やばい!」と思って手を引っこ抜いたんだけど、あれも急速冷凍みたいなものなのかなぁ? ――みんな、どうだったんでしょうか?それじゃ、みんな風邪とかに気を付けてね。新学期を乗り越えて行きましょう! また来週も夕方5時半ね。バイバ〜イ!