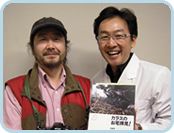キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。さぁ節分も終わりまして、暦の上では春となりました。みんなもいい春を迎えてねっ。ということで、今週もカラスの巣を特集したいと思っているんですけど、サイコー史上、もっともワイルドなサイコーが、また長野県から来てくれました。お知らせの後、興味深い話が待ってま〜す。
今週のサイコーは先週に続きまして、写真家の宮崎学さんです。長野県からまた来ていただきました。こんばんは。

- どうも、こんばんは。
ようこそラボへ! 宮崎さんは、新樹社から写真集『カラスのお宅拝見!』という本を去年の12月に出版されました。これが写真家の本だけあって、写真主体の非常に興味深い作品になってますよね。

- ありがとうございます。
僕、驚いたのが、北海道から沖縄までのカラスの巣の写真の中で、この“巣”が地域によって違う材料でできているという…。

- はい(笑)。
これ、衝撃なんです! じゃあ、キッズのみんな、クイズだよっ。
「ラボの近くにゆりかもめやバスに乗っていくとお台場があるんだけど、お台場のカラスの巣は主に何でできているでしょうか?」。
――正解は…宮崎さん、何でできてますか?

-
防虫ネットとか人間の髪の毛とか、あとは洗濯ハンガーですね。
ハハハハハハ。

-
フフフフフフ。
だから、天然物ではなく、人工物でできてるということですね。

- そうです。
これ、何でですか?

- 東京都内だって、全部天然素材というより、化学繊維から始まっていろいろな人工素材でしょ。
僕らの生活は、ですよ。でも、自然界に生きるカラスが?

-
そういうゴミが出てくるんですよ。要するに、人間が出した周辺のあまりもので、彼らは全部衣食住をまかなっているんですから(笑)。
先週は“食”の話で、人間の残飯をカラスが処理するということでしたが、この“衣住”に関するあまりものとは、いわゆるゴミってことですね。

- はい。
ゴミで巣を作っているということですね。

- はい。
いや、衝撃ですよ。

- ですから、競馬の馬の産地で北海道の新冠(にいかっぷ)に行くと、1頭3千万とか1億のたか〜い馬の毛を持ってきて巣の材料にしたりとか(笑)。
サラブレッドの毛でカラスの巣が! 北海道の!

- そうですよ。ぜいたくなもんですよ(笑)。
寝心地よさそうですねぇ。そのヒナたちは。

- と思いますよ(笑)。

- あと、クツワというかロープの端っこを持ってきて巣にしたり。
へぇ〜。

- 巣には、その地域色ってけっこう出てますね。漁村に行けば魚網の残りとか。
じゃあ、この『カラスのお宅拝見!』の表紙は、2羽のカラスがけっこう可愛い顔をしてるんですけど、よ〜く見たら、銅の赤茶色っぽい…。

-
銅線ですね。
電気コードの上にいるんですけど、バックにはビル群が見えてる。

- それは、丸ビルの工事現場です。
ということは、この表紙は丸の内ですか?

- そうそう。
丸の内のカラスが表紙!?

- はい、そうです。
その巣は、針金とか電気コードとか。つまり工事現場から出されたカスということですか?

- そうです。それを失敬してるんですね(笑)。
この裏表紙は、ちょっと黄緑っぽいタマゴのカラスの巣です。タマゴがあって、この巣は天然素材、木の皮とか小枝でできてますが…。

- これは、北海道の網走です。
網走ということは、木が、自然が豊富ですね。

- そうなんです。
じゃあ、自然が豊富な場所は、比較的に天然素材物のカラスの巣ができるんだけれど、都会に来れば来るほど、人間の不用なゴミなどで巣ができてるということですね。

- はい。
これまでいろんなカラスの巣を撮ってこられて、たとえば「あっ、このあたりはこうなんだ!」というカラスの巣はありますか? 驚いたのは?

- 結局、そのサラブレッドなどは非常に面白かったのと、あと不思議なのは、カラスはいろいろおたまじゃくしや魚の腐ったようなところを食べるでしょ。ものすごく衛生上よくないんですよ。
ええ。

- だから殺菌するために、必ずヒノキの皮、要するにヒノキチオールとか殺菌力の強い物質が入っています。それを必ず入れているのが本州から南のカラスです。つまり、青森から九州までのカラス。
へぇ〜。

-
そして、北海道へ行くとヒノキがないんですよ。だから、ブドウの皮が入ってるんです。
それはカラスの知恵として、必ずヒノキとかブドウの皮を巣に入れることによって、子どもを守るということですか?

- どうもそうみたいですね。ブドウにはポリフェノールの効果があるでしょ。ですから、殺菌効果があるんですね。
でも、都会にはそういうヒノキの皮があるんですか?

- 何とか見つけてきます。
へぇ〜!

-
だいたい入ってますね。
でも、銀座や日比谷、お台場のようなヒノキがなさそうなところに巣を作るよりは、ちょっと郊外のヒノキがあるところに巣を作るわけにいかないんですか?

- それは結局、人間も含めて通勤圏、要するに生活するためにお給料をいただく会社があるでしょ。
ええ。

-
それと同じでカラスは、生活のために周辺からどれだけエサが出るか。どんなにいい木があっても、エサがないところでは巣が作れないんですよ。
なるほど。都会のほうが残飯が豊富でおいしいものがいただけるから、多少の不便はあっても、ヒノキの皮を取りに行くには「ちょっと出張しようかな」と。

- そうそう(笑)。
「頑張って1回出張したら、おいしいものが待ってる」という感じなんですね。

- 東京には貯木場とかありますから、その周辺から皮を持って来ますね。
じゃあ、新木場とかあのあたりは、カラスが飛びかっていたら「アイツ、ヒノキの皮を取りに来たな」と思えばいいんですね。

- そうです、そうです(笑)。
へぇ〜、すごい! 大阪の巣は、やっぱり東京と同じような?

- 同じですね。名古屋もそうです。洗濯ハンガーが多いですねぇ。要するに外装と内装で作り方を分けるんですが、外装はほとんど洗濯ハンガーですね。
この写真を見ると、けっこうピンクとか水色のクリーニング屋さんからのハンガーですね。

- はい(笑)。
あれをカラスがくわえて来るということですね。

-
そうなんです。
そんなカラスが飛んでるの見たことないですよ、僕は。

- いや、時々ありますよ。
宮崎さんはあるの?

- はい、ありますよ。
じゃあ、ハンガーくわえてたら、「おっ、巣を作りに行くな」と微笑みながら見てるわけですか?

- そうそうそう(笑)。
へぇ〜。すごい! あと、タヌキの毛でできてる巣の写真があるんですが、これもすごい面白いエピソートがありましたね。

-
あんまりタヌキの毛が多いから、「おかしいなぁ」と思って、木から降りてフッと歩き始めたら、近所にタヌキがやっぱり死んでたんですね。見事に頭のところから背中の一番いいところだけ、カラスが引きむしってましたね。
それを巣のクッションに使っているということですか?

-
そうそう。人間でいえば、お布団の毛布ですね。そういうところに使うんですね。
へぇ〜。この写真に出てるカラスのヒナたちはみんな口を開けて、親を求めるこの表情…。いわゆる表情がこの写真にあるわけですよ。そうすると、先週、僕はカラスがちょっと苦手だなと思ったのが、やっぱりこういう可愛いヒナがいて、親も一生懸命エサを与える。その子どもたちが大きくなって、やがて自分の子どもに返していくという。この写真にも愛が感じられて…。カラスのすごい生態系プラス、カラスのイメージがずいぶん変わる1冊だったんです。

-
ありがとうございます。
この写真を撮影するにあたって、木登り以外のご苦労はどういうところにあったんですか?

-
え〜と、人になるべく見つからないこと。
撮影するときに?

- はい。やっかいなんですよね、人に見つかると。今どき、日本で木に登る人間なんかいないでしょ。
ちょっと待って。カラスに見つからないようにじゃなくて、人に見つからないように(笑)。

-
そうそう。
アッハハハハ。カラスを警戒しているんじゃなくて、人に見られるのがちょっと抵抗があるということですか。

- すぐおまわりさんが飛んで来たりとか、そういうことになるじゃないですか(笑)。だから、むしろそれに気をつけましたね。
逆にカラスは宮崎さんが上がってきて、木が多少なりとも揺れるわけじゃないですか。

-
揺れるどころか、もう100メートルぐらいのところから完全に「あいつはちょっと異常だぞ!」と見分けてます。
それに対して、カラスから攻撃とかないんですか?

- ないです。
警戒はされない? 大丈夫なんですか?

- スーッとカラスは逃げて行っちゃうんですよ。「お〜、アイツ意識したな」ということで。
そこにヒナが、守るべき子どもがいるわけですよね。じゃあ、「このおじさんは家の子は傷つけない」ことをカラスは分かってくれてるんですか?

- もう傷つけようが、子どもを持って行こうが、カラスの親は抵抗できないですね、僕に対しては。
そうなんですか。

- はい(笑)。
じゃあ、たとえば僕みたいな素人が、巣に上がって行ったらどうなりますか?

- 危険だと思います。
危険…やっぱり。分かりました。まねしちゃいけないということですね。

- 木登りも、登る木にも全部習性がありますから見分けられないと、やっぱり危険です。
登れる木と登れない木があるんですね。

- そうなんです。バキッと枝が折れたり、巣が枝先にあったら、ものすごく体のバランスをくずしますから。木の幹に沿った巣でないと登っちゃいけないとか。いろいろ条件があるんです。
ステキな団塊世代のおじさまでした! 今週のサイコーは、写真家の宮崎学さんでした。ありがとうございました。

- どうもありがとうございました。
宮崎さん、今年61歳になるということだけど、すごいオーラをかもし出した人でした。こういう方だから、きっとカラスと信頼関係を構築して、このような本ができるんだろうなと思いました。ほんとにすごい写真がいっぱい載ってます。 それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!