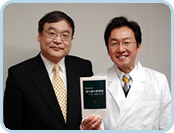キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。3月に入りました。ほんとに3学期って短いね。もうすぐ春休みだし、進学のシーズンだし、みんなもそれぞれいろいろな3月への想いがあるかも知れないけれど、僕は、今年はスギ花粉が少ないので、ホッとして3月を迎えました。さて今日のテーマは、毒と薬。花粉症の薬をこの時季どうしても飲んでしまうのですが、「今年は若干少なめです」という人もけっこういるんじゃないかなぁと思います。お知らせの後、薬の専門家の方が登場します。
今週のサイコーは、日本薬科大学教授の船山信次先生です。こんばんは。

- こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。船山先生は、中央公論新社から『毒と薬の世界史』という本を出版されてます。この“毒と薬”って、まったく反対じゃないですか?

- アッハハ。そうですね。
これはどういう内容ですか? 何で“毒と薬”を比べるんですか?

- “毒と薬”というと、ちょうど逆のような感じがしますよね。
ええ。

-
でも毒とか薬は、私たち人間があるものを服用したり使ったりした時、都合がいい時に「薬」といっている。それから、何か不都合なことが起きた時に「毒」といっている。それに過ぎないと思いませんか?
分からない! じゃあ、“毒と薬”は紙一重ということですか?

-
紙一重です(笑)。同じと思ってもいいと思うんです。
え〜っ!?

- 私はそれを“薬毒同源”。薬と毒は同じ源とよくいってるんですけれども。
えぇ〜!?

- 薬として一般に使われているようなものでも使い方を間違ったりすると、いわゆる毒という。副作用の中で非常に麗しくないものを毒作用、といってもいいと思います。
副作用ですよね。

- はい。
あと、「定められた用量・用法をお守りください」と書いてありますよね。つまり、「薬だと思っても、場合によっては毒になりますよ」ということですか?

- そういうことです。それから、トリカブトという毒草がありますね、非常に有名な毒草ですが。
ええ。

-
もちろんこれはある程度加工してですが、漢方で非常に重要な薬でもあるんですね。
えぇ〜、そうなんですか?

- ですから、「いったいトリカブトって毒草なの? 薬草なの?」といわれると、どっちでもあるんですよね。
トリカブトって、人が死んじゃうわけですよね。

- はい。
だけど、薬としても成り立っているんですか?

- 薬としても使われている。
誰が飲むんですか、それは?

- 大村さんも飲んだことがあるんじゃないでしょうか(笑)。
僕も! トリカブト? どんな症状の時ですか?

- 漢方の八味丸(ハチミガン)とかあるんですが、けっこう入っているものがありますよ。
八味丸は何の薬ですか?

- いわゆる西洋の医学でいうと、糖尿などの系統の疾患に使われるものです。
なるほど。漢方薬っていろいろな薬とか煎じて調合したものですが、単体では毒である植物も含まれている。でも、適度な量だったら薬にもなり得るということですか?

-
トリカブトの場合は、修治(シュウチ)といってるんですが、ちょっと熱をかけたり、毒性を下げて使っている。しかも、量を非常に吟味して使っています。
だけど、調合を間違えたら…。

- これはもう大変です!
いや〜、“毒と薬”ですねぇ。

- まさに“毒と薬”です。自分の健康のために、トリカブトの根っこを調合して飲んでおられた有名な植物学者がいらっしゃいますが、ある時、間違ってしまって中毒で亡くなっている。
えっ、そうですか。あと、アサガオは何に効くんですか?

- アサガオの種子を牽牛子(ケンゴシ)というのですが、下剤だったんです。
下剤?

- はい。下剤として入ってきたんですが、非常に強すぎる。強すぎるというか、危険なぐらい強いのです。
アサガオの種が!?

- 今では、一般には使われておりません。
へぇ〜。じゃあ、便秘がちな女性が、子どもの育てたアサガオが種になったとき、それを飲んじゃったら大変なことに!

- それは、やめたほうがいいと思います。絶対におすすめできません。
かつては薬だったけれど、現代人には効きすぎて逆に毒ということですね。

- ということですかね。非常に強いので、むしろ危険であるということで、今は決してすすめられてません。ですから識者のなかには、「子どもがアサガオを育てるのも危険じゃないか」といっておられる方もいるぐらいです。
そうなんですか。毒というと、僕のイメージは身近なところではヘビ、かまれたことがないけれど。あとはハチの毒でしょ。めったに食べないけど、フグ。あと、「毒の代名詞は青酸カリ」といいますよね。

- ええ。
青酸カリは植物ですか?

- いえ、いえ。
違う?

-
これは化学合成品で、工業などに多量に使うものです。
青酸カリは自然界に存在してない?

- そのものは、ありません。
でも、フグやハチ、ヘビの毒は、自然界に存在する毒ですよね。

- そうですね。
毒性が世界で一番強いのは何ですか?

- ボツリヌスという食中毒の菌がありますが、それが出すボツリヌストキシンが今、単位の量あたりで一番強い毒を持っているといわれています。
へぇ〜。まもなく発生から15年ですが、地下鉄サリン事件の直前には、ボツリヌス菌をまこうとした事件もあったけど、そのボツリヌスですか?

- そうです。
それは、どれぐらいの毒性があるんですか?

- ボツリヌストキシンは、いくつかの毒、化学的に似た化合物の混合物になってます。その中で一番強いもの――なかには人間に対して大した毒性がないものもあるんですが、一番強いものになると、1グラムの純粋なものがあったら5500万人の命が危うくなるくらいの毒性を持っています。
1グラムということは、1円玉1個分ぐらいの量で5500万人!

- はい。
じゃあ、2円分の量で1億1千万人。日本の人口がほとんど全滅しちゃうじゃないですか!

- そうなんです。
ボツリヌスで。

- それぐらいの人の命に関わるぐらいの毒性を持っています。
でも、それは人工的に作らなければ、できない。

-
そういうことです。
でも、あるんですか、それが?

- この世の中にはあるということです。
何のために、それを作るんですか?

- これはですね。いろんな生物進化のいたずらとしかいわざるを得ないんじゃないかと思うんです。結局、先ほどのフグやトリカブトも、「自分の身を守るために毒を持つようになった」などという場合がありますが、それは当たってないですよね。
そうなんですか。動物って身を守るために毒を持っているんじゃないですか?

- トリカブトやフグは、自分で身を守るために毒をどこかから仕入れてくることはできませんよね。
でも、進化の過程で外敵に襲われやすいから毒を身につけた、というわけではないんですか?

- 私は、「結果として考えたらいかがかな」といつも思うんです。生物はめたらやったらといろんな進化をして、いろんな生物、ものすごい種類の生物がこれまでに出てきてるわけです。
ええ。

- ちょっとでも生き残るのに有利だったものが残り、今にいたっている。今も絶滅と生き残りの戦いが続いていると思うんですが、そのなかで何か生き残りに有利だったものが残っているわけです。
ほぉ〜。

- たまたま人間が毒といっているものを持った生物は、ほかのものに対して若干有利だったんじゃないかと。だから、人間だって“頭で考える”という、ほかにはない能力を持っている。それで今、これだけ栄えているということがいえるんじゃないかと思うんです。
それも動物たちから見れば、人間の脳みそは“考える毒”という考え方もあるかもしれないですよね。

- ハハハハ。“毒”といういい方をしてもいいかもしれませんね。確かに戦う武器ですよね。
恐ろしい話というか、何かすごくいい話ですけれど(笑)。

- フフフ。
あら、もうこんな時間だ。来週また、この毒に関しての話をうかがってよろしいですか?

- はい。よろしくお願いいたします。
今日のサイコーは、日本薬科大学教授の船山信次先生でした。ありがとうございました。
いやぁ、表裏一体という言葉があって、薬と毒――ほんとギリギリなんだね。使い方を間違えたら、毒にもなっちゃう。やっぱり毒を持ったものが生き残って、毒のないものが淘汰されちゃうとなると、人間はほんとに毒を持ってる。 このいわゆる業界と呼ばれる世界も、毒を持った人が生き残るというのかなぁ。だから、やっぱりラジオに出ている有名司会者の方も、毒があって長く番組ができるということなのかなぁ(笑)。僕もちょっと毒を持って、あと10年ぐらいこの番組ができたらいいなぁと思ってますけれどね。それでは、みんなもいい毒を持って、そしてリーダーシップを持って頑張っていきましょう! じゃあ、また来週。バイバ〜イ!