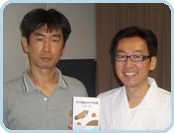キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。 あ〜、運命の6月19日が来ちゃったよ。今夜、日本代表はオランダと戦うんだよ。もうねぇ、これでもしダメだったら、今週のテーマであるモグラみたいに僕も地中で暮らすようになるかもしれないなぁ。ということで、先週に続いてモグラのことをもっともっと詳しく聞いていきたいと思います。お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
今週のサイコーもモグラ博士、国立科学博物館研究員の川田伸一郎さんです。こんにちは。

-
どうも、よろしくお願いいたします。
川田さん、モグラ好きだけあって声のトーンもモグラっぽいですね。
“くぐモグラ”系ですね。

- 「なかなか聞き取りにくい」とよくいわれますね。
「やっぱりモグラっぽい」っていわれませんか?

-
「モグラっぽい」っていわれたことはないですけど(笑)。
だいたいそのトーンですか? 「僕は〜」(高いトーンで)なんて絶対いわないですか?

-
いわないですね(笑)。
そうですか、分かりました。モグラのことなら何でもご存じの川田さん、日本のモグラ、例えば種類とかあるんですか? モグラはモグラだけですか?

-
大きく2つに分かれるんですよ。いわゆるわれわれが知っているモグラと、ヒミズというのがいるんです。
ヒミズ?

-
はい。ヒミズは、しっぽがちょっと長くて、体の3分の1ぐらいあるんですね。それで、どっちかというとトンネル掘りが得意ではない、半地中性という生き様をしてるモグラです。図鑑などに載ってますが。
カタカナで書くんですか?

-
はい。“日を見ず”というところから来てるらしいです。
へぇ〜。それは正式名称?

- はい。
それもモグラの仲間ですか?

-
そうです。モグラ科という分類群になりますが、われわれはヒト科ですよね。モグラ科がありまして、そこにヒミズの仲間、モグラの仲間。
ほぉ〜。

-
日本にはヒミズの仲間が2種いるんですね。ヒメヒミズとヒミズがいまして。
ヒメヒミズ?

-
はい。ヒメヒミズとヒミズの2種。モグラのほうは、今6種に分けられてますね。全部で8種。
モグラ科は8種類。で、ヒミズ目(モク)とモグラ目(モク)?

- ヒミズ亜科とか呼んでます。
亜科、アジアの亜ですね。

- モグラ亜科。
モグラは6種類。

- そうです。
生息地は違うんですか?

-
だいぶかぶってますけど、北海道にはいないんですね。
モグラがいない?

- はい。
へぇ〜。

- 不思議なんですけどね。よく分からないですが、なぜか…。
じゃあ、青森から沖縄まではいるんですか?

-
沖縄にもいないですね、基本的には。沖縄県にいるのは、尖閣諸島にセンカクモグラがいまして、今まで1匹しかつかまってない、とんでもなく珍しいモグラです。
へぇ〜。

- 要するに調査できないんですよ。
あのあたりは中国ともめてますからね。

- はい。
そのモグラの名前は、「モグラ」という名前があるんですか? 何とかモグラとかついてる?

- はい、全部、何とかモグラとついてます。
例えば、どんな?

-
コウベモグラ、アズマモグラ、サドモグラ、エチゴモグラ、ミズラモグラというのが本州にいる。
ちょっと待って(笑)。アズマとコウベ、東と神戸は分かるけれど、佐渡?

-
佐渡島にしかないモグラがいるんです。
越後っておっしゃってました?

-
越後平野にしかいないモグラ。
同じ新潟県でも越後と佐渡で分かれる?

-
そうです。
あとは?

- ミズラモグラ。これは、本州全体から見つかってますが、山のけっこう高いところでよく見つかるモグラです。
はぁ〜。

-
これが一番ナゾに包まれているモグラといっていい。
ミズラモグラ。こういうのをやっぱり探されるわけですか?

-
そうですねぇ。ミズラモグラは、今一番調べたいもののひとつですね。
今ちょっと初めて川田さんが科学者の目というか、すごくキラキラ輝きました!

-
ハハハ。
ミズラモグラは、まだご自分では?

-
昔つかまえたことはありますけれど、ただミズラモグラをつかまえようと思ってつかまえたことはないです。
偶然つかまえた。じゃあ、それを目標にしてゲットできたらすごい?

-
すごいですねぇ。
へぇ〜。

-
何が珍しいかというと、つまえられた例よりも、ひろわれたほうが多いんですよ。
それは死がいで、ということですか?

-
そうです。
生け捕りになったことはないということですか?

-
生け捕りは2〜3例あると思うんですが、ほとんどは死体をひろった。それも研究者がひろったんじゃなくて、山歩きしてる人が見つけて調べてもらったら、ミズラモグラだったということが多い。ほんとにナゾに包まれたモグラです。
生息域はどのあたりですか?

- 本州、中国地方から東北地方まで。山地沿いにあちこちで見つかってます。
ほぉ〜。でも、その大半は死がいということですね。

- そうなんです。
川田さんがかつて見つけた時は、生きてた?

- 死んでましたね。
そうなんですか。じゃあ、生きてるミズラモグラをまだ見たことがない?

- 一度見たことがあります。
それは?

- 知り合いの研究者がつかまえたのを、わざわざ京都まで見に行きました。
自然の中で生息しているものを見たことはない?

- ないですねぇ。
それは、見た目にアズマモグラと違うんですか?

- 違います。
どう違うんですか?

-
しっぽがやや長い。小さい、世界で一番小さなモグラです。
へぇ〜。

-
ヒミズの仲間を除くと、モグラといういわゆる地中性の中では一番小さい。
普通のモグラのミニチュア版で、しっぽ長バージョンということですよね。

- で、鼻先の形態とかも全然違う。
違うんですね。へぇ〜。僕、帰ったらネットで調べてみようかな。興味深い。あと、モグラって毛の生え方は、ネズミやリスの毛のイメージ?


- モグラの毛は、よくいわれるんですが体の表面から比較的垂直に近い方向に生えてる。
ヤマアラシ系ですか?

- ヤマアラシも、まだ後ろに倒れてるんですよ。
へぇ〜。

- 立てることはできるんですけれど。普通どんな動物でも、毛の生える方向は前のほうから後ろのほうへ向かって生える。
そうですよね。ウマやウシもみんな。

-
やっぱり空気の抵抗とか考えると、それが一番理想的なんですね。
はい。

-
ところがモグラの場合は、ほとんど垂直に。
へぇ〜。

-
これは、土の中で前にも後ろにも移動するためという説明がされてるんですね。
ほんとだ。川田さんの著書『モグラ博士のモグラの話』にモグラの写真があるけれど、タワシみたいですね。

-
はい。いい表現だと思います。
モグラの毛は固いんですか?

-
柔らかいです。すごく柔らかい。
柔らかいけど、おっ立ってるということですね。

-
おっ立ってる。
何センチぐらいですか?

-
毛の長さ、1センチもないですね。5ミリぐらいかな。やっぱり冬のほうが長い毛が生えるんですよ。ちゃんと毛変わりがあるんです。
垂直なのは、前後に移動できるためですか?

-
そうですね。やっぱりトンネルの狭い空間なので、いきなり折り返すことができないんですね。
ユーターンができない。

-
ですから、前にも後ろにも進めるように体の構造が進化してる。
そうか。モグラのトンネルは縦が3センチ、横がだいたい4センチぐらい。そうすると、モグラの本体はフィットしちゃってユーターンできない。

-
そうなんです。だから前にも後ろにも同じぐらいのスピードで動くことができる。
足の向きは前に歩くようにできてるけれど、この足の向きは後ろにも同じ速度で動けるようにできてるんですか?

-
できてる。
不思議ですねぇ。

-
不思議ですね。
へぇ〜。毛は垂直で前後に行けるようになってるけれど、足は前向きになってるし、顔も前にしかついてないけれど、前後自由自在に?

-
はい。
チューブ内を自由に移動するカプセルみたいなイメージですね。

-
そうですねぇ。しっぽが短いのも、そういうことに関係した特長だといわれてまして、しっぽが長いと後ろに歩く時にジャマでしょう?
はい。

-
だから、短くなったという。
へぇ〜。

-
土の中にいる動物は、基本的にしっぽが短いものが多いんですね。
なるほどね。子どもの頃から昆虫、生き物が好きで、今これをお仕事とされてる。しかもキラキラと目が輝いていて。モグラの目はちっちゃいけれど、川田さん、目が輝いてました。

-
ハハハ。
目標は何かありますか?

-
そうですね。僕は世界にモグラが何種いるかを、死ぬまでにつきとめるのが一応究極のテーマなので(笑)。まぁ、できるだけ生きてる間にたくさんつかまえて、ちゃんと調べてやっていきたいなぁと思ってます。
分かりました。ぜひ極めてください。

-
はい。
ありがとうございました。

-
ありがとうございます。
今週のサイコーは、国立科学博物館研究員の川田伸一郎さんでした。
ということで、モグラに6種類あって、ミズラモグラが非常に珍しい。夏休みに山へ行くキッズがいたら、ひょっとしたらミズラモグラの生け捕りに成功するかもしれない。そしたら、川田さんにぜひ報告をしてください。飛んで来ると思います。 ということで、川田さんの『モグラ博士のモグラの話』という本が岩波ジュニア新書から出版されてます。この本、意外なモグラの生態や、川田さんがなぜモグラに行き着いたのかという歴史なども書いてあります。ほんとにおもしろい本でした。 それでは今夜のオランダ戦、みんなサッカーに興味がなくても応援しよう!そして、来週楽しいトークで再会しよう!じゃあね。