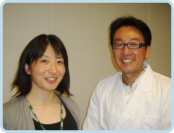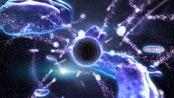キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、夏休みエンジョイしてると思いますけれど、自由研究のテーマにぴったりなサイコーをお呼びして今月も放送します。みんな、細胞って分かるよね。みんなの体は細胞のかたまり、何兆個の細胞でできているんだけど、この細胞の中で病気が治っちゃう夢のような細胞があるのを知ってるかな?すっごい興味深い話なんだよ。お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
今週のサイコーは、日本科学未来館・科学コミュニケーターの森田由子さんです。こんにちは。

こんにちは。
日本科学未来館はお台場にあるんだけれど、『Young Alive!〜iPS細胞がひらく未来〜』という映像作品を今やっていますよね。僕はまだ観てないんですけれど…。

はい。公開したばかりです。
そうなんですか。Young Alive(ヤングアライブ)、若い人が生きる? iPS?

フフフ。タイトルは“若々しく元気に生きよう”ということで、主題歌を歌ってくださってる水樹奈々さんの歌のタイトルから取らせていただきました。
『Young Alive!』という歌が、へぇ〜。“若々しく生きよう”、OK、OK(笑)。これでいきましょう。僕らもヤングアライブで!

はい(笑)。
iPS-iPS細胞ということなんですね。何ですか、iPS細胞って?

ニュースでよく医療コーナーとか、新聞でもこの名前を聞いたことがある方が多いと思いますが、実は特別な細胞なんです。この紹介をするために今回作られたドームでの映像作品が『Young Alive!』ということで、7月17日から公開しています。
未来館の上のドームね。

そうです。
昔、ガイアとかやっていた。

はい。
あそこで、映像作品でやってるんですね。

はい。
iPS細胞のiPSはどういう意味ですか?

iPSの部分は英語なので、これを全部説明するのは難しいんですが、インデュースド・プルリポテント・ステム・セルというのが英語の名前で、この細胞…。
すみません、和訳してもらえますか?

はい。日本語では、人工多能性細胞と呼んだりするんですけれど、今、私たちの体を作っている細胞にちょっと手を加えることでいろいろな−例えば皮膚の細胞だったものが神経の細胞に変われるような能力を取り戻させてあげるということができるんですね。そういうふうにして作られた細胞のことをiPS細胞、全部英語でいってしまうと長いので、省略してiPS細胞と呼んでます。
ふ〜ん。これは、これからキッズたちも覚えておいたほうがいいキーワードですかねぇ。

はい。ぜひ覚えておいてほしい言葉です。
すごくメジャーになってくる言葉なんですね。

そうですね。最初にニュースに一般的に出てきたのは3年前、ちょっと専門的な方は4年ぐらい前に知ってると思うんですが、もう毎週のようにニュースに取り上げられる言葉なので、iPS細胞という言葉だけちょっと覚えてもらえるとニュースが楽しく読めると思います。
iPS細胞は何に役立つのでしょうか?

もともとこの細胞を開発したのは、京都大学の山中伸弥先生という…。
ノーベル賞の山中先生。

そうです。ノーベル賞候補ということで、山中先生のお名前を知ってる方もいらっしゃると思うんですけれど。
まだ取ってなかったんでしたっけ?

まだです。
そうか。最後まで残ってるんだけれど、まだ候補なんですね。山中先生がiPS細胞を作った人ですね。

そうです。山中先生はもともとお医者さんでいらして、医療で治せない病気があったりというご経験をされた。そこを何とかできないかということで、臨床といって実際に患者さんに携わるのではなく、研究することでいろいろな治療法を開発できないかと研究されてこの細胞を生み出したということです。
治らない病気はガンとか?

治らない病気はほんとにいろいろあるんですけれど、ガンもそうですし、アルツハイマーもまだですね。薬はありますが、完全に治すための薬ではないですし…。
アルツハイマーね。

それに、ほかにもケガをしてしまって体の一部が失われることもありますし、いろいろな病気やケガはまだまだ治せないものがあるんです。
その治せない病気に対して、ひょっとしたら治るんじゃないかという可能性を秘めてるのがiPS細胞ということですか?

そうですね。すぐ治せるというわけにはいかないんですが、治療法を研究するとか、どうしてそういう病気になるんだろうというメカニズムを調べるのに非常に役立つ細胞です。
ラジオの前のキッズは今、夏休みだから、例えば外へ出たときに、すりむいてケガをすることがある。でも、ツバをつけとけばだいたい治るもので、2週間もすれば、だいたい治っちゃいますよね。これも細胞のおかげで治ってるということですよね。

そうですね(笑)。
爪が伸びたり髪の毛が伸びたりするのも、細胞のおかげで伸びてるわけですよね。

そうですね。
で、その細胞とiPS細胞は一緒じゃないんですか?

細胞という意味では一緒です。例えば顕微鏡でずっと見ていくと、すごく小さい粒々のようなものでできていることがたぶん分かると思うんですが、その細胞はみんな同じではないんです。例えば神経細胞は神経細胞の特別な形と能力を持ってますし、筋肉細胞は筋肉細胞で伸び縮みするような仕組みをちゃんと持っていたり、役割分担しているんですね。
ちなみに神経細胞は、脳みその中にあるんですか?

脳みその中にもあります。例えば手を切った時に痛いですよね。それは皮膚のちょっと下のところまで神経細胞が伸びてたりするからなんです。
指の先にも神経細胞と筋肉細胞といろいろな細胞があって、人間を形成しているということですか?

そうです。いろいろな細胞が種類分けすると、人間の場合には200種類以上あるといわれています。
へぇ〜。でも、その細胞すべてが再生可能、ケガを治せたりするわけではない。

ではないです。例えば皮膚の細胞だったら皮膚の細胞のまま一生終える、というと変ですが、一度皮膚の細胞になってしまうと、そこから「神経細胞になりたいな」といってなれるものではないんです。
ほうほう。

でも、このiPS細胞は、逆にいうと役割がまだ何も決まってない状態なんですね。だから、そこに手をもう一度加えてうまく育ててあげると、神経細胞にもなれるし筋肉細胞にもなれるし、皮膚の細胞にもなれる。ほかにも内臓の、例えばすい臓の細胞になったり肝臓の細胞になったりというように、まだ運命が決まってないのでこれから個性を発揮できる細胞なんです。
わかりやすくいうと、腎臓が2つあって移植手術で腎臓が2つともダメになった人のために1個移植します。でも腎臓が1個でも人間は生きていけますよといわれてるけれど、腎臓という細胞は再生できない。切り傷みたいに治らないわけですね。

そういうふうにはいかないですね。
このiPS細胞を研究することによって、腎臓を1個とられた方でも、もう1個再生することも夢じゃないということですか?

そうですね。腎臓の細胞を育てて腎臓をということはできるんですが、ただ腎臓はすごく、いろいろな細胞が協力し合ってできている。皮膚も表面のはがれてくる表皮の部分と、その下に真皮といわれている部分がある。いろいろ複雑なので、すぐに腎臓ができるというわけではないですけれども。
う〜ん。

腎臓を作っているいろいろな細胞を、今はiPS細胞から作り出すことを研究しているところですね。
そもそもiPS細胞は顕微鏡で見えるんですか?

見ることができます。
例えば、人間の細胞でも筋肉細胞とiPS細胞だったら、どう違うんですか?

筋肉細胞はどちらかというと細長くて繊維みたいな形をしてる。実際、細胞の中に細い細〜い繊維が入ってるんですね。でも、iPS細胞の場合はそういう役割が決まってない、形が決まってない。
アメーバ状の細胞ですか?

アメーバ状というとピロッと広がったりとか、またそれはそれで機能を持っちゃうんですが、例えば普通にシャーレーの中で育てているとモコモコモコッと丸っこく育つような感じの細胞です。
えぇ〜、不思議。見た〜い! 森田さん、見たことがあるんですか?

はい、写真で。
見た〜い! えっ、もう時間。めちゃくちゃ短かった。僕も勉強させてもらったので、森田さん、来週このiPS細胞でどんなことができて、どういうふうに使われるのか、近い将来の展望もうかがってよろしいですか?

はい。どこまでしゃべれるか頑張ってみます(笑)。
大村も夏の自由研究のテーマにしよう。ということで、今回のサイコーは、日本科学未来館・科学コミュニケーターの森田由子さんでした。ありがとうございました。

ありがとうございました。
今週はちょっとサワリだけだったんですが、簡単に取り出せる細胞だけど、そこからiPS細胞の抽出はすごく希少というか数少ないそうです。これを病気の治療に使えるという話ですが、興味のあるキッズはお台場の未来館で映像、アニメでiPS細胞を詳しく紹介しています。未来館、よかったら行ってね。ドームシアターです。それじゃ、また来週も夏休みの期間中、夕方5時半に会いましょう。バイバイ!