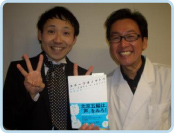キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回もフランス語だというオノマトペをご紹介します。スポーツで使われる擬態語、擬音語のこと。この1週間、僕もいろいろなところで声を出してましたが、けっこうそれが筋肉を助けてくれることがよくわかりました。有名なスポーツ選手がどういう時にオノマトペを使うのか? この後、サイコーに聞いてみま〜す。
今週のサイコーもわざわざ岐阜からお越しいただきました、朝日大学の藤野良孝先生です。こんばんは。

こんばんは。
ありがとうございます、遠くから。今週も水玉のネクタイを2本つけて、おしゃれな藤野先生。

ありがとうございます。
藤野先生は、手品師の人みたい。袖からハトとか出てきそう。

出てきたらいいですけれど(笑)。用意しておりませんでした。
さて、フランス語で擬音というオノマトペ。先週は、スポーツ選手は擬音効果によって、実はパフォーマンスが向上するという話を聞きました。卓球の福原愛選手のこととか、野球の選手もバチンと打つとか。そういえば昔、長嶋茂雄さんが、「フワッと来たボールをカッとやって、パチンと打ってピョーン!」というような指導方法をしてたんですが、あれもオノマトペなんですかねぇ?

あれが“スポーツオノマトペ”でして、私の研究の一番の着想になってます。
えっ、長嶋茂雄さんが先生の研究の入口?

そうなんです。
ほんとですか(笑)?

監督が「スパーン!」とか「グッ」というと、選手がうなずいていたんですね。「僕はあまり理解できないと思うんだけどなぁ」と思っていたんですが…。「でも選手はうなずいているから理解してるんだ」と。それで監督の言葉を起点にちょっと調べてみようといろいろ分析していったのが、この研究を始めるスタートになりました。
長嶋さんのいう微妙な英語に着眼せずに、オノマトペのほうに着眼したのが、今の先生にとってはよかったことなのですね。

はい。
なるほど。福原愛選手、愛ちゃんというとやっぱり「サー」ですよね。

「サー」です。
あれもオノマトペですか?

はい、オノマトペです。
基本的に「サー」は1種類ですかねぇ。

「サー」は、実は7種類。
えぇ〜! 愛ちゃんの? 例えば?

愛ちゃんは「サー」をベースにして、2回連続する「サーサー」。
聞いたことない。えぇっ!?

あと、3回連続する「サーサーサー」。
「サー」、「サーサー」、「サーサーサー」。

そして、「サーサーヤー」というのが。
「サーサーヤー」。

はい。そして、「サー」、ひと呼吸置いて「サー」。
へぇ〜。

あと、「サー」ひと呼吸置いて「サー」、またひと呼吸置いて「サー」。そして、「サーサー」ひと呼吸置いて「ヤー」という、合計7タイプの「サー」があります。
使い道が違うんですか?

はい。この音は、心理的状況や感情の変化によって異なります。愛ちゃんが試合でのっている時は「サーサーサー!」と何回も重複して、感情が入ると「サー」が増えたり。もう苦労して苦労してようやく点を入れた時には「サーサーヤー!」というふうに、ガッツポーズの「ヤー!」が同時に出るんですけれど、そういった感情の変化によって音がどんどん変わってくるのが愛ちゃんの「サー」の特徴です。
知らなかった。だってポイント取ったら「サー!」ってガッツポーズをしますよね。あれだけじゃないということですか?

あれだけではございません。
ヘぇ〜。それは実際、先生が愛ちゃんにお会いして当てたりしたんですか?

愛ちゃんにはアポイントメントがなかなか取れずに、試合を何回も何回も洞察した結果、一言一句全部メモにしていったら合計7つあったということです。
使いわけてる。

使いわけていることがわかりました。
へぇ〜。ほかにオノマトペを使ってる人は誰ですか?

ソフトボールの上野選手が…。
ピッチャーの?

そうです。ピッチングの瞬間に「ヨイショ!」と発声しまして、投球のリズムとタイミングを取っているということです。
僕らも「よいしょっ」とやりますが、あれはオノマトペですか?

はい。あれは非常にオノマトペに近い、“スポーツオノマトペ”という意味で。オノマトペといったらちょっとオノマトペの研究者からいわれてしまいそうなので、“スポーツオノマトペ”として「ヨイショ!」は含めています。
上野投手のは、ね。僕らの生活の中で「どっこいしょ」というのは、“スポーツオノマトペ”の範ちゅうではないということですね。

あれも“スポーツオノマトペ”の範ちゅうにして…。
入ってる?

はい。
「どっこいしょ」ということによって、パフォーマンスは上がっているわけですか?

上がっています。
無言で椅子から立ち上がるよりも、「どっこいしょ」と立ち上がったほうが楽ということですか?

そうなんです。大学生で調査もしまして、「よいしょ」と発声するとタイミングとリズムがあるので体が楽に動けるという。
だからだんだん年をとってくると、いちいち行動に音がともなってくる。オノマトペで助けられてる、サポートしてもらってるんですね。

筋肉が低下して声を出すとスポーツ心理学でいうシャウト効果があって、筋力をより最大に発揮する、声を出すことで大きく発揮できるという効果があります。
へぇ〜。

そういった効果もありまして、筋力低下の時は声を出すと、筋肉に弾みがつきますので。ぜひ年をとって筋肉がなくなったら、使われると楽になります。
「どっこいしょ」というのがおじさん呼ばわりされる理由、それは研究の成果で当たってるわけですね、残念ながら。

当たってました。「おじさんくさい」、「おばさんくさい」とか、「誰にも聞かれたくない」とか、ちょっとネガティブな言葉が若者からは聞こえておりまして。
そうですか。ハンマー投げの人たちは、投げた後に叫んでいるじゃないですか。あれって投げる前に叫んでたらオノマトペでパフォーマンスアップする気がするんですが、投げた後に叫んでも結果と関係があるんですかねぇ?

それが投げる前の過程でも空気を吸い込む、音の素を吸い込むので、その声がエネルギーになってるんですね。「ンガーッ!」と出した時、エネルギーが外に出る時に筋力発揮もアップするメカニズムを持ってます。
それでため込んだものが、投げ終わった後でオノマトペという形で出されるということですね。

声がもうエネルギーという単位で考えていただければいいと思います。
なるほど。投げる前にオノマトペのエネルギーを体内に吸収して、投げ終わったら発散してるから、ハンマー投げの選手は事後でも効果があるわけですね。

はい。エネルギーを吸い込んでお腹にグッとためて、投げると同時に「ンガーッ!」と腹筋を使ってエネルギーを解放させる。そうすると筋力のシャウト効果が−だいたい人間というのは3割ぐらい余力を残してるんですが、それを解放させるので限りなく100パーセントに近い力を発揮することができます。
人間って一生懸命やっているけれど、実は余力は3割残ってるんですか?

そうなんです。脳がブレーキさせちゃう。
えぇ〜?

100パーセント出してしまうと体の骨とか筋の繊維がこわれてしまうので、人間は脳でブレーキをかける。
へぇ〜。じゃあ、“火事場の馬鹿力”は、その3割が加わって思わぬ結果をもたらすこともあるということですね。

そうです。
オリンピックの選手も実はブレーキをかけてるから、3割のエネルギーを出してないんですか?

そこで、“スポーツオノマトペ”を使うことで潜在的能力を大きく発揮できる可能性が…。
100に近づけるということ?

はい。
すご〜い! 声を出す効果はそこまで!

そうなんです。
確かに事後だったら、ピッチャーでもボールを投げ終わったら「ウッ!」といいますよね。あれもため込んだパワーを投げ終わった後に出しているということですね。

はい。
じゃあ、声を出すのはいいということですね。

声を出すことは、運動パフォーマンスで絶対にいいことです。私はいつも推奨しております。
日常から声を出していこう。「よいしょ」、さぁ座るか。「あ〜っ」といって、そしていちいち「ウワーッ」とかいう。おっちゃんくさいけど“あり”ということですよね。

“あり”でございます。
いや、すごい! ありがとうございました。今日、岐阜に帰るんですか?

そうなんです。切なくなっちゃいます。
僕も切なくなってきて、ポロリンですよ。

もう涙ポロポロですよ。
ポロリ〜ン。ありがとうございます。今週のサイコーも岐阜の朝日大学の藤野良孝先生でした。

ありがとうございました。
2週にわたって藤野先生、番組史上最高の“不思議ちゃん”サイコーだったね、助手(笑)。ほんとに、オノマトペをさんざん語ったと思ったら、趣味はスイーツの食べ歩きですって。これもまたすごくて、めちゃめちゃ詳しいんです。また会いたいなと思っちゃいました。それじゃまた来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。僕は「どっこいしょ」!