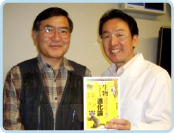キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。今、日が暮れて、この時季一番きれいだね。クリスマスまであと1週間でしょ。来週の今頃はクリスマス終わっちゃう雰囲気で、このクリスマス直前の1週間が何か一番いいなと思うんだよねぇ。でも終わったらお正月があるからいいか。お年玉もあるしね。 さぁ、今回も生き物の進化を取り上げます。先週お話を聞きました。都会の生き物は、都会の環境に合わせて進化、それから順応するという話だったんですねぇ。この後、もっと詳しい話を聞いていきます。お知らせの後、サイコーの登場です。
今週のサイコーも、シェアリングアース協会代表の藤本和典さんです。こんばんは。

こんばんは。
藤本さんは、技術評論社から『生物いまどき進化論』という本を出版されてます。都会の生き物はその都会だけで進化しているという話を先週うかがいましたが、この中で「ツバメはクリーニング屋さんが好き」というのがあるんですけれど、これはどういうことですか?

人の出入りがあるところはカラスとか外敵が来ない。ということで、軒下にかけたほうが安全ということなんです。
ツバメの巣は、確かに人の家の軒下にありますよね。

はい。元々は岩棚とか崖のところに巣を作っていた。ところが人間が家を作り出したら、「ここはカラスとか来ないな」と何となく気がついたんですね。それで、そこに土を持ってきて巣を作った。
じゃあ、ツバメは人間よりカラスのほうが怖いということですか?

とっても怖い。
えぇ〜! 人間のことは怖くないんですか?

ツバメが巣を作ると幸福を招くという昔からの言い伝えがある。そうすると、ツバメが来るとみんな大喜びなんですね。イタズラをしない。
ツバメもそれが分かるんですか?

何となく分かる。早いんです、それが分かるのが。
いわゆる学習能力というものですね。

最近、脳学者の先生にお聞きしたんですが、世界的に鳥は頭がいい、研究しようという風潮だそうです。
へぇ〜、ほんとですか?

例えばハトを置いておいて、絵がある。この絵と、また別の絵がある。その画風をハトは感じるんですって。だから、「これとこれは同じ」と当てる。同じ絵じゃなくても画風、絵を描いた人のものか分かるそうです。
いわゆる絵の機微みたいなものが分かる。

そうそう(笑)。
頭がいいといったらイルカや犬で、鳥は脳みそがちょっとしか入ってないというイメージが…。

いえいえ、飛ぶからそれだけでも小脳が発達してますよね。
なるほど。

それによって目の発達もすごいですし、すばらしいんですって。
本題で、何でクリーニング屋さんですか?

実は不動産屋さんには、あまり来ない。
何でですかぁ?

不動産屋さんは、そんなにお客さんが出入りしない。クリーニング屋さんは1日にだいたい何百人と来ますよね、はやっているところは。そういうことをちゃんと知ってるんです。そういうところに巣を作る。
危害を加えられないということを?

そう、知ってるんです。
すご〜い! クリーニング屋さんが超清潔で、こんなツバメの巣を追っ払えという家主かも知れないですよ。

すごく少ないですね、率として。
クリーニング屋さんは、基本的にツバメ好きですか?

昔から、巣を作るということで家が幸福になることを知っている。
人間そのものの言い伝えで?

昔からの伝わりがあるんです。
へぇ〜。

ところが、それが最近途切れてきた。そしたら、どうなったと思います?
えぇ〜、じゃあ…。

ある私鉄の駅などは落とすんです。
えっ、どういうことですか?

お客様にフンが落ちるからと。私はその駅へ行って話したら、聞いてくれなかった。それでもまだ落とすと。
へぇ〜。

「小さい100円のビニール傘、あれを下に置くだけで大丈夫ですよ」といろいろ全部教えたんですけれど。仕方なく総務部や広報にも連絡して、私は「ラジオの番組とか本を書いたりする時にお宅の会社名を出してもいいですか?」といったら、「いい」といってくれた。
そしたら?

いっちゃいけないでしょ、今(笑)。
いっちゃいけないけれど、それは私鉄の人からすると「嫌な藤本さんだな」と思われてるかもしれない。

それでも、鳥のためには。
ということですよね。

ほかのところ、湘南のほうを走ってる私鉄の会社などは、すぐにツバメの巣を落とすのを止めてフン受け台を作って助けるようになりました。
これは、やっぱり都会ならではの進化論の過程ですか?

そうですねぇ。やっぱり人との関係で上手に生きていくのが都会的な関係の大きなひとつですね。
都会と生き物というと丸の内のカルガモ、あれは三井物産の女性社員が“カルガモレディ”というのを代々やってて。もうカルガモブームからずい分経つけれど、まだ“カルガモレディ”の五代目がいらっしゃるんですよ。

あそこのカルガモの一番初めのエサと隠れ家を作ったのは、私です。
えっ! 90年代ですか?

はい、一番初めに。
すご〜い! じゃあ、カルガモの皇居前のお堀から三井物産の池までの横断も見ているんですか?

その時は職員で野鳥の会にいたので見られなかったんですが、頼まれて「エサは何ですか?」とか聞かれた時は、全部教えました。
カルガモの都会ならではの親子の横断も、やっぱり進化の過程で独特のものですか?

まぁそうだと思うんですが、一番問題はカルガモ自身がカルガモじゃないんですよ。
何でですか、あれはカルガモでしょ?

三井物産には悪いんですけどね。当時、今はあまりないんですがアヒルのヒナを露店で売ってましたよね。夜店などで買って帰った人が、たくさん食べるしウンチをたくさんするから大きくなると飼いきれなくなっちゃった。それを近くの池とか川に放した。
東京で?

そしたら、野生のカルガモと結婚しちゃった。
じゃあ、アヒルと本当の野生のカルガモの間にできたのが都会のカルガモたち?

代々するうちに、カルガモの色にみんななってるんです。
へぇ〜。

四代目ぐらいには、完全にカルガモの色。
ちょっと待ってください。東京には純粋なカルガモの子孫はいないんですか?

少ない。
えぇ〜、知らないよ、そんなの(笑)。

見た目はカルガモですけどね。アヒルは元々マガモで、マガモは野生のカモ。
ちょっと待って。アヒルはアヒルじゃないんですか?

マガモです。マガモを飼って、大きくして飛べなくなったのがアヒルなんです。
じゃあ、アヒルとマガモは似てるんですね。

遺伝子は同じです。
ヘぇ〜。

みんな見ると、井の頭公園や石神井公園にいるカルガモが「ちょっと違うな」とか「大きいなぁ」とか、「羽根の色がちょっと薄いなぁ」とか「この頭はマガモに似ているな」というのがずい分います。
先週お話いただいた各公園、緑地ごとに個体の生態系みたいなものもあるというのは、そういう話ですかねぇ。

これは飛ぶので混じっちゃいますけどね。
すみません、カルガモ飛ぶんですか!?

カルガモ、飛びますよ。
飛べるんですか。じゃあ、何で道路を渡るんですか? 飛べばいいのに。

いや、それはできないです。ヒナが飛べないから。
なるほど。

ヒナに合わせて渡るんですね。
大人になると飛べるんですか?

十分飛べます。
知らなかったぁ。

半年後ぐらいは、普通に親と一緒に行動してます。
へぇ〜。

成長も非常に早い。
あと、ヤモリの話があって、今ヤモリを知ってる子どもたちは少ないと思うんですが、漢字では家に守ると書いて・・・。

イモリと間違えちゃうんですね。
そうそう、イモリはお腹が赤い。ヤモリはトカゲみたいな。

ヤモリはトカゲみたいなので、は虫類です。イモリは両生類。
そうなんですか!?

まったく別です!
お腹の赤いほうは両生類のイモリ。

はい。井戸を守る、泉を守る。ヤモリはは虫類で、全身が灰色っぽい茶色ですね。それでちょっと色が変わったりします。日向に置くと白っぽくなったりとか、色を変えることもできます。
へぇ〜。

これは家の周りにいて、すき間に入って生活をしてるので、“家を守る”でヤモリ。
ヤモリが現れると縁起がいいって、ツバメじゃないけど言われてましたよね。

はい。
今、都会でヤモリはいます?

いるんです。
えっ、どこにいるんですか?

荻窪のほうのある鳥好きの方で、二階のベッドの窓にヒヨドリが巣を作った。23センチぐらいの鳥が何のエサを持ってくるか見てたら、一番多いのはヤモリでした。
ヒヨドリは、ヤモリをエサにするんですか? ヤモリを食べちゃうということ?

食べちゃいます。
その辺にヤモリがいっぱいいるということですか?

そう、上手に見つけてきますねぇ。
へぇ〜。都会のヤモリの進化的な特徴は何ですか?

一番は、やっぱりエサですね。
何を食べるんですか?

元々は小さなガが大好き。
ガ?

だから電灯のところにやってきて、昔はヤモリがくっついていた。
そうなのかぁ。

今は都会にガが全然いないんですよ。
僕はヤモリを見たの、家もそうだし、夜、誘蛾灯みたいなところにヤモリがくっついてた。

ところが今いなくなっちゃったので何を食べるかといったら、彼らはかなり増えているんですけどアブラムシの子ども。
アブラムシって東京にいるんですか?

アブラムシって、ゴキブリ。
えっ!

ゴキブリの子ども。特にチャバネゴキブリの子どもをどうも好きみたいです。
ヤモリが?

こんな小っちゃいんですけどね。
それはどこにでもいそうですね。

はい。これをエサにして、東京の都心部でもいます。また卵も産んでます。
へぇ〜。本来のヤモリは、ゴキブリの子どもなんか食べなかった。

食べなかったでしょうね。
じゃあ、これは都会のヤモリの特徴ですね。

しょうがないなと食べてるんだと思います。
それこそ青森からヤモリを東京へ連れてきたら、ゴキブリの子は食べないですよね?

知らないですね、それは確かに。
じゃあ、これは東京ならではの独特の嗜好品ということですね。

というか、南西日本にかけてはそういう形になってると思います。
へぇ〜、分かりました。もうこんな時間です。2週にわたってありがとうございました。今週のサイコーは、シェアリングアース協会代表の藤本和典さんでした。

ありがとうございます。
僕んちの近くに葛西臨海公園という野鳥の楽園みたいな場所があるんですけど、「何でここにこれだけの鳥たちが集まってくるの?」という話を藤本さんに聞いたら、それは藤本さんが鳥たちが集まるような木を植えたり、環境を整えたという話なのね。葛西臨海公園を藤本さんがプロデュースされたという話を聞いて、すごい方だったなと。いなくなって今頃いったら遅いかなぁ。でもね、おもしろかったなぁ。ということで、バイバイ!