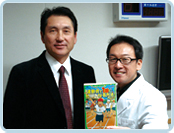キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今日はずばり運動会のかけっこで1番になる方法ということで、すごいサイコーが来られているんです。以前に「スポーツも科学だよ」という話を聞いたことあるんだけれど、まさに科学的な見地から「みんなのかけっこを速くしちゃおう!」という話です。お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
今週のサイコーは、東京大学大学院教授の深代千之(フカシロセンシ)先生です。こんばんは。

こんばんは。
先生は、東大の大学院の先生ですか?

大学院でも教えてますね。
ということは、日本で1番頭のいい人たちに教えているんですね。

いやぁ、一応そうなってますけれど(笑)。
すご〜い! しかも、先生は角川つばさ文庫、いわゆる児童書の中で『運動会で1番になる方法』という本を出版されてます。これは興味深い! 大人でも読みたくなっちゃうんですが、バイオメカニクスというジャンルを研究されている。

そうです。
東大でスポーツを教えてらっしゃるということですね。

スポーツを教えて、理屈を研究しているということです。
スポーツの理屈?

そうですね。
これがバイオメカニクス?

メカニクスなので、力学的な観点から見るということですね。
この番組は科学番組で…。

ちょうどいいですね。
ちょうどいい、そうですか。具体的にはどういうことですか?

ビデオやモーションキャプチャという機械を使って動きを分析して、走っている人や投げてる人がどんな力を入れて動作を作っているかを解析し、わかったことをこれからうまくなろう、速くなろうとしてる人たちに教えてあげるということですね。
ちょっと待ってください。まさに今、小学生たちって春に運動会をやるんで、あと3ヵ月後ぐらいには運動会がやってきますよ。これから速くなろうという子どもたちには…。

そのコツがわかってきたんですね。
そうですか。コツはラジオでも伝えられますか?

コツは、まぁまぁ伝えられると思います。
そうですか。例えば2008年の北京オリンピック、日本が400メートルの男子リレーで銅メダルを獲得しましたよね。

昔はマラソンだと勝負できたんですけれど、短距離であそこまで勝負できることはなかったんですね。
はい。

いろんな要件があるんですけれど、ひとつは私たちの科学的な成果をコーチを通して選手に伝えていったことがあると思いますね。
北京オリンピックの日本の銅メダルは、バイオメカニクスのたまものだったんですか?

たまものということが、ひとつあると思います。
へぇ〜。

選手に走り方を教えたことと、リレーはバトンパスが命なんですね。そのバトンパスで、いかにロスをしないようなことをどうやったらできるかもやってあげました。
バトンね。いわゆるチームワーク、コンビネーションですよね。

アメリカとかそれぞれが強いチームは、バトンパスを練習しないんですよ。ですから、つけ入るすきがあるんですね。
それもバイオメカニクスの一部ですか?

はい、そうですね。
もともと日本人は、黒人の人に比べて身体能力が劣るといわれてるじゃないですか。

そうですね。
あるいは「かけっこが遅いのは、お父さんもお母さんも遺伝だから」というふうにいわれてますが、実際のところどうですか?

ボールを投げるとか鉄棒で逆上がりや前回りするとかいろいろな運動能力がありますが、これはほとんどが生まれてからやるかどうかです。
遺伝は関係ない!?

遺伝は関係ないです。
へぇ〜。

すごく高くなって日本のトップになるとか、世界で勝負するような時になったら遺伝がきいてきます。
う〜ん。

だから、普通の子どもたちは“やるか、やらないか”だけです。
ということは、オリンピックでメダルをとるには遺伝が関係あるかもしれないけれど…。

少しあります。
運動会で1番をとるには、遺伝は関係ない。

ないです。
素晴らしい。そうですか。黒人に比べて黄色人種は身体能力が劣るというのはどうですか?

劣るというかちょっと不利な面がありまして、日本人をはじめとしてアジア人は米を一部の地域に植えて、そこで定住して生活することが基盤でした。動かないことが基盤だったんです。
はい。

ヨーロッパの人たちは騎馬民族とか狩猟民族といいまして、獲物をとったり、獲物から逃げるというフットワークがいいことをベースに生活を築いてきた。だから動くことがいいヨーロッパ人と動かないことがいい日本人が、動くことで勝負すると不利な面があったわけですね。
すごい理論ですねぇ。へぇ〜。僕は子どもの時から速く走りたいと思いながらも、長距離のほうが得意だったんです。マラソンがすごい得意で、短距離はいまいち伸びなかったんですね。これは筋肉なのか肺活量とか持久力…、どう違うんですか?

-
ひとつは筋肉の質ですね。筋肉の中に大きくわけて2つの筋線維があって…。
線維?

-
筋線維は、髪の毛ぐらいの太さです。束になってるんですが、1つの種類は白い筋肉で速く縮む。
白い筋肉?

-
ええ。速い筋肉と書いて速筋(ソッキン)といってます。もう1つは赤い筋肉で、速く縮まないんだけども疲れない。持久力がある筋肉です。
はい。

-
魚で例えるとわかりやすいんですが、白身の魚は何ですか?
ヒラメとかカレイ。

-
そういう魚たちはどこに住んでます?
えっ、わからない。海の底ですか?

-
海の底ですが、陸に近いところの近海に住んでます。
あっ、そうなのか。

-
近海魚といって、いつもは静かにしていて、エサが来るとシュシュッと取ってシュシュッと帰ってきて休んでいる。シュシュッは速いわけです。
はい。

-
赤い魚は何ですか?
マグロ、カツオ。

-
そういう魚はどこを泳いでます?
マグロは遠洋漁業だから、遠いところだ。

-
回遊魚といって、ずーっと泳いでいて疲れない。
だから赤身で、赤い筋肉ということですか?

-
そうなんです。
すごい!

-
僕たちも赤と白の両方必ず持っていて…。
でも切り身にしたらヤダ。死んじゃうもの(笑)。

-
ハハハハ。それはだいたいわかっていて、ひとつは遺伝がききます。遊びの中で短距離が速いとか長距離が得意とか、どっちが得意かわかってきますよね。
はい。

-
そのタイプと、お父さんお母さんを考えてみてください。
はい。

-
似てますか、似ていませんか?
はぁ〜。

-
似てる、というのがだいたい多いです。遺伝がきいているので。似てないという人も出てきて、似ていないのは生まれてからのトレーニングの仕方が親御さんと違っているということなんですね。
なるほど。トレーニング次第では、速筋遅筋の持ち主でも遺伝は関係なくトレーニングの仕方で遅筋も速筋に変わる可能性がある?

-
変わらないんですが、割合が変わってきます。トレーニングをすると筋肉は太くなりますよね。
はい。

-
あれはどっちが太くなるかというと、白いほうの速筋なんです。筋骨隆々の人は速筋が太くて、だから瞬発力があるわけです。
なるほど。

-
逆に長距離トレーニングをしている人たちは、赤いのが太くなるかというとそうではなくて、白いほうが縮む。相対的には赤いほうが多くなって、長距離に適した体になるということですね。
へぇ〜。

-
そういう特性が違うということです。
なるほど。

-
だから、そういう特性を見てあげることと、うまく鍛えれば速く走れる体になって、前の自分より必ず速く走れることをちゃんと教えてあげたい、ということがこの本の内容です。
すごい! ちょっと講義みたい。先生、とりあえず宿題として3ヵ月後の運動会に向けて来週までにキッズたちがやっておくことは何ですか? トレーニング方法をひとつ教えてください。

-
まずは、まっすぐ走れない子がいます。20センチぐらいのあいだを取ったひも、あるいは線を引いて左右でちゃんと歩く。その後、その線の上を走る。まっすぐ後ろに蹴るということが1つです。
20センチのレールみたいなところをまっすぐ走る。それが練習。

-
もう1つ、運動会だと周りに人がいて緊張しちゃいますよね。周りに勝ちたいと相対的なことで走っちゃいますけれど、そうではなくて自分のことだけを考えて走る。この2つですね、まずは。
はい、わかりました。よし、僕も1週間がんばります。来週またうかがいますね。

-
はい。
今週のサイコーは、東京大学大学院教授の深代千之先生でした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
いやぁ、白い筋肉と赤い筋肉があるなんて知らなかったなぁ。僕、個人的には白い筋肉が欲しかったなぁ。助手はどっち、赤、白?
助手1:赤です。
助手2:赤です。
赤なの、同じだねぇ。そうか、わかった。体幹を鍛えるのが大事なんだね。さぁ来週までに20センチの幅に合わせてまっすぐ歩く練習、みんなもしてみてね。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなもまっすぐ歩く練習だよっ。バイバイ!