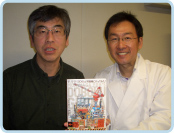キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、3月に入りました。ところで、みんなは「土木」という言葉を知ってる? 土と木と書いて、土木といいます。工事のイメージね。土木って何なのかって考えたことないでしょう? 意外に土木って僕らの身近な世界なんだって。お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
今週のサイコーは、私の母校、法政大学のデザイン工学部教授の溝渕利明先生です。こんばんは。

こんばんは。よろしくお願いします。
先生、僕は法政出身ですけれど、工学部系の友だちは誰もいなかったんですけどねぇ(笑)。

離れてますからねぇ、やっぱり。小金井というところにありますから、なかなか市ヶ谷までみなさん行くこともなかったものですから、申し訳ございません(笑)。
溝渕先生は土木のご専門ということで、これねぇ、アスペクトという出版社からイラストレーターのモリナガヨウさんがイラストを描いて、『モリナガ・ヨウの土木現場に行ってみた』という本の監修などもなさっています。この本がおもしろい!

ありがとうございます。
写真とモリナガヨウさんのイラストをまじえながら、こういう難しい大きな工事現場はこうやってできてるんだという。

そうなんですね。
すっごくわかりやすい! ちょっとお見せできないのが残念ですけれど。土木は、建築とは違うんですか?

-
みなさんに必ず最初に聞かれる言葉です。入学してくる学生も、土木と建築の区別がつかない。いってみますと、土木は土から下のものをつくっていると思っていただければ…。そして地上から上の建物、つまり箱物ですね。建物をつくっているのが建築だと思っていただけると一番いいかなと。本当はそんな区分けではないんですが…。例えばそうすると、橋はどうなるのか?実は橋は土木なんですけれど、みなさん建築だと思ってますよね。
じゃあ、車輪の下、車などの下は土木ということですかね。

-
そうですねぇ〜。微妙なんですよ。
では、地盤を支えているのが土木ということですかね?

-
私が必ずいうのは、みなさんの生活を支えているのが土木。
おぉ〜、いいですね。

-
例えば、大村さんが今朝起きられて最初に何をされたか知りませんけれど、たいてい顔を洗ったりされますよね。蛇口をひねったら水が出てきますね。何で出てくるかわかりますか?
水道管を通して…。それが、土木、ということですね。

-
そうです。
ありがとうございます。

-
スイッチを入れてもそうですね。電気が通るのは、送電線を並べてつくっていく。火力発電所をつくったり、ダムをつくったり、電子力発電所をつくるのはみんな土木がやっているわけです。
そうなんですかぁ。じゃあ、別に地中じゃなくて、発電所とかダムとか…。へぇ〜。

そういうのがみんな土木なんですよ。みなさんが普段あまり感じられないもの、それこそ道路なんて当たり前のように走ってますけれど、あの道路をつくるのもかなり大変で…。
道路も土木ということですね。

はい。
じゃあ、大きいものは土木ですね。

だいたいそう思っていただくといいかもしれません。スケールの大きなもの…。でもビルは大きいし、スカイツリーは建築ですしね。
スカイツリーは建築。

そうです(笑)。
大きいマンションとか、この文化放送の建物は?

-
建築です。
建築、あぁ〜。じゃあ何か人が住まないような、人間があまり行かないようなところの大きな建物は土木とか?

-
まぁ、それもひとつかもしれませんね。近いと思います。
中国の万里の長城は?

-
あれは、土木なんです。
土木、へぇ〜。いいなぁ。

-
もうひとつおもしろいのは、土木と建築ってわけているのは日本だけなんですね。
へぇ〜。

-
ヨーロッパでは、土木はシビルエンジニアリングというんです。こういう建物をつくるのもシビルエンジニアリングなんですよ。日本の建築は、いろいろ混ざっているんですけれどアーキテクトというんです。アーキテクトは、それこそアートとテクノロジーを組み合わせた言葉らしいんですが、いってみればデザインをするのが建築の主体です。海外ではハードの部分はみんな土木です。
ほぉ〜。

-
だから、海外ではシビルエンジニアというと非常に尊敬される。
なるほど。土木って、濁点がふたつあるからいけないんですね。3分の2が「ド」と「ボ」の濁点だから。

-
スマートさがない(笑)。
何かいい言葉があるといいですね。何か考えましょう。

-
ありがとうございます。
溝渕先生、「溝」という字に「渕」でしょう。土木的な名字ですねぇ。

-
そのままかな、と。
ハハハハハ。トンネルなども土木ですから。

-
そうですね。
地下鉄あるいは車に乗ってると、四角いトンネルと丸いトンネルがあるじゃないですか。あれって、どうやって使いわけて、つくる側がどうつくっているか気になるけれど、そこを教えてもらっていいですか?

-
まず穴を掘るのに一番安定した掘り方は、どういう掘り方かわかります?
よく丸っていいますよね。

-
そうですよね。周りから力が均等にかかりますから、ほとんど丸でつくる。なかが四角になっている部分は、埋めてる部分が多いんですよ。
四角く形を埋めてる。

-
そういうのもあるし、四角いものをコンクリートでつくって押し込むというやり方もあるんです。
へぇ〜。

-
あと、海底ですと、こういう箱をつくって沈めてしまってつなげるというのもある。
へぇ〜。

-
羽田に行くトンネルはほとんど沈埋(チンマイ)というんですが、海底に箱を沈めてつくっている方法です。
羽田へ行くトンネルは、京急のトンネルとか?

-
自動車がほとんどですけれど。
自動車の。それは、四角い筆箱みたいなものを?

-
地上でつくって、船で運んでいって沈める。そうやって沈めていってつなげていくんです。
それが海底トンネル。じゃあ、海の中の車のチューブみたいなものですか?

-
そうですね。ほんとに地底を掘る。例えば、青函トンネルは海底の下をずーっと穴を掘っていった。
それは、どういうやり方で掘ったんですか?

-
あれは、昔からいう穴を開けてダイナマイトを入れてボーンと破裂させて、それを集めてというのを順番にやっていく。
穴を掘った後、当然、水とかも出てくるわけですよね。水とか出る前にどうしてコンクリートが固められるのかすごく不思議ですけれど。

-
コンクリートを吹き付けるというんですけれど、瞬間的に固まるコンクリートがあるんですよ。
へぇ〜。

-
普通コンクリートはすぐ固まらないので、だいたい1ヵ月ぐらいかかるんですけれど、それは吹いた瞬間に固まる薬を入れている。
瞬間接着剤みたいなものですか?

-
そうですね(笑)。それを吹き付ける。スプレーをかけてるようなものですね。それがある厚みで吹いていくんですけれど、それでだいたい固めていく。ただ、それだと弱いので、その後にもう一度コンクリートを厚みがあるような形に打ち直すんですね。
ほぉ〜。

-
まぁ仮止めしておいて、最後にしっかりつくるというやり方。フッコウという言葉を使うんが、「覆う」という字に、工事の「工」。
覆う、工事ね。

-
覆工コンクリートというんですが、それできれいになる。みなさん、だいたい見られているのは、そこの部分ですね。最近はあまりお金をかけたくなくて、という言い方ではいけないんでしょうけれど…、例えば、ガリガリガリと掘っていくやり方もあるんですよ。
ドリルで?

-
ドリルで、それこそ漫画で見るような丸い先に刃がついたもので、ガリガリガリと。
ペットボトルのお尻のところに刃を付けて、グルグルグルグル回すような感じですよね。

-
シールドというんです。
シールド。

-
鉄の輪っかで覆いながら、後ろからセグメントというコンクリートのかけらみたいなものをはめ込みながら、輪っかをつくって後ろから掘った分だけ押し込んでいく。
ロボットが掘っていってくれて、それと同時にコンクリートのセグメントというやつをはめ込んで、水が漏れたり岩が落ちてこないようにしてるんですか。

-
今は掘るのもいろいろな形があって、自在に動けて四角に掘れるやつもあるんですよ。
それは同じシールドという工法で?

-
丸いちっちゃなドリルで、腕を伸ばしながらカリカリと掘っていく。完全な四角ではないんですが、丸いような四角いような形ができる。
そのほうが掘る量が少なくて、四角いすみずみまで掘れる。それはまだポピュラーではないんですか?

-
お金がやっぱり高いですね。
へぇ〜。あと、例えば羽田のD滑走路とかアクアライン、ダムの水のせき止めとか、湿っているところで何で土木工事ができるのかがすごく不思議で、来週またお話をうかがってよろしいですか?

-
はい、わかりました。
短い時間でしたけれど、今週のサイコーは、法政大学・デザイン工学部教授の溝渕利明先生でした。ありがとうございました。

-
どうもありがとうございました。
確かに丸いトンネルを地下鉄で見たりしたけど、穴が大きすぎると思う時あるものね。最近の工法では、小さい丸から四隅を広げていくという工法も増えてきているということです。東京も地下鉄網とか道路網が整備されてくると、地下も掘る場所がなくなっちゃうかもしれないからねぇ。なるべく掘る体積は少なくしてもらうに越したことないのかなと思いましたけれど。みんなは土木工事のイメージはできたかな? 僕はかなりよくわかりました。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!