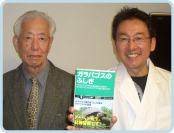キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。みんなは学習机の周辺に世界地図とかある?僕の時代は絶対地球儀があったんだけれど、最近は地球儀を持っているキッズが少ないことに気がついて、地球儀があったらなおいいんだけどね。今日は地球の裏側、南アメリカ大陸があります。南アメリカ大陸の西側、地図では左側ね。島々がいくつかあるんですけれど、その中でガラパゴス諸島、これ興味深い島なんです。そこの専門のサイコーをお招きしています。お知らせの後で〜す。
今日のサイコーはNPO法人日本ガラパゴスの会のメンバーで、東京都立大学名誉教授の小野幹雄先生です。こんにちは。

こんにちは。
いやぁ、凛とした男性が私の目の前に…。

ハッハハ。
ガラパゴスを地図で調べていただくと、南アメリカ大陸の地図の西側の海にガラパゴス諸島があります。これは行きたくてもなかなか行けるものじゃありません。そこに関して、小野先生はいろいろと活動されていらっしゃる。日本ガラパゴスの会とはどういう会ですか?

NPO法人ですけれど、ダーウィンが行って以来、ガラパゴスは進化論の島みたいになっています。
ダーウィンの進化論ですね。

有名な島ですよね。
はい。

毎年、大勢の人が観光で行くようになって、そのために島に住み着いた人たちもいて、けっこう自然が荒れているわけです。その自然環境を何とか守っていこう、世界自然遺産の第1号ですが、荒れもはなはだしいので環境を何とか保護しながら維持し続けていこう、研究の場所だけではなくて観光も秩序のある観光をしてもらおう…と、そういう関係で地域の自然保護はダーウィン研究所というところがやっているんですけれど、その研究所を支援する団体のひとつ−世界に10ばかりあるのですが、そのうちのひとつです。
ガラパゴスの生き物というと、何かサイみたいな色のネズミ色した生き物で、は虫類系とかカメとか、小さい恐竜みたいなひと昔前の生き物みたいなイメージが非常に強いんですけれど、そこを研究するのではなくて、ガラパゴス諸島に観光客が足を踏み入れるので自然を守りましょうという団体なんですね。

はい、そういう団体です。
先生はガラパゴスは何度も行っていらっしゃる?

4、5回は行っています。
最初に行かれたのはいつですか?

1959年です。
わぉ!

50年以上は経ってますねぇ(笑)。
半世紀以上前にガラパゴスに行った日本人が先生!

一人じゃないです。東京水産大学の調査団で、水産大は船を持っていますのでその船で出かけた中の一人だったわけです。
日本から船でガラパゴス諸島まで行ったんですか!

ずいぶんかかりましたよ。
だって地球の裏側ですものね。

それに近いですね。
どれぐらいかかって行ったんですか?

10月の初めに出て、向こうに最初に着いたのが12月の半ばぐらい。
2ヵ月半ぐらいかかったということですか(笑)。

途中ハワイに1週間ぐらいいたということもありますけどね。水産大学の船は海洋調査のために緯度と経度に沿って動くようなことをするので、けっこう時間がかかります。
なるほど。今でこそガラパゴス諸島というと生態系の貴重な勉強になるとか、いろんな自然が残っていることで知られてますけれど、52年前のガラパゴス諸島は世界的にはどういうポジションだったんですか?

やっぱり進化論以来、あそこの生物は世界でも独特な生物がいるということで、日本でも「ガラパゴス現象」という世界的ではないユニークな場所という意味で使われてますけれど、そういう場所であったということは違いないですね。
ガラパゴスはどういう意味なんですか?

もともとはあそこに住んでいるゾウガメのスペイン語の名前。
そうなんですか! へぇ〜。ガラパゴスの象徴的な生き物がガラパゴスということになりますよね。

ガラパゴ、つまりゾウガメですね。
へぇ〜。ガラパゴにS(エス)をつけ複数形にしてガラパゴス?

ええ。ガラパゴス諸島という名前は、英語の名前としてずっとありました。ただ正式な名前ではないですよね。
正式名称は何ですか?

正式にはコロン諸島といっているはずです。
コロン諸島、へぇ〜。

エクアドルが領有して以来、英語を何となく嫌って、コロンブスが南米を発見してますでしょ。ですからコロンブスの名を取ってコロン諸島という言い方をしてます。
もともとはコロン諸島だけれど、アメリカがガラパゴス諸島という名前をつけたということですか?

いえ、アメリカ以前にイギリスの人たちが使ってたでしょう。ですから、ダーウィンが行った頃もガラパゴス諸島でした。
もともとはコロン諸島なんですね。どれぐらいの広さですか?

-
意外に大きな島がありまして、地図で見ると豆粒みたいに描くのですが、小笠原などと比べると100倍近く大きな島ですよ。
へぇ〜。

-
一番大きな島は、房総半島1個ぐらいありますし。
千葉県の?

-
ええ。
イサベラ島が一番大きいと聞いてますけれど。

-
ほぼそれぐらいあります。
ちっちゃいものは、ちっちゃいんですね。

-
全部で50ぐらいの島があって、人の住んでいるところとか、あるいは10平方キロ以上の島などは数えると10あまりあります。全部で50ぐらい。
50ぐらいの島からなっていて、国はエクアドルになるわけですよね。

-
はい。
エクアドルって赤道という意味?

-
はい。赤道の直下で。
赤道近くのこの島で何で自然が残されているのか。ハワイだって赤道の近くだし、赤道の近くはいっぱい島がありますよね。何でガラパゴスだけが昔ながらの生態系が残っているんですか?

-
必ずしも昔ながらずっと続いているわけではないです。ずいぶん人が入って、けっこう壊してますけれど、それにしてもやっぱり遠くて行きにくいことがあるでしょうね。ハワイと違って、そう毎日飛行機がたくさん飛んでいくという状況ではないですから。現在では定期便が毎日ありますけれど、それにしてもガラパゴスを目的にした人しか来ない。そういう状況です。
観光のためだけしか人は来ないんですか?

-
観光のため、あるいは研究者もいますし、それからマスコミがけっこう入れ替わり立ち替わり世界から行っている。
テレビ番組をつくったりとか?

-
はい。
人は住んでないんですか?

-
住んでますよ。今、2万5000人ぐらい住んでます。
人はいるんですね、へぇ〜。すごく疑問ですが、この島で独特の生き物がたくさんいるわけですよね。何で独特の生態系が生き残っているんですか?

-
ひとつは天敵がいなかったということでしょうね。
なるほど。

-
生態系のトップを占めるような…。要するに生態系というのは食物網ですから、何が何を食べて、という関係でしょ。
ええ。

-
その場合に生態系の一番上のほうに君臨するというのは、たいていタカの類の猛禽類か、あるいはネコ属のライオンみたいなものか、あるいはオオカミみたいなものか、そんなものですよね。そういう連中はガラパゴスにはいなかった。
なるほど。

-
人間が行くまでは、ガラパゴスの生物をとるものはいなかったと思います。
つまり肉食の動物がいなかったから、ということですか?

-
肉食はいても、そんな大型のものを食べるような強力なものはいなかった。
だから、それぞれの生態系が安穏と生活する環境があったということですね。

-
ですから、そこの鳥はあんまり人が行っても逃げない。怖いものを知らないですから。
のんびりと暮らしちゃってるから、鳥はほんとは昔飛べたんだけど飛べなくなっちゃったよという。

-
そういうのもいますね。
いるんですか! このあたりの生態系の話、変わった動物については、また来週うかがってよろしいですか?

-
そういう機会があったらお話しましょう。
先生、あっという間ですよね。時間、短いんです。また来週詳しい話をうかがいたいと思います。今週のサイコーはNPO法人日本ガラパゴスの会のメンバーで、東京都立大学名誉教授の小野幹雄先生でした。ありがとうございました。

-
どうも。
ガラパゴス諸島、僕も行きたい場所ですけれどけっこう遠いんです。アメリカのどこかに行って、どこかのアメリカからトランジットしてエクアドルという南アメリカ大陸の国に到着します。だから、絶対1回乗り換えなくちゃいけない。そしてエクアドルに着いて、エクアドルの本土からガラパゴスの3つの島まで国内線が飛んでいるそうです。そのどこかに上陸して、ガラパゴスを探索するという。ほんと究極の自然の島といわれています。みんなも今の段階から興味を持って、いつか大きくなったらガラパゴスに行きたいという夢を持ってもらえるといいかなぁと思います。ほんと手付かずの自然が残っているといわれていますが、行ってみたいなぁ。みんな、どうだったでしょうか?それでは、また来週も夕方5時半に会いましょうね。バイバイ!