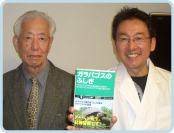キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回もミステリアスな島、手つかずの自然の島、ガラパゴス諸島を特集します。ガラパゴスには独自の進化を遂げた生き物たちがたくさんいるということですが、みんながイメージしてるのはカメやイグアナ系。その辺の話をお知らせの後、たっぷりうかがっていきます。
今週のサイコーも東京都立大学名誉教授でNPO法人日本ガラパゴスの会のメンバー、小野幹雄先生です。こんにちは。

こんにちは。
先週ガラパゴスのほんのさわりだけうかがったんですけれど、僕、本当に行きたいんです、この諸島に。

ぜひ行ってください。
本当に時間があれば行きたいんですが、とりあえず今日行った気分にさせてください(笑)。

はい。
今日は、日本ガラパゴスの会が出されている『ガラパゴスのふしぎ』という本があります。この本を見ながらお話を聞いていきます。僕、は虫類が大嫌いなんですが、ガラパゴス諸島は、は虫類の宝庫なんですね。

そうですね。ヘビはそんなに、やたらにいるわけではありません。
それはちょっと安心です。でもカメがいますよね。

ええ。
ガラパゴスというとカメ。表紙に出てくるのは、何てカメですか?

ガラパゴスゾウガメです。
ガラパゴスゾウガメ。象徴ですよね。

そうですね。スペイン語でこれをガラパゴといって、そこから名前が出たわけですから。
なるほど。このカメが、スペイン語でガラパゴというカメ。で、ガラパゴスという言葉が世界中の言葉になっているわけですね。

はい。
このカメがすっごく大きいことは写真を見てわかるんですけれど、具体的にどれぐらいの規模ですか?

長さは1メーター半ぐらいありますかね。目方が200キロ以上といわれてます。
重さが200キロ以上! めちゃくちゃ大きいじゃないですか。

大きいですねぇ。日本でも小笠原や四国の南などには大きなウミガメが来ますけれども、ウミガメはだいたい背中が平らなんですよ。ところがこのゾウガメは背中が丸く盛り上がってます。
ポコッと山みたいに。

わりに背が高い。1メーターはないですけれど、50センチぐらいまで上がりますね。
ウミガメの産卵も見たことがあるんですけれど、あのウミガメに比べると背中がこんもりしてて、何かヘルメットをかぶってるような“こんもり”の仕方ですね。

そうですね。
大きさやかわいらしさが全然違って、むしろこのガラパゴスのカメは怖いイメージですけれど、先生じかに会った時は怖くなかったですか?

それほど怖くは…。だいたいカメがそこら中に歩いてることはあまりなくて、飼われていることが多い。
飼われてる!?

ダーウィン研が飼って子どもを増やして現地に戻そうということもやってますけれども。
へぇ〜。

戻されたカメに出会うことはわりに少ないですから。
そうなんですか。研究のために人間が飼育していることが最近多くなってるんですか?

はい。研究のためだけではなくて人間が増殖のお手伝いをして、行く行くは現地に戻そうと。現にガラパゴスでは戻しているカメもいます。
新潟の佐渡のトキと同じですね。

そんな感じですね。
カメか。あとは、ガラパゴスというとイグアナですよ。

大きなトカゲね。
もうあれも気持ち悪いですけれど。あれはゾウガメを見るぐらいに同じような頻度でけっこういるんですか?

これはたくさんいます。
たくさんいる。頻度がはるかに高い?

はるかに高いです。
イグアナは、毒はあるんですか?

いやいや、毒はない。おとなしいですよ。
これはどういう生態系ですか?

海に入ってエサをとるイグアナがいて、ウミイグアナというんですが…。
へぇ〜。

世界でも大変珍しい。トカゲが海に入るのは、おそらくこの種類しか見つかってないと思います。
このカメやイグアナは、相当昔のものなんですね。

はい。南米から移ったものでしょうね。
彼らは進化してるんですか?

それなりにしてるんだと思います。
例えば?

島ごとにカメの甲羅の模様が違いまして、島の人たちから見ると背中の甲羅を見ただけでどこの島のカメか分かるというふうな話があります。ダーウィンが行った時にその話を聞いて、たぶんこれは同じ先祖から分かれたものではないかと。それが生物進化の思想の始まりのひとつなんですね。
ふ〜ん。50ぐらいの島からなると先週うかがいましたよね。その島ごとにウミガメの甲羅の模様が違う?

模様が少しずつ違う。50全部にいるわけではなくカメのいる島はせいぜい20ぐらいでしょうけれど、それぞれの島で甲羅の模様が違う。その違いが、多分同じ先祖からのその後の進化の違いだろうとダーウィンは考えたんですね。
500万年ぐらい前からの島ですよね。

はい。古いところは500万年ぐらい。
その頃から進化の歴史で、甲羅の模様も変わってるということですね。

そういうことでしょうね。
人間もやっぱり島によって変わってくるわけですよね。

婚姻圏が別々であれば。
そういうことか。子孫ってことですね!

ええ、そういうことです。
そうか、そうか。そこで変わるわけですね。

人間は非常にいろんなところで婚姻しますから、そういうことはたぶんないと思いますが、カメはその島の中のもの同士しかおそらく子どもを産まないでしょうから。
へぇ〜。そのほか、先週チラッとお話をうかがったんですけれど、飛べない鳥。もともとは飛べた鳥ですが、ガラパゴスの進化の中で飛べなくなっちゃった鳥がいるんですよね。

そうですね。羽根があまり発達しなくて、コバネウという名前がついてます。
鵜ですか?

羽根が小さい。鵜の仲間です。
長良川の鵜?

鵜です。
食べても全部吐き出さなくちゃいけない鵜ですか?

はい、そうです。
かわいそうな鵜…。ガラパゴスにも鵜はいるんですね。

はい、います。
ガラパゴスの鵜は、自分で食べたいものは食べることができる?

長良川の鵜と種は違いますけれどね。
種が違うんですね。

あの仲間でコルモラントといってるんですが、羽根があまり発達してなくて飛べないものがあります。
へぇ〜。

小さな羽根の鵜という意味で、コバネウという名がついてます。
コバネウ。これは日本人だけですよね、コバネウと呼ぶのは。

ええ、日本語での和名です。
外国では何というんですか?

ウィングレスコルモラント。
ウィングレス、へぇ〜、羽根なし。これは羽根が退化したということですよね?

そうですね、あまり発達しなかった。羽根を使わないですから。羽根そのものはありますけれど、3キロ以上あるような体を空中に持ち上げるだけの飛翔力はないでしょう。
飛べない鳥は、鳥の範ちゅうに入れてもいいんですか?

それはニュージーランドのキーウィとかモアとかいますから。
ニュージーランドの国鳥ですね。

ですから、飛ぶ必要がなければ飛ばないですむ。そういうことはあったでしょうね。天敵がいなければ鳥だってそういう苦労はしたくないでしょうから。
じゃあ、コバネウは、いまだに天敵がいない状態でガラパゴス諸島で生活できてるということですね。

できてるはずです。
ガラパゴスに天敵がもたらされるという可能性はゼロじゃないと思うんですけれど。

いや、あります。イヌやネコとか人間が連れてきて、そのまま逃げ出すとか。はなはだしい場合は置いていくという話がありまして、これはガラパゴスでなくても小笠原でもそうですが、人間が持ち込んできて害獣になった。もともとの自然の生物にとっては害獣になった。そういうものはたくさんいます。
だから、そういうのを監視するためにも先生方の活動は必要なわけですよね。

エクアドル政府とかダーウィン研の指導もありますけれど、かなり本気になって外来の生物を排除しようという運動をずっとしています。
なるほど。ちょっと行きたくなったんですけれど、なかなか時間がなくて。でも行く時間がないのは言い訳に過ぎなくて、本当に行きたくなったら行くべきなんだよね。先生、ちょっと行く気になってきました(笑)。

ぜひ行ってみてください。
どこで乗り換えればいいんですか?

エクアドルの本土まで飛行機で行って、本土のグアヤキルとかキトの街からガラパゴスに行く飛行機が毎日2便、場合によっては3便出てる時があります。
わかりました。ほんとの自然を見にぜひ行きたいと思います。今週のサイコーは、NPO法人日本ガラパゴスの会のメンバーで、東京都立大学名誉教授の小野幹雄先生でした。ありがとうございました。

どうも失礼しました。
今日はこのラボに小野先生以外にもガラパゴスの会の方々がお二方お見えになってました。やっぱりみなさん、ガラパゴスのことを語る時はキラキラしてるんです。うらやましいなぁ。僕も去年行きたかったんですよ。話を聞いたら、やっぱりガラパゴスは外からの種に関しては非常にナーバスになっていて、観光客の持ち込むもの、なま物とか汚れているものとかに関しては過敏だということなんですよね。確かに生態系が乱れちゃうのは、ちょっとしたきっかけでガラガラガラッと乱れちゃいますからねぇ。ほんとにますます行きたくなりました。それでは、来週はもうゴールデンウイークだぁ。みんな、楽しい週末を。バイバ〜イ!