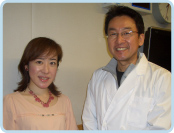キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回も台所、料理にまつわる科学のお話で〜す。これを聴くと、ますますお母さんのお手伝いがしたくなっちゃうと思います。でもお母さんの手伝いが好きになるのは、とてもいいことだと思いますよ。お知らせの後、サイコーの登場だよん。
今週のサイコーもサイエンスライターの内田麻理香さんです。こんにちは。

こんにちは。
内田さんは家庭生活を科学するエキスパートでいらっしゃいますが、ちっちゃい頃から家事とかお母さんの手伝いが好きだったんですか?

いえ、それがまったくしない子でした。料理本は見るのが好きで、食べることも好きだったんですが、ようやく家事をする場面になってみたら、まったくできなくて失敗の連続だったんですね。
へぇ〜。それは東大を出てからということですか?

はい、そうです。それこそ勉強ばっかりしてて、家事ができないダメな女だったんですよね(笑)。
いってみたいですね、「勉強ばっかりして、家事をすることがダメな女」って。カッコいい!

いやいや(笑)。
家事をしなくちゃいけない時期が来て、家事をやって…。で、今は家事が得意なんですね。

いえ、今も失敗が多いですね(笑)。
失敗が多い。だけど、その家事と科学を結びつけて、いろいろ結論づけるのが好きなんですね。

そうですね。
例えば、何ですか? 台所の科学、ほかに何かあります?

そうですね。一番自分でびっくりしたのが、とろみをつける時に片栗粉と小麦粉を間違えて入れてしまいまして。
すご〜い。サザエさんみたい。

ハハハハハ。
それで?

そしたら、とろみがつかないんですね。いくら熱を加えても全然サラサラのままなので「おかしいな」と思ったら、入れたのが小麦粉だった。
そこで当然、科学者としては、「何で片栗粉はとろみがつくんだろう?」と思いますよね。

はい。くやしくて調べたんですよ。
何でですか?

そしたら、固化というんですがとろみがつく温度が片栗粉は低いんですけれど、小麦粉は高い温度じゃないとつかない。あとはとろみがつく粘度、とろみの具合が片栗粉は強いんですが、小麦粉の場合はサラサラしている。同じ澱粉でも科学的な性質の違いがあったんですね。
そうそう、固化で思い出した。僕はけっこう熱いものが好きなんです。でも、熱いものばかり好んでると食道ガンになりやすいというから気をつけるようにしてるんですが、スープとか頼んでもコーンクリームスープは長く温かい。だけどコンソメスープは比較的早く冷めちゃうんですけれど、科学的な根拠があるんですか?

ありますね。
教えてください。

温度は低いほうから高いほうに、下から上に流れていくんですね。
下から上に。

対流といってクーラーでもわかると思うんですが、空調を使うと上のほうが温度が高くて下のほうが温度が低いですよね。
ええ。

それと一緒で、空気や液体の中での温度はグルグル回っていく。グルグル回ることによって表面が冷めたりするんですが、粘度が高いコーンクリームスープのようにドロドロしてるとグルグル回る度合いがゆっくりなので表面が冷めにくいということになります。
ちょっと待ってください。フラットな状態に置いてあるスープも、中で液体がグルグル回転しているんですか?

はい、そうです。
知らなかったぁ! じゃあ、その中にパセリの葉っぱを入れたらグルグル回ってるのが見えるんですか?

多分見えると思います。
えぇ〜! 生きてるんですね。

はい。空気もグルグル回ってますね。
空気も?

はい。
空気は止まってないんですか?

止まってません。やはりクーラーや暖房が上のほうが温かくなるようにグルグル回ってますね。
そうか。確かにエアコン効いてますものね。その時は空気がクルクル回ってるんですね。

そうです。
へぇ〜。あと、すごいクダラナイことを聞いていいですか?

どうぞ(笑)。
僕は今、北海道で生活してるんです。で、トウモロコシが大好きでして、トウモロコシを炒ってもはじけない。ポップコーンはもともとトウモロコシの形をしてますね。何でポップコーンがはじけて、トウモロコシを炒めてもはじけないんですか?


はい(笑)。ポップコーンは種類が違うトウモロコシで…。
そうなんですか! 何という種類ですか?

あれは皮がとても固いんですね。
コーンの?

黄色い粒々の皮が固いので、はじけてしまうのは中の柔らかい部分が熱を加えると水分が膨張して空気になります。その時、水分が気体になると1000倍とか2000倍になる。
パーンとはじける。

普通のトウモロコシですと空気がどんどん逃げてってしまいますが、ポップコーンの場合はギリギリまで我慢してるんですね。
はい。

そうするとパーンとはじけて、裏返ってポップコーンになる。
じゃあ、通常のトウモロコシ、北海道ではトウキビというんですが、トウキビとポップコーンはコーンの種類が違うんですか?

違います。
ポップコーンのコーンの種類は、日本ではあるんですか?

一応、栽培されているとは聞いております。
へぇ〜。じゃあ、今の話は『さるかに合戦』の栗が、あったまって鬼退治の時にパチンとはじけるのと同じ原理ですかねぇ。

そうですね。
『さるかに合戦』の栗は、弱い栗だったらあんな風にはじけなかったわけですね。

そうですね。空気の逃げ場があるとはじけないんですけれど、皮がしっかりしてるのでギリギリまで我慢してる。
じゃあ、ポップコーンを炒めて残ってはじけなかったやつは、結局、皮がどこかで空気の逃げ道をつくっちゃったハズレ、ということですね。

まさにおっしゃる通りです。
勉強になったぁ。あと、先生は卵に詳しいと聞いたんですが、何か卵に関してウンチクを語ってくださいよ。

そうですね。やはり普通のゆで卵と温泉卵の違いですが。
僕、温泉卵好き!

はい。なかなか温泉卵は不思議な存在だと思うんですけれど。
あれはゆで時間によって違うんですよね。

いえ、温泉卵の場合は、ゆで時間ではないですね。
違う。何ですか?

白身と黄身の固まる温度が違うんですね。
そうなんですか。えっ、100度で沸騰しているのではないんですか?

100度で沸騰して普通に固まる場合は、まず白身のほうから固まっていきます。外側のあったかいほうから固まっていくんですが、白身の固まる温度はだいたい80度ぐらいです。
へぇ〜、100度じゃないのか。黄身は?

70度ぐらいです。
10度の違いがあるんですか?

そうです。
ということは、黄身が先に固まって、その後に白身が固まるということ?

逆なんです。
えっ!?

沸騰したところに入れると、まず普通に100度なので外側から固まっていくので、半熟卵から完熟卵になっていきます。
そうだ。

ただそれを60度か70度辺りの温泉のようなお湯につけておきますと、先にジワジワッと温まってくのが黄身のほうになるんです。
そうかっ! すみません、半熟卵と温泉卵は違うんですね。

はい、違います。
僕は半熟、好きでした。

はい(笑)。
白身が固くて中の黄身がトロッとしているのがいいんだけれど、温泉卵は黄身が固まっていて白身がまだ固まってない。

ええ。
なるほど。ということは、温泉卵は70度から80度のお湯とか蒸気にあててるから、あんな風になるということですか?

そうですね。もう少し低い温度がいいですね。
へぇ〜。

もしご家庭でつくる場合は、その程度の温度のものを発砲スチロールの容器とかに入れてフタをした状態で温泉卵がつくれます。
例えばお湯を入れた鍋を発砲スチロールに入れて、その横に卵を置いておくと温泉卵ができるということですか?

いえ、発砲スチロールの中にお湯を入れまして、そこに卵を入れる。
すると、あまり温度も下がらなくて温泉卵ができる。

そうです。
何分ぐらいでできるんですか?

30分ぐらいかかるかもしれませんけれど。
だけど、温泉卵は独特な硫黄のにおいが加わるわけじゃないですか。

はい。
発砲スチロールでやったら、硫黄のにおいは入らないですよね。

そうですね。そのにおいは入らないですね。
なるほど。勉強になりました。もう時間。きれいな人としゃべってるとあっという間だ。僕、絶対東大でも高田万由子さんより菊川怜さんより、先生のほうがきれいだと思います。

とんでもないです(笑)。
ネイルもきれいにしてらっしゃるし、春らしい。すみません。

フフフフ。
まだしゃべり足りないですよね。大丈夫ですか?

はい。
すみません、こんな短い時間で。もっともっと聞きたいことがいっぱいあったんですけれど、この番組30分になったらまた来てください。

はい、ありがとうございます。
今週のサイコーは、サイエンスライターの内田麻理香さんでした。ありがとうございました。

ありがとうございました。
サイコーの内田麻理香さんは本をいっぱい出してらっしゃるんですけれど、インターネットでカタカナで『カソウケン』というホームページも出してらして、家庭の科学のことを書いてありとっても興味深かったんです。興味があったら、ぜひ見てください。こんなきれいな人がサイコーで来られているので、今年の夏のイベントは内田さんに来てもらおうかなぁ。絶対面白いよねぇ。いろいろ実験もしてくれそうだし…。勝手に個人的に思ってますけれど。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょうね。バイバイ!