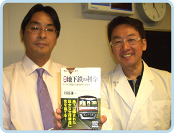キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、番組ではこれまで飛行機、新幹線、鉄道、車とかいろいろな乗物関係を取り上げてきたんだけれど、今回は地下鉄。すっごく身近でしょ。みんな地下鉄には乗ったことあるだろうし、東京に住んでたら必要な交通手段だよね。地下鉄には実はいろんな科学がひそんでいるということなんです。お知らせの後、サイコーの登場だよっ。
今週のサイコーは、技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは。

こんにちは。
川辺さんは東北大学工学部ご出身ということで、被災地ですから気になりますよね。

気になりますね。
工学部を卒業された後、化学メーカーに入社されて、7年前に独立されて技術ライターとして本や雑誌を書かれていらっしゃる。その中の1冊が講談社ブルーバックス『地下鉄の科学』で、地下鉄で科学というこの番組にぴったりのタイトルですね。

はい(笑)。
僕たちは東京に住んでますから、地下鉄はなじみが深い。でも、僕はこの春から札幌に移住してるんですが…。

そうですか。
ですから僕は札幌の地下鉄にもなじみがあります。ところで、日本には何ヵ所の地下鉄があるんですか?

地下を走っている鉄道という意味でいうと、いろんな場所にあるんですけれど、地下鉄と俗にいわれているものは9都市。
9。札幌、東京…。

大阪、名古屋、仙台、横浜、京都、神戸、福岡の9つです。
おぉ〜、9つの都市かぁ。地下鉄はやっぱり東京が一番ですよね。

そうですね、利用者数でいったら。
世界的に見ても、東京の地下鉄は先進的ですか?

そうですね。ひとつの都市としては1日の利用者数が785万人で、世界で1位。
えっ、東京の地下鉄が世界一の利用者!

そうですね。一都市としては世界一。

そうです。
距離はどうなんですか?

距離としては、ロンドンとかはもっと距離があるんですけれど、1日の利用者数の密度でいいますと世界一だという。
へぇ〜。すごい! 誇れますねぇ。

そうです。
そもそも一番古いのは銀座線で、浅草から上野というのは有名ですよね。

そうですね。
あれは何年前ですか?

80年以上前ですけれど、1927年に開業して。
じゃあ、地下鉄は今年で84歳!

84歳です。
へぇ〜。きっとキッズのおじいちゃんよりも年上ってことですね。ひいおじいちゃん世代かもしれない。

そうですね。
世界初はどこだったんですか?

世界初は、イギリスのロンドンが最初です。
東京よりもロンドンが古くて、ロンドンはいつですか?

ロンドンは1863年で日本が江戸時代、まだ幕末の頃につくられた。
ということは、138年前…。江戸時代から地下鉄が走ってたんですか!

そうですね。
えっ、だって当時まだ電車ってないわけですよね。

そうですね。
地下をどういう形で? ガスとか溜まったりして一酸化炭素中毒にならないですか?

当時は動力として電気で動くものとか、車のようにエンジンで動くものがまだ開発ができてなかったものですから蒸気機関車が走ってました。
地下を?

はい。
えっ、ロンドンは!

そうですね。
東京の上野〜浅草間はもう電車?

電車だった。
138年前のロンドンは、蒸気機関車が地下を!

蒸気機関車が人が乗っている客車を引っぱって走ってたんです。
その煙はどうなったんですか?

煙を抜くための穴を、駅の近くに縦穴としてあけてあった。たくさん煙を出して排出する穴があるんです。そこで出してから勢いでバーンと走るという。
へぇ〜。じゃあ、昔の地下鉄は路上から下を見たらゴトゴト音が聴こえたし、蒸気が出る穴があることは、よーく見たら「あっ、地下鉄!」とわかる環境だったんですね。

そうですね。その穴が今も残ってるんですね。
ロンドンには!?

はい。
東京では、そんなの考えられないですよね。

ちょっと考えられないですねぇ。
前に東京に住んでた時に、江東区の東陽町に東西線の車庫があって。

ありますねぇ。
そこに行くと地下鉄が地上にあるのがわかったんですけれど、あれはどういう…?

あれは車両の検査をするための車庫で、地下の線路とトンネルでつながってるんです。
へぇ〜。で、地上に出て検査をする。

そういうことです。
東京都内に東陽町みたいな場所、つまり地上に地下鉄が現れる場所は何ヵ所かあるんですか?

何ヵ所かあります。
例えばどこですか?

車庫という意味でいいますと、中野とか。
丸の内線?

丸の内線の中野とか、銀座線でも上野の駅の近くにあります。
えっ!

住宅街のところにあるんです。
上野駅の近くに?

はい。
各線は、必ずどこか地上でメンテナンスする場所があるんですか?

必ずしも地上というわけではなくて、例えば大江戸線は2つ車庫があるんだけれど全部公園の下にある。
例えばどこですか、それは?

江東区の木場公園。
清澄白河駅の近く?

あの近くの木場公園の下には、実は車庫がある。
へぇ〜。もう1ヵ所は?

もう1ヵ所は光が丘というところの公園の下にある。
いやぁ、すごい! でも、それは僕らが見ることはなかなかできない。

なかなかできないですね。
今年の夏は節電じゃないですか。そういう中で、地上でメンテナンスするよりも地下でのメンテナンスは、節電の関係上なかなか大変かもしれませんねぇ。

地下の場合のほうが気温の差が小さいので、空調という意味での電気代は節約できるかもしれないですけれど。
へぇ〜。ということで、『地下鉄の科学』という本にちなみまして、地下鉄に搭載されている科学技術をちょっとうかがっていきたいと思います。

はい。
例えば、どんな技術がありますか?

すべての鉄道に共通するんですけれど、まず安全に列車が走らなければならないという大前提があります。安全に走るためには、列車同士が衝突したりとか起こらないようなシステムをつくらなければならない。
そりゃそうですねぇ。

そのひとつがATC、自動列車制御装置という難しい名前ですが信号のシステムのひとつです。列車の走っている速度を調節したり、前を走っている電車との間が短くなり、過ぎると速度を落とすように指令を出したりなど自動に行なうシステムがあります。
コンピュータで?

そうです。
それはどこかで管理して、ひとつに情報が見られる場所があるんですか?

指令センターというのがあります。
地下鉄も航空の管制みたいな感じの指令室があるんですか?

そうですね、はい。
どこにあるんですか?

どこにあるかは、なかなかいえないんですけれど(笑)。
いえない! えっ、東京の地下ですか、地上ですか?

おそらく地上だと思いますけれど、どこにあるかはわかりません。
コンピュータの画面を見ながらとか、点々で「何号列車はここを通過中」とか一目瞭然の場所が、シークレットラボみたいなところがあるんですね。

そういうところがあるわけです。どこかにあるわけです(笑)。
えぇ〜、気になる!

そうですね。
あと、1人で運転手が乗っている地下鉄もあるんですって?

そうですね、ワンマン運転といわれてますけれど。
車掌さんがいないんですか?

車掌さんがいない。
例えば、どこで走ってるんですか?

東京でも増えてまして、この近くですと大江戸線もそうです。
えぇ〜、そうなんですか! 今日ちょっと僕、大門駅から大江戸線で帰ります。ワンマン運転。

はい。
じゃあ、「次は光が丘〜」というのは、運転手さんが自分でいってるんですか?

運転手がいってるわけではなくて、自動放送システムがあります。
えぇ〜!

列車が発車し始めてから何秒後に放送が流れるというようにつくってある。
いやぁ、知らなかったぁ。地下鉄、東京でもワンマン運転。あっという間でした。すみません川辺さん、このラボに来て面白かったですか?

面白いですね!
だったらまたお話を来週うかがってよろしいですか?

はい。
今日のサイコーは、技術ライターの川辺謙一さんでした。また来週お願いします。

よろしくお願いします。
東京には東京メトロと都営地下鉄があって、石原知事が「こんなの一つにまとめちゃえ」という話もあるんだよね。僕もそう思うのね。だって、東京メトロから都営に乗り換えるとお金が余分にかかるでしょ。そもそも東京メトロって値段が安いので、できればそれに統一してもらったらありがたいんですけど(笑)。これ、科学でも何でもないねっ。ふだん地下鉄を利用する人のグチでございました。みんな、どうでしょうか(笑)?それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!