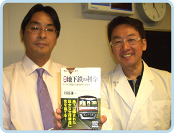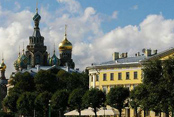キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、ラボは最寄駅がJRの浜松町、それから東京モノレールの浜松町、地下鉄大江戸線の大門駅、このあたりが近いんだけれど、今回も地下鉄を取り上げます。先週、地下鉄の話を聞いて大江戸線に乗ってきて、地下鉄にはいろんな話があるんだなと勉強しました。今日はさらに深〜い地下鉄の話を聞いていきたいと思います。お知らせの後、サイコーが登場しま〜す。
今週のサイコーも、技術ライターの川辺謙一さんです。こんにちは。

こんにちは。
川辺さんは、『地下鉄の科学』という本を出していらっしゃいます。先週ちらっと話しましたけれど、僕は現在、札幌在住で、札幌の地下鉄は何と全国で唯一ゴムタイヤで動くという…。

そうですね。日本の中では唯一です。
だけれど、けっこう歴史が古く40年ぐらい前からゴムタイヤでやっているのに、何でそれをほかの地下鉄がマネしないんですか?

マネしないというか、札幌ならではの事情が関係している。
えっ! そうなんですか。

ええ。
ゴムタイヤは静かだからすごくいいし、継ぎ目もないからカタンカタンと音がしなくて、何かズルズルズルズルッと動いて気持ちがいいんですよ。札幌ならではの事情、それは何ですか?

札幌は東京、大阪、名古屋の次4番目にできた都市で…。
東京、大阪、名古屋、札幌。

すぐに横浜ができたんですけれど、横浜も含めて4都市に比べると人口が非常に少なかった。地下鉄をつくっても建設費に見合う運賃収入、つまりお金が入ってこない可能性があったので、安く維持できる地下鉄をつくろうとしたんですね。
へぇ〜。ゴムタイヤは安く維持できる。

そうです。安くできるといわれてまして、なおかつその前にできた東京、大阪、名古屋の地下鉄で問題になっている騒音を解決しようとしてゴムタイヤを採用したという歴史があります。
ほかにもそういう事情で安くつくりたいという都市があったと思うんですけれど、何でゴムタイヤ形式をとらなかったんですか?

ゴムタイヤの電車をわざわざつくりますと、かえって普通の電車より高くついてしまう可能性が…。
車両を製造するためのコストが?

そうです。電車を開発するためのコストが、非常にお金がかかってしまうところがあって必ずしもいいとは限らない。
じゃあ、札幌は試しにゴムタイヤを導入したけれど意外に高かったからということで、「札幌みたいになっちゃダメだ」とほかの都市はマネしなかったという(笑)。

なかなかいいづらいですけれど(笑)。ただひとつの試みとして非常に面白い例だと思いますし、それが応用されてこの近くを走っている「ゆりかもめ」とか。
えっ、「ゆりかもめ」はゴムタイヤですか?

ゴムタイヤで走ってますね。
そうかぁ。

札幌で試した技術があったからこそ、「ゆりかもめ」やモノレールもゴムタイヤで走ってます。
なるほど、へぇ〜。そうか、札幌の地下鉄が「ゆりかもめ」につながってくるわけですね。

そういうことですね。
いやぁ、うれしい〜! キッズも夏休みに北海道へ行くチャンスがあったら、札幌の地下鉄に乗ってみて。すごい静かよ。だけど札幌の地下鉄、コストの話ですが初乗り200円するんです。高〜い。

そうですねぇ。
4つぐらい駅行くともう240円で。東京メトロとか安いなぁと思うんですね。

そうですね。
そうか、コストがかかっているのか。ほかに、世界でもかまいませんが変わり種の地下鉄はありますか?

変わった地下鉄…。実現しなかった地下鉄としては、ニューヨークで空気圧、空気の力で列車を動かそうという計画がありました。結局、実現はしなかったんですけれど、実はこっそりトンネルを掘って実験してた人がいたという話があります。
それはトンネルをチューブみたいにして、ピストンの原理で?

そうです。ピストンの部分が列車、シリンダーといわれる筒の部分がトンネルという形で、空気で列車を押すという。空気圧鉄道というんですが、これを試した実験がニューヨークで行なわれたことがありました。
いつごろですか?

ロンドンの地下鉄が誕生した頃ですけれど、1800年代。
へぇ〜。あとは?

珍しいものとしては、地下鉄に深いところがたくさんあるという。例えば旧ソ連のほうでは、かなり深いところに地下鉄が走っている都市、サンクトペテルブルグとかがあります。
美しい街といわれているサンクトペテルブルグは、地下深くに地下鉄が走っている。何でですか?

ひとつの理由は地盤の関係もあるんですけれど、もうひとつの理由としては防衛という形で核シェルターの代わりにというふうにいわれています。
地下どれぐらいですか?

今年開業する予定の一番深い駅が、地下105メートルという。
めちゃめちゃ深いですねぇ。

そうですね。
日本で一番深いのは、どこの駅ですか?

東京のこの近くを走っている大江戸線の六本木駅で、1番ホームと2番ホームの二層構造になっているんですけれど、深いほうの1番ホームが地下42メートル。
ということは、サンクトペテルブルグは東京の六本木駅よりもさらに60メートル深くということですか。いやぁ、すごい! 掘るための技術も大変ですよね。

そうですね。
奥深く掘ったら地盤が固くなるとか、工事に障害はなかったんですか?

地盤の固さは深さに関係するわけではないですね。深くなれば地盤が固くなるとか、浅いから弱いとかではない。その都市によっても違います。
そうですか。スペースマウンテンがディズニーランドにありますね。あれ乗って暗いところを走っているとすごく速く感じるじゃないですか。

そうですね。
地下鉄の実際の速度は、マックスどれぐらいで走るんですか?

大体ですけれど、速いものですと80キロ。
通常の速度だったらどれぐらい?

路線によりますけれど、40キロぐらい。
えっ、40キロ!

意外とあまり速くないと思われるかもしれませんが、地上のバスや自動車の渋滞している状況を考えるとずっと速いわけです。
まぁそうですね。でも、山手線に比べると遅いですよね。何か感覚的にすごい速く感じるけど40キロぐらい。

地下鉄の場合は窓から見るところの壁がものすごい近くにあるので、速く感じるんですね。
へぇ〜。地下鉄の高速化、例えばリニアモーターカーはないですかねぇ。

今、研究している磁石の力で浮き上がるリニアモーターカーは現在開発中のものもありますし、名古屋のほうで実用化されているものもあるんですけれど、地下鉄で実用化されているものは車輪がついている、浮き上がらないリニアモーターカーが走ってます。
えっ! そんなのがあるんですか? 日本で?

日本で、ここの一番近くですと大江戸線がそれに当たります。
えっ、大江戸線は若干磁力を使っているんですか?

磁力といいますか、線路の間にリアクションプレートという板が敷いてありまして、そのすぐ近くに電磁石を近づけることによって、電車が前に行ったり後ろに行ったりという動きをする。
大江戸線の推進力というのは、磁石の力で動いてるんですか?

そうですね。
それは大江戸線ができた時からですか?

そうです。できた時からそういうふうになっています。
それは有名な話ですか?

一部ではよく知られている(笑)。
ちょっとラボ内の助手たち、みんな知ってた? −誰も知らない。ラボ内の大人たち、誰も知りません(笑)。そうなんですか!

はい。
大江戸線はリニアモーターカーの原理を多少取り入れている?

そうです。普通の電車ですと丸い筒のような円筒形の形をしたモーターで動いてるんですけれど、そうではなくて真っ平らな電磁石で先ほど言いましたリアクションプレートという板と一緒に推進力を生み出している。
大江戸線に乗ったら、レールとレールの間にリアクションプレートという板がある。

あります。
僕らでも見ることができるわけですか?

ホームから見えますから。
いや、教えてくださいよ、先週の段階で。

ハハハハハ。
何で教えてくれないんですかぁ。

いや、いや(笑)。
まいったなぁ。今から大江戸線乗りに行かなくちゃ。もう時間ですね。あと何かいい残したことはありませんか?

いえ、ありません(笑)。
大丈夫ですね。すごい、楽しかったぁ! 地下鉄は奥が深い。地中が深いだけではないですね。

そうです。いろいろあるんですね。
機会があったら、またぜひお話を聞かせてください!

はい!
今週のサイコーは、技術ライターの川辺謙一さんでした。ありがとうございました。

ありがとうございました。
そうなのか、大江戸線。磁石の力、リニアの力で推進力になっているという。驚いたなぁ! 今から乗って帰る時によーく見ておこう。地下鉄に興味を持っても、ホームは危ないから気をつけてねっ。みんなも地下鉄にいろいろな不思議があることがわかったと思いますが、東京の地下鉄は世界に誇れることも、この2週間でわかってもらえたかな。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!