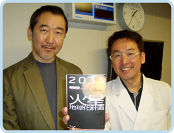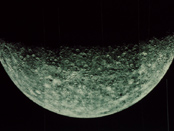キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、7月になったね。ということは今月から夏休みが始まるということで、何か気分も夏休みに向けて上がってきたと思います。夏休みというと自由研究があるでしょ。先週から火星の話を聞いてます。火星の話なんて自由研究にぴったりだと思うので、事前に頭に入れておくといいよっ。お知らせの後、火星の話をさらに深く聞いちゃうからね。
1週間待ち遠しかったです。今週のサイコーも、サイエンス作家の竹内薫さんです。こんにちは。

こんにちは。
火星について、すごく興味があって、先週は生命体の話で終わって決着がつかなかったんですけれど…。僕が子どもの頃は、火星人はイカみたいな三角形の頭に足が8本ぐらいついていて、イカとタコのごっちゃまぜみたいなものが火星人のイメージで(笑)。火星人というと、多くの子どもたちは、そんなイメージを描いたんです。

ええ。

そうです。
火星人は、やっぱり地球から近いということで、人がいるんじゃないかという推測が成り立ったんですかねぇ。

発端は1877年ぐらいかと思うのですが。
140年ぐらい前。

そうですね。イタリアのスキアパレッリという天文学者が火星を観測したのですが、そこにたくさんの筋があるといったんですよ。
火星に?

ええ。それがイタリア語でカナリというんですね。
筋がカナリ。

それをフランス語に翻訳して、さらに英語に翻訳された時にキャナルといったんです。
キャナル、運河。

つまり誤訳しちゃったんですよ(笑)。
えっ、もともとは、筋でイタリア語。

で、フランス語を経て英語になった時に、それが運河と翻訳されちゃった。
へぇ〜。

最初は単なる模様があるというだけだったのが、運河と翻訳されたために「運河は人工物だから、誰かがつくったんだよね」という話になって。
アハハハ。134年前にそういう言葉のあやみたいなものがあったんですか。

そうです。それが、火星人のある意味の発端ですね。
へぇ〜。「運河があるから火星人がいるんだ」という。

そういうことですね。
それでイメージしたのが、イカとタコを合わせたような動物をみんな描くようになった(笑)。

あれがどうして出てきたかがちょっとわからないんですが、SF小説とかの影響もあったんじゃないでしょうかね。
火星って、これまで新聞とかニュースを見ると、各国の探査機が一応着陸はしているというニュースがありますよね。

はい。
これまで火星にいわゆる人間の文明の利器みたいなもの、探査ロケットは何台ぐらい行っているんですか?

もう数えきれないほど行ってるんです。
相当行ってるんですか?

最初は1960年に旧ソビエトが打ち上げているんです。
50年前か。

それからものすごい数が行ってます。ただその3分の2ぐらいは失敗してるんですよ。
へぇ〜。

どうしてこんなに火星探査機が失敗するのかはちょっとわからないんですが、すごく遠いんですね。遠いということは電波が届くのがそれこそ7、8分かかったりするという状況があったりして、なかなか制御が難しい。
ええ。

すごく失敗の連続で、例えばアメリカもたくさん失敗していて、1,000億円のプロジェクトが全くダメだったこともあります。
宇宙開発はそういう可能性がありますよねぇ。

日本も火星探査機の「のぞみ」を打ち上げたんですけれど…。
日本もチャレンジしたことがあるんですか?

これが残念ながら火星の軌道に乗ることができなかったんですよ。
それって2、3年前ですか?

そうですね、数年前ですね。そのプロジェクトも100億円以上かかっているわけで、かなりマスコミにもたたかれたんです。
日本の「のぞみ」は火星に着陸ができなかったんですか?

着陸ではなくて、周回軌道に乗って観測するはずだったんですよ。それもダメだったんですね。
着陸したことがあるのは、ほかの国で旧ソ連とかアメリカの探査機は?

きちんと着陸をして全部観測したのはアメリカだけですね。ヨーロッパも失敗してます。2003年に打ち上げた探査機は、やはり火星に激突して粉々になってしまったらしいですよ。
へぇ〜。

だから、ほんとうに火星探査は失敗の連続なんですよ。
火星は地球上から見ることは可能なんですよね。

そうですね。
そこから研究は進んでいるわけですか?

火星の大気とかもわかっていますし、いろいろなことがわかっているんですが、実際にやっぱり行ってみて、そこで掘ってみたりして、できればそれを持ち帰ってくることをしないとなかなか本当のところってわからないんですよ。
はぁ。

例えば、宇宙人が「地球を探査しよう」といって無人探査機を送るとします。それがたまたま北極に着いちゃったとか、あるいはサハラ砂漠に着いたのかによって全然違ってくるんですね。
う〜ん。

だからたくさんの探査機を送って、いろいろな場所に着陸させて調査をしないとわからないんですよ。
確かにそうですよね。いろんな可能性がありますよね。ある程度、火星の探査に関しては、あたりをつけて飛ばすことができなくて、どこに着陸するかわからないという。

最初はそうでしたけれど、最近はこれまでと違う地形のところを選んで探査するということで、それでスピリット号とオポチュニティ号はこれまでと違ったところで違った写真を撮って、水が発見されたということですね。
まだ火星に人類が降り立ったことはないわけですね。

ありませんね。
今は月だけですよね。

そうですね。
でも、「2035年には降り立つことが可能かもしれない」というのが竹内さんの著書の中にあって。

そうですね。今、例えばカナダのデボン島というところがあって。
北のほうですか?

そうです。カナダは僕も住んでましたが、ものすごく冬が寒いんですよ。例えば、モントリオールも冬だとマイナス20度とか。
オリンピックがあったところですね。

はい。デボン島はすごく寒い。そこに巨大なクレーターがあるんですね。直径20キロぐらいのクレーターがあって、その中はすごい風が強いし寒い。どうもこれが「火星と似ているぞ」ということでいろいろなプロジェクトがありました。実際に火星の基地をつくって宇宙服を着て探査するというようなプロジェクトもあるんですよ。
へぇ〜、へぇ〜。それは日本人で参加した人はいないんですか?

僕が知る限りでは、日本人で行った人はいないのでは…。もしかしたらいるかもしれませんが。
極寒の中で訓練しているわけですね。

そうですね。あと、日本だと大手のゼネコンが2057年を目途に火星に居住するというようなプロジェクトもやってますね。
46年後に?

ええ。どうやったら火星にちゃんとした住居をつくって、そこで酸素をつくったりできるかといった、かなり広大な計画ですけれど、いろいろな人が実際に火星に住んだ時にどうなるかというシミュレーションをやっています。
はい。

そういうのがたくさん蓄積されてきた時に初めてまず火星に誰かが行ってみて、そこに基地をつくって、それから火星を改造していくという方向に行くんじゃないでしょうか。
なるほどねぇ。僕、子どもの頃『銀河鉄道999』を観て、もう小学校の高学年だったから「まぁ、先の話だろう」と思っていたわけで(笑)。そろそろその予感みたいなものがあってもいいかと思ってるんですが、まだないわけですよ。惑星間を人類が自由に往来できる時代が来ればいいなと思って、生きてる内に。

『銀河鉄道999』の元になった『銀河鉄道の夜』。
宮沢賢治さんの『銀河鉄道の夜』ですね。

あれはジョバンニとカムパネルラが銀河を旅するんですね。
はい。

そういった時代がほんとに来てほしいなぁと思うし、それはやっぱりわれわれが「そういった時代が来るぞ!」と信じていれば、必ず来ますよ。
ラジオを聴いている子どもたちも、そういう思いを捨てないでもらいたいですよね。

そうですよね。
あぁもう時間か。番組、短かったですよね。しゃべり足りなかったら、来てくださいね。

はい。わかりました。
今週のサイコーもサイエンス作家の竹内薫さんでした。ありがとうございました。
僕も子どもの頃、大きくなったらたぶん宇宙に行けてるんじゃないかと思ったら、全然行けてないから、間に合わないかもしれないけれど、夢は忘れないでいたいんだ。だから、ラジオの前のキッズもぜひ宇宙のことを思っていてください。「大きくなったら必ず実現するんだ!」と思ってたら、もしかしたら、その時には宇宙の夢がかなってるかもしれないからね。夢は大事だよ。それでは、来週もまた夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!