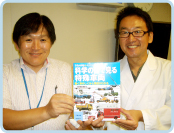キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。昨日の金曜日は秋分の日でお休み。三連休が続くと、みんなけっこうエンジョイしちゃってるでしょ? 今回も車を取り上げます。特殊な車、いろいろありますよね。消防車とか救急車。その中にはいろいろなものが科学として詰まっているということです。お知らせの後、サイコーに聞いてみるよん!
今週のサイコーも、モータースポーツ解説者の小倉茂徳さんです。こんにちは。

こんにちは。
前回はF1カーの話で終わってしまいました。小倉さんは『科学の目で見る特殊車両』という本を出していらっしゃるので、そのあたりの特殊車両に関するお話をうかがいたいと思います。

はい。
特殊車両というと、何といっても救急車とか消防車。消防車のたぐいだったら、一番特殊性が高いのは何だろう? はしご車ですかねぇ。

そうですね。
あれはやっぱり科学があるんですか?

ええ。はしご車は、上にはしごを載せていますよね。ビルの上にビヨーンと伸びるんですけれど、実ははしごの端と端に滑車がついているんですね。
へぇ〜。

その滑車にワイヤーがかかっていて、そのワイヤーを引っぱったり、ゆるめたりする。みなさんが学校の理科の授業でやる動滑車という滑車の仕組みなんです。
あぁ。

ワイヤーが引っぱられることによって、滑車と滑車がズーッと寄っていくんです。そうすると、はしごの片方の端ともう一つのはしごの片方の端がどんどん近づいてくる。どんどんどんどんビヨ〜ンとはしごが伸びていくんです。
ミニカーのはしご車は、だいたい伸び縮みするストローみたいな原理で伸び縮みするけれど、本物のはしご車は滑車がついているわけですね。

でも結局そのワイヤーを伸び縮みさせるために、ストローみたいな油圧アクチュエータというのでやってたりするんです。
そうなんですか。そういう原理もある。

ええ。みなさんがこれから小学校中学校高校の理科の授業で学んでいくことが、そのまま使われているんですね。
はしご車が働いているシーンを見ると、何かテコの原理でコケないかと思うんですよ。よく東京都内でも、工事作業現場でクレーン車が転んだとかあるじゃないですか。

ええ。
はしご車が転んだというニュースは聞かないですよね?

ないですね。
何でですか?

クレーン車もはしご車もそうなんですが、そのまま長いはしごを立てちゃうと倒れやすくなるので、そのためにアウトリガーといって横に踏んばる足が出てくる。
カニみたいなのが出てくるんですか?

ガーッ!と踏んばって、ガッチリ踏んばるんで何というか、最終的には重心を低くできるんですね。
ええ。

ですから、みなさんでもスポーツをやる時って、ただ棒立ちしないですよね。例えば柔道をやる時は、ちょっと腰を落として低くして足をちょっと広げて安定しますよね。その仕組みを使っているんです。
じゃあ、はしご車が動いている時によーく見ると、アウトリガーという足がニョロニョロニョロッと出て支えてるんですか?

横に大きく出ている。ものすごく丈夫な足が出ています。
でも、それを見に行って「じゃまだっ」と怒られてはまずいから(笑)、キッズのみんなはマネしないでね。

確か出初式の時、お正月過ぎにやってくれるので。
でも、それを見に行って「じゃまだっ」と怒られてはまずいから(笑)、キッズのみんなはマネしないでね。

確か出初式の時、お正月過ぎにやってくれるので。
なるほど。消防車の話の次は救急車を聞きたいんですが、救急車は一般的には僕らが見る救急車以外に特殊なものはあるんですか?

はい。例えばスーパーアンビュランスというのがあるんですよ。
知らないです。えっ、 それは何ですか?

実は大きなトラックみたいなものですが、多くの人がケガや病気したという災害が起きた時に行くんですね。
へぇ〜。

現場に着いたら、大きなトラックの後ろの部分がビヨ〜ンと横に広がって、そこにいくつもベッドが広げられるようになっています。
小倉さんの本にありました。『科学の目で見る特殊車両』にスーパーアンビュランスの写真があって、普通のバスみたいなものの幅が2倍になるんですね。横からグリグリッと出てきてちょっと家みたいになっている、プレハブ小屋みたいな感じで。

そうです。そこに十幾つもベッドがあって、すぐ応急措置をしてあげたりとか。
へぇ〜。

「この人はすぐ運ばなければいけません」、「この人はまだ大丈夫です」とかいろんなことをやってあげられる場所なんですね。すぐ救急車で運ぶのかどうするのかも、近所の道路に寝かせとくのではなく、ちゃんと処置ができる。あるいは血圧や必要なデータもとれて、場合によっては病院にそのまま通信回線を使って送ることができるものまであるんです。
ほぉ〜。

-
実はこれ以前、地下鉄で毒ガスがまかれた事件がありまして。
地下鉄サリン事件ですね。

-
あの時に出動してるんです。
その時からあったんですか! 95年から?

-
これが多くの人を救ったんです。
スーパーアンビュランス。これは東京消防庁で所有しているものなんですね。

-
はい。
これを見る機会はなかなかないかもしれないですねぇ。

-
展示してくれる時に見るだけのほうがいいですよね。この車が出動することは、多くの人が病気になったり傷ついたりということなので。
はい。あと、レスキューの車があるじゃないですか。オレンジ色の服を着たレスキュー隊、あの車も消防車の色ですが、レスキューの車は何が載っているんですか?

-
救助用の機材です。後ろにいろんな引出しがついていて、救助に必要な器具が全部入ってます。
はぁ〜。

-
上には投光機がついていて、暗い所でも強い照明を当ててよく見えるようにしたりします。
へぇ〜。

-
例えば重いものにはさまれた人を、油圧という装置を使って大きな力を発生させて切り開いてあげて助け出すとか。
油圧ね。いわゆるしぼんだ風船をあいだに入れてふくらませて、すき間をつくって人を助けるとか?

-
そうなんですよ。あるいは簡単にいうと注射器、水を吸い込んだり出したりする力も油圧なんですね。
ほぉ〜。そういうのがレスキューの車に載ってるんですね。消防車は別にホースを持ってればいいというものではないんですね。

-
ええ。いろんなもの、ポンプ車とか…。
はしごがあったり、レスキューがあったり。

-
そうなんですよ。全てが特殊な装備を持っていて、全部サイエンスの固まりなんですよ。
僕は今、北海道に住んでいるんですが、冬になると特殊な車がいっぱいありますよね、除雪車とか。

-
はい。除雪車のメインのメーカーは北海道なんですよ。
へぇ〜。やっぱりそうでしょうねぇ。

-
除雪車は雪をかいて飛ばすじゃないですか。雪をかいて飛ばすのも機械の歯車を使って雪をかく装置を回しているものもあるし、物によっては高圧の液体でもってモーターを回す−要は油圧モーターというシステムを使っていたりします。
ふ〜ん。その油圧というと身近なところでは、タクシーの扉の自動ドアも油圧なんですって?

-
あれは空気のほうです。
空気の圧? また、それは違うんですか?

-
ほぼ似たような仕組みです。かすかにプシュ〜と音がします。
えぇ〜、今度見なくちゃ! パッと見にはわからないわけですね。

-
なかなかわかんないですね(笑)。
音を聴かなくちゃいけないんですね。

-
あとは運転手さんの右手の動きです。
僕、ほとんど右手の動きしか見てないけど(笑)。最近、空気圧増えているわけですね。

-
でも、まだまだ主流はどうも機械式です。でも、あれも頭よくて、座席とかデコボコしているとうまくよけながら、クランクとかいろいろな装置を使って動きの向きを変えていくんですね。
ふ〜ん。

-
90度変えたり、いろんな角度を変えていって、最後は運転手さんの上下の手の動きがドアの開く、閉まるという動きに変えていくわけです。
不思議だなぁと思うんですよ。原始的だけど、“たかだか自動ドア、されど自動ドア”ですよね。

-
はい。あれもメカニカルサイエンスなんです。
元々自分で開けると思っていればあんな機械をつくらなくていいのに、日本ぐらいじゃないですか(笑)。

-
そうですよね。世界中で日本だけなんですよ、あんなに発達しているのは。
ないものと思えばいいんだけれど、あると便利だから甘えちゃいますね。でも、そこにもやっぱり科学があるわけですね。

-
はい。
今度よく見てみよう!わかりました。車の中にはいろんな科学があるので、よかったらお父さんに話を聞いてみるのもいいかもしれないですね。今週のサイコーは、モータースポーツ解説者の小倉茂徳さんでした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
では、キッズのみんなも楽しい週末を。じゃあね!