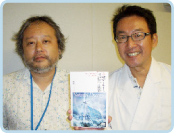キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。この番組、5年前の10月7日が1回目の放送だったんですよ。今日は8日でしょ。ということで今日から6年目に入るという。すごいねぇ!よくこんなに長く…。僕もこんなに長く番組をやるとは、もう250回以上でしょう。いやぁ、それなりにスタッフもみんな年をとったなぁと思いながら、まだまだ元気に科学の疑問に切り込んでいきますからね。今週も自然エネルギーを取り上げます。どんな研究が進められているのか、自然エネルギーの可能性とか太陽光パネル、この辺りをサイコーに聞いちゃうよ。
今週のサイコーも科学技術ジャーナリストの石川憲二さんです。こんにちは。

お願いします。
石川さんはオーム社から『自然エネルギーの可能性と限界』という本を出されています。自然エネルギーに関して先週いろいろうかがって、「自然エネルギーは効率があまりよろしくない」、「じゃあ火力が一番いいよね」という話で終わりました。火力というと、日本はやっぱり燃料がないわけで、中東などからの輸入に頼っているわけじゃないですか。

はい。
思い起こしてみると昔、炭鉱ってあったじゃないですか。だけど事故があったりしてほとんど閉鎖になってしまった。今、昔の炭鉱を掘り返してエネルギーを得ることはできないんですか?

できると思います。その前にひとつ誤解なんですが、「中東から」といったけれど、火力発電の燃料で一番多いのは石炭で、石油じゃないんですよ。
石炭!?

うん、石炭。それで2番目が天然ガス。
へぇ〜。

だから中東ではなく、いろんなところから持ってきてるのね。
そうなんですか。

1970年のオイルショックがあって、石油が政治的な事情ですぐ値段が上がったりするので危ないということになって、いろんな国に発電とかに頼っているといけないから、自動車はどうしても石油を使わざるを得ないからそっちに回し、発電ができる石炭とかを使いましょうねということになった。
じゃあ、アジア諸国とか…。

オーストラリアが多いと思う。
南半球から?

ええ。
昔、蒸気機関車というイメージがあったけれど、あの石炭がいまだに日本の主力になっている。

世界的に火力発電は今や石炭が主力になりつつあります。
へぇ〜。

さっきの日本の石炭でいうと、まだ日本も掘れば石炭があると思うけれど、値段との問題だから手間がかかれば高くなる、かからなければ安くなるというだけの話で。だから日本の石炭でもオーストラリアの石炭でもどっちが安いかというだけの話なんですよ。
次が天然ガス。天然ガスはけっこう、日本の近海でもあるじゃないですか。

といわれているんだけれどね。
所有権を主張して大変なこともありますけれど。

この下にあるって知ってる?
東京に?

関東地方の下は、天然ガスのガス田です。
かつての関東ローム層の?

そうそう。日本で有数のガス田です。
だから、大江戸温泉とか。

いつか渋谷で温泉の爆発事故があったでしょ。あれも地下水と一緒にガスが出るので、その分離が悪くて燃えちゃったんじゃないかという…。実は東京の下を掘ると、天然ガスがあるらしいけれど、ただ地盤沈下するから採ったらいけないらしいの。
はい。

千葉県の一部で採掘権があってやってるところがあるんだけれど、何か大がかりで掘りにくいらしいの、変な話だけど。ただけっこうそういう意味ではあるんです。
日本列島は、天然ガスはけっこう…?

新潟とかもあるんだけれど、ただいっぱいあるかというとまだちょっとわからない。
で、3番目が石油ということですか?

ただ石油はできるだけ発電に使わないようにしようという…。だから大きな電力会社はもうほとんど使ってなくて、自家用発電みたいな器具をやってるのは使っているけれど。
それこそ石炭が主力な火力発電に使われているのであれば、夕張とか福岡には炭鉱の盛んな町があったじゃないですか。あれをもう1回掘り起こすのはどういう…?

経済的にはやればいいけど、値段的に…。結局、オーストラリアの場合はあんな穴を掘らなくても、順番に上からすくっていくだけで採れるところはいっぱいあるんですよ。
はぁ〜。

すくっていくのと、穴を掘ってやるのだとやっぱり値段が違ってきちゃう。
なるほど。

それを「国内の石炭を使いましょう」という運動を起こして産業にすればいいのかもしれないけれど、たぶん値段があまりにも合わない。
わかりやすい話だ。ありがとうございます。先週、まだ聞いてなかった話がありまして、太陽光発電。太陽光発電は、僕は家に帰ったらお湯が出るやつかと思ってたんだけれど、あれはソーラーパネルでしょ?

太陽の熱。
ということですよね。だから、それとは違うんですよね。

ただあちらのほうが効率はいいのだけれど、電気にしない分…。
屋根の上にあったかいお湯が出るよという…。太陽光発電の仕組みは何ですか?

-
仕組みはちょっと難しいのだけれど、光があたると電子が動くような状態のものをつくるんですよ。電子が動くのは電気が流れることなので、太陽光のエネルギーを電気に変えるという仕組みです。
よくベネッセや学研の付録で太陽電池がついてくるけど、あのシステム?

-
同じ、同じ。
発電に活かしている。

-
はい、はい。
コスト的には風力発電と比べてどうですか?

-
コストは、やっぱり専門家にいわせるとかなり高い。
太陽光パネルも?

-
一番高いという。
一番高い。割が合わない?

-
基本的には、エネルギーを多量に使うのは割が合わないといわれる。
へぇ〜。だけど、これから次世代エネルギーとしていろいろな企業が太陽光パネルの開発に力を入れてくるということはあり得ませんか?

-
各家庭にああいうのをつけて、省エネ装置として使う。例えば家で使っている電気の半分ぐらいまかなえば、省エネになるわけでしょ。そういう方法だってあると思うんです。ただ大きいところに太陽電池をいっぱい置いて大きな発電所をつくろうというのは、日本みたいな土地がないところだと、その分は何も使えない土地になっちゃうわけで、どっちがいいかは微妙ですよね。
なるほど。そんなパネルを置く土地があるんだったら、生産活動をする土地も必要だし。

-
食糧自給率の問題もあるんだから畑とかしたほうがいいかも。例えばあるとすれば、住宅の屋根やビルの屋上などは逆に守ってくれたらいいわけだから、そういうところは無駄にしないで太陽光発電をやるのはいいと思うんだよね。
でも、それを取り付けるには経済的なものも必要だし。

-
実際、経済的には割が合わないから、そこは何らかの導入するシステムをつくらなければいけないと思いますよ。
なるほど。じゃあ先週うかがった地熱エネルギー、それから水力発電。この2つを加えると4種類の自然エネルギーと呼ばれる中で一番効率がよい、日本に適したものは何ですか?

-
適しているのは水力だけれど、もうだいたい開発がすんでしまって…。
そうか、ひと昔もふた昔も前の発電方式が日本の地形とか自然に合ってるということですね。

-
北海道でもほとんどダムができちゃってるでしょ。
ありますねぇ。

-
そこまで開発してるので、あと1.5倍ぐらい増やせという考え方もあるんだけれど、今よりもコストがかかってしまううから微妙なんで…。もうちょっと増やせるんだけれど、ただ日本の場合は水力はかなり利用しつくしている。あと期待できるのは地熱発電かなという…。
そうか。地熱は東京でも地下を掘れば天然ガスも出るし…。

-
地熱は、基本的に火山があるところが有利です。
じゃあ、やっぱり九州とか北海道とか。

-
日本は割と多いですよ。北海道とかいっぱいあるし。地熱はエネルギー量が多いので、もっと使っていいと思うんだよね。
地獄谷として観光地にするのであれば、それをエネルギー活用したほうがいいですよ、ということですね。

-
はい。
すごい考えさせられる。

-
ただね、地熱は温泉とのかかわり合いが難しくて、あんまり温泉のそばにつくってしまうと温泉が出なくなる可能性があるので反対運動になりやすい。
温泉地として、われわれの癒しの場が奪われちゃうということですね。

-
その辺が地面の中でわからないので、もうちょっと研究が進んでいろんなことがわかると「ここだったらつくれる」ということができると思うのね。
わかりました。ほんと石川さんの本、おもしろいんだ。『自然エネルギーの可能性と限界』。それ以外にも3Dのテレビに関する本とかエコカーの話とか。果ては宇宙エレベーターの夢みたいな話まで色んな本がオーム社からそれぞれ出ています。関心があったらどうぞ。今週のサイコーは、科学技術ジャーナリストの石川憲二さんでした。ありがとうございました。

ありがとうございました。
何か風力発電とか太陽光発電とかいわれているけれど、結局原点に戻って、発電の原点である水力発電がこの日本という土地に最も適しているという。確かに川の高低さ、山岳地帯が多い日本だから、その川の流れ、水の流れを利用して発電機を回すというシステムが自然エネルギーの原点だったというねぇ。かといって、ダムをジャンジャンつくれといっても、今、この国が許さないしねぇ。難しいですね。みんなどう思ったかな?今週は勉強になったね。それでは、6年目もガンガン頑張ります。また来週。バイバ〜イ!