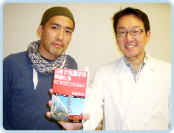キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、街はイルミネーションがすごくきれいだけれど、みんなはお気に入りのきれいなところある? 今年は節電ということで、ただ発光ダイオードに代わっているから逆に明るく見えて非常にきれいだよね、イルミネーション。みんなも年末に向けての美しい街を楽しんでね。今年は3月11日にとても大きな地震が東北地方でありました。今週のサイコーは、そういう被災地で活躍する乗物に詳しい方に来てもらっています。お知らせの後、サイコーの登場です。
今週のサイコーも、フォトジャーナリストの柿谷哲也さんです。こんばんは。

こんばんは。
3.11の地震によって津波も含めて今年、日本は大きく変わりました。その現場に行かれた柿谷さんはいろいろなものを見てこられたと思いますが、僕らはテレビやラジオ、新聞で知ったあの福島第一原発、あそこだけはやっぱりメディアすらも近づけないところだったじゃないですか。

はい。
初期の段階ではあの水蒸気爆発、そして放水活動ですよね。

はい、そうですね。
当然あそこにも、いわゆるハイテクな車両やヘリコプターなども出てくるわけですよね。

はい、投入されました。
印象的だったのは、赤いバケツから水を巻いているヘリコプター。

あぁ、ありましたねぇ。
何ですか、あれは?

原子炉を冷却する目的で、何とかして水を投入したいという考えだったようです。アイデアとしてヘリコプターから水を投下するという奇抜なアイデアに出たわけで、もともと陸上自衛隊のヘリコプター、それから消防のヘリコプターが森林火災などのために7,500リットルぐらいの水を入れられるバケツですね。
えっ!ということは、7.5トンもあの赤い微妙なバケツに入れることができる。

このバケツをふだんから持っておりまして、一気に投入することができるんです。そのアイデアがたぶん出てきて、すぐにこの方法を使おうということだったのではないでしょうか。
なるほど。あれは消防、警察、自衛隊だったら何の範ちゅうに?

-
陸上自衛隊が持っているCH-47と呼ばれる大型のヘリコプターです。
ほぉ〜。

-
自衛隊が持っているヘリコプターで一番大きなものです。
でも、先週出てきたロシアの全長40メートルに比べると?

-
はい、それよりはちょっと小さいです。
小さい。7.5トンのバケツで空中から水を巻いてましたけど、もっと近づいたらピンポイントでスポンというわけには、やっぱり放射能の問題でいかなかったんですかねぇ。

-
そうですね。森林火災の場合は火災の真上から落とすことが普通行われるんですが、今度の場合は相手が原発ですので大気中に放射能がどのぐらい出ているか、パイロットにしてみれば命がけの話です。
ほぉ〜。

-
というのは、先週もお伝えしたロシアの大きなヘリコプターをチェルノブイリ原発事故の時に同じように投入して、その時あまり知識がなかったものでロシアのパイロットは原発の上でホバリング、要するに空中停止して水を投下したんです。
はい。

-
その時は冷却したり効果があったようですけれど、それから数年後、そのヘリコプターに乗っていた隊員、パイロットのほとんどが喉頭ガンによって亡くなられています。
被爆した…。

-
被爆したということですね。この事実があるので、陸上自衛隊のヘリコプターのパイロット、それから国のほうもおそらく原発にCH-47のヘリコプターを投入して冷却するというアイデアはあったけれども空中停止はできなかった。
ほぉ〜。

-
ちょっとゆっくりとした速度で上空を通過しながら落とすということだったようです。
なるほど。

-
かなり高度な難しいテクニックが必要だったと思います。
その後出てきたのが、今度は東京消防庁の放水車が出てきて、これも命がけの作業だとニュースになりました。あの放水車もやっぱりハイテクなんですか?

-
はい。東京消防庁だけでなく横浜とか各地から消防車が集まってきて、高さ22メートルから放水ができる−都会にあるマンションやビルの高層建築物、高いところにある火災を消火するためにもともとあるものなんですね。ですから、原発の上から水を入れるということを想定したものではないんですが射程がだいたい70メートルもありますので、特殊な環境の中で水を放水することはできるということです。
射程70メートルということは、リモコンでやったとかいわれてましたよね。

-
はい。
遠隔操作で?

-
当初は隊員がやっぱり乗り込んで行いました。
あの近くまで近づいたわけですね。

-
近づきました。
大丈夫だったんですかねぇ?

-
やはりかなり防護衣等を着用して、短時間で行うということをしていました。
はぁ。

-
車両も予備の車両として各消防局から集合してるんですが、1台だけをずっと使いっぱなしにして隊員だけが乗り換えるという方法で冷却にあたっていたようです。
今出てきた日本の射程70メートルという放水車は、世界的に見ると相当レベルが高いんですか?

-
そうですね。日本はやはり高層建築物が多いので使われています。外国には、実はもっと能力の高いものもあったりするんですね。
何メートルぐらい飛ぶんですか?

-
100メートル以上飛ぶものもあります。
日本の1.4倍ぐらい飛ぶものもある。今度スカイツリーができると、どういう放水車が出るのかもちょっと注目ですけれど。上の展望台に行って何かあったら大変ですからねぇ。

-
まぁ、あそこまで来ると消火設備が整っているようなので、問題ないと思うんですけれども。
へぇ〜。いよいよ年の瀬ですが、柿谷さん、フォトジャーナリストとして色んなものをカメラにおさめてきたんでしょう。そういう中で今年の3.11は、これまでのジャーナリスト生活の中でどういう位置付けになりますか?

-
はい。今回やっぱり一番感動したのは、先週今週と紹介してきたビークル−乗物、装備はもともと災害のために開発されたものではないんですね。別の目的で開発された。例えばさっきの消防車でしたら消火活動、それからヘリコプターは何かの輸送ですね。自衛隊、警察、それから米軍も出てきたんですが、そういった人たちが「この装備、使えるな!」とか、「この方法でこの装備が使えないんだろうか?」といういろんなアイデアや知恵が出てきたわけです。
ええ。

-
今あるものを応用する、ひらめくことがすごいことだなと感じました。感動したことですね。
日本は決して広い国ではないですが、こういう災害派遣の救助体制、車両などの性能は世界的にはどういうレベルですか?

-
はい。日本の救助レベルは、実は世界トップクラスです。
へぇ〜。

-
特に各自治体の消防、それから警察の救助隊、海上保安庁の救助部隊が合同で国際緊急援助隊という組織をつくっていて、海外の災害に対して派遣されることがあります。最近ではニュージーランドの地震がありました。
ええ。

-
こういったケースを考えると、日本人は優秀な救助隊が近くにいることでやはり幸せな国民なのかと感じますね。
「万一の時はしっかり守ってくれる体勢はできてるよ」ということですね。わかりました。今回は、番組史上もっとも無骨な男性、フォトジャーナリストの柿谷哲也さんでした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
フォトジャーナリストというと、有名な戦場カメラマンの人もフォトジャーナリストという肩書きも持っていて、何かオーラが似てたね。帽子をかぶって首に何か巻いて、ちょっと無骨な雰囲気だけど穏やかで、すごく不思議な感じですけれど(笑)。こういう方がきっと危険地域に行くとアドレナリンみたいなものが出て来るんだろうと思います。柿谷さんはソフトバンククリエイティブから『災害で活躍する乗物たち』という本を出されてます。いろんな写真があって、被災地でこういう人たちが活躍して、こういう車両が出てくるんだと、とてもよくわかる一冊です。じゃあね!