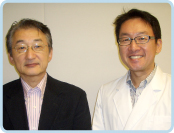キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ大晦日だよ、みんな。今晩どんなふうに過ごすの? ちゃんと夜更かしの準備できてる? 早く寝てもいいけどね。やっぱりカウントダウンは大事だからね。これから、みなさんがどう過ごすのか…。今年最後となりましたサイエンスキッズです。来年2012年に期待される科学について、「もう来年の話をしちゃいましょう!」ということで、お知らせの後、サイコーの登場で〜す。
大晦日のサイコーは、やっぱりこの方に締めてもらいましょう。科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんばんは。

こんばんは。
ほんとに今年はいろいろありましたけれど、来年のことを見ていきましょう。来年2012年に期待される科学について、まず何が期待されるでしょうか?

そうですね。今年は大震災がありましたので、やはり新エネルギーというんですか、太陽とか風力を使ったエネルギーの問題をもう1回ちゃんと考えなければいけないんじゃないかと思いますねぇ。
実際に今、風力発電が注目されてます。あと、太陽光パネル。ソフトバンクの孫さんが「メガソーラー」とかいろいろやってますけれど。

-
そうですね。
どちらが現実問題として、コスト的な問題も含め実用可能か?

-
えーと、いろいろな考え方があります。それから日本ではあまり利用が進んでないので、これから進むと思いますけれど。すぐにある程度効率的に発電を行なうことでいうと、風力発電のほうが少し現実的かもしれませんね。
そうなんですか。

-
というのは、風力発電は技術的にはあまり難しいことはないんですよ。
まぁまぁそうですよね。

-
風の多いところに大型の風車をつくればいいので、それほど難しいことはないし、つくる費用もある程度現実的にできる範囲に入っています。
ほぉ〜。

-
ただ太陽電池のほうはまだまだ値段が高いとか、それから発電効率、つまり太陽の光から電気をつくる効率がまだそんなに高くない。いくつか技術的にいうと、太陽電池のほうがこれからもっと研究しなければいけないことが多いですね。
へぇ〜。僕は今、北海道に住んでいて、北海道で風力発電の話をすると、実は風力発電のプロペラに鳥があたってしまって野生動物の保護の問題とか、あと周辺に住んでいる方が風力発電の音に微妙な周波数みたいなものがあって体調不良を訴えたりで賛否両論があるんですけれど。ただ、現実問題として風力発電のほうが可能性としては?

-
そうですね。特に北海道ですと、やっぱり北なので太陽の日射量も南よりは少ないですね。
はい。

-
そういった意味では風力発電のほうが現実的です。ただ今おっしゃったようにいろんな問題もあるんですね。ですからすべてを風力発電とか太陽でまかなうのは、ちょっと難しいですね。
そうなると、ほかのエネルギーって例えば地熱エネルギーとか?

-
地熱エネルギーとかもありますね。日本は火山の国ですから。
この時季「じゃあ、温泉行こうか!」なんてのは、地熱エネルギーのおかげですよね。

-
そうですね。
地熱エネルギーってお湯はわくけれど、いわゆる電気にはかえられるんですか?

-
結局、温泉はお湯をそのまま利用しているわけですが、地熱で蒸気をつくって発電するので、これは火力発電も原子力発電もまったく同じですね。
はぁ。

-
蒸気をつくって、そしてタービンを回して発電するというのは、まったく同じなんですよ。
そうか。

-
水蒸気をどうやってつくるかというところで原子力の場合は核分裂という反応を使うし、火力発電の場合には石油を燃やして熱をとるわけですね。
水蒸気が出るというのは、沸騰したお湯の蒸気から出るわけじゃないですか。

-
そうですね。
温泉は「いい湯だな」という気持ちいい雰囲気で、あの温泉の地熱だけではそこまで沸騰するイメージがないんですが、実際は沸騰しているということですか?

-
たぶん地熱発電の時に使うお湯あるいは熱い蒸気は、もっと深いところから温度が高く圧力が高いものを使うことになるんですね。
ふ〜ん。

-
ですから、それを地上に持ってくると、ものすごい圧力だったので蒸気となって吹き出す。そういったものを使うことになると思います。
僕らの今いる東京は関東ローム層が地中にあって、ある程度掘ると温泉が出ることがわかったので東京ドームに温泉ができたり、大江戸温泉ができたり。あれもいうなれば地熱ですか?

-
そうですね。温泉は、深く掘ればたぶん日本列島どこでも出てくると思います。ですから、そういった意味では地熱を利用するのは、やっぱりかなり可能性が高いですね。
ほぉ〜。

-
どんどん深く掘っていって、熱いマグマに近づけば近づくほど高い温度が得られることになります。
この地熱エネルギーはいわゆる“枯れる”、枯渇する可能性は?

-
ないでしょうね。地球そのもののエネルギーですからね。
へぇ〜。じゃあ、ちょっと期待できますね。

-
そうです。結局、新エネルギーといわれてるものは、地熱みたいに地球本来のエネルギーを使ったり、太陽という、これも無尽蔵のエネルギーですよね。風も一種の太陽のエネルギーなので、そういった枯れることのないエネルギーを利用していこうということですね。
ええ。

-
ですから、現実的にいろんな影響が出ない範囲で使っていくことが、やっぱりこれからの日本にとっては大事なことになります。
なるほど。あと天然ガス、ガス田ってありますね。ちょっと日本と中国でモメちゃってますけれど、東シナ海のガス田。あのイメージもよくわからないんですが、ガス田は海底深くの海の底にガスがあるんですか?

-
そうです。
何ガスなんですか?

-
基本的にはメタンとかそういったものです。
それは、温泉とは違うのですか?

-
温泉とは違って、あれはまさに石油と同じような材料のものがガスになってるという、そういったものですね。石油は液体でとれますけれど、天然ガスの場合には気体の状態で地下に存在しているということです。
そのガスも新エネルギーの範ちゅう?

-
天然ガスはどちらかというと昔から使っている火力発電の中の化石燃料のひとつだから、石油、石炭に並ぶものとして天然ガスと位置づけられてます。
はい。

-
天然ガスはいろんな利用が可能だしCO2を出す量も少ないとか、それから今話題になってますがコンバインドサイクルというものを使うと効率の高い発電ができるんですね。そういった意味で、今かなり注目されているところです。
ほぉ〜。じゃあ新エネルギーは太陽光、それから風力、地熱の3つをおさえておけば?

-
主に日本で利用できるのは、その3つですね。
なるほど。もう年の瀬ですが、このマスコミの世界にいると変なうわさを聞いて、来年2012年じゃないですか。2012年にあの1999年のノストラダムスの大予言じゃないけれど「地球があやしいよ」、「滅亡するんじゃないの?」といううわさをチラッと聞いたんですけれど。

-
そうなんですね。
えっ、知ってます?

-
知ってます、知ってます。
何ですかねぇ、出所は?

-
いろんな出所があるようですが、僕が知ってる限りでいうと古代マヤの文明が南米にありましたね。
マヤ文明、何年前ですか?

-
数百年ぐらい前から今までずっと続いているんですけれど、その時にマヤのカレンダーを解読してみると、要するに日付が刻まれている。ずーっと昔からそのカレンダーは続いているみたいですが、カレンダー自体を計算してみると来年で日付が終わってしまうということらしいんですね。
マヤ文明の暦では、2012年でカレンダーが終わりということ?

-
そうです。2012年の12月20何日で暦の桁が全部満杯になってしまうわけです。
はい。

-
地球が滅亡する話はノストラダムスもそうだし今回もそうですけれど、科学的にみるとあまり根拠がないんです。でも、いろんな話があるので子ども達もやっぱりそういった話がある時に、「それは本当に科学的に正しいのかどうかなぁ?」ということを来年は考えてほしいと思っているんですよ。
ということは1年後の大晦日、またその時にお会いしましょう、寺門さん。

-
そうしましょう(笑)。
ハハハハ。時間かな? いやぁ、最後の放送が時間になってしまいました。寺門さんにとって今年はどういう1年だったでしょうか?

-
今年はやはり大変な年でした。地震があったり津波があったり、原発事故があったりしましていろいろ僕も考えることがあったし、「技術は何か?」、「科学は何か?」ということですね。「どうやったら人のために役に立てるのか?」ということを考えさせられた年になりました。
ありがとうございました。今週のサイコー、今年最後のサイコーは科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。

-
そうですね。
そうですか。また明日から来年ですよ。何か変わるといいですね。

-
どうも!
今年最後の放送となりました。ほんとに今年はいろんなことが起きましたけれど、大村さんにとって最大の出来事は、サイエンスキッズは普通どおり放送させていただきましたが、実は北海道に拠点を移して、北海道のテレビもやっているんです。で、何と北海道は…。いい? おせち料理を今日から食べるんです! おせち料理食べるのは明日じゃん、みんな。北海道は、なぜか今日から食べる。おせちのセットを頼んだら、年越しそばもついてきました。それを今日食べろってことなのね(笑)。ちょっと驚きましたけれどねぇ。いやぁ、年末最大の驚きはそれでした。ということで、いろんなことがあった1年でしたけれど、リスナーのみんな、キッズのみんなによって支えられた1年でした。サイエンスキッズは来年もまた頑張って放送していきますので、キッズのみんなもぜひ応援してください。それでは、サイエンスキッズを聴いているすべてのみなさん、今年はどうもありがとうございました。よいお年を!