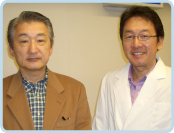キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、明日で東日本大震災、あの津波から1年ですねぇ。1年前のみんな、おぼえているかなぁ?下校の前後の時間帯、東京でも大きな揺れがありました。あれから1年です。最近のニュースで首都圏でも近い将来大きな地震が起こるという予測が報道されていていろいろびっくりしたと思うんですが、先週ひと通りそれは解決しました。ただ、「備えることは大事だよ!」という話。じゃあ、備えも大事だけれど地震の予知「いつ何どき、こういう地震がここで起きますよ」に関しては、今どこまで科学は進んでいるのか?これを聞いてみます。
明日であの東日本大震災から1年、今週も科学ジャーナリストの寺門和夫さんにお越しいただきました。こんにちは。

こんにちは。
先週は、テレビでやっていた「4年以内に70パーセントの確率でマグニチュード7クラスの地震が来るよ」という話ですが、これが「若干違うよ」というお話を聞いて、少し安心したんですけれど。でも、地震の予知については、1年前大きな地震が起きた時に、あれだけ地震予知が進んでいるといわれながら、誰も予知しなかったじゃないですか。地震予知はどこまで進んでいるかをうかがいたいんですけれど。

はい、わかりました。まず、地震予知は非常に難しいんですね。原理的なことからいうと、地震が起こるのはちょっと難しい専門的な言葉で「確率過程」といっています。つまり、ある確率で起こっていくものなんです。ですから、「何時何分にこういう状態になったら必ず起こります」ということは予測できない。
ええ。

-
地震が起こるのは地下の岩盤が割れる、破壊されるわけですけれど、例えば板チョコを折ることを考えてください。
はい。

-
板チョコに力をかけて折ろうとする。どんどん力を入れていくと、どこかでパキッとわかれますね。
はい。

-
だけれど、どの時点でパキッとわかれるかは、自分で力を入れていってもなかなか分からない。
チョコの硬さにもよりますね。

-
そうですね。突然板チョコは折れるわけです。同じように地震の岩盤もいろんな兆候が出てひずみがあって少しずつ動いたりはあるんですけれど、ものすごい大きな破壊として、板チョコが割れるような形でいつ岩盤が破壊されて大きな地震が起こるかは、なかなか正確に予測することができない。これがまずひとつ、一番大きな問題です。
はい。

-
ただし、それに至る兆候はいろいろ出てくるので、今、日本では地下のひずみを測る−例えばGPSなどを使ってかなり正確に「ここの場所はどのくらい動いたり、エネルギーがたまってます」とある程度予測できるようになっているので、「だんだんこの辺が危なくなってきますよ」ということはわかっているわけです。
はい。

-
ですから、ごく大まかにいうと「だんだんこの地域は危なくなってきてます」。それから、「これから何年かわからないけれど、いずれここでは大きな地震が起こりますよ」。例えば、東海地震などはそうですね。
今、一番いわれていますよね。

-
ええ。観測が進んでるし、やっぱり準備しなければいけないといわれてます。ただし、これもとても難しい。例えば去年の東北沖の地震ですが、今回は非常に大きな地震が起こりましたけれど、そこまで大きくない地震は、実は周期的に起こっていたわけです。
三陸沖などで、ちょこちょこありましたよね。

-
そうです。ですから三陸沖地震とか宮城県沖地震がある程度周期的に起こってたので、「そういったものを厳密に調べていけば、きっとあの辺で起こる地震は予測できるだろう」と科学者は考えていたわけです。
はい。

-
ところがまったく別なメカニズムのもの、すごく大きな地震が起こってしまったわけです。
あっ、メカニズムが違ったから。

-
ということなので結局、地震の予知はなかなか難しい。ですから、ごく大まかに「だんだんここが危なくなってますよ」という指標として使うものではないかと思ってます。
よく終わった後に「こういう雲が発生した」とか「妙なイナビカリが起きた」とか「海がこうなった」といろいろな情報が去年もありました。ああいう自然現象みたいなものから予知することは、昔からいわれてますよね。

-
例えば、ナマズの話とか有名ですね。
そうだ、ナマズ!

-
これについて科学者の意見は、大きくいうと二つにわかれているかもしれません。ひとつは、「そういったものは余り地震の予知に役に立たない」という考え方の人がいます。それからもうひとつは、「その中にはちょっと怪しいものもあるかもしれないけれど、もしかしたら地震の予知に役立つものもあるかもしれない」と考えている人たちもいるわけです。
ええ。

-
今、雲の話とかいろんな話があって、その中には確かに後になって「解釈するとこうだったよ」としかいえないものもあるわけですが、中には「科学的にもう少し研究してもいいんじゃないか」というものもあるんです。
はい。

-
というのは、地震は地下の岩盤が割れて起こるわけですが、割れる時に確かにいろんな物理的な現象が起こっている。単に揺れるだけではなくて、例えば地中を流れる電気に影響を与えたりなどがよくいわれています。それ自体はまちがいないですね、電気の状況が変わるのは。
ええ。

-
ですからナマズが地震の前にあばれるというのも、そういった電気を感知してるのかもしれないんですよ。
ふ〜ん。

-
けれど、そこのところはなかなか実証が難しくて、いまだに研究途中です。少なくともそういった分野の研究は、科学の研究としてはもう少し進めてもいいのではないかと僕は思っています。
なるほど。

-
そうすると、単に地殻のひずみというか、「エネルギーがたまってますよ」ということだけではなくて、もうひとつ別の観点から、もしかしたらある程度地震の発生を事前に知ることもできるかもしれない。それは単なる可能性ですけどね。
今、僕らのお茶の間だと緊急地震速報、あるいは携帯電話の速報などがあって、あれはかなりの確率で?

-
はい、そうですね。
でも、「それじゃ手遅れ」という地震もありますよね。

-
あれは非常にいいシステムだと思いますけれど、知らされても避難したり準備するための時間があまりにも短いですね、地震が発生してから信号が出ますので。
はい。

-
やっぱり地震予知として一番いいのは何日前とか数時間前とか、ある程度こちらが準備できる時間的な余裕があるくらいのタイミングで警報が出されるのがいいわけですよね。
そういう時代は来ますかねぇ。

-
これは、なかなか難しいですけれど、いろいろこれから研究者には研究してもらって、少しでも可能性があれば実現してほしいと思います。
なるほどねぇ。僕もそれなりに生きていると、阪神淡路の地震の時もあれだけ大きな被害が起きて「これを超えるものはないんじゃないか」とまでいわれていたのが、1年前起きたじゃないですか。しかも、今ラジオが流れている関東地方にも影響があって、その時に誰もそれを予知してなくて、世間の注目はそれまでは東海地方だったんですよね。

-
そうですねぇ。
だから、本当に地震は…。まぁ「地震・雷・火事・親父」−やっぱり地震が“いの一番”に来るように、日本人は昔から地震と付き合いながら生きてきた歴史もあるし、それに対して「永遠の課題なのかなぁ」と思いましたけれど。

-
そうですねぇ。ですから、われわれが予測していなかったクラスの地震が起こることが分かったわけです、1年前に。つまり、われわれの知識は十分ではなくて、自然で起こることについてまだ知らないこともたくさんあるというような気持ちで、これから自然の研究をもっとしていくことが大事なんじゃないでしょうかね。
なるほど。いやぁ、わかりました。あれから1年ということで考えさせられる放送でした。みんなもわかったかな? 今週のサイコーは、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございました。

-
どうも失礼しました。
ほんとに日本で生活すると、地震はいつ何どき、どこかで突然やって来るわけで、避けられないということです。サイコーに聞くと、備えが大事になってくることがよくわかりました。そうか、板チョコがパキッとどこで割れるか、それが地震なんだけれどねぇ。明日は日曜日ですが、みなさんそれぞれの思いでその日を迎えると思います。いろんなことがあった1年だったけれど、この地震の予知に関してはまだまだ難しいようですね。それでは、来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。3学期ってあっという間だね。