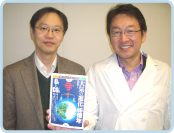キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、新しい学年になって、もうクラス慣れたかなぁ。教室へ入って一番最初にやることは何? あいさつ? ―違うでしょ。呼吸でしょう。そうです。僕たち人間は呼吸をしています。息を吸って吐き出している。酸素を吸って、二酸化炭素を出している。「二酸化炭素って何なのかな?」「いつ頃から酸素ってあったんだろうか?」最も詳しいサイコーが登場します。
今週のサイコーは、東京大学大学院教授の田近英一先生です。こんにちは。

こんにちは。
先生は大気に詳しくて、技術評論社から『大気の進化46億年 O2とCO2』という本を出版されています。酸素と二酸化炭素って誰もが知ってると思うんですよ。僕らは、空気がなくちゃ生きていけないといわれている。

はい。
空気があるから生きているといわれますが、それは酸素という意識でいいですよね。

そうですね。酸素を吸っているということです。
酸素を吸って、二酸化炭素を吐き出している。

-
はい。
それを植物が吸って酸素に変えてくれてるから僕たちが生きている、ということは共通認識でよろしいですよね。

-
はい、そうです。
そもそも空気と酸素って何が違うんですか?

-
空気の大部分は、別の窒素で…。
えぇ〜! そうなんですか?

-
8割ぐらいは窒素です。
窒素って何ですか?

-
窒素は酸素と違う元素からできている分子ですが、これはあまり影響が周りにない。酸素は、物が燃えたりする時に化学反応が起こる。ですから、反応性にすごく富んだ物質です。酸素を吸って体の中でいろんな反応を起こしてエネルギーになる、という大事な物資なわけです。
空気の中で窒素が8割、残りは?

-
残り2割はほとんど酸素ですね。
僕ら深呼吸をしているけれど、体にいいものは2割しか吸ってないということですか?

-
そういうことです!
あと8割は無駄な窒素を吸っている?

-
まぁ、そういうことです(笑)。
あら〜!

-
でも酸素の濃度が高いところに行くと逆に苦しくなるという話もありますから、今の濃度が私たちにちょうどいいようですねぇ。
よく山の天辺に行くと酸素が薄い。

-
ええ、薄くなる。
エベレストの頂上だと、窒素と酸素の割合は何対何ですか?

-
割合は変わらないです。
えっ?

-
ただ薄くなるので呼吸は苦しくなりますねぇ。酸素が少なくなっちゃうので。
じゃあ、酸素の濃度が高いのはどこですか?

-
地面です。低いところですね。高度が低いところは濃度が高くなってきます。
割合は変わらないけれど、酸素が濃いか薄いかでまた違ってくるんですね。

-
はい。
早くも混乱してきた…。

-
フフフフ。
酸素があるから僕らは生きていて、だから地球に人がいるわけで、お隣の金星や水星には酸素がないという解釈でいいんですか?

-
そうですね。ほとんどゼロです。
ゼロ! 何があるんですか、そこは?

-
二酸化炭素があるんですね。
じゃあ、僕らが吐き出したものがあるということですね。

-
そうです。空気がほとんど二酸化炭素でできているという。
先生は『O2とCO2』という著書を出してらっしゃいますが、宇宙はほとんどが二酸化炭素で、酸素がある地球はまれな星ということですか?

-
そうですね。宇宙というとまた別ですが惑星、地球みたいな惑星の大気は二酸化炭素が普通ですね。
ふ〜ん。

-
だから、地球はちょっと変わっているんです。
何でこんなことになったのでしょうか?

-
何ででしょうか? そこが面白いところですね!
わかっているんですか、先生?

-
地球ができた時は、やっぱり金星や火星みたいに二酸化炭素の大気を持っていた。今、地球温暖化問題で二酸化炭素が増えるといってますが、二酸化炭素は割合からすると0.03パーセントですから酸素の20パーセント、窒素の80パーセントに比べますと、すごく微量ですよね。これがちょっと増えてるので温暖化してしまうといってるんですが、実はとても微量です。
はい。

-
ところが、金星や火星は95パーセント以上が二酸化炭素でできてます。これは、長い長い地球の歴史の間にどんどんどんどん二酸化炭素が減っていって今にいたっているんですね。
はい。

-
ですから、「二酸化炭素が増えてる」といってますが、地球の歴史上では二酸化炭素は今最低のレベルにあるんです。
へぇ〜。46億年前に地球ができた時は酸素がなかったってこと?

-
そうです。地球ができた時はなかったんです。
じゃあ、誰が酸素を発明したんだろう?

-
はい。それは植物、光合成をする植物ですね。
ほぉほぉ。

-
植物といってもみなさんがイメージする木などではなくて、プランクトンですね。
ミトコンドリアとか?

-
まぁミトコンドリアとか、光合成をする植物プランクトンですね。そういうものが酸素をどんどんつくっていって、やがて陸上に植物などが出てきて、さらに酸素をつくって…という歴史があるんです。
いわゆる微生物の類いが地球には存在したから、光合成をして酸素が生まれたということですね。

-
そうなんです。
わかりやすい。酸素が生まれて生き物が出てくるわけですよね。そうなると、人間の起源はどこになるんですか?

-
人間は、地球の歴史の最後の最後、本当に最後のところです。
最後のほうか。

-
ですから、人間の歴史の前に動物の歴史があります。人間も動物ですから、動物が出てきたのが今から6億年ぐらい前。
はい。

-
地球の歴史が46億年ですから、最初の40億年間は動物がいなかったわけです。
そういうことですねぇ。動物が生まれたのは、もともとはプランクトンが光合成をして酸素を生み出した。

-
はい。
この酸素によって生き物が生きる環境ができたんでしょうけれど、最初の動物が気になりますね。

-
これは、みなさんが興味を持っているところですが、「そもそもどうして動物が出てきたか?」これは基本的には、「周りの酸素の濃度が増えたから動物が出てこられたんじゃないか」というふうに最近では考えられるようになってます。
はい。

-
ということは、6億年ぐらい前に酸素の濃度が今ぐらいにギュッと上がったような事件があって…。
へぇ〜。

-
それ以前は酸素濃度がずーっと今より低かったので、動物は出てこられなかったという。
そうかぁ。6億年前に地球全体にある事件が起きて生物が誕生したということ?

-
動物ですね。
ちょっと待って。その事件は新聞には載らないけれど、想像するにどういう事件ですか?

-
いろいろ議論になっているんですが、ひとつの有力な今出てきている仮説は、その時、地球が凍りついてしまった。北極から南極、赤道まで全部凍ってしまった。「全球凍結」というんですけれど。
全球凍結。

-
そういうすごい出来事があって、その後に酸素の濃度が一気に増えて生物が進化したというストーリーですね、今注目されてるのは。
へぇ〜。その地球の環境が今、問題になっているじゃないですか。

-
はい。
この二酸化炭素が悪者になるというのは、何でなんでしょうか?

-
「何でなんでしょうか?」というと、私たちの目の前にある十年後、百年後という近い将来に暖かくなると困るからです。いろいろな変化が急激に起こります。
はい。

-
今まで私たちが暮らしていた環境と変わってしまう。そこが困るんですが、実はもし二酸化炭素がないと地球は凍りついてしまうことがわかっているんです。
ほぉ〜。

-
ですから、二酸化炭素がほどよくあるおかげで、私たちはこういう温暖な環境で暮らしていける。二酸化炭素は、実はとってもエライんです。エライというか、役に立っているんですね。
えぇ〜! 二酸化炭素がなければ、6億年前の全球凍結時代に戻る可能性もあるということ?

-
そうです、そうです。
ということで、今お父さんが運転する車の中で聴いているキッズ、このあたりをお父さんと話し合いながら家路に着いてね。また来週、この話を聞いていきたいと思います。ちょっとこの番組短いのでよろしいですか?

-
はい。
今週のサイコーは、東京大学大学院教授の田近英一先生でした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
かなり脱線しちゃったんだけれど、動物の歴史がどうやって生まれたのか、ルーツは?。それから二酸化炭素が悪者扱いされているけれど、実はけっこう大事な役割をしているとか、ちょっと意味深で気になってしょうがないけれど…。実は先生、携帯電話を持ってないというから、次ここに来るまでその辺の話を聞けないというんだよね。今どき携帯電話を持ってない人いるんですね。そういう部分でもチャーミングな先生でした。それでは、来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんな、楽しい週末を。じゃあね!