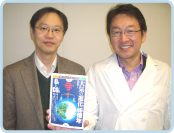キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回も僕たちの日常生活に欠かせない呼吸、酸素を吸って二酸化炭素を出す。この二酸化炭素は、実はある意味地球の中では重要な役割をになっているとのことです。お知らせの後、詳しい話をサイコーに聞いてみるよ。
今週のサイコーも、東京大学大学院で教授をされてらっしゃる田近英一先生です。こんにちは。

こんにちは。
先生、私とたぶん同じぐらいの世代で40代ですか?

はい、そうです。
先生は携帯電話を持ってないそうですが、本当ですか?

-
そうですよ、電話が嫌いなので。
えっ、この時代に!?(笑)メールとかしないんですか?

-
メールはしてます。メールで十分だと思っていて。
パソコンのメール?

-
いえいえ、いろいろ。携帯端末も持ってますけれど、電話をしないというだけです。
すごい! 何でですか?

-
つかまるんですよね。メールだけでもすごくいろんな仕事が舞い込んできて、これに電話を加えたらどこにいても仕事がどんどんどんどん増えてしまうので…ということです。
うわぁ、ちょっとインテリな意見で、いってみたいなぁそれぐらい(笑)。カッコいいなぁ! 不自由だと思ったことは?

-
ないですね。メールで足りてますね。
カーッ!(笑) さぁ、田近先生は技術評論社から『大気の進化46億年O2とCO2』という本を出版されてます。前回気になったのは、地球温暖化で「CO2を削減しましょう」という話。僕らはエコカーに乗り換えたり、暖房の設定温度を低くしたり、いろんな努力をしてきているわけですよ。そういう中で、ただ「CO2がなくなっちゃうと地球が凍っちゃうよ」ということでしたが…。

-
はい。
これはショッキングですねぇ!

-
そうですね。CO2は悪者で温暖化の原因とされてますから、ちょっと意外ですが、もしCO2が地球の大気からなくなってしまうと、気温がマイナス18度ぐらいになっちゃうんです。ということは、氷点下ですね。
はい。

-
つまり地球全体が凍ってしまう。そういうことなんですね。
私は札幌在住で、この冬マイナス11.5度ぐらいまで。

-
なるほど。
でも、北海道はマイナス30度もあったんですけれど…人間は生きてますよ。

-
ええ。ですから、今いったのは平均気温ですから。
それは大変だ!

-
冬場はもっと大変です。寒いところはもっと大変ですから。
ですねぇ。地球上がマイナス18度になっちゃったら、生活はいとなめない。

-
もう全然。というよりも水が凍っちゃうんですね。これはすごく大事なことで、生き物は水がないと生きていけない。1年中氷点下では、生物は生きていけなくなります。
ほぉ〜。

-
もし、そんなことになってしまうと生物が大絶滅しちゃいますから。ですから、二酸化炭素が今、大気中にあるおかげで、地球は生物がこうやって生きていける星になっている。
じゃあ、ほどよく共存してればいいわけですね。

-
そうですね。
ただ僕らが生きて呼吸をして、酸素を吸って二酸化炭素を出すという営みは問題なかったけれど、世の中で余計に二酸化炭素を出すものが多過ぎるということですか?

-
そうです。自然の仕組みはうまくできていて、例えば火山が噴火すると火山ガスは二酸化炭素なので放出されます。ところが人間が出している二酸化炭素は、その100倍〜300倍ぐらいの量を出しているんですね。
はい。

-
ですから、自然の仕組みが追いつかなくなってしまって、それでどんどんどんどん増えていることが問題になっているんです。
僕らの便利な暮らしから出している二酸化炭素が…。

-
はい。
ここ数年で具体的な数値でいうと、どういう上がり方をしているんですか?

-
産業革命がありましたけれど、それより以前の二酸化炭素は280ppmという量だったんですね。ずーっとずっとその量だったんですが、今現在380ppmとか390ppmとか400ppmに近くなっている。非常に短期間、百何十年の間にそうなっているわけです。
30パーセントぐらい上がっているわけですね。

-
そうですね。どんどんどんどんこの先も増えていって、百年後には倍ぐらいの濃度になっているんじゃないかと。
えっ、でもマイナス18度…。たぶん誰もが知ってると思うけれど、氷河期が昔地球にあったというじゃないですか。あれで恐竜がいなくなったといわれてますよね。

-
そういう説もありましたねぇ。
いろいろな説があるみたいですけど、氷河期は実際あったわけですか?

-
あったというよりも、今がその氷河期というか氷河時代なんですね。
えっ! 今?

-
そうです。
今の地球が!?

-
そうです。
何でですか?

-
例えば、南極大陸は氷におおわれてますよね、真っ白で。
はい。

-
ああいう「氷床」というんですが、氷のかたまりがある時代のことを氷河時代というんです。
えっ、そうなんですか!

-
現在は氷河時代なんです。
未来の人から見たら、僕らものすごく寒々とした人たちと思われちゃう。

-
そうです。地球の歴史からみると、今は寒い時代なんですね。
じゃあ、暑い時代はどういう時代だったんですか?

-
暑い時代は、それこそ恐竜がいた時代です。この時代は南極にも北極にも氷はなかったんです。
それは何年前だろう?

-
1億年ぐらいですね(笑)。
1億年前ね。動物が生まれたのは6億年前で、1億年ぐらい前までは恐竜がいたんですね。

-
そうです。
この恐竜がいた時代は、暑い時代。

-
そうです。
地球の平均気温は何度ぐらい?

-
今よりも10度まではいかないですが、6度7度8度ぐらい平均気温が高かった。
それでも、南極北極の氷床はなかった?

-
ええ。ですから今は「温暖化の時代」といわれてますけれど、本当の温暖な時代は恐竜がいた時代のことをいいます。
へぇ〜。

-
何かちょっと違和感というか「おかしいな」と思うのは、氷河期、いわゆるマンモスがいたような時代は今から2万年ぐらい前がそうだったんですが、その時代は今よりももっと氷がはり出していた時代なんですね。
はい。

-
今は、その氷がちょっと後退して小さくなってる時代です。そのはり出していた時代がみなさんのイメージする氷河期ですね。
ですねぇ。でもまだまだ現在も氷河期。

-
そうです。その頃よりはちょっと暖かいんですが、まだ氷が残ってますから氷河時代の中にあるということです。
地球の長〜い歴史の中では、今は寒い時期ということなんですねぇ(笑)。

-
意外にもそうなんです。
暑い時代は近い将来、先生の分析では来るんでしょうか?

-
どうでしょうか。化石燃料がなくなっちゃいますよね。
地下の石炭とか石油。

-
今、二酸化炭素を出してますけれど、もうちょっとしたら出せなくなってるかもしれませんね。
ええ。

-
そうすると二酸化炭素はどんどん元に戻っていこうとしますので、やがて将来は氷河期にまた戻る。氷河期と氷河期の間のカンピョウ期−氷河期の間と書くんですが、間氷期が繰り返してますから、また氷河期になるという。寒いのとちょっと暖かいのを繰り返してるんですね。
今は氷河期だけど、ちょっと暖かいところに来ている。

-
そうです、そうです。
またもっと寒くなる可能性もあるという。

-
そうですね。今までの歴史をみると寒くなって、ちょっと暖かくなって寒くなって何回も繰り返してますから、普通に行くとまた今度は寒くなるという予定ですねぇ。
へぇ〜。今ラジオの前のキッズたちが将来お父さんになる頃、そんな先じゃないですよ。20年30年、その頃の僕たちの暮らし、東京はどうなっていると思いますか?

-
どうでしょう。私たちが努力をしつづければ、今とそんなに大きくは変わらないんじゃないかと期待も込めて思っていますけれど。
何もしないじゃなくて、努力はやっぱりしなくちゃいけない?

-
そうですね。やっぱり努力はしつづけないといけませんね。
そういった意味では去年の節電が今も続いてますけれど、そこは少なからずいい方向に…。

-
そうですね。「努力しよう!」「協力しよう!」という気持ちがあるという意味では、とてもいいことですね。
なるほどねぇ。先生の講義、今度行っていいですか?

-
ハハハハ。どうぞどうぞ!
でも嫌ですよね、こんな同い年ぐらいの人がいたら。

-
いえいえ、質問をどんどんしていただければ。
今の若者たちは、私みたいな質問をちゃんとします?

-
いえ、しないですね。恥ずかしがってるのかもしれませんが、質問しないですねぇ。
今日みたいにレベルの低い質問でもいいんですか?

-
そこからどんどんひも解いていけば。
そうなんですよ。そこから議論していくのが大事ですよね。

-
そうです。大事ですね。
昔はそれでよかったんですが、自分もいい年になってくると恥ずかしいので(笑)。

-
いえいえ、何でも質問するのはいいことだと思いますよ。
お時間となりました。ありがとうございました。今週のサイコーは、東京大学大学院教授の田近英一先生でした。

-
ありがとうございました。
今、地球は寒い時期なんですね。温暖化防止といいながら寒い時期という“目からウロコ”の話だったけれど、いろいろ勉強になりました。みんなはどうだったかな?それでは、もう来週末はゴールデンウィークのウキウキモードに入ってるのかな。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!