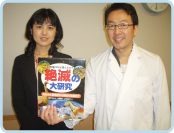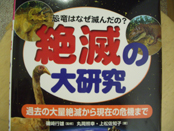キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さあ、今日のテーマは、絶滅。お友だちとよく「絶滅」という言葉を使うかもしれないけれど、本当の絶滅って何なんだろうか? ということで、お知らせの後、サイコーに聞いてみるよっ。
今回のサイコーは、筑波大学大学院准教授の上松佐知子さんです。こんにちは。

こんにちは、上松です。
筑波大学の大学院の先生?

-
はい。
おきれいな方が私の目の前にいらっしゃいます。ご専門は生命環境科学で、PHP研究所から『絶滅の大研究』という本も出版されてます。絶滅−基本的なところからうかがいますが、絶滅ってどういうことですか?

-
絶滅は、生物の種がその後の子孫を残さずに全部滅びてしまうことをいいます。地球上では常に新しい種が次々と生まれているんですが、その一方で別の種がどんどん滅んでいくことで生物界の全体のバランスが保たれています。
はい。

-
いつも起こっていて日常的にあるんですが、それを「背景絶滅」といい、これに対して多くの生物が一度に姿を消してしまうことを「大量絶滅」と呼んで区別しています。
では、背景絶滅が日常的に起きているということは、最近も誰か絶滅したんですか?

-
たぶんどこか、アマゾンのジャングルの中とか深海のどこかで…。
えぇっ! 今日も今どこかで?

-
ええ(笑)。
ゴールデンウィークなのに?

-
はい(笑)。
ヤだぁ〜。逆に誕生もしてるということですか?

-
そうですね、してると思います。
えぇ〜! 例えば、ラジオの前のキッズが知ってるウマも進化と絶滅を繰り返しているって?

-
そうですね。われわれの知っているウマはウマ科という種類の中に含まれている動物で、一番古いウマは大昔にいたヒラコテリウム属という種類になります。
ヒラコテリウム属?

-
はい。これが進化をしましていろんな種が生まれたり、一度産まれた種がどこかで絶滅したり。そういうことをずーっと繰り返して、現在生き残ってるのはエクウスという属ただ一つとなります。
エクウスというのがウマの種類?

-
そうですね。
では、競馬場のウマとか動物園のウマとか、全部エクウスというウマですか?体形がちょっと違うけれど?

-
ちょっと違いますけれど、エクウスという…。
シマウマもエクウス?

-
そうです。シマウマと競馬場のウマは種が違うんですが、属はエクウスという一つの属におさめられています。
日本語でウマだけど、英語ではホースというじゃないですか?

-
そうですね(笑)。
エクウスって何語ですか?

-
エクウスはラテン語です。
ラテン語で、学術名はエクウス。ウマのこと?

-
はい、そうです。カッコよく聞こえると思います。
ヒラコテリウムから今、エクウスになってる。

-
そうですね。20〜30ぐらいの属が生まれては消えていって最後生き残ってきて、最近新しい属としてエクウスが誕生して、それが今見られるウマになっているということです。
へぇ〜。絶滅していなくなった生き物、動物のことをどうやって調べているんですか?

-
みなさん、化石を知ってると思うんですが、化石というのは昔の生物が残した体の一部分であったり、生活のこん跡のことをいいます。
はい。

-
生物が死ぬと体が水の中の砂や泥に埋まって、柔らかい部分がなくなって殻や骨や歯などの硬い部分が化石として残ります。
ええ。

-
化石は生物そのものですが、その生物以外の情報も教えてくれる便利なものです。例えば、生物は生きられる環境が種類によって決まってますので、化石を一つ調べるとその生物が当時生きていた環境がどんなものであったかを知ることができます。
はい。

-
一般的に木の葉っぱは、暖かい場所に生えてるものは輪郭が丸くなってます。寒い地方に行くほど細かいギザギザが出てくる。松や杉の葉っぱも細くとがってますよね。
ほぉ、ほぉ。

-
ですから、地層から出てくる葉っぱの化石が丸い輪郭をしてるかギザギザしてるかを調べると、当時の場所が暖かかったか寒かったかがわかることになります。
なるほど。大量絶滅という、まとめてドカンと一気に絶滅してしまうのが過去に5回ぐらいあったって本に書いてあったんですが。

-
はい。大規模な絶滅は5回というのが一般的な見解です。
例えば?

-
一番大きな絶滅はぺルム紀という時代の終わり、古生代の終わりに起きた絶滅事件で、だいたい2億5,100万年前のことになります。
記憶にないですねぇ、生まれてないから。そんな昔の話。

-
ウフフフ。
それも化石からひも解いて2億5,100万年前という?

-
そうですね、はい。
ぺルム紀の終わり頃?

-
そうです。
どれぐらい絶滅したんですか?

-
陸上にその頃いたのは、古い種類のは虫類や植物ですね。あと、熱帯の海には海洋生物がたくさんいたんですが科のレベルで52パーセント、種レベルではもう90パーセント以上。一説では96パーセントとか99パーセントといわれてますけれど、生物が死滅していなくなりました。
ほとんど地球上の生き物たちが死滅しちゃったということ?

-
ほとんどいなくなったと思います。
じゃあ、種で残った3〜4パーセントといわれているのは誰なんですか?

-
それが有名な、みなさんが知っているアンモナイトの一種です。
へぇ〜。巻き貝みたいなやつ? デンデンムシ系?

-
はい。あれは、イカやタコの仲間です。
アンモナイトはイカやタコなんですか!?

-
はい、そうです(笑)。
全然知りませんでした。

-
グルグル巻いた殻からイカの足が出てると思っていただければいいと思うんですけれど。
ちょっと待ってください。僕らってアンモナイトの化石が世界最古の化石と思い込んでいたんですよ。

-
はい(笑)。
ということは、その前の2億5,100万年前のぺルム紀の段階では、もっと別の生き物が96パーセントぐらいいたということ?

-
いたということですね。全然違う姿かもしれませんし…。
恐竜が絶滅したのは何年前ですか?

-
恐竜が絶滅したのは、6,550万年前です。
最近ですね、2億5,100万年前に比べると(笑)。

-
ついこの間の(笑)。
最近かぁ、恐竜は6,000万年前まで生きていたのか。それは、過去5回の大量絶滅の一つに含まれるわけですか?

-
はい。過去5回の最後の大量絶滅になります。
恐竜の時代は1億3,000万年ぐらい続いて、突然絶滅した理由は氷河期が来たからといわれてますが、諸説ある中で上松さんは何だとお考えですか?

-
もう少し細かい原因がたくさんあったと思うんですね。中生代の終わり、白亜紀末ですが、白亜紀の後半に例えば酸素欠乏事件が起きたり、寒冷化が起こったりして、いろんな原因でだんだん数が減ってきたところに、有名な大規模な隕石が落ちてきて地球にぶつかった。それが最後のとどめですね。とどめをさされて恐竜が死んでしまったと考えられます。
ふ〜ん。隕石が恐竜にあたって死んじゃったわけではないんですよね。

-
そうですね(笑)。
隕石があたって、地球の環境が恐竜が住むのに適さなくなって絶滅したということですよね。

-
そうですね。直接的にぶつかったところにあった岩石が全部吹き飛ばされて、ちっちゃなチリになります。同時に周りに大規模な山火事が起こり、ススが巻き上げられて空気中に漂います。
はい。

-
そうすると地球全体をチリや雲がおおってしまって、太陽の光を遮断して寒冷化も起きます。光合成ができなくなるので植物がまず激減して、植物を食べていた草食動物が減り、それを食べていた肉食動物も減る。どんどん連鎖的に絶滅が起きていくことになります。
ドミノ倒しみたいなものですね。1個ドボッと来たらバタバタバタッと。

-
そうですねぇ。
6,000万年前の恐竜の絶滅後、生き残った生き物がいるわけですよね?

-
そうですね。
それは恐竜よりもタフな生き物ということですよねぇ。

-
タフな、そうですね。
それは一体誰ですか?

-
はい。ここにいるわれわれ人間を含めた哺乳類になります。
へぇ〜。

-
哺乳類ともう一つ…。今地球上を支配しているぐらいの大型生物というと、哺乳類と鳥類という。
トリ。はぁ〜!

-
トリですね、はい。トリと哺乳類が地球上の恐竜がいなくなったすき間に入り込んでいって生態系を支配するようになります。
実は、トリは恐竜の生き残りという説もあるということで。

-
はい。
このあたりをまた来週うかがっていきたいと思います。あっという間でしたよね。

-
あっという間でした(笑)。
また来週よろしくお願いします。

-
よろしくお願いします。
今週のサイコーは、筑波大学大学院准教授の上松佐知子さんでした。
ぺルム紀、恐竜よりもさらに2億年も昔に大量絶滅が起きていた。それで生き残った種もいるという。来週またサイコーに詳しく聞いてみようかなぁ。とてもわかりやすいお話でしたね。それでは、バイバイ!