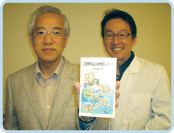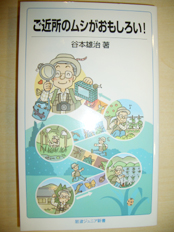キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今日はユニークな肩書きのサイコーが登場します。「プチ生物研究家」、わかる?小さな生き物を研究してるってことなのかな。ということでお知らせの後、プチ生物研究家が登場しま〜す。
今週のサイコーは、プチ生物研究家の谷本雄治さんです。こんにちは。

こんにちは。
谷本さんは現役の新聞記者でありながら、プチ生物研究家として生き物に関わっている。岩波ジュニア新書から『ご近所のムシがおもしろい!』という本をはじめ、多くのムシに関する本を出されてるということですねぇ。かなりムシに詳しい?

あんまり詳しくはないですけれど(笑)。あまり詳しくないところで、プチ生物研究家という肩書きを使ってるんです。
この「プチ」というのは小動物のプチではなくて、谷本さんそのものが謙虚でプチということですか?

-
そうですねぇ、二つにかけてるんですが(笑)。プチという小さな生き物の意味と、研究者のようにまじめな研究はとてもできないんで、ちょっと子どもの自由研究の延長ぐらいですね。そういったことをやっている、ちょっとだけ研究気分を味わっているという意味で両方にかけて「プチ生物研究家」にさせてもらってます(笑)。
ちびっ子たちはこのプチ生物、興味深いわけですよ〜。

-
そうですか。
あと2ヵ月もすると夏休みの真っ只中でいろんな昆虫採集があると思うんですが、インターネットのアンケートでこんなランキングを見つけました。「形がカッコいいと思うムシは何か?」。上位三つがやっぱり定番ですよ。カブトムシでしょ。

-
はい。

-
ふ〜ん。
これはプチ生物研究家としては?

-
そうですねぇ、カマキリがちょっと意外な感じがします。
そうですか。カブト、クワガタは“あり”と?

-
そうですね。カマキリは意外に嫌われてるんじゃないかぁと(笑)。
そうですか。でも、カッコいいじゃないですか。

-
まぁ悪役というか…。
悪役ですか。

-
そちらの意味で何かサングラスが似合いそうですよねぇ、黒いサングラスが。
イラストにしたらカマキリはねぇ(笑)。

-
カッコいいですねぇ、そういう意味では。
やっぱりつかまえる子どもたちは多いじゃないですか。コツがありますよねぇ。夏を前にぜひ採取のコツを教えてください。

-
カブトムシ、クワガタというとクヌギの木の樹液のところにだいたい集まることが多くて、よく本にも書かれてるし調べてると思います。私も実はクワガタムシを3匹飼っていて、去年の主に夏ですが拾ったんですね。
ええ。

-
わが家の前に雑木林があって、夜の帰り道に道路を見ていると1匹ずつ転がっているのがいて、それを3匹ぐらい集めたことが一つと、それから灯りに集まってくるんですね。その灯りをチェックしてると、大物はなかなか難しいけれどコクワガタというクワガタの中では小さなものですが意外と灯りに集まってくるので盲点かもしれないですね。
カブトムシやクワガタは早朝のクヌギ林の樹液のあるところという定説だったんですが、灯りですか!?

-
そうです。
夜ということですか? 夜も“あり”ですか?

-
“あり”ですね。
それはちょっと…、衝撃ですねぇ。

-
そうですか。私は学生時代、実はガを…。嫌われ者ですが、ガを集めてたんですよ。建前はガの分布を調べるという。どこにどんなガがいるかという種類を調べることですが、そういう時に白いシーツを張って灯りをともすんです。
はい。

-
ガはいっぱい飛んでくるんですが、その中に混じってクワガタやカブトムシもよく飛んでくるんですよ。
へぇ〜。

-
ですので、灯りはやっぱり好まれてるんでしょうねぇ。
都心部だと誘蛾灯(ゆうがとう)というガをおびき寄せ感電させて殺しちゃうというものを見ませんが、田舎に行くと誘蛾灯にいろんなガがバチバチバチバチ。その中にカブトムシやクワガタもいるということですか?

-
そうですね。灯りの下を見たり、その近くに木があればしがみついたりしてますので。
へぇ〜。

-
私はふだんどこか地方へ行っても、灯りがあるとたいてい見て回るんです。
クヌギ林は関係なく、灯りのもとにカブトムシやクワガタが集まってくる?

-
はい。
なるほど。いいこと聞いたなぁ。そしてもう一つ、カマキリですよ。つかまえ方というかコツはあるんですか?

-
後ろから首筋を指2本でつかむ。そうすれば、かまれるというかカマでひっかかれることもまずないと思います。
身をよじって抵抗してくるじゃないですか、カマをこっち側に向けたりして。

-
首のところがちょっと硬い感じになってるので、あそこをつかめばまず大丈夫だと思います。
大丈夫?

-
大丈夫です。今度やってみてください。
やってみたいと思います。人気のムシがあれば嫌われるムシもいるわけで、嫌われ者というとやっぱりゴキブリですよね。

-
そうですねぇ。
ゴキブリは何であんなに嫌われるんですか?

-
まず色合いですね。色が茶色っぽくて暗いところにいることがありますよね。
はい。

-
それから脂ぎったようなイメージがあるし、体が平べったくて細いすき間にも入ってしまい人間にできないようなことをするというすごい能力も、ひょっとしたら嫌われる原因かもしれないですね。
でも、ゴキブリってすごい歴史のあるプチ生物らしいですね。

-
そうですねぇ。化石が現実に残っているので、どのくらい前にいたかがわかるそうですが、だいたい3億年ぐらい前にはいたといわれてます。
はぁ〜。

-
われわれ人類が500万年ぐらいとすると、それよりもずっとずっと大先輩なわけですよね。ですので、本来は敬意をはらわないといけない生き物かもしれないですね。
かといって、台所で「ゴキブリ先輩〜」と言ったらお母さんにひっぱたかれそうですからねぇ。

-
ハッハハ。そうですねぇ。
ゴキブリって万国共通ですか、嫌われ方は? 世界中でやっぱり、じゃけんにされている?

-
ゴキブリというと、日本で目にするのは屋内ですよね。台所で見ることが多いというイメージがあるんですが、ゴキブリ全体から見るとほんの一部です。
ええ。

-
たいていは森の中にいて、森のゴミ掃除というかいろいろ分解するような役割をしてるんです。外国に行くと、日本で見るよりずっと大きなゴキブリがいたりして、それをまたペットにして飼って楽しむ人もいらっしゃるんですよね。
うん!? ゴキブリがペットということは、カナブンとかのノリでゴキブリを飼っちゃう感じですか?

-
そうです。
僕は、ゴキブリイコール不潔なイメージがあるんですけど。ゴキブリは不潔なんですか?

-
日本の室内にいるものは、いろんなところにばい菌を運ぶことであまりよくないと思うんですが、森の中にいるゴキブリは、そういうのはあまり聞かないですね。
なるほど。屋内のゴキブリは、屋内の様々な雑菌などを運んじゃう。ハエみたいなもんですよね。

-
そういうことです。
汚いものについているハエがいたら、やっぱり嫌ですものね。それと同じ感覚ですね。

-
そうですね。日本にもオオゴキブリというのが森林にいるんですが、そのオオゴキブリを子ども達に見せるとすごく喜ぶんですよ。
ほぉ〜。

-
なぜかというと、体が5センチぐらいあるのかな。それくらい大きなものということもあるんですが、見た目がよろいを身に着けているようなカッコよさもありますし、やっぱり堂々としているというんで、ゴキブリだとわかっていても見せると手を出す子ども達が多いんですよ。
ほぉ〜。

-
彼らに聞いてみると、やっぱりクワガタやカブトムシの仲間と同じような感覚でそういったものを触るらしいんです。
そうか、ゴキブリそのものに罪はないんですね。

-
ないんですね(笑)。
いわゆる不潔感でいわれちゃうのは、不潔なものから不潔なものへ渡り鳥的な動きをしているイメージがあるからでゴキブリは不潔じゃない。

-
そうですね。圧倒的に清潔なものが多いということでしょうね。
おっ、すごい衝撃的な言葉をいただきました! いやぁ、昼日中にこの番組はゴキブリの話で盛り上がっているというのも…。

-
ハハハ。
いいお話でしたね。もうこんな時間だ。今週のサイコーは、プチ生物研究家の谷本雄治さんでした。また来週もよろしくお願いします。

-
はい、よろしくお願いします。
ゴキブリの大半は汚れてないという衝撃だったんですけれど、やっぱりイメージだよね。何かほかの名前があるといいんですけどねぇ。いい名前があったら教えてください、みなさん。谷本さんはちょうど昨日、また新しい本を出版されたそうです。岩波書店科学ライブラリーから『週末ナチュラリストのすすめ』ということで、週末の土曜日日曜日、みんなのお休みの時に自然と触れ合うすすめです。昆虫採集に関してもいろいろ書いてあるということなので、ぜひ手にとって読んでみてください。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんな、楽しい週末を。バイバイ!