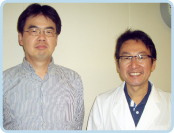キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、みんなは五感という言葉を聞いたことある? 視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚−これ五感です。みんなが今聞いているラジオは耳、聴覚でキャッチするものですね。今日はその聴覚を研究している人が登場するんですけれど、聴覚は耳だけではないという深いお話だそうです。
今週のサイコーは、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の柏野牧夫さんです。こんにちは。

こんにちは。
柏野さんは、NTTの研究所で聴覚の研究をされていらっしゃる。

そうです。
まさにラジオにぴったりじゃないですか!

そうですねぇ、まさに。
例えば、どんな?


聴覚というと普通の人が考えるのは耳だと思うんですが、実は音を聞くのは耳だけではない。
はい。

脳があってはじめて音がちゃんとわかるわけで、私が研究しているのはその脳の仕組み、働きです。
ちょっと難しいんですけれど、何かツカミを。

そうですね。じゃあ、一番有名なデモンストレーションをいきましょうか。
はい。

-
まずちょっと変な音楽を聞いていただきましょう。ぶつ切りというか、変な感じの音楽です。
みんなも聞いてね!

-
いきます。
(※途切れ途切れのピアノの曲)
有名な曲ですね。ベートーベンの『エリーゼのために』。何ですか、これ?

-
たぶん曲だとわかると思うんですが、非常に不自然じゃないですか。
はい。

-
これは、『エリーゼのために』を演奏したものから一定の時間ごとに音を取ってしまったものです。なので、取ったところが抜けて聞こえて非常に聞き苦しい。そこで、今度は抜いたところに関係ない雑音、ザッザッという音を入れてみます。ちょっと聞いていただきましょう。
はい。
(※抜けた箇所に雑音が入った曲)
耳ざわりですけれど、抜けたところにこの耳ざわりな音を入れるとナチュラルになるんですね。

-
そうです。ちゃんと余韻までなめらかに聞こえましたよね。切れ切れではなく、音楽のリズムなども戻ってくる。
はい。

-
これは何でそうなってるかというと、まさに脳が補っているわけです。
えぇ〜! 空白を雑音で埋めることによってなめらかに聞こえるのは、脳がそこを補填(ほてん)してるってこと?

-
そういうことです。大きい音があると聞こえなくなります。聞こえなくなったらあきらめるんじゃなくて、そこを何とかして補ってやろう。要するに前、後ろにある音から頭の中でそこをつくり出すということですね。
じゃあ、みんな同じことを考えたと思うんですけれど脳みそが働いたんですね、今。

-
働いたんです。
へぇ〜。

-
だから「働かせよう」と思って、脳みそは働いてない。
はい。

-
算数の問題を考える時みたいに一生懸命「う〜ん」と考えはじめて働くものではなくて、日常暮らしている時でも息している時でも、何か物を持つ時でも脳みそはずっと働いているわけです。
ほぉ〜!

-
音を聞く時でもずっと働いてます。
ふ〜ん。

-
その働きを研究してるということです。
なるほどねぇ。もうちょっとデモンストレーションでおもしろいものはありますか?

-
そうですねぇ。
今のおもしろかったなぁ!

-
変なもののほうがいいですよね。
変なことをしてください(笑)。

-
はい(笑)。言葉を聞くのは当たり前だと思うじゃないですか。
はい。

-
それがそうでもない、というのをやりましょうか。まずは、この言葉を聞いてください。
(※「バナナ」という言葉を1回)

-
これは何と?
バナナ。

-
普通にはっきり発声した「バナナ」という言葉です。これをちょっと細工するんですが、「バナナ」をずーっと繰り返し再生します。ただただ繰り返します。そうするとどういうふうに聞こえてくるのか、ちょっと注意して聞いてみてください。
(※「バナナ」という言葉の繰り返し)

-
人によっては「まったく変わらない」という人もいます。
「バナナ」のまま?

-
「ずっと最後までバナナのままで何がおもしろいの?」という人もいます。
えぇ〜!

-
それは別に異常というわけではないです。また別の人だったら、「あまりにも変わりすぎてちょっと報告できない」、「毎回毎回違うことになっていくので訳がわからない」という人もいます。
ほぉ〜。ちなみに柏野さんは何て聞こえますか?

-
私はかなりいろいろ聞こえるほうで、「ナッパ」とか「ナンパ」とか「ハナ」とか。あと別の人の声とか機械の音とか。要は1人ではなく2人に聞こえたり3人に聞こえたり、変なドラムみたいな音がずっと鳴っているように聞こえたり、わかれてくるだけじゃなくて、それがまた違うふうにどんどん組み変わっていく。
今ので?

-
ええ。
ご自身がプレゼンテーションしてらっしゃいますが、もうかなりふくらんでいろいろな方向性で聞こえてるんですか?

-
もう、聞こえてますねぇ。
えっ、うそ! 僕は「ダンナ、ダンナ」とか「ダン、ダン」しか聞こえなかったんですが、聴覚的な視野じゃないですけど“聴野”が狭いんでしょうか?

-
いえ、狭いかどうかわからないですけれど、ただ我々が脳の働きを調べてる内にわかってきたことがいくつかあります。ひとつは脳の中にブローカ野というところがあって…。
ブローカ?

-
カタカナでブローカと書きます。そこがこわれるとしゃべれなくなるような失語症になる。そこの活動が大きいと、どんどん変化する。要するにたくさん変わる傾向が強いとか。
ほぉ〜。

-
また別のところの活動が非常に強いと、逆に変化する傾向が少ないとか。要は脳の中にせめぎ合いがあって、ある場所はどんどん変える方向に「こうかな、ああかな?」と仮説をつくり出していくわけです。
ええ。

-
ところがそれがいいかというとそうでもなくて、そうすると安定しない。ある物を見たらそれはある物だと認識しなければいけないわけで、「こうかな、ああかな?」と思っていると世の中が常に変わってしまうじゃないですか。
はい。

-
だから二つの働きの両方が必要で、世の中をいろいろに解釈しようという働きと、世の中を止めてみよう安定させようという働きがあって、それが脳の中で綱引きをしている。
ふ〜ん。

-
そのバランスが違うと、ある人はものすごく変わって聞こえる。ある人はあまり変わって聞こえないという差が出てきたりするんですよね。
ということは、柏野さんの場合はけっこう前者ですね。

-
前者です。新し物好きというか、「こうかな、ああかな?」と。要は落ち着かないともいえますよね。
でも、そちらのほうがクリエイティブ的な脳を持っていることになるんですかねぇ。

-
そうかもしれないです。そのあたりのつながり、本当にその人がクリエイティブかどうか調べたことはないのでわかりませんけれど。
いやぁ、ちょっと柏野さん明言を避けたけれど、僕は保守的な脳みそになってると今気づき…。

-
ハハハハ。
ちょっと落ちこんでます。

-
いやいや、落ちこむ必要は全然ないです。
まいったなぁ。政治の世界とあい通じるものがありますねぇ(笑)。

-
世の中だいたいバランスですから、そのバランスのどこがいいかは状況によって変わるんですね。
はい。

-
状況が不安定な、例えばいっぱい雑音があって声がはっきり聞こえないような場合は「こうかな、ああかな?」が必要かもしれない。でも明々白々よく聞こえている時に「こうかな、ああかな?」といっても仕様がない。
ええ。

-
非常に安定している時、あるいはそうじゃない時−声で言えば非常にクリアに聞こえている時そうじゃない時、一番いいバランスでたぶん違うんですよ。だから個性とはそういうことで、どっちが偉いじゃない。いろんな人がいるから全体としてうまくいく。
よかった、今ので救われた。

-
これで耳が悪いと思う必要はまったくない。そういう性質だと思うのはいいかもしれないですけれど。
今、最後のお言葉でSMAPの『世界に一つだけの花』がふわっと脳に来ましたねぇ。みなさんもきっと来てますね。もうこんな時間ですか、ありがとうございます。柏野さん、うちの番組は放送時間が短いんですよ。また来週、続きを聞かせていただけるということでよろしいでしょうか?

-
もちろん!
よろしくお願いいたします。今週のサイコーは、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の柏野牧夫さんでした。ありがとうございました。

-
ありがとうございました。
結局、脳なんだよねぇ。でも「痛い」とか「かゆい」のも脳が反応するから、そういう感覚になるということで、やっぱり五感をつかさどるものは脳ということなんですかねぇ。おもしろかったねぇ。じゃあ、また来週も夕方5時半ね。バイバイ!