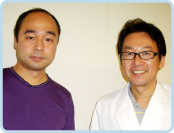キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。夏休みは充実してるかな? 楽しい思い出をたくさんつくる時間ですけれど、気がつけば、もう半分過ぎちゃってます。宿題もそろそろ手つけてね。そんな宿題、自由研究のヒントになるようなサイコーが今週も登場しますよ。生き物の巣、今日は外国編だそうです。
今週のサイコーもサイエンスライターでイラストレーターでもいらっしゃる北村雄一さんです。こんにちは。

はい、こんにちは。
前回のモグラの話はおもしろかったですねぇ。あれから僕は、地面を見ると土の固まり、洗面器をひっくり返したような土を探してばっかりですよ。

そうですか。
モグラ塚。

フフフ、モグラ塚。モグラ塚のあるあたりを見ると、だいたいどこにトンネルが通っているか見えるんですよ。意外と直線状に並んでたりしますから。
いやぁ、そこまで専門になるにはちょっと時間がかかるかもしれないけれど。でも地中で生き物がどんな暮らしをしているか、想像するのも楽しいですよねぇ。

ええ、ええ。
今週は日本を離れて、北村さんが海外で「この生き物の巣はすごいな!」と感心したお話をいくつかうかがっていきます。まずは、シロアリ。

シロアリですね。
キノコシロアリの一種、ベリコサスというアリがいる?

そうです。
この巣がすごいと思われた。

そうですね。
まずベリコサスってどんなアリですか?

シロアリで、ちなみにシロアリってアリじゃないんですよね、形がアリっぽいですけれど。
そうなんですかぁ!? 何だよ、それ(笑)。

よく見るとお腹にベロベロベロッと節があって、アリみたいにウエストがキュッと細まってなく、ずん胴で頭がカチッとしてます。あの形を見ると、ゴキブリの子どもによく似てるんですよ。
ゴキブリ系!?シロアリはゴキブリ!

-
あれ、ゴキブリなんですよ。
昔、“シロアリ参上”という駆除する会社がありましたよね(笑)。

-
ええ(笑)。
あれは、実は“ゴキブリ参上”なんですね。

-
アハハ、まぁそういうことですね。
聞こえが悪くなると、急にイメージが悪くなりますね(笑)。

-
なりますねぇ。シロアリって外国の地方によると食べ物にする時もありますが、シロアリを食うのはいいけれど、ゴキブリは嫌ですねぇ(笑)。
うわぁ。わかりました。じゃあ、ゴキブリの一種シロアリのベリコサスはどこに住んでいるんですか?

-
アフリカです。
ベリコサスの巣は、何がすごいんですか?

-
草原やサバンナの乾いたところにいきなり、例えば高さが大きなもので8メートルぐらいの塔になってダーンと立ってる。
巣がタワーなんですね。スカイツリー状?

-
ええ、もうほとんどそうです。見た目はサグラダ・ファミリアとか…。
スペインの?

-
ああいう(笑)。スカイツリーをちょっと円錐(えんすい)形にしたような、これはもう立派な建築物です。考えてみれば、アリからしてみたらスカイツリーどころの騒ぎじゃない大きさですからね。
サグラダ・ファミリアということは、何百年たってもまだ建築中ですね。

-
そうですね、確かにこわれても増築して…。ちっちゃいところから始めて、最初「あれっ、コブみたいなのが地面にある」ぐらいの状態からだんだんだんだん成長して、ずっと建築中です。
ほぉ〜! イメージは何色の?

-
茶色です。
茶色で8メートルぐらいの高さ。

-
カチカチで、たたくと中が空洞っぽい。ポンポンと音がするんですよ。
思いっきりたたくと折れちゃうような?

-
いえ、そう簡単にこわれるものではないです。
太さはどれぐらいですか?

-
太さは底面で2〜3メートルぐらいあるとか。
かなり、すそ野は広いですね。

-
ええ。それでなおかつサグラダ・ファミリアみたいに他にもサブのタワーがついているんです、ペタペタペタペタ。
ほぉ〜!

-
それもなかなかこわれなくて、ノコギリで切ってみると中がスカスカになっていて、シロアリがいっぱいワーッと行ったり来たりしている。
そのベリコサスの巣をノコギリで切ったら、いわゆるゴキブリなわけですよね(笑)。

-
まぁゴキブリには、もはや見えないけれど(笑)。
研究のために切ってみると中が空洞になってた。

-
しかも地面の下のほうまで、タワーの木をさらに掘り下げると要するに地下があるんですよ。そこに本体があって、でっかい饅頭みたいなのがボコッとあるんです。
へぇ〜。

-
その饅頭の中身が何かというと、実はシロアリは木や草を食べるので、周りにワーッと出かけて行って「よいしょ、よいしょ」と持ち帰った物をペタペタペタペタくっつけて、そこにキノコが生えるんですよ。
ほぉ〜。

-
そのキノコを食べているという。
えぇ〜、そうか。あと南アメリカに珍しいクモの巣があるという?

-
ムレアシブトヒメグモですね。
ムレアシブトヒメグモ。

-
ええ。群れで足が太くて、姫のクモという意味です。
読んで字の通りなんですね。

-
そのまんまです(笑)。
アハハハハ。

-
だいたい1メートル、大きいもので4メートルぐらいの巣をつくります。
1メートルから4メートルのクモの巣!?

-
ええ。
クモの巣は、あの張ってるやつですよね。

-
よく草原や生け垣にワシャッと白く固まってるクモの巣があるじゃないですか。
いわゆるテントをピンと張ってるようなクモの巣じゃなくて、ワラワラッといるようなクモの巣?

-
クモの巣にもいろいろありまして、僕らがよくイメージする網を張る円形のクモの巣を「円の網」と書いて円網(えんもう)といいます。
はい。

-
もっと原始的なやつらだと「適当に糸を引っかきまわしておけばいいじゃん」みたいな感じで、お皿みたいな巣をつくるんですよ。それの発展型で、見た目はバカデカイ虫の繭(まゆ)かというようなワシャッとした固まりで、中にいるのは4ミリぐらいのクモが何十何百何千とワーッといるという。
その4メートルの巣の中に4ミリぐらいのクモが?

-
ええ。
へぇ〜!

-
中に虫が入ると襲うんですね、ワーッと。
虫がそこにつかまっちゃったら、4ミリのクモたちに襲われて解体されるわけですね。

-
いいように襲われて、もはや大きくてもどうにもならないですね。
へぇ〜。いやぁ、おもしろい! さっきのアフリカのシロアリじゃないですけれど、高さ8メートルでずっとつくり続けるといいましたが、巣って永久に使えるんですか?

-
ほとんど永久に、何世代何世代も使うやつがいますよね。
へぇ〜。

-
例えば南アフリカの鳥ですが、シャカイハタオリドリとか。
シャカイハタオリドリ? これはどういうふうに和訳すればいいんですか?

-
社会と機(はた)を織(お)る、要するにキッコンキッコン、機を織る鳥という意味です(笑)。
社会って、どういう意味の社会ですか?

-
群れで社会なので(笑)。
日本人が勝手につけた学術名みたいな感じですね(笑)。

-
日本語名で和名といいますが、まんまな呼び名です(笑)。“社会の機織鳥(はたおりどり)”。
“社会の機織鳥”はどこに住んでて、巣は何年ぐらい持つんですか?

-
南アフリカのカラハリ砂漠にいて、砂漠に巣をつくるんですよ。だいたい100年ぐらい持つといわれてます。
へぇ〜。

-
こいつらネコジャラシの茎をパキパキッと持ってくると、「よいしょ、よいしょ」と木にくっつけてみんなでワーッと差し込むんですよ。
へぇ〜。

-
かやぶき屋根はカヤをふいてるだけの屋根ですが、「えいえいっ」と中につっ込んでぎっしり詰まってくるので、「本当にかやぶき屋根みたいになったぞ。でもこれじゃ屋根だけだよなぁ」と思ってると、そこにさらに穴をつくる。ここにもう少しつっ込むなどやると穴ができるんで、人間のかやぶき屋根の屋根だけで穴がモコモコあいててそれぞれ巣になってて、みんなが子育てしている。
へぇ〜。

-
日本だと、ひとたまりもないですよね、すぐ腐ったり傷んじゃいますから。日本人はかやぶき屋根をふき替えますから。でも砂漠だったら、そう簡単に傷まないですよね。
カラッとしてるからですね。

-
だから100年も持つ。でも100年持ってる間に鳥の寿命で考えたら一体何世代たっているという。
僕らの住宅を100年持たせるには相当大変といわれている中で、南アフリカのその…。

-
シャカイハタオリドリ。
アハハハ、シャカイハタオリドリ。

-
ハタオリドリという鳥がいて、彼らは求愛する時にオスが稲の仲間やネコジャラシの細長い葉っぱを持ってきて「よいしょ、よいしょ」と編んで巣をつくる。それでハタオリドリというんです。
へぇ〜。

-
その発展型がシャカイハタオリドリになっている。
そうですかぁ。あっという間でしたねぇ。おもしろいなぁ! また、ぜひもっといろんな生き物の生態を教えてください。

-
ええ、わかりました。
化石の発掘もまたやってくださいね。今週のサイコーはサイエンスライターでイラストレーターでいらっしゃる北村雄一さんでした。ありがとうございました。

-
はい、ありがとうございます。
何か外国に住んでいても、ムレアシブトヒメグモという日本の名前をつけられちゃうという。見た目で学者さんは判断するんだろうけれど、不思議ですねぇ。巣の話も興味深かったですが、生き物の名前の由来を自由研究のテーマにどうかなぁと思いました。みんな、どうだったかな?それでは、楽しい夏休みの後半を過ごしてね。バイバ〜イ!