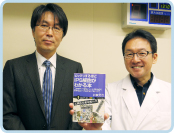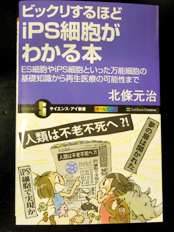キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、いよいよ街のイルミネーションもきれいで、明後日はクリスマスイブですね。今年も残りわずかになってきましたよ。何といっても今年、科学の世界で大きなニュースというと京都大学の山中先生のあのiPS細胞のノーベル賞ですよねぇ。iPS細胞、聞いたことあるけれど、再生医療といわれています。「これ、具体的に何ができて、今後どうなるの?」 とても詳しいサイコーが登場します。
今週のサイコーは、東海大学の兼任講師でセルバンクという会社の代表をやってらっしゃいます北條元治さんです。こんばんは。

こんばんは、よろしくお願いします。
先生は、弘前大学医学部を卒業した後でセルバンクという会社を立ち上げて、複合型培養皮膚の事業を東海大学と協同で実施されている。ちょっと難しい話ですが、わかりやすく教えてください。

ほんとに平たくいってしまうと、人の皮膚のコピーをつくる。皮膚という臓器のコピーをつくっていく。
はい。

-
じゃあ何に使うのかというと、やけどで体のほとんどの皮膚を失ってしまった人は従来の植皮術という手術は残っている皮膚が少なくできませんので、その人のコピーをつくるというような技術で救命していくことを医療の専門でやっています。
とてもわかりやすいですね。皮膚、バカにしちゃいけませんよね。

-
そうですね(笑)。
いや、本当に。皮膚切ったら痛いし、皮膚けずれちゃったら貼りつけなきゃいけないんですが、コピーをとれるように発展させようとされている。

-
はい。
iPS細胞って今年話題になったじゃないですか、京都大学の山中先生。

-
はい。
あれも再生医療といわれてますけれど、iPS細胞と先生のセルバンクのやってらっしゃる複合型培養皮膚というのはイコールですか?

-
これもなかなか難しいご質問ですが、大きな意味でいうとイコールです。ただ私がやっているのは皮膚の細胞をとってきてCPCというプロセスと加工するので、皮膚という臓器しかできないんですね。
ほぉ〜。

-
皮膚の細胞を持ってきますので。それから骨の細胞を持ってくれば、骨のコピーしかできない。神経の細胞を持ってくれば、神経のコピーしかできない。ただiPS細胞を使うと、たったそれ1つだけで皮膚にも神経にも血管にも角膜にも何にでもなることができるので、iPS細胞はその1個だけで万能ということです。ですので、万能細胞と呼ばれてるんですね。
6年ぐらい前にこの細胞の話が話題になった時、当初は万能細胞といってマスコミなども取り上げてましたよね。

-
そうですね。そういう意味での万能ということですね。
このiPS細胞、万能細胞はゆくゆくはどういう医療のジャンルで使われていきそうですか?

-
時間軸を無視して夢ということで話をしてしまうと、心臓のコピーができたり神経のコピーができる。今まで半身不随の人はどんなに手術をやってもお薬を飲んでも治らなかったけれど、ご本人の神経や脊髄のコピーができたら治ってしまう可能性がある。
ほぉ〜。

-
非常に夢のような技術です。まぁこれは時間軸を無視しての話ですけれど。
極論をいうと、そこまで可能性を秘めているということですね。

-
今まではSFで空想の出来事として語られていたものが、時間軸を無視してですが現実の世界におりてきた。人間の届くところにおりてきたというのがiPS細胞と考えていだたければいいと思います。
でも、時間軸というのが障害になっているんですか?

-
はい(笑)。
それはどういうことですか?

-
実際に私がやけど用の皮膚のコピーをつくって熱傷、やけどの患者さんの治療に使っているんですけれど、実はこの技術ができたのが1975年なんです。
じゃあ、37年ぐらい。

-
40年近く経って、でもいろいろな社会的仕組みや薬事、薬価修正…、いろんな社会的な仕組みでまだ実用化はされてない。
できるんだけれど、ルール上やっちゃダメという。

-
そうですね。それでiPS細胞に関してはまだ臨床応用もできていませんので、臨床応用ができてだいたい30年ぐらいといわれてます。最初にいった脊髄損傷の話とか本当に実用化されて恩恵によくすることができるのは、ちょっと悲観的な話ですが50年ぐらいかかるんじゃないでしょうかねぇ。
じゃあ、なが〜い話ですか?

-
そうですねぇ。今の社会システムがこのままで行ったらという前提の話ですけれど。ただ国のほうも厚労省、経産省もどういうふうにしていくべきかという委員会に出てきたんですけれど、「やっぱりこのシステム、何とかしないといけない」というのが中央官庁みんなの意識としてありますので、そこに期待していくというような感じでしょうか。
そうなると難しい話だけれど、この間の選挙があって政治もいろいろ動きがあるから、そういうのも障害になっているわけですね。

-
そうですね。科学技術は技術さえできれば全てOKというものではなくて、制度的なもの、それからコンセンサス、倫理的なもの全てが解決して実用化という1つの大きな花になりますので、そういうことも含めて考えていかなきゃいけない、政治家には考えてもらわなきゃいけないなと思いつつ…。
ですよね。ちなみにiPS細胞ならいろんな臓器−先生のご専門の皮膚、皮膚も臓器なんですね。内臓のことを臓器というかと思ったけれど(笑)、皮膚や目も…。

-
臓器ですね。
臓器なんですか?

-
はい。
臓器のかたまりなんですね、僕らは。

-
そうですね。
iPS細胞だと、全ての臓器を再生可能なんですか?

-
可能ですね。
じゃあ、「ちょっとこのジャンルの再生は難しいぞ」という臓器はありますか?

-
臓器というか、みなさんにお話して「じゃあ、指をつくれるの?」という話ですが、指という臓器はないんですね。
ええ。

-
どうしてかというと、指は爪という臓器、皮膚という臓器、骨という臓器、筋肉、神経、血管、全ての臓器が1つのコンプレックスとして固まって指という概念をつくっていますので、こういう概念を再生することはなかなか難しい。
ふ〜ん。

-
ただ皮膚だけとか骨だけとか軟骨だけ、爪だけというコンプレックスを形成してないものですと非常に簡単にできていく可能性はあります。
いわゆる体の一部でも単体として存在する臓器は再生可能ですが、複合体となるとちょっと難しいという。

-
そうですね。
先生のやってらっしゃるセルバンクは皮膚に特化してますが、皮膚は例えば1つの細胞からマックス何平方メートルぐらいまで培養が可能ですか?

-
コピーですので、元々の自分のものがどのぐらいあれば自分の全てのホールの皮膚をコピーできるかという話はよく聞くんですが、人の表面積は畳でだいたい一坪ぐらいなんですね、広げると。それが切手1万円分ぐらいの皮膚があれば全部コピーできますので、理論上は。
だけど、皮膚にふさわしい部位とふさわしくない部位があるじゃないですか、表面に出ていいところと。皮膚だって手のひらと手の甲だったら皮膚の種類が全然違いますよね。

-
おっしゃる通りですね。
種類分けはできるんですか?

-
これがなかなかできずに、厳密にいうと顔の皮膚と手のひらの皮膚は違うんですけれど構造的には真皮があって表皮があるという大ざっぱな構造は一緒ですから、手のひらから取ると、手のひらのコピーを全身に使うというイメージでしょうか。
もしキッズがお母さんと一緒にラジオを聴いてたら、お母さんは「目じりの小じわとか顔の部分だけでもいいから、畳2枚とはいわないけれどほんの30センチ四方ぐらいはコピーできないかしら。若い時の自分に!」と思ってるかもしれません。

-
そうですね。それは簡単にできますね。
そうですか(笑)。

-
簡単にできます。
北條先生、今、全ての奥さま方がキュンと来ました。

-
あっ、そうですか(笑)。
できるんですね。

-
できますね。自分のものですから副作用もなく、心配もなく。
あと時間軸の問題ですね。

-
そうですね。
この国のルールがどうなるか?

-
はい。
いやぁ、夢のようなお話でした。あっという間でした。また来週もうかがいたいと思います。今週のサイコーは、セルバンク代表の北條元治さんでした。どうもありがとうございました。

-
こちらこそ、ありがとうございました。
お母さん、鏡見たりしてません?できるんですって、若返ること。ただ、それにはいろんなプロセス、時間軸が必要だということなので、これ以上のしわを増やさないのも大事かもしれませんよ。じゃあ、すてきな週末を。バイバ〜イ!