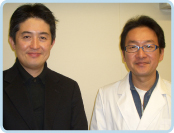キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。今回も水についてお話をうかがいます。世界中には水が飲みたくても飲めない人が相当数いるというお話を先週聞いて、「水、大事だなぁ」と思ったキッズもたくさんいると思います。僕もそう思いました。「水の危機を防ぐにはどんなことが必要だろうか?」ということをサイコーにお知らせの後、聞いちゃいま〜す。
今週のサイコーも水の専門家、東京大学教授の沖大幹先生です。こんにちは。

こんにちは。
沖先生は、新潮社から『水危機 ほんとうの話』という本も出されてます。先週は、「日常生活の中に当たり前のようにある水が、場所によってはとても不自由な人たちもいるんだよ」という生々しいお話を聞きました。あらためて僕ら日本人と水の関係をうかがいたいのですけれど。

はい。
先生からご覧になると、日本人って水とうまく付きあっていると思います?

どうでしょうね。例えば神社へ行ったらまず手を清めるとか、あるいはお神酒(みき)もだいたい水でできていますよね。だから水に対して非常に清らかなものとか、精神的なあこがれみたいなものがあると思うんです。
はい。

かたや、ジャブジャブ水を使う文化でもあるような気がします。
ジャブジャブ−無駄遣いということですか?

あるいは「水に流す」という言い方をします。
日本語で、はい。

-
あるいは「湯水のように使う」。
あぁ。

-
「湯水のように使う」というのは、あまり大事にしないことですよね。
ということですね。

-
だから「水はそんなに大事にしなくていいんだ」と考えちゃっているんじゃないですかねぇ。
昔からそうですね。いわれてみれば、そんな気がしてきました。

-
世界と比べてみると、飲む水の量はそんなに変わらない。どんな水を飲むかは、国によっていろいろ嗜好もありますけれど。ところが一番違うのは、炊事する水ですね。お皿を洗ったり、野菜を洗ったりする水です。
お母さんが台所で使う水。

-
これ、日本が多いんですよ。
無駄遣いすること?

-
無駄ということもないんでしょうけれど。お母さんにしてみれば「ちゃんとお皿をみがきたい」、「きれいにしたい」、「清潔にしたい」と思ってやる。
いわゆる洗うことで水を使うというのは、国によってはないところもあるということですね。

-
あるいは食器洗い機を使うと、手で洗うよりも10分の1ぐらいの水で足りるんです。
食洗機はそういう効果もあるんですね。

-
そうなんですよ。
ほぉ〜。

-
なので水が足りない時は、エネルギーは必要になるけれども食洗機を使ったほうが水の量は少なくてすむ。
へぇ〜。お米を洗う時に、最近は無洗米とかありますね。あれのほうがいいかもしれない(笑)。

-
無洗米のほうが、200から300ミリリットルちょっと節約できるかもしれないですね。
あと、お野菜を洗ったりとか。でもやっぱり今、体も敏感になっているので「よく洗わなければお腹をこわす」とか子どものことを思ってのお母さんの使い方もあると思うんですよね。

-
多分そういうところが日本は「ちゃんときれいに食器を洗ってピカピカにしましょう」と。でも国によっては、「そんなの洗剤つけて、あとは乾かせばいいじゃない」と。水でゆすいだりしない国もあるんですよ。
思い出した。「お尻を洗う国は日本が一番だ」といいますもんね。

-
はい、そうなんです。でもこの前トルコに行ったら、日本のお尻洗い便器みたいなものが…。
ありました?

-
日本だとスイッチを押すとウィーンと出てきて、シュッと洗うじゃないですか。
はい。

-
トルコのものは、最初から出ているんです。別の蛇口があるんですね。それをやるとピュッと出るんです。
そういう国もあるんですね。

-
あるんです。あとは東南アジアに行くと右手はご飯を食べる手、左手はお尻を洗う手という国がありますね。
ありますねぇ。

-
ああいうところは、ホースが置いてあってお尻を洗ったりします。
タイなどね。

-
シンガポール、マレーシアもそうです。なので、僕は日本のお尻洗い機がついている便座は世界に広がっていくんじゃないかと期待しています。
それはいい話ですね。今から18年ほど前に世界銀行のとても偉い方が「20世紀は領土紛争の時代だったが、21世紀は水紛争の時代になるだろう」という話をされた。

-
はい。
水紛争って、ちょっと穏やかではないけれど。

-
そうですね。第三次中東戦争は、水をめぐる争いだったという見方もあるんですね。
そうなんですか。第三次中東戦争はどことどこが?

-
エジプトとイスラエルが戦争したんですね。
エジプトとイスラエル。

-
ゴラン高原というヨルダン側の水源の土地をどっちが持つかで、イスラエルがとっちゃった。
日本の自衛隊が派遣された場所ですね。

-
そうです。「水源を確保することも一つの目的だったんじゃないか?」という話があるんですね。
はぁ〜。

-
あるんですけれども、それだけじゃない。イスラエルの問題は、水というよりはもともとのパレスチナの問題があります。水を理由にすることはあるんですが、基本的には水をめぐって争っても、水は毎日、毎月、毎年必要ですよね。
はい。

-
そうすると水をめぐってケンカすると、ケンカし続けなきゃいけないんですよ。
ええ。

-
例えば、大村さんの水を僕が盗ったとします。でも隣に住んでいる。そうすると毎日「返してよ」というじゃないですか。
ええ。

-
これが未来永劫(みらいえいごう)、続くわけです。なので、たいていの場合は水をめぐって争うと「しょうがない」と、ちょっとお互い妥協して仲良くなるケースのほうが世界的に調べてみると多いんです。
じゃあ、逆に「水に流す」じゃないけれど…。

-
「水に流す」じゃなくて、水が取り持つ縁なんですね。
ほぉ〜。僕は今、北海道で生活しているんですが、実は北海道の経済はあまりよくないんです。

-
はい。
土地を持っている人で水源地があると、外国のお金持ちに「これぐらいでちょっと譲ってくれないか?」といわれ、けっこう譲ってしまっている人がいる。これが北海道で問題になっているんです。

-
知っています、知っています。
これはゆくゆく日本中に広がる可能性はないですかねぇ。

-
だから、やっぱり一つは森林が安すぎるんですね。
日本のですか?

-
日本の森林が。もう一つは、もともと水源地はその集落の共有の土地だったのが、「ここの山は誰のものでしょう」とわけてしまって、地主さんを決めちゃった瞬間に「じゃあ、売るか」となったんですけれど、昔は山というのは集落のみんなの共有地でお互いに大事にしてきたとこだったんです。そういうものを売り買いの対象にできちゃうところが、やっぱり問題じゃないでしょうかねぇ。
そうですよ。そういうのを外国の人に支配されてしまうと、水に対しての値段がはね上がっちゃう可能性もあるわけで…。

-
いや、でも土地は持っていけないですから。日本の領土であり、水源地はそこにありますから。ただ、その水源地で、例えば地下水は市町村の条例で制限されない限りは汲み上げ放題なんですよ。
ほぉ〜。

-
そうしますと、せっかくの水源地でたくさん地下水の汲み上げをされてしまうと、それまで使えていた人たちが使えなくなっちゃう。下流に流れて来なくなっちゃうことはあり得ますし、そこで水質を汚されてしまう、あるいは油が流れてきてしまうことがあると、それこそ水源が汚染されますよね。
はい。

-
ですから、本当は水源地域はやっぱり水の恩恵を受けているところで共同で大事に管理すべきだと思います。
なるほど。これから暖かくなってくると水と接する機会が増えると思いますが、ラジオの前のキッズたちが節水意識を高めることも後々大事になってきますよね。

-
そうですね。節水も大事ですが、それよりは身の回りの水が楽しいかどうか、きれいかどうか、快適かどうかというところにもっと目を向けて欲しいですね。
はい。

-
ただし、水と遊ぶ時には安全も気をつけないと、日本では毎年1,000人ぐらいの方が実は水死されているんですよ。
あぁ。

-
溺れちゃっている…。洪水で死ぬ人は100人200人なのに、その10倍ぐらいの人が溺れて亡くなっているので水遊びをする時には必ず気をつけて。
ええ。

-
水遊びができる川とか海辺になってなかったら「どうしてなんだろう?」と考えて、少しでもきれいにして「自分たちの世代あるいは次の世代も水辺で遊べるように」ということを考えて欲しいと思います。
「僕らの暮らしの中で目を向けた水が、僕らに何をもたらしてくれるか?」ということを考えるのも大事かも知れませんね。

-
ぜひよろしくお願いします。
興味深かったです。今週のサイコーは、東京大学教授の沖大幹先生でした。どうもありがとうございました。

-
ありがとうございました。
先生は先週、地球にある水の量は全部同じだと。それがクルクルクルクル回って、僕らの生活に1万分の1が役立っているというお話をされました。ただそれでも水資源の恩恵を受けてない国もあるんですよねぇ。日本人は日本人の知恵で昔から水とうまく付きあってきましたけど、今日は「僕ら日本人がこれからの国に何ができるか?」ということもちょっと考えるきっかけになりました。それでは水に関して考えながら、みなさん素敵な週末を。バイバ〜イ!