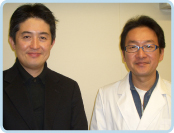キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、3月だねぇ。まだちょっと早いけれど、もう数ヵ月たつと「暑いよ〜。水、水、水!」、「水、飲みた〜い!」っていうシーズンが来るじゃない。日常的に水ってあるんだけれど、もし水が飲めなくなる日が来ると聞いたら、みんなとってもこわくない? 今回のテーマは水の危機。どういうお話でしょうか。お知らせの後、日本一水に詳しいサイコーが登場します。
今週のサイコーは、東京大学教授の沖大幹先生です。こんにちは。

こんにちは。
東大の先生ですね。水の専門家でいらっしゃる。

はい、そうですね。水なんですが、水といってもビーカーの中−実験室の水というよりは地球の水、身の回りの水から雲、そして地球をおおっている川の水などがどう回っているか、どう循環しているかを研究しています。
沖先生は水の循環システムの第一人者ということで、新潮社から『水危機 ほんとうの話』という本も出版されています。水の危機といわれても、僕らの生活の中では台所の蛇口をひねれば水は出る。最近はもう水を買う時代、宅配もされる時代。スーパーでも売っているし、コンビニでも買える…。

はい。
だから、水の危機といってもピンと来ないんですよね。

まぁ、そうですね。
地球上には水があふれているわけじゃないですか。何を持って危機感を持つんですかねぇ?

地球に水があふれているといっても、その地球上の水のほとんどは海の水だったり、湖の水でもしょっぱい塩水だったりすると、それは人間を含めた多くの生き物にとってはないのと同じですよね。つまり使えない水、飲めない水じゃないですか。
「のどが乾いた〜」といって、海の水が飲めるかといったら飲めない。

-
ダメなんですね、あれは。なので、地球の上にたくさん水があるといっても、その中で生き物にとって飲める水。ふだん、海水で体を洗うのはちょっとあれですよね。
ええ。

-
本当に水が足りない地域では、トイレの水は海水で流しているところもあるんですよ。
ほぉ〜。

-
香港とか。
トイレの水は海水にしても問題ないですよね。

-
問題ないですね。船なども昔は海水で流していました。
はぁ〜、そうですか。

-
やっぱりもったいないので。
なるほど。日常生活、人間にメリットのある水というのは限られている?

-
そうですね。ですからわれわれが使える水は降る雨、これは真水でちょっと汚れているんですがきれいにしたら飲める。川の水もきれいにしたら飲める。湖の水や地下水も、地球全体の水の中で身近にあって使いやすい水は0.01パーセントぐらいじゃないかといわれているんですよ。
えっ、0.01というのは1,000分の1?

-
もうひとつ。
1万分の1。

-
そっちです。
1万分の1! うわぁ、地球上で水がいっぱいある、海もある。だけど1万分の1しか僕ら人類は使えない。

-
そうです。
いやぁ、すごいショック!

-
1万分の1だからといって足りないかというと、それは必要な水が10万分の1だったら十分あるということになりますよね。
はい。

-
なので1万分の1だから少ないというのもあれですが、全体から比べたらちっちゃいのは確かですね。結局、どこにどのぐらい水があるかも大事ですが、どのぐらい目の前を流れてくるかも大事なんですよ。
ほぉ〜。

-
つまり水というのは、石油みたいにどこかに溜まっているものを毎日使ってなくなったら終わりじゃなくて、循環しているじゃないですか。雨が降って川に流れ海へ行って、海からまた蒸発して流れてきて水蒸気が凝結して雨になって降るというのを繰り返しています。
はい。

-
そうしますと、じゃあ「流れる量がどのぐらいあるんだろう?」というのが大事なんですね。
はぁ〜。

-
ちょっとお金の話に例えていいですか?
はい。

-
貯金でも入ってこなかったら、いずれなくなっちゃいますよね。
なくなっちゃう。

-
だけれどもお給料とか毎月いくら残すかあると、それは「毎月これくらいまでは使える」となりますでしょ。その「毎月どのぐらいあるか?」、「水がどのぐらい毎月使えるのか?」が大事なんです。
いわゆる自由に使える水、貯金の中でおこづかいとして使えるお水の量で例えると、ということですね。

-
そうです、はい。
実際、水の危機とおっしゃっていますが、危機に瀕している具体的な話はどういうことですか?

-
例えば先ほど話に出た通り、日本でいると蛇口をひねったら水が出てくる。でも蛇口がない国、いっぱいあるんですよ。
あぁ、あるかもしれないですねぇ。

-
50年ぐらい前の東京でも、朝起きたら井戸の水を汲むなんて人はいっぱいいたんですよ。お家に水道がなかったら、水があるところまで汲みに行かなきゃいけない。
はい。

-
それがもし片道1キロ−1キロというと歩いたら15分ぐらいかかりますよね。往復30分かけてようやく水が得られる人が、全世界で8億人ぐらいまだいる。
日本の人口の7倍の人が水に不自由しているということですか?

-
そうですね。
地球上で?

-
地球上で。
8億人!?

-
はい。70億人の中の8億人です。昔55億人しか人口がいなかった時に、11億人ぐらいの人がそういう水がなかったといわれています。それでも減ったんですよ。
でも、70億人の地球上の人間のうち8億というと、9人に1人は水に困っているということですね。

-
そうですよ。飲む水がない。
僕らが当たり前と思っている水がないということですね。

-
水って、しかも飲むだけじゃないですよね。
ええ。

-
ふだんの生活で、もしピタッと水道が出なくなったらどうなります?
お米がたけない。お風呂入れない。

-
トイレも流せない。お洗濯もできない。どうします?
どうしましょう?

-
困るんですよ。日本にいると「そんなこと決して起こらないなぁ」と思うかもしれないですが、地震が起こって水道が止まる。あるいは大雨が降って水道管がこわされちゃうなどで、われわれもそういうことになる可能性がゼロじゃないんですよ。
さらに夏場の渇水といって、ダムの水が干上がっちゃって取水制限もたまにありますものねぇ。

-
ちょうど去年の9月にそうなるんじゃないか。みんなで「渇水になったら困るなぁ」となったんですが、雨が降ったのでその時はよかったんですね。
う〜ん。

-
実は日本も東京の臨海部、海の近くは人がたくさんいるので1人当たりの使える水資源の量はあまり多くないんですよ。
へぇ〜。具体的に数字であるんですか?

-
具体的にいうと、例えば1人当たり年間300立方メートルとか400立方メートルぐらいなんですね。ほんとは1,000とか2,000ぐらいあって欲しいんですよ、豊かであるためには。
はい。

-
「1,000〜2,000あったら、まぁ困らないかな」という中で、300〜400しかない。だけれども、多摩川の上流に奥多摩湖ってありますよね。
あります。

-
あそこの水あるいは利根川の奥の水、そういうところにダムとか貯水池をつくり水を溜めとくことによって、何とかわれわれは水で困らないようになっているんです。
じゃあダムがなかったら、水のコントロールができなくなると場合によっては水が全く出ないという暮らしもあり得るということですか?

-
そうですね。だから江戸の頃は100万人しかいなかった。
東京は100万人しかいなかったんですか。

-
その頃でも多摩川の水を延々40キロ運んできて、玉川上水で江戸の水を何とかまかなったわけですよ。
はぁ〜。

-
ところがその後の高度成長期、年間30万40万と人が増えるんですよ、東京。そして今は800万、都内全体では1,300万、周辺含め3,000万人、水が足りないんです。
ええ。

-
なので、しょうがなしにダムをつくって水を溜めて、雨が降って川の水が多い時に溜めておいて、少ない時にチョロチョロ使って何とかふだん困らないようになっているんです。
へぇ〜。メカニズムがよくわかりました。でも先生のおっしゃることでは、それでも足りないんですね。

-
日本はそれでも何とか足りるようになったんです。ところが考えてみると50年60年前、あるいはもっと前からため池をつくって、水が足りない時には溜めといた水を使うような仕組みを日本のご先祖様たちがやってきてくれたわけですね。
はぁ〜。

-
それがまだできてない国、あるいは日本の50年60年前はまだ足りなかったんです。
はい。

-
例えば昭和39年、1964年の東京オリンピックの年には、オリンピック渇水というのがあったんですね。
へぇ〜。

-
東京でも断水といって水道が1日24時間出ない。
オリンピックで沸いている中で?

-
「どうしよう、オリンピック開けないんじゃないか」と思うぐらいに水が足りなくなったんです。
そうなんですか。

-
この時にできた言葉が「東京砂漠」です。
そうなんですか! 歌にもなった?

-
そうです、そうです。
へぇ〜。勉強になりました。地球儀を見ながら話したい内容ですよね。

-
そうですね。
あっという間に時間が来てしまいました。来週も、より水に関してのお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。

-
はい、よろしくお願いします。
今週のサイコーは、東京大学教授の沖大幹先生でした。ありがとうございました。
実は何年か前にアフリカのある国で、泥水を子どもたちが洗面器みたいなやつに汲んできて3時間ぐらい待っているんですよ。そうすると、上のほうに透明な水があらわれる。それをコップですくって飲んでる姿を見たんですけどねぇ。先生の話を聞いてそういうのを思い出してしまいました。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。じゃあね!