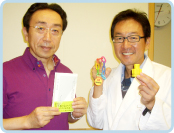キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。みんな、3Dプリンターって知ってる?聞いたことあるでしょ。最近、話題なんだよねぇ。プリンターを使って印刷する感覚で立体のものをつくっちゃう。何か魔法の箱みたい。テレビなどで見たことあるよねぇ。これ、何でこんなことできるのか、みんな不思議に思ったことない? 「何に使われるのか?」も含めてサイコーに聞いてみたいと思います。
今週のサイコーは、マイクロジェットの山口修一さんです。こんにちは。

こんにちは。みなさん、よろしくお願いします。
お願いしま〜す。マイクロジェットは、会社名になるんですか?

そうですね。
どういうことをご専門にされているんでしょうか?

マイクロというのは非常に小さな、ジェットは液体を飛ばすということで、いろんな色のついたインク以外のある機能を持った液体を正確に並べて、さまざまな電子部品やバイオ関係の研究をするための装置を開発して弊社で販売しています。
光文社新書から『インクジェット時代がきた!』という本も山口さんは出されてらっしゃいます。今、世の中で3Dプリンター、テレビなどでもとても有名じゃないですか。

そうですね。
これのご専門であるということですね。

専門はインクジェットですが、その3Dプリンターの中には一部インクジェットを使ったものもあるので、3Dプリンターのことにも少し詳しいという…。
そうですか。謙遜されてらっしゃいますけれど、とても詳しいと思います。

いえ、いえ。
テレビで「3Dプリンター」とかいってプラモデルみたいなものができたり、たぶん見たことがある人が多いと思うんです。あれが3Dプリンターみたいなものですよね。

そうですね。3Dプリンターには、実はいろんな方式があるんです。特に今話題になっているのはプラスチックの樹脂を使って立体物を目の前でつくっていくというプリンターで、非常に安く普及してきたため注目を集めているんですね。
僕は古い人間なのかもわかりませんけれど、あれをプリンターというにはとても違和感があるんです。

あぁ、そうですね。
だって模型をつくっているわけでしょ。プリンターは紙に印刷したりというイメージで、だからプリント作業じゃないんですよね。

でもいろんな方式の中にはインクジェットという方式があって、インクジェットはみなさんご存じのように家庭で写真やさまざまな印刷をしますよね。
きれいにできます。

紙に印刷しますが、紙自体はすごく薄い。その印刷した紙を100枚重ねたら厚みが出てきますね。
インクの厚みが?

印刷した紙を重ねると、紙がどんどんどんどん厚くなって立体物に近い3次元の印刷物になりますね。
はい。

ですから3Dプリンターは実は1回1回印刷をして、1回は非常に薄いんですが100回200回積み重ねていくとほんとに立体になるということで、基本はやっぱり平らな薄いものに印刷するというところでプリンターになるんですね。
なるほど、わかりました。“チリも積もれば山となる”みたいなイメージですかね(笑)。

まさに!(笑)
すごく細かいものが重なって重なって、いろいろな模型みたいな形になっていくわけですね。

ええ、積みあがって立体になっていくんですね。
この3Dプリンターの材料って「樹脂」とおっしゃっていましたが、プラスチックが機械の中にインクの代わりに入ってるんですか?

はい。いくつか方法があって、今一番話題になっているのはプラスチックでつくった細〜い糸状のものがリールに巻いてあるんですが、その糸状のプラスチックを小さなノズルという穴から溶かして押し出してソフトクリームをつくる時のようにグルグルグルグル一筆書きのように平面の中で塗っていくんですね。
はい。

そうすると薄〜い一つの層ができるので、その上に次のソフトクリームを上に巻いていくようにどんどんどんどん積み重ねていく方法ですね。
ほぉ〜。何かサンプルはないですか?

じゃあ、まず黄色い、これですね。
ワァ〜、ボルトとナットだ! 今、大村さんの目の前にプラスチックでできたボルトとナット。イメージできる? もう1個来た! チェーン来た、チェーン!

色のついたフルカラーのチェーンです。
レインボーのチェーン。みんな、ブランコのチェーンがあるでしょ。あのチェーンが緑だったり黄色だったりオレンジだったり赤だったり青だったり紫だったりという。この七色のチェーンがあらわれて、これ明らかにプラスチックでできてるんだ。これは3Dプリンターでつくったチェーン!?

はい、そうです。3Dプリンターには今紹介した細い樹脂の糸でつくる方法と、インクジェットで白い石灰の粉−石膏を固めてつくっていく方法、そして光で固めると積みあがっていくような液の材料を飛ばす方法と大きく、みなさまの身近なプリンターとしては3つの方式があるんですね。
ええ。

今、大村さんがお持ちのレインボーの鎖は白い石膏からつくっているんです。
石膏!石膏というと、学校のどういうところにありますか?

今はどうかわかりませんがグラウンドに白線を引く、あれは石膏の粉ですね。
ああいうのが材料!いやぁ、グラウンドで運動会だと踏まれてすぐ消えちゃうけれど、3Dプリンターの材料にしたら鎖みたいなチェーンができるということ!?

色をつけて、色をつけた後に粉を固める糊をすぐ後に吹き付けるんですね。そうすると色つきのこういった固まりでいろんな立体物ができるんです。
ブランコのチェーンをキッズのみんながよ〜く見たら、チェーンの一つ一つに継ぎ目が見えると思うんですよ。あれは鉄をつなげて楕円形の輪っかにしてチェーンになっているわけじゃないですか。

はい。
この3Dプリンターでつくったチェーンは継ぎ目がない。

そうなんです! そこがポイントです。
何でですか?

継ぎ目なしにチェーンとチェーンがきちんと組み合わさった状態で、もうでき上がってくるんです。
でも、乾燥する過程でくっついたりしないんですか?

ちゃんとつくる時にチェーンを空中に浮かせてつくるんです。空中に浮いてると液を吹きかけられません。ただ粉の中でつくりますから、浮いているチェーンの下にはまだ固めてない粉が下で支えていますので、浮かせるようにしてつくっていくことができるんです。
すごい!

ハハハハ。
すごい! 水の中や砂の中で工作するような感じで?

そうです。
干渉しないで、ちゃんとこう結合する部分ができるんですね。

そうです。
ボルトとナットも同じ原理ですか?

別々につくってはめたんではなくて、一緒にできてくるんですね。
はぁ〜。これ、いつ頃から始められた技術ですか、3Dプリンターって?

3Dプリンターはいろいろな方式があるんですが、本格的なものから実は始まっていて1980年代から研究が始まってます。
30年ぐらい前から?

そうです。糸状の樹脂を使ってやるものは、1990年前後から研究がされていたんですね。特にここ4〜5年で特許が切れてきたので、そこに参入するメーカーがいっぱい増えて装置も安くなって普及がどんどん進んでるんです。
へぇ〜、いやぁ衝撃! この衝撃をラジオの前のキッズにどう伝えていいのかわからないから、どこかで見せる機会があるといいけど。この3Dプリンターってなかなか家庭じゃないですよね。

ええ。
いくらぐらいするんですか?

3Dプリンターは、アメリカですと一番安いものが400ドルぐらい。
えっ!

高いもので4,000ドル。つまり4万円。
ちょっと待って(笑)。

安い4万円ぐらいのものは3Dプリンター自体がキットになって来ますから、自分で組み立ててプリンターをつくるんです。でも国内では10万円から20万円ぐらいのものが相次いで発売になっています。
へぇ〜! めちゃくちゃ衝撃なんだけど、この衝撃はこのチェーンの音で(※ジャラジャラというチェーンの音)。プリンターでチェーンができるんだよ。衝撃だぁ! もう時間。ちょっと次回は、もっとふくらませた話をうかがってよろしいですか?

はい。
今週のサイコーは、マイクロジェットの山口修一さんでした。ありがとうございました。

どうもありがとうございました。
何となくわかったような、わからないような。ただ、まだ家庭にはそんなに普及していないから、いち早くこういうお話を知っとくのも大事かなと思いました。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょうね。夏休み真っ盛りだねぇ。いいねぇ。バイバ〜イ!