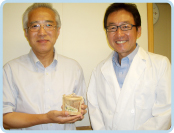キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。おぉ〜、今日で8月も終わりですねぇ。暦の上ではもうとっくに秋ですが、まだまだ残暑は厳しいですよ。今日は気分だけでも秋を感じてもらおうと、耳から、耳障りのよい秋の虫の声、これをみんなに聞いてもらいたいと思います。秋の虫たちの科学をさらにサイコーから聞いていきます。お知らせの後です。
今週のサイコーは、暑いけど秋の入口にふさわしい方ですね。プチ生物研究家の谷本雄治さんです。こんにちは。

こんにちは。
谷本さんはプチ生物研究家として生き物に関わっていらして、岩波科学ライブラリーから『週末ナチュラリストのすすめ』など多くの本を出されています。今回のテーマは秋の虫ということで、秋の虫のお話をしていこうと思っています。東京にいると虫の声って聞くようで聞かないし、でも何気に耳に入ってきたりするんですよね。

よく聞いていないと聞きのがしてしまうこともあるんですが、コオロギの仲間などは秋になると、よく聞けると思うんですよね。
これからは、コオロギの鳴き声のシーズンになってくるんですか?

そうですね。いい季節ですよね。
谷本さんのお好きな秋の虫は何ですか?

いろいろあるんですが、とりあえず「いい声だなぁ」と思うのが、昔から飼っているスズムシ、マツムシ。それから、クサヒバリというのがいるんですけれど…。
スズムシはイメージできます。マツムシも昔から童謡に出てくるんで。「あれマツムシが鳴いている♪」ですよね。「チンチロ、チンチロ、チンチロリン♪」って。

小学校唱歌ですよね。歌ではそういうふうに歌われていますけれど、実際は「チンチロリン、チンチロリン」という感じで聞こえると思います。
あぁ。

小人によっては「チンチコチン」という人もいます。
チンチコチン?

ええ。
鳴き声が一番お好きなのは何ですか?

鳴き声は、ちょっと見た目は悪いんですがエンマコオロギ。
エンマコオロギって、どんなコオロギ?

エンマコオロギは、ゴキブリみたいな脂ぎった茶色い色をした…。
あちこちにいるやつですよね。足のバネが太い?

そうです、そうです。
あれがエンマコオロギ?鳴くんですか?

鳴くんです。
コオロギの中で一番大きいものがエンマコオロギですか?

ええ。私はえん魔さんに会ったことはないんですが、えん魔さんの顔に似ているということでエンマコオロギと。
へぇ〜。

なおかつ日本にいるコオロギの中でたぶん最大級だと思うので、それでエンマコオロギというふうな名前がついたようですね。
子どもの頃、千葉県でエンマコオロギをよくつかまえました。

そうですか。
鳴くイメージが全然なかったですね。

たぶん普通に聞いているのがエンマコオロギだったと思います。
そうですか。いわゆる秋の虫の鳴き声で主流なのはエンマコオロギ?

そうですね。エンマコオロギが一番多いと思います。
今、助手が準備してくれた、エンマコオロギ。早いねぇ、やること。みんな、エンマコオロギの鳴き声、今から聞きま〜す。
(※エンマコオロギの鳴き声)
これ、エンマという名前をやめてあげたほうがいいんじゃないですか?

そうですね、きれいな声ですよねぇ。
かわいいじゃないですか。何でエンマコオロギなんて、人間は勝手ですねぇ。

そうですね。このエンマコオロギは、知らない人が見るとゴキブリと間違えるかもしれないですが…。
失礼ですよ。

失礼ですね(笑)。鳴き声はこういうふうにいい声で鳴くんですが、何種類もあるといわれています。コオロギの仲間で、耳がよくて聞き分けができる人は8種類ぐらいあるというんですよ。
ええ。

今の鳴き方は、ちょっと自分で鳴き声を楽しんでいるような鳴き方ですが、メスを誘う時の鳴き方とかケンカをする時の鳴き方、ケンカをして今度は勝った時の鳴き方とか、いろんな鳴き分けをしているらしいといわれていますね。
へぇ〜。でも今たぶん聞いたら、ラジオの前のみんなも「聞いたことある!」って絶対思ったと思います。これエンマコオロギで、主流ですね。

はい。
ちょっと秋めいてきました。スズムシも用意してくれたの!? やること、早いなぁ。楽しくなってきた。スズムシです。
(※スズムシの鳴き声)
いいですねぇ。

いいですね。ただこのスズムシ、あまり鳴き方がうまくないように聞こえますねぇ(笑)。
ちょっとヨイショしただけですから(笑)。 助手、下手くそだなぁ、スズムシ。

もう少し伸びやかな鳴き方をするのがいいとされていて、スズムシは俗に“七振り”、7回振るというんですかね。音を振る意味だと思うんですが、七振りするスズムシが優秀なスズムシだと、名演奏家ですね。
スズムシって羽根をすり合わせて音を出すといいますよね。これ、羽根のすり合わせの音?

そうです。
七振りしてるんですか?

そうですね。七振りは「リーン、リーン」と続けて7回連続するという意味ですが、そもそも音を出す時には2枚の羽根がありますね。羽根のところにヤスリ−人間が持っている道具でいうとヤスリの目がありますね。目立てをする時の目、その目をこすり合わせるんですけれど、スズムシの場合には自分で数えたことがないんですが、いろんなものを読むと300ぐらいあるといわれているんです。
ほぉ〜。

それが虫の種類によってヤスリの目の数が違うので、鳴く声、聞こえる音も違ってくるといわれてます。
ふ〜ん。秋といえばキリギリス。キリギリスも秋の虫ですよね。

キリギリスは、どちらかというと印象としてはやっぱり夏ですね。
夏!じゃあ、今はもう聞こえているんですか?

今もまだ聞こえるんですけれど、どちらかというとイメージとしては、夏。
そうですか。

キリギリスとコオロギが大きく鳴く虫で分かれるんですが、キリギリスの場合は先ほどのスズムシと逆で左の羽根が上になるんですね。人によっては“サウスポー”という言い方をするんです。
へぇ〜。

キリギリスはどちらかといえば−これもどちらかといえばですが昼間鳴いて、季節が変わってきたり温度や環境によって違ってくる。私も何度も飼ったりしたんですが、夜になって鳴くこともあって、ただ今話題にしている秋の鳴く虫といった時にはスズムシもコオロギも入るけれど、キリギリスははずすのがたぶん普通のとらえ方だと思うんですよ。
ハハハハハ。キリギリスは、はずされちゃうんですか?

そうなんです。
しかも昆虫の専門家の方の中で、キリギリスは別名“サウスポー”というんですか?

そうです。
アッハハ。じゃあ、野球でよく実況アナウンサーが「サウスポーの誰々」といったら、谷本さんは「おっ、キリギリスだ」と。

「キリギリスの誰々」というような選手名ですよね(笑)。
そうなんですか(笑)。おそろしい隠語ですねぇ。さすがに助手、キリギリスはないでしょ? あるの? 何、虫図鑑のCDとかあるわけ? さっきのスズムシはダメ出しをくらったんだよ。完璧なキリギリスあるんだろうね。ある? じゃあ谷本さん、聞いてみましょう。
(※キリギリスの音)

これ、あんまりうまくないですね(笑)。最後にちょっと聞こえましたけれど、だいたい「ギース、チョン」というのがセットなんですね。
聞こえた。じゃあインターバル、「チョン」までが長すぎるということですか?

そうですねぇ。これも、「チョン、ギース」っていう人と、「ギース、チョン」で「ギッチョン」といったり、人によって聞き方が違ってきますからね。
なるほど。

ただ「ギース」と「チョン」はだいたいセットだと思います。
セット。このCDのやり方は、編集が間違っているということですね。

そうですね(笑)。まぁ間違ってはいないんでしょうけれど、あまり優秀な“サウスポー”じゃないかもしれない。
ハハハハ。この音源はちゃんと天然のキリギリスから録ったものですよね。でも、こういう“サウスポー”もいるということですね。

そうなんでしょうね。
勉強になりました。キリギリスの鳴き声を聞いたら、谷本さんのイメージの「ギース、チョン」になるか、インターバルのある「チョン」になるか聞きごたえがあります。

そうですね(笑)。
面白かった。ちょっと秋を感じたかな? 明日から9月だから秋だね。また来週も谷本さんの話をうかがっていきたいと思います。
今週のサイコーは、プチ生物研究家の谷本雄治さんでした。ありがとうございました。

どうもありがとうございました。
スズムシとキリギリスの鳴き声にダメ出しされて、この助手たちのへこみ具合。しょうがないよ、これ。しょうがない。元気を出そう。専門家の方は厳しいですね。僕もそれで緊張して、全部ふっとんだけど(笑)。でも、みなさんもいやされたでしょ。いいじゃないか。よし、来週リベンジするぞ、みんな。それでは、みんな、すてきな週末を。バイバ〜イ!