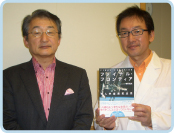キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。もうすぐクリスマスだねぇ。街はもうクリスマスムード一色だけれど、みんないろいろ予定があるよねぇ。さぁ、今日お送りするのは、みんなからの質問特集で〜す。キッズならではのユニークな科学の疑問がたくさん届いているので、お知らせの後、時間の許す限りサイコーがお話をしてくれます。
今週のサイコーは、おなじみ科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんばんは。

こんばんは。
寺門さんがお見えということは、キッズからの質問でございます。埼玉県のラジオネーム、カンガルーちゃん、小学校6年生の女の子からいただきました。どうもありがとうね。「クリスマスに友だちの家でパーティをします。とっても楽しみです! いつも不思議に思うのは、楽しい時間はあっという間なのに退屈な時間は長く感じられることです。本当に同じだけの時間が流れているのか不思議なくらいです。なぜなんですか?」。同感!(笑)

本当ですね。
寺門さん、教えてください。

そうですね。実際、同じ時間が流れているはずなのに、本当にそう感じられるわけですよね。昔は心理学的な問題−つまり気のせいで感じてしまうと考えられていたんですが、最近になって脳の研究が進んでくると、もしかしたら脳は実際に短く感じているかもしれないということがだんだんわかってきたんですね。
僕らはずっと気のせいかと思っていましたが、もうこれは脳のジャンルに入ってくるわけですね。

そうです。どうもそのようです。
医学的な分野ですね。

つまり脳の中にはいろんな時計があることがわかってきているんですね。
ええ。

一番有名なのが24時間の時計で、これが狂うことによっていわゆる海外旅行に行った時の時差ボケが起こるわけです。
はい。

でも、それ以外に小さな細胞の中でいろんな役割をする細胞があって、その役割に応じていろんな時間の刻み方があるようなんです。例えば何かに集中しているところとか、物を考えているところとか、そういう場所にある細胞ですね。これについていうと、時間が流れているスピードがもしかしたら違って感じているかもしれない。だから、実際に短く脳は感じているのかもしれないということがだんだんわかってきたんです。
すみません、ラジオの前のキッズがわかりやすいように、それを感じる脳の部分は頭のどの辺ですか?

それはいろんな部分です。
いろんな部分。

つまり脳は運動している時とか本を読んでいる時とか物をおぼえている時で、活動している場所が違うんです。
運動脳と考える脳…。

そうです。いろんな場所で活動が起こって、それによって人間の脳はできているわけですね。今はどこで脳が特に活発に働いているかという場所を見ることができるんですが、その中で例えばどんな時間が流れているとか、なかなかわからなかった。
はぁ〜。

これだけバイオの技術が進歩してくると、ひとつひとつの細胞の中で起こっていることと、その細胞と隣の細胞の間でどんなやり取りをしているか、そんなことがわかってきているんです。
はい。

僕もよくあるんですが、電車に乗って面白い本を読んでいると集中しちゃって、あっという間に時間が過ぎて、降りる駅を乗り過ごすことがあるでしょ。
はい。

例えば、ああいう時はきっと、脳が実際にすごく短く感じているはずです。だんだんそういうことがわかってきた。まだ全貌が解明されているわけではないので何ともいえないですが、どうもやっぱり単なる気のせいではなくて、実際に人間の脳はそういうふうに感じている。だから、やっぱり人間の脳は不思議な存在ですね。
さぁ、荒川区のユウタ君、小学校6年生からもらいました。「今年もいろいろなことがありました。僕は2020年の東京オリンピックが決まったことにびっくりしました」。びっくりしたのかぁ。うれしいじゃなくて、びっくりしたんだな。「2020年にはサッカーを見たいです。でもチケットを取るのは難しいので、現実はテレビ観戦だと思います」。そんなことない(笑)。「そこで思ったのですが、映像の技術が進んだらその試合会場にいるような気分で見られる立体テレビはできないでしょうか? 自分のすぐ目の前でAKBが歌っていたら楽しいと思います」。最後はAKBでおとしてきましたね。

そうですね。
サッカー選手をリアルに体感したいというのが、たぶんユウタ君の夢ですね。でもこれは2020年の話。とり急ぎAKBが目の前で歌って踊っている姿を見たいという、小学生らしいですね。最近ちょっと聞かなくなったけど、3Dテレビが2年前ぐらいから売り出されてたじゃないですか。あの原理でサッカーを見たら?

それなりに立体的に見えると思いますね。ただ、今はさらに技術の研究が進んでいて、もっとリアルに体験できる方法がないかと研究しているんです。そういった研究を「超臨場感」技術というんです。つまり“まるでその場にいるような”という技術をつくる。
へぇ〜。

ですから一番中心となるのは、いわゆる立体的なテレビ。つまり映像を立体的に見ることができるようにすることですね。じゃあどんな方法があるかというと、なかなか難しい。結局、今の3Dテレビみたいに平面だけれど、肉眼で見たりあるいはメガネをかけたりすると立体に見える方法はあるわけです。
はい。

もうちょっとすると平面のスクリーンではなくて、こういうテーブルの上に立体的な映像ができる。極端な話でいうと、このテーブルの上にサッカー場がそのまま出現してしまうみたいな、そういった技術がつくれないかと考えられてますね。
じゃあテーブルの上にサッカー場ができた時に、テレビの便利さって、見たい選手がボーンとアップで出ることじゃないですか。

そうですね。
でも今の話だとそのサッカー場で見ている空気にはなるけれど、それをアップで見ることはできないわけですか?

ですから、それを組み合わせようとしているんです。
えぇ〜!

つまりサッカーの観客席で、一番上のほうの席から選手の動きを全部見たい人もいますよね。
はい。

それから特に好きな選手の動きだけじっと見ていたい人もいるし、あるゴールシーンがあった時にもう1回見たいということもありますね。
はい。そうだ(笑)。

みんな同じひとつのサッカー場を見てるんだけれど、例えばそれを拡大したり、リプレイしたり、そういったことまでできるようなある種のスクリーンみたいなものをつくろうというのが超臨場感技術の目標なんです。
えぇ〜!! なるほど。

しかも超臨場感技術は視覚、目で見る映像だけじゃない。それ以外にわれわれの感覚はにおいを感じたり、もちろん音も聴いていますね。
はい。

それから手で触った触覚があります。そういったものも再現しようと思っていて、特に音響は今もちろん立体音響があるんだけれど、もっとリアルに見える音響のシステムがないかと研究されています。
はい。

それから、例えばにおいもなかなか今は再現できないんですね。
はい。

これを何とか再現できないかとか、それから触覚ですね、触った感じ。こういったものも再現できないかという研究が進んでいて、実はこういったものはサッカーの試合にはあまり関係ないかもしれないけれど、今テレビショッピングやネット上のショッピングがありますね。
ええ。

例えば女性が香水を買う時、「ちょっとにおいをかぎたいな」とかありますね。そういった時のにおいの再現。それからあるバッグを買いたい時、「この皮の手ざわりはどんな感じだろう?」ということが例えばインターネットを介してわかるような、触覚みたいなもの。
いやぁ〜!

そういったものがあると、もっとテレビショッピングやネットショッピングが便利になるわけですよ。そういったことまで実現できるような研究が進んでいて、超臨場感技術はなかなか実現できないようだけれど、あなどれない技術がけっこう進んでいるんですよ。
えぇ〜、こわい!(笑)

2020年東京オリンピックの時に間に合うかどうかはちょっと別として、いずれだんだん家庭のテレビもそんなふうに進化してくる可能性がありますね。
そうですかぁ。たぶんユウタ君はラジオの前で放心状態ですよ。

でもね、ユウタ君が大人になる頃は、本当にそれぐらいになっているかもしれませんよ。
僕も何かそんな気がしてきました(笑)。はい、みなさんどうもありがとうございました。来週はサイエンスキッズ、2013年最後の放送だ。この際、寺門さん来週も来ていただけますか?

はい、わかりました。
よろしくお願いします。今週のサイコーは、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございました。

どうも失礼しました。
最近、確かにテレビでショッピングものが多くて「これ、どうなんだろう?」って思うんだけど、テレビから超臨場感技術で「こんな手ざわりですよ」といわれたらびっくりだよね。そうしたらお店なくなっちゃうよね(笑)。「どっちがいいんだろうか?」と思いながら、でも本当に夢のある話だったなぁ。質問くれたユウタ君、カンガルーちゃん、どうもありがとうね。それではひと足早いけれど、メリークリスマス!