 |
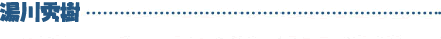
湯川秀樹は1907年、東京市麻布区(現在の東京都港区)に生まれました。父親は地理学者で、さらに二人の兄と弟の一人が後に大学教授になるという学者一家。湯川博士は小さなころから読書に親しみ、高校生の頃、物理学に興味を持ちました。あるとき、「物質はどこまで小さくすることができるか」という問題について、兄と激しく議論しました。「分子という単位が一番小さく、それ以上小さく分けられない」といった兄に対し、湯川博士は「もっと小さい単位に分けることができるはず」と主張しました。
大学を卒業後、湯川博士はそんな小さな世界を研究する物理学者となりました。京都大学の講師をしていたころ、物理学の分野で大きな発見がありました。原子核が「陽子」とよばれるプラスの電荷をもった粒子と、「中性子」とよばれる電気的に中性の粒子でできていることがわかったのです。湯川博士はそれをさらに詳しく研究して、27歳のときに『中間子理論』を発表。湯川博士は、「原子核の中で、なぜ陽子と中性子がバラバラにならずにいられるのか」という疑問に、「陽子と中性子が中間子をキャッチボールしているからではないか」という理論によって突き止めようとしたのです。
2年後、アメリカの学者によって中間子が発見され、湯川博士の論文が一気に脚光を浴びました。そして1949年、日本人初のノーベル物理学賞を受賞すると、湯川博士の名前は世界中に知れ渡りました。それは、第二次世界大戦が終わり、暗く悲しい思いをしていた日本人を勇気づける大きなニュースでした。晩年、湯川博士は若い研究者を育てる一方で、平和運動に力を入れました。
|

