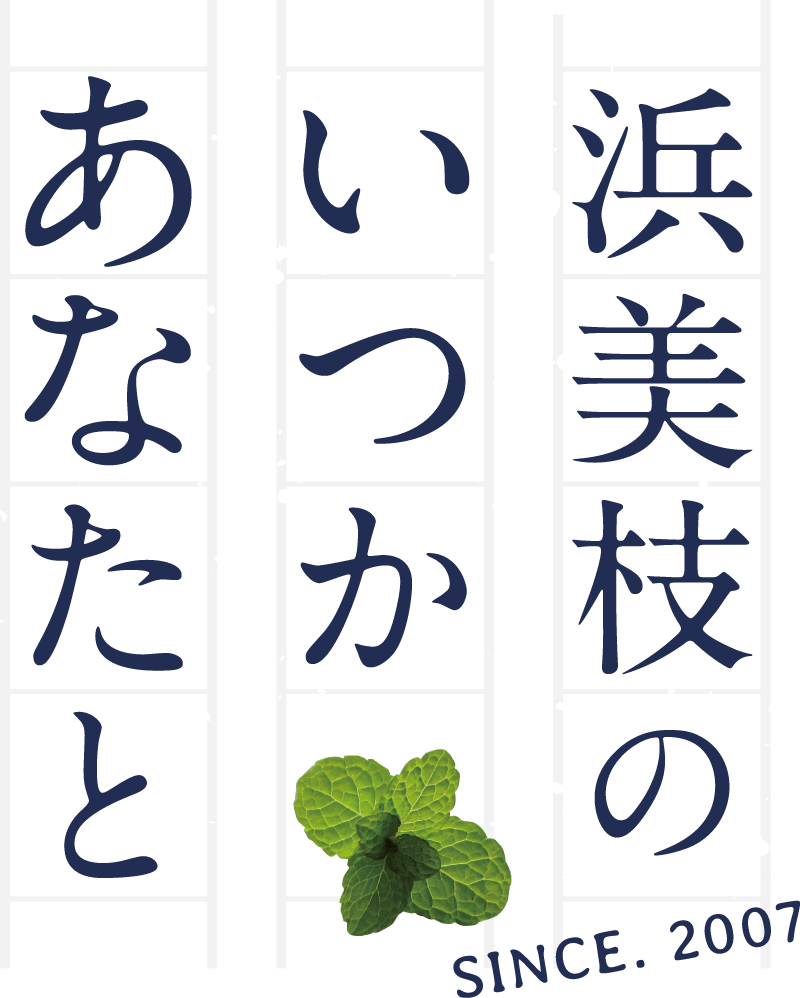寺島尚正 今日の絵日記
2025年4月7日 サクラ満開
3月23日に熊本と高知で開花した今年のサクラ前線は4月6日新潟まで来た。
予想によると、7日に長野、秋田が11日、盛岡が12日、青森が15日にソメイヨシノが花を開く。
北海道札幌は5月4日、釧路が5月7日である。
毎年の事とは言うものの、日本列島は南から北まで長いのを実感する。
古来より桜は穀物の神が宿るものと大切にされてきた、日本を象徴する馴染み深い植物である。
桜は「バラ科サクラ亜科サクラ属」の落葉樹で、ウメやモモもサクラ属の仲間。
ヒマラヤを原産とし、アジアを中心に北半球に広く分布しているが、特に日本列島に集中している。
日本では固有種、交配種合わせて600種類もの桜が確認されている。
桜の分類は複雑だが、一般的には山野に自生する野生の「山桜」、品種改良された「里桜」と「一重の里桜」に分けることができるという。
山桜は古くから山に自生している桜。
山桜をもとに園芸用に品種改良された桜が里桜。
桜の品種改良は平安時代から行われていたと考えられている。
里桜は、花びらの数を増やしたヤエザクラや、枝を垂らしたシダレザクラ、秋に咲くジュウガツザクラが有名である。ヤエザクラは花びらが重なって咲く里桜の総称だ。
一重の里桜は、オオシマザクラとエドヒガンの雑種であるソメイヨシノが代表。現状、全国の桜の約80%がソメイヨシノと言われている。
ソメイヨシノは江戸時代末に江戸染井村の植木屋が吉野桜と名付けて売り出した品種で、明治以降に河川敷や学校の校門近くに多く植えられた。
花びらは楕円形で一重となり、花柄は長く伸びることが特徴。咲き始めは淡紅色ですが、満開になると白色に近づき、花が散った後に葉が生える。柄には毛が生えており、葉はギザギザである。
岡山県真庭市の「醍醐桜」が満開となり、訪れた人たちを楽しませている。
醍醐桜は、岡山県真庭市別所大字吉念寺にあるエドヒガンザクラの巨木で、新日本名木百選の一つだ。
名前の由来は隠岐の島に配流される途上の後醍醐天皇がこの桜を愛でたという伝説によるものであるが、地元の住民は「大桜」と呼んでいるようだ。
樹高18メートル、幹周り7メートル、根本周囲9,2メートル、枝張りは南北20メートル。
近くに二代目の醍醐桜が植えられ成長していると聞く。
春の訪れを告げ、古くから日本で愛されてきた桜だが、そんな桜にも寿命がある。
中でも、日本の代表的な桜であるソメイヨシノは比較的寿命が短いといわれている。
一般的に日本の野山に元々生息していた基本種の桜は比較的寿命が長く、それらが交雑して生まれた園芸品種は寿命が短い傾向がある。
ただし、樹木の寿命はあくまで目安であり、生育環境や個体によって大きく異なるようである。
ソメイヨシノの寿命は、約60年、長くても100年ほどと桜のなかでも比較的短いとされる。
ただ他の桜と比べて成長スピードが速いのが特徴だ。
ヤマザクラの寿命は200~300年とされている。
ヤマザクラは、関東以西の本州と四国の山間に自生する桜で、原種のひとつ。大きいものだと高さ30mほどになり、樹形は不規則で、幹が太くなりにくいのが特徴である。
エドヒガンザクラは桜のなかでも長寿の種類として知られており、樹齢1000年を越える古木がいくつか現存している。
なかでも、山梨県の「山高神代桜」は樹齢2000年といわれ、日本最古の桜といわれている。
桜の花が最初に咲くのは、十月桜だ。
1月下旬くらいから咲きだすのは、寒被桜。
2月中旬には冬桜、河津桜が咲き出し3月の彼岸ごろには、彼岸桜、しだれ桜が咲き出し、続いて、大島桜、ソメイヨシノが咲きだす。
その後、山桜の季節になり、八重桜等のサトザクラの季節になる。
5月の末には関東では桜の開花は終了となる。
桜開花のメカニズムは、桜は夏に花の芽を作り、冬の初めに花の芽はいったん眠りに入り成長が止まる。
そして、真冬の寒さによって休眠から目覚め(休眠打破)、春に向けて暖かさによって成長し、開花する。
サクラは、春に花を咲かせるために、寒い冬を経験しなくてはならない。
長く厳しい冬を過ごしてきた分だけ、春に咲くサクラを見ると嬉しく感じるものだ。
人生も同じ。
春の様な麗らかな時期もあれば、冬の様な厳しい時期もある。
厳しい冬の時期には、ただ春の訪れを待つのではなく、コツコツと春に向けた準備が必要なのだろう。
辛いことがあったら、サクラの休眠打破を想い出し、その先にある春を目指して努力を続ける自分でありたいと思う。

サクラ満開

枝垂れの佇まい

独りで咲く

夜に映える