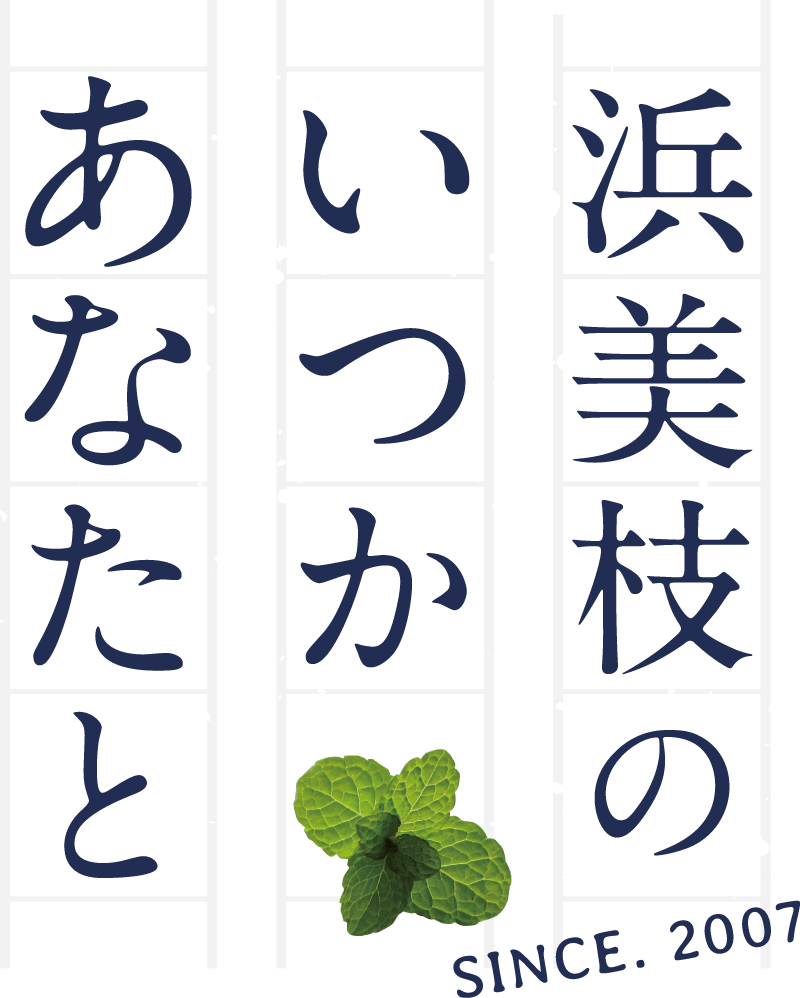寺島尚正 今日の絵日記
2025年4月14日 しばし佇む
東京の桜は、ソメイヨシノから八重桜やハナミズキにバトンタッチしつつある。
そんな中、4月13日日曜、大阪・関西万博が開幕した。
テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。158の国と地域、7つの国際機関が参加する。
会場のシンボルは、海外のパビリオンを包み込むような形で建設された1周およそ2キロ、世界最大の木造建築「大屋根リング」。
「多様でありながらひとつ」という万博の理念をイメージしたとしている。
今回の万博では、「iPS細胞から作った動くミニ心臓」や「最新のアンドロイド」が展示される他、
「空飛ぶクルマ」のデモ飛行も行われるなど、社会課題の解決に向けた次世代の技術が披露される。
また参加する国や地域、国際機関には、1日ずつ「ナショナルデー」が割り当てられ、伝統や文化を紹介しながら来場者などと交流する催しも予定されている。
世界の分断が進む中、国際交流の場としての役割を果たすことができるかに注目が集まっている。
ところで、工期の遅れから直前まで全部のパビリオンが開館できるのか心配されていたが、
博覧会協会発表によると、自前のパビリオンを建てるネパールや、博覧会協会の用意した建物に外装や内装を施して参加するインド、
博覧会協会が建設した建物を単独で借りる形で参加するチリとベトナム、
博覧会協会が建設した建物に複数の国や地域で入る形式のブルネイの、あわせて5か国は、
内装工事などの準備が開幕に間に合わないことからまだ開館しないことになった。
今後、博覧会協会では毎日、翌日の開館情報をホームページで公開することにしている。
そもそも万博とは何だろうか。 正式名称は国際博覧会、もしくは万国博覧会。
「万博」は略称だ。万博は1928年に締結された国際博覧会条約に基づいて開催される。条約で開催条件などのルールが定められている。
万博の目的は、地球規模の課題の解決に寄与すること。もともとは1851年に世界中のヒトとモノが出会う場としてイギリスで初めて開かれた。
1990年代まで開催の目的は国威発揚につなげることだと言われてきた。
1996年以前はテーマを特定の分野に絞っているかどうかなどで「一般博」と「特別博」に分けられていた。1970年の大阪万博は「一般博」だった。
1996年以降は会場の規模によって分けられていて、規模に制限がない「登録博覧会」と制限がある「認定博覧会」の2種類がある。
今回の大阪・関西万博と2005年に開かれた愛知万博は「登録博覧会」だ。登録博覧会は5年以上、間隔を空ける決まりで、認定博覧会は登録博覧会の間に1回、開くことできる。
1970年の大阪万博には6400万人が訪れたが、その後、1992年に開かれたスペインのセビリア万博までの22年間、「一般博」は開催されなかった。
交通や通信の発達もあって万博でこそ見られるものが少なくなり、大規模な万博に多くの費用をかけたいという国が少なくなったのが理由だとみられている。
そこで万博に新たな価値を加えるため1994年の決議で、開催にあたっては「現代社会の要請に応えられる今日的なテーマ」などを定めることを必須とした。
この決議をきっかけに開催国は地球規模の課題の解決策を考えるためのテーマを掲げなければならなくなったとされている。
日本では 大阪、沖縄、茨城、愛知であわせて5回開催され、今回で6回目となり20年ぶりである。
日本で最初の万博は1970年の大阪万博で、「人類の進歩と調和」がテーマに掲げられた。
2005年の愛知万博では「自然の叡智」をテーマに掲げ、「環境万博」を打ち出した。
今回のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。
今の世の中は55年前と比べて、世界各地で紛争が起きるなど問題が多様化し、混沌としている。来場者はパビリオンを見学して、何を感じ取るのだろう。

しばし佇む

サクラのトンネル

土手の花束

タワーとビルとドローンと

初?
- 4月 7日
- 4月14日