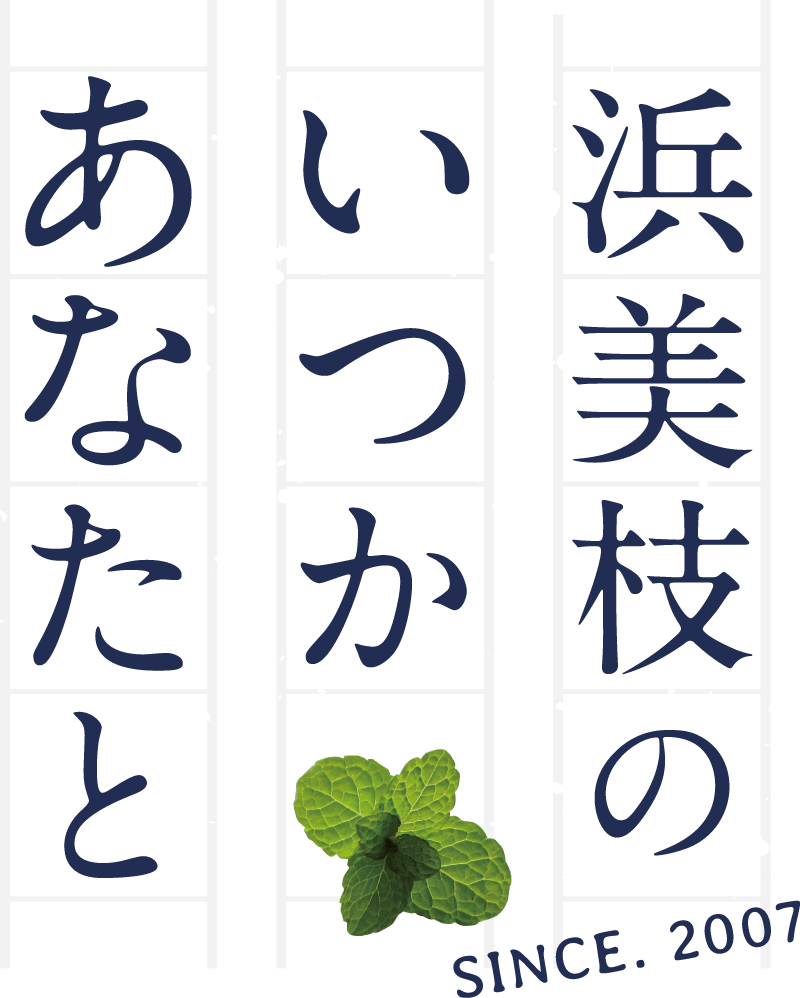寺島尚正 今日の絵日記
2025年7月28日 蝉のお出迎え
久しぶりに訪れた自然公園を訪れた。
朝6時、生き物達は、この時間まだ人間に比較的無防とみえ、入り口で、直ぐ近く迄寄ってもセミが逃げなかった。
もしくは、虫たちも連日の暑さで夏バテ気味なのかも知れない。
石段を踏みしめながら進む。木立の向こうに見え隠れする朝日が眩しくなってきた。
懐かしい木々の香りを味わう。
「ユリ」が、盛りを過ぎながらも凜と咲いている。
ウグイス始め野鳥の囀りが、森が醸し出すひんやりとした空気とぴったりだ。
更に深くと進んでいく。ふと枯れ木に覆われた地面で、身を潜める様存在する異色の物体に目が留まった。
キノコである。鮮やかなキツネ色だ。
不思議なもので、キノコを見付けると「これは食べられるのだろうか」との気持ちが過ぎる。食する気も無いのに、である。
この思いは、先祖がキノコを生活上頻繁に食していたからに違いない。
DNAにすり込まれているのだ。
キノコを見ながら様々疑問が浮かんできた。
「キノコのシーズンといえば秋」ではなかったか。
「なぜ、キノコは毒を持っているのか」
調べてみると、種類を問わなければキノコは年中見ることができるのだという。
多くの種類が発生する時期は、平地では6月から7月と9月から11月頃だ。
続いて毒についてだ。
キノコが毒を持つ理由は、現在でも完全には解明されていない。
しかし、いくつかの説がある。
その1、防御手段のため。
キノコは、動物に食べられるのを防ぐために毒を持つと考えられている。
ただし、植物は捕食者から身を守るために毒を合成するが、キノコの場合、毒はゆっくりと効き目を現すため、すぐに毒と分からない。
食べられてしまってでは遅いのだ。
この推測は後程。
その2、生存競争 。
地下で他の菌類との生存競争に打ち勝つために、毒という防御手段を身につけたという説がある。
その3、偶然。
キノコが偶然に獲得した物質が、人間にとってたまたま有害だったということも考えられている。
キノコ中毒の主な原因は、ツキヨタケ、クサウラベニタケ、テングタケの3種類で、これらが全体の約70%を占めている。
これらの毒キノコは地味な色をしており、食用キノコと間違えやすいことが中毒の原因となっている。
キノコ中毒の約9割は家庭で発生しており、秋に多く発生する。
キノコの見分け方には多くの迷信があるが、これらを信じて毒キノコを食べると中毒を起こす可能性がある。
例えば、「柄が縦に裂けるものは食べられる」「地味な色をしたキノコは食べられる」「虫が食べているキノコは食べられる」「塩漬けにし、水洗いすると食べられる」といった説は誤り。
キノコはその道のプロにお願いしたい。
キノコという名前は「木を切り倒したところによく生えている」ということに由来する。
それで「木の子」と書いて「きのこ」と呼ばれるようになった。
というものの、漢字では木の子とは書かずに「茸」と書くことが多い。
舞茸や椎茸などだ。
茸という漢字は「草冠」に「耳」と書くが、耳たぶのような食感のことや、耳にうぶ毛が生えている外見の様子から、茸という漢字が使われるようになった。
キノコの種類は非常に多く、日本には4,000~5,000種類のキノコが存在すると言われている。
キノコは、自然界では植物や動物の遺体などの有機物を分解して無機物へ還元し、植物 の栄養として土へ戻す役割を果たす「森の掃除屋」と呼ばれている。
他の菌類や微生物が分解できない分解が難しい物質であるリグニンを含む樹木の幹や枝なども分解することができるのだ。
また、樹木と共生し、互いに栄養を与え合うものもいる。
いずれにしても、キノコが毒を持つ理由について、未だ解明されていない。
キノコが食に適するか否かについては、人類の歴史の中で自らが試食することによって安全性を確認してきたものと思われる。
先祖に感謝なのである。
先述したが、一般的に植物の場合は、動物から捕食されないために様々な毒を合成し防御を行っている。
防御としての毒の場合、動物が食べてすぐに毒と分かるような成分だ。
つまり、食べられないように自分の身を守るための毒である。
しかし、キノコ毒は比較的ゆっくりと効き目を現すため、食べた側は、すぐには毒と分からない。
こんな悠長な反応では自分の身を守ることなどできない。
それが理由で、キノコの毒は、逆に食べられることで摂食者を死に追いやり、地球上の物質循環に意図的に係っているのではないかとも考えられている。
キノコは、植物や動物の死骸を土へ還す役割を担っている。
そして共生関係にある植物に養分を与えるために動物を死に追いやることも考えられるのだ。
キノコの色のカラフルさは、暗い森の中では目立つ存在。
胞子は、動物に食べられない場合は風で飛散し、また動物に食べられることも考慮して姿を表しているのではないか。
キノコを見つけた動物がきのこを食べて糞として胞子を拡散するもよし、死に至ればキノコの菌糸やバクテリアが死体を分解して土壌へ養分の形で還元し、それを植物が利用する。
キノコの毒は、強かな物質循環を考えて菌糸が身に付けたものともいえるのである。
恐るべし、キノコ。
森から、また教えて貰った。
「自然を深く観察しなさい、そうすればすべてのことがよく理解できるようになるでしょう」アインシュタイン

蝉のお出迎え

ユリも暑さで疲れ気味

目立ち過ぎ

キノコならでは

一風変わった
- 7月22日
- 7月28日