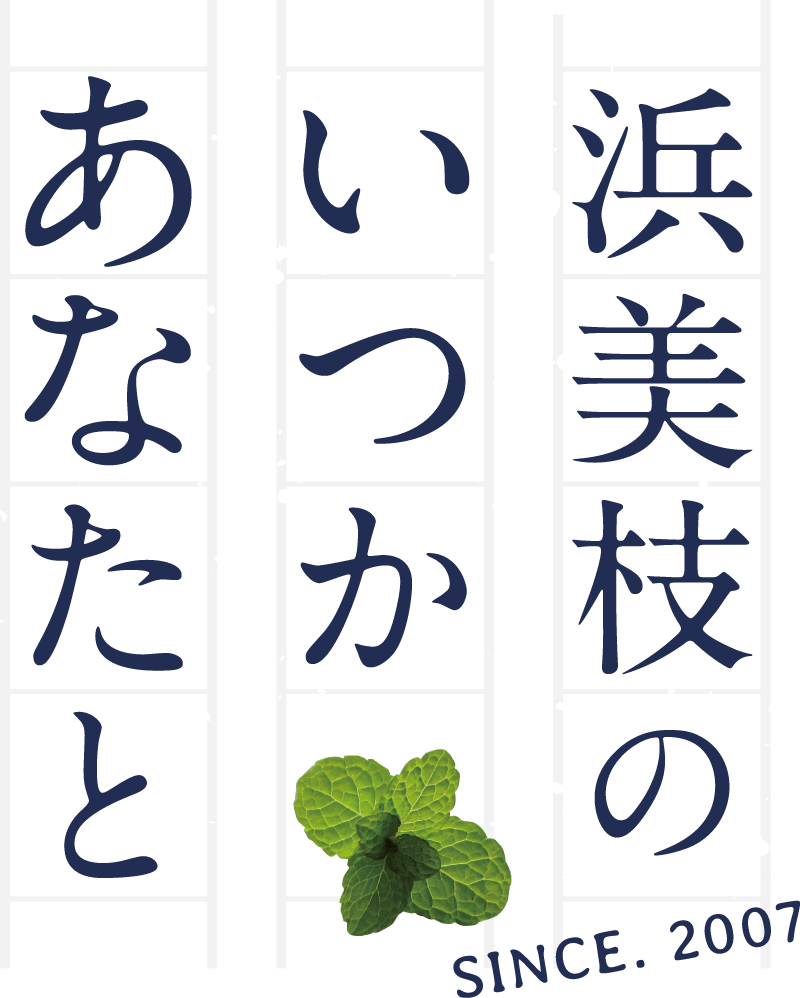寺島尚正 今日の絵日記
2025年9月1日 秋近づく
今年も、9月1日が訪れた。
1923年(大正12年)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災から102年が経つ。
神奈川県北西部の相模湾を震源とするマグニチュード7.9の海溝型地震で、明治以降の日本では最大の地震被害をもたらした地震だ。
死者・行方不明者は推定10万5,000人に上り、そのうち約9割が火災による焼死だった。地震発生が昼食時だったため、多くの家庭で火が使われていたのに加え、台風の影響による強風が、街全体に燃え広がるのを助長した。
全損家屋は30万戸に達し、電気、水道、道路、鉄道などのライフラインにも甚大な被害が出た。首都東京や横浜も壊滅的な被害を受け、社会に大きな衝撃を与えた。
特に東京では、数万人の避難者が集まっていた場所で火災旋風が発生し、約4万人が犠牲になるという大惨事も起きた。
火災旋風は、広い空き地や市街地、山林、石油コンビナートでの大規模火災時に発生することが知られている。
関東大震災では、100以上の火災旋風の発生が報告されていて、特に、本所被服廠跡(現在の東京都墨田区)では火災旋風により約3万8000人が焼死したとされ、避難者が持ち込んだ荷物などに引火し、大きな炎となって火災旋風が発生した可能性が指摘されている。
ところで、先にも記したが、関東大震災の震源は、陸の直下ではなく、海溝型地震だった。
その為、地震の揺れだけでなく、火災、津波、土砂災害、液状化など、多様な被害が広範囲に及んだ複雑な災害だったのである。
地震の規模はマグニチュード7.9、エネルギーに換算すると阪神・淡路大震災をもたらした「1995 年兵庫県南部地震」の約8個分に相当する。
さらに、その3分後にはマグニチュード7.2、さらにその2分後にはマグニチュード7.1の余震が起こった。
首都圏は、わずか5分の間に、マグニチュード7クラスの強い揺れに3回も襲われたのである。
大きな余震はさらに続き、翌9月2日には勝浦の沖合を震源とするマグニチュード7.6 の本震にも匹敵する地震が発生し、さらに2日夕方には、九十九里沖でマグニチュード7.1 の地震が発生した。
震源が相模湾内であったため、伊豆半島、伊豆大島、三浦半島、房総半島の海岸には津波が押し寄せた。
津波の高さは、伊豆大島や静岡県熱海市で最大12メートル、千葉県の旧館山市では最大9メートルに達した。
津波の到達時間は早いところでは地震発生後わずか5分で津波が来襲したとされている。
具体的には、現在のJR東海道本線、根府川駅の南側の河口付近では、地震発生時に遊んでいた子供達20人が津波と山津波の挟み撃ちにあい犠牲になった。
また宇佐美では、高さ約5メートルの津波が二度にわたって押し寄せ、家屋全壊33戸、半壊67戸、流失111戸の被害が出た。
一方で、1703年元禄地震や1854年安政東海地震の津波被害経験があった伊豆半島の宇佐美や下田では、言い伝えに従って住民が地震直後に高台に避難したため、家屋の流失は多数に及んだものの、人的被害は最小限に抑えられたという。
元禄地震を体験した人々は、「大きな地震が発生した場合は家財を捨てて早く丘に逃げる」ことを後世に伝えている。
これは、津波から命を守るための最も重要な行動であることを示唆しているのである。
これらの教訓は、現代の防災対策に生かされ、特に海溝型地震が発生する可能性のある地域では、地震発生時、津波からの避難経路確認や、早期避難の意識付けが重要とされている。
ところで、私達は様々なタイプの地震に備えなければならない。
阪神・淡路大震災(1995年)
兵庫県南部地震と称され、1995年1月17日午前5時46分に発生したマグニチュード7.3の内陸直下型地震。戦後初めて「震度7」が適用された地震であり、人的被害は6,434人で、死者の約9割が家屋倒壊による圧死・窒息死だった。
神戸市東灘区では阪神高速道路の高架が倒壊し、六甲アイランドやポートアイランドなどの埋立地では液状化現象が発生した。
東日本大震災(2011年)
2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の巨大地震であり、日本国内観測史上最大規模、世界でも4番目の規模だった。
最大の特徴は、巨大津波が広範囲に押し寄せた複合災害である点である。
津波の高さは福島県相馬市で9.3m以上、岩手県宮古市で8.5m以上が観測され、遡上高は国内観測史上最大の40.5mに達した地点もあった。
津波により壊滅的な被害が生じ、死者・行方不明者は2万人を超えた。
福島第一原子力発電所事故も引き起こし、大規模な放射能汚染が生じた。
熊本地震(2016年)
2016年4月14日にマグニチュード6.5の前震、その約28時間後の4月16日にマグニチュード7.3の本震が発生し、短期間に震度7の地震が2度発生したことで、「前震」と「本震」という概念が強く認識されるようになったことが最大の特徴。本震では熊本県益城町と西原村で震度7を観測。
震度6弱以上の余震が頻繁に発生した。
家屋倒壊による圧死が主な死因で、犠牲者の多くが高齢者だった。災害関連死が多数発生したことも特徴である。
能登半島地震(2024年)
2024年1月1日にマグニチュード7.6の地震が発生し、石川県輪島市と志賀町で震度7を観測した。関東大震災や東日本大震災と同じプレート境界型地震(海溝型地震)で、震源が深く、揺れが広範囲に及び、長周期のゆっくりとした揺れが特徴。内陸の活断層が上下に動く逆断層型の地震で、輪島市沿岸では最大約4メートルの隆起が発生した。
能登半島では群発地震が先行し、地下の流体が断層の動きを助長した可能性が指摘されている。
古い木造住宅の倒壊や土砂崩れ、液状化、火災など、地震で起こりうる被害が複合的に発生した。
過去の災害から得られた知識や教訓は、日本の防災対策に継続的に活かされてきた。
阪神・淡路大震災や東日本大震災といった大規模災害の教訓は、耐震化の促進、津波対策の強化、防災意識の向上など、多岐にわたる取り組みにつながっている。
地震はいつ、どこで起こるか予測が難しい自然災害だが、地球のプレートの動きが続く限り、大きな地震は必ず発生する。
日本は地震が多い国であるため、地震から命を守るためには、過去の教訓を活かした備えが不可欠だ。
まず、揺れへの備え。
大きな地震が発生した際には、建物の倒壊や家具の転倒などによる被害を軽減するための対策が重要である。
そして津波への備え。
東日本大震災では、地震の揺れだけでなく、巨大な津波によって甚大な被害が発生した。
一方で適切な避難行動をとることが人的被害をゼロにすることも可能なのである。
「悲観的に準備して、楽観的に行動せよ」
この言葉は、最悪の事態に備えつつ、実際には冷静で前向きに行動することの重要性を示している。そうありたい。

秋近づく

花元気

太陽の色

色で涼を感じる
- 8月25日
- 9月 1日