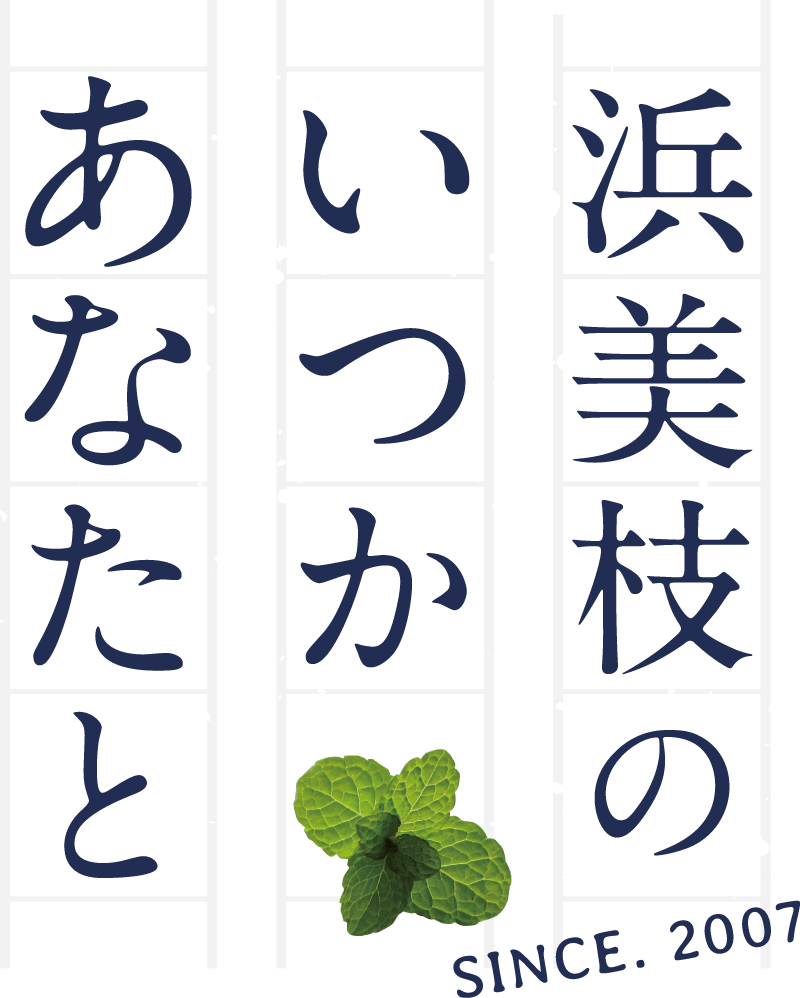寺島尚正 今日の絵日記
2025年9月16日 朝焼け
今年9月15日は「敬老の日」。
以前「敬老の日」は9月15日と決まっていたが、連休を多く作る目的で2003年から9月の第3月曜日となった。
戦後間もない1950年代に兵庫県の町や村から始まった「年寄りの日」が母体となり、やがて全国に広がり祝日として定着したと聞く。
今年も、花屋の店先には小振りの花束が並んでいる。
改めて考えると、この「敬老」という言葉が持つ響きは、時代ごとに少しずつ変わってきたように感じられる。
昔の日本社会における「老人」像は、家族や地域にとっての知恵の宝庫だった。
農作業の経験、生活の知恵、人生を生き抜いた物語。
それらを語る人は、家の縁側に座り、孫たちに囲まれながら、しみじみと話を聞かせてくれる、そんなイメージであった。
そこには「老いることは役割から解放されること」ではなく、「蓄積を生かして支えること」という意味が込められていたように思う。
実際、戦前から戦後しばらくの日本では、長寿それ自体が珍しく、老いはある種の尊敬と感謝を集める対象だった。
一方で、現代では「老人」と呼ばれる世代は、医学の発達と生活水準の向上により、かつてないほど長寿を享受している。
いまや日本の平均寿命は世界の最長レベルにあり、65歳を過ぎてもなお現役で働く人は珍しくない。
「高齢者=隠居」という図式は次第に崩れ、「生涯現役」といった言葉が広がった。
老いは、弱まりや終末のイメージでなく、「新しい時間をどう生きるか」という前向きな選択肢を含むようになったのである。
一方で、その変化の陰に、老いをどう受け止め、どう意味づけるかという難しさも存在する。
例えば、かつては家族が自然に担っていた介護や扶養は、核家族化や少子化によって社会全体の課題へと変化した。
今や老いることは「家族の中で自然に支えられる」ことに距離を置き、「制度や仕組みによって社会的に支えられる」ことが不可欠となった。
また「老いる」という現象はどうだろうか。
それは単なる身体の衰えではなく、自分の時間との向き合い方を変える契機ともいえる。
若い時期には未来が無限にあるかのように思えた。
しかし齢を重ねるごとに時間の有限さが現実味を帯びてくる。
そのことは必ずしも悲観を導くものではない。むしろ有限だからこそ、日常の一つ一つに重みと味わいが加わる気がしている。
例えば、季節の移ろいに敏感になり、小さな子供の元気な声に、未来ある輝きを感じ何だか嬉しくなってくる。
それは「老いたからこそ得られる感受性」だと感じる。
敬老の日の意義は、単に長寿を祝うことにとどまらない。
それは「老いる」という営みをどう価値づけるかを、私たち一人ひとりに考えさせる日でもある。
老いることは避けられない。
しかし「どう老いるか」は選ぶことができる。
孤独に閉ざされる老いもあれば、世代を越えた関わりを形作る老いもある。
その選択を社会の仕組みと個々人の心がどう支えるかが、これからの日本にとっての大きな課題になる。
その出発点として「敬う」という行為の意味を見直すことが大切だ。
「敬う」とは、ただ頭を下げることではなく、相手を認め、その存在の意味を受け入れることではないだろうか。
敬老の日、祖父母に電話一本入れてみる。
たとえ短い時間でも、その行為が世代をつなぐはずだ。
老いることを恐れるのではなく、そこで広がる新たな関係性を喜ぶことができるとすれば、この祝日は大切な意味を持ち続けるはずである。

朝焼け

老若男女が集う場所
- 9月 8日
- 9月16日