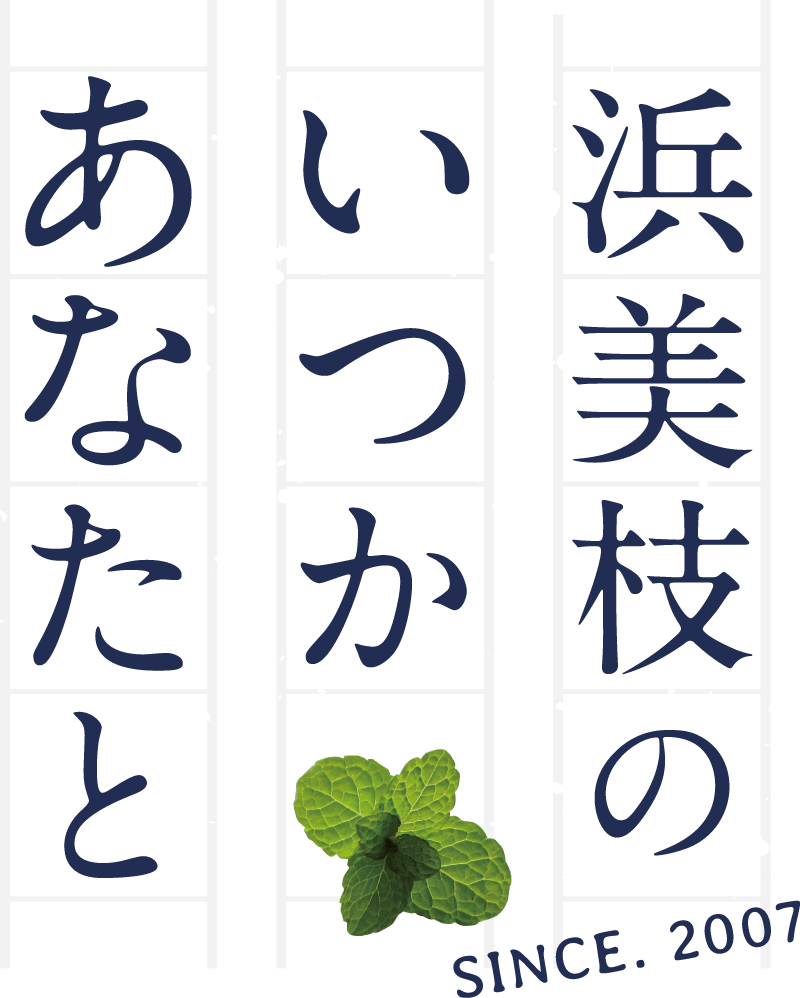寺島尚正 今日の絵日記
2025年9月22日 秋の色
9月21日、秋の彼岸に入った日曜、空の高くなった東京は、晴れてカラッとした空気に包まれた。
最高気温が都心で31度。
9月下旬になってもこの気温、体には堪える。
前日の土曜日が涼しかったので余計暑く感じられた方も多いと察する。
22日月曜からは数日間涼しくなる予想がでているが、26日(金)は再び多くの所で真夏日になりそうだ。
さらに、台風19号が暖かく湿った空気を運んでくるため、とても蒸し暑くなるという。
秋のお彼岸を過ぎても熱中症に注意が必要である。
そんな気温の変化によって体調が悪くなる人が多いと聞く。
原因はいくつかあり、主なものとして、自律神経の乱れ、寒暖差疲労、湿度の影響、低気圧の影響が挙げられる。
まず自律神経の乱れ。気温が急激に変化すると、体温調節を司る自律神経のバランスが崩れやすくなる。
自律神経は体温だけでなく、血圧や消化機能なども管理しているため、そのバランスが乱れると頭痛、めまい、倦怠感、胃腸の不調、肩こりなどを引き起こすことがあるのだ。
続いて、寒暖差疲労。特に春や秋など、朝晩の寒暖差が大きい時期には、体が温度に適応するためにエネルギーを多く消費し、疲労が蓄積されることがある。
これを「寒暖差疲労」と呼び、だるさや体力の低下につながる。
1日の気温差が7℃以上になると、体調不良を感じやすくなると言われている。
さらに湿度の影響だ。
湿度も体調に影響を与える。湿度が高すぎると汗が蒸発しにくくなり、体温調節がうまくいかなくなることがあるのだ。
逆に乾燥した環境では、肌や喉が乾燥し、風邪を引きやすくなることもある。
加えて低気圧の影響である。
台風や梅雨の時期に多い低気圧は、血管を膨張させやすく、頭痛や関節痛、気分の落ち込みを引き起こすことがある。
気圧の変化は内耳が感知し、それが自律神経に影響を与えて不調を招くと考えられている。
このような気象条件による体調不良は「気象病」や「天気痛」と呼ばれている。
これらの体調不良を和らげるためには、規則正しい生活習慣を保ち、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることが大切である。
また、気温に合わせて服装をこまめに調節することや、室内外の温度差を小さくすることも有効だ。専門家は、「中心は自律神経を整えること」と口を揃える。
寒暖差疲労の具体的な対策をいくつかご紹介しておく。
初めに服装の工夫。具体的には重ね着で調節するのが良いとされる。
気温に合わせて脱ぎ着しやすいように薄手の服を重ね着する。
必要に応じて帽子やストールなども活用すると、急激な温度変化から体を守れるのだ。
続いて室温の調整。 外出前に室温を調整し、外と室内との温度差をなるべくなくすよう、エアコンなどを上手に活用する事をお勧めする。
次に入浴とリラックスだ。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで血行が良くなり、体温のバランスが整いリラックス効果も期待できる。
具体的には38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分程度肩まで浸かる入浴。
入浴後は体を冷やさないよう注意すること。
さらに深呼吸。
リラックスするための深呼吸は、自律神経を整えるのに役立つ。
デスク作業中、深呼吸を意識し1~2分軽く目をつむって鼻から吸い、口からゆっくり吐き出す。
自律神経のバランス調整に有効である。
そして規則正しい生活習慣。
言わずもがなではあるが、十分な睡眠は大切だ。
寝る前はスマホやPCを控え、リラックスする時間を作る。
なるべく毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することで、自律神経のバランスが整いやすくなり、疲労回復を促すという。
結びにバランスの取れた食事。
冷たいものを取りすぎず、体を温める食材を積極的に摂るようにする。
特にビタミンB群やマグネシウム豊富な魚・ナッツ・葉物野菜、根菜類や発酵食品を意識するとよい。
質の良い食事は、自律神経を整える基本なのである。
なるべく体を冷やさず、食事に気をつけ、よく眠る、忘れないようにしたい。
今年も近所の区営プールが閉園となり、プールの上に板を敷きフットサル場に変更中である。
暑さの残る列島に、今年も彼岸花の季節がやってきた。

秋の色

秋の光景

夏の終わり
- 9月16日
- 9月22日