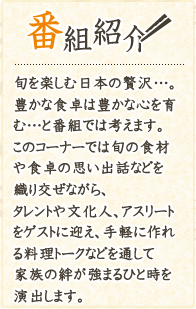『食べもの歳時記』8回目のゲストは、
和文化研究家の三浦康子さんです。
和文化という事で、お着物でいらっしゃいました。
「いただきます」「ごちそうさま」の意味。
「いただきます」には2つの意味があります。
1つ目は、人への感謝。
2つ目は、食材(命)への感謝。
また、「ごちそうさま(ご馳走さま)」には、
馳走(ちそう)というのが、食事を用意してもてなすために奔走する様子を表し、
食事を準備してくれた人への感謝する意味があります。
食べることは、生きる力を授かること。
ないがしろにしてはいけませんね
季節の食べもの、旬のものには力がある。
季節の食べものには、体調を整える効果や、
邪気払いの効果があると言われています。
そして、節供(せっく)料理の最たるものがお正月の「おせち」です。
最たるもの?おせちって1回じゃないの?
実は、節供料理は1年に5回あります。
1月1日の元日、3月3日のひな祭り、5月5日の端午の節句、
7月7日の七夕、9月9日の重陽(ちょうよう)。
現在では節供の1番目にあたるお正月の料理を表す言葉として
「おせち」が使われます。
節供料理の最たるものが「おせち」なんです。
おせちを食べるときに使うのが「祝い箸」。
祝い箸は、神人共食を象徴する道具で、片方は自分が、
もう片方は年神様が、使うとされているため、
両方細くなっています。
おせち料理を食べている時は、もう片方で神様が食事をしていると
思ってください。