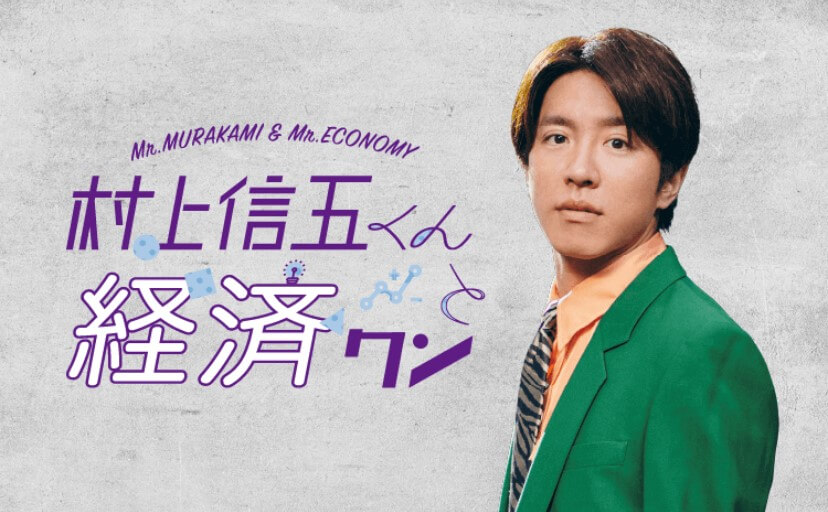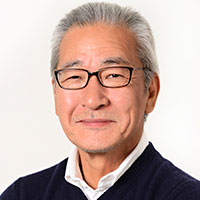株価上昇しても不況を感じる理由
大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」(文化放送・月曜日~金曜日11時30分~15時)、10月9日の放送に第一生命経済研究所・主席エコノミストの藤代宏一が出演。発売中の著書『株高不況 株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』にちなみ、株高と生活苦との関係について解説した。
大竹まこと「こういう名前(エコノミスト)、よく聞くけど、どういうお仕事をしているんですか?」
藤代宏一「エコノミストやアナリストと呼ばれる人たち、そこの違いって、まずないんですね。民間の金融機関に属している、というパターンが多くて。仕事としては私、普段は『金融市場の分析』です。日本、アメリカの経済指標が出ればデータをダウンロードして、どういう動きをしたのか。それが金融市場でどう昇華されていくか、といったところを分析しています」
大竹「本題です。『株高不況 株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』(藤代宏一の著書。発売中)。お金はいったいどこに行ってしまっているんでしょうか?」
藤代「まず、株が高いというのはご承知のとおりで。日経平均が4万8000円といった水準まで上がってきていて。それが実態を伴っているものなんですか、という質問が来るわけです。ここでいう実態とは企業収益(企業の利益)ですね」
大竹「うん」
藤代「まず株高の実態というのは、裏付けがあるということ。裏付けがない上昇というのが、よく引き合いに出される1989年のバブルで。あのときは利益が大して伸びないけど過度の楽観があったんだと思います。なので株価が4万円近くまで上がった。対していまは実態を伴っている。ただ消費者の実感は伴っていない、と。経済指標から見ても明らかで」
大竹「はい」
藤代「たとえば日本銀行や内閣府が調査している消費者心理の指標を見ると、かなり悪い。消費者心理としては不況なのに株価がどんどん伸びる。その間にあるのはなんですか、というのを分析したのがこの書籍でして。いちばん大きいのはインフレです。簡単な例で申しますとインフレというのはありとあらゆるものの価格が上がる、と。人件費や給料、といったものも含まれます。いま賃金も物価もかなり上がり始めているんですね」
大竹「物価はわかりますけど、賃金は?」
藤代「じつは上がっているんです。物価に追いついていない、というポイントはありますが。『名目値』というんですけど、純な、目の前にある金額は増えているわけです。これがいわゆるインフレで。ありとあらゆる、という中に株も入ってくるんです」
大竹「ああ」
藤代「いまインフレで、企業収益そのものが膨らんでいる、という状態です。大して儲けるようなビジネスはしていないけど、見た目の企業収益は膨らむ、かさ上げされる、ということになっていて。具体的な例に落とすと、たとえば売上が100、コストが50、利益が50という利益率50%の会社があるとします。それがインフレで全部2倍になる、利益率は変わっていない。株価は2倍になる、ということが起きています」
青木理「物価が上がっているのは恐らく、ラジオをお聴きの方も実感していて。まさにインフレ状態になっていると。大竹さんも疑問を呈されたように、大企業の賃金はそれなりに上がっている。ただ物価高に追いつくほどの上がり方ではないから生活が苦しく感じる、となっていると思う。中小企業や非正規労働みたいな不安定な働き方をしている人たちからすれば『上がっていると言われても、実感ないよね』と」
さらに大竹、青木からの質問に藤代が回答していった。詳しくはradikoのタイムフリー機能で確認してほしい。
「大竹まこと ゴールデンラジオ」は午前11時30分~午後3時、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。
※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。
関連記事
この記事の番組情報