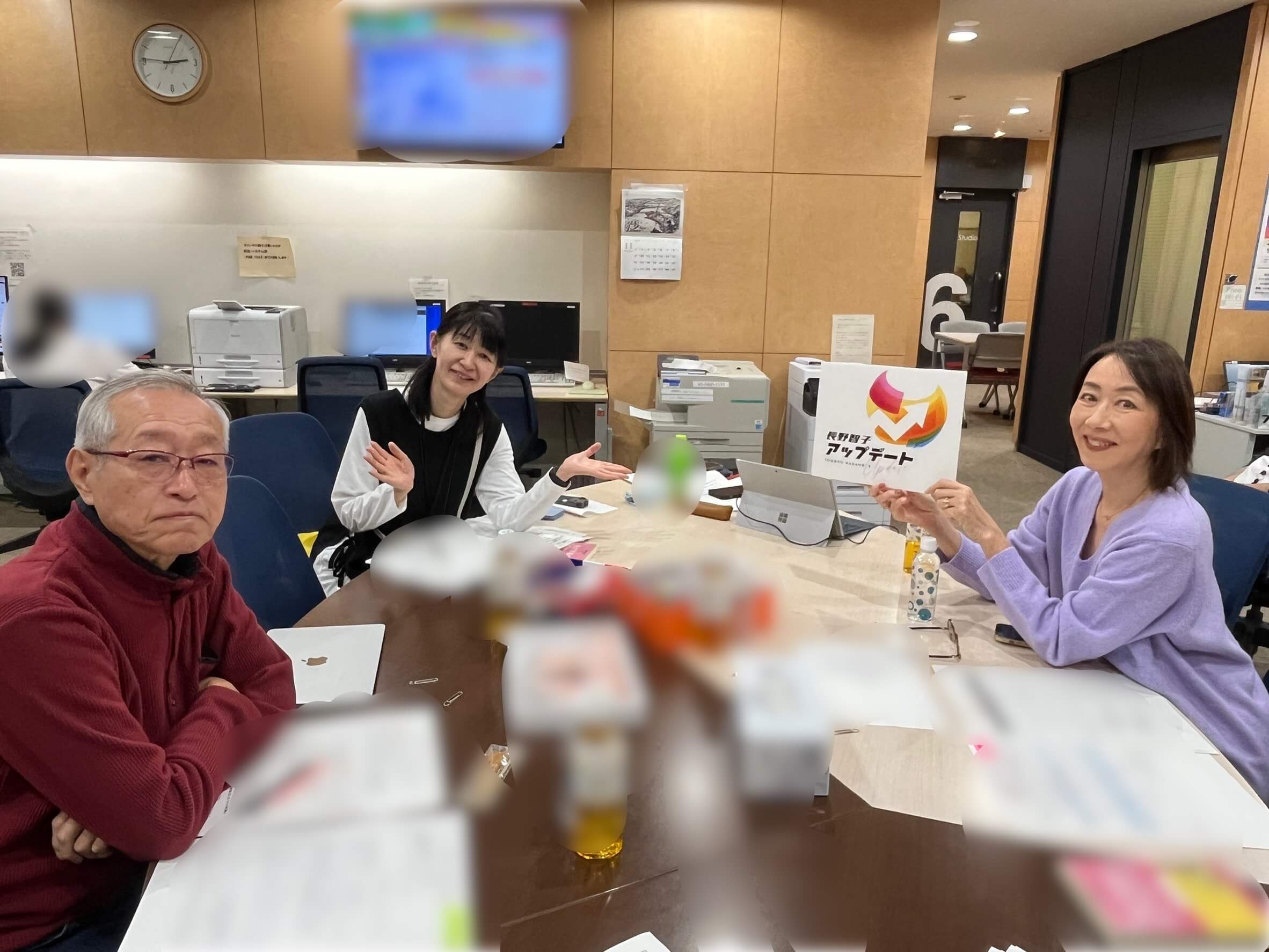
「デジタル赤字」とは何かを解説。「技術立国」だった日本でなぜ膨らむのか
ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日15時~17時、火~金曜日15時~17時35分)、11月24日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。膨らみ続けているという「デジタル赤字」について解説した。
二木啓孝「デジタル赤字は皆さん、意識していないけど、じつは毎日払っているものなんです。スマホやパソコンを使っているとき、海外に支払っているデジタルの料金があるんですね。MicrosoftやAppleなどの基本ソフトがあります、アプリをとったときライセンス料がかかる。私も最近、使っているChatGPTなんかのAI、人工知能にだってかかる。クルマに入っているデジタルの海外のものも、ソフトがあるから払っている、と」
長野智子「私も毎日、すごく払っていますね」
二木「そうでしょう。LINEは日本で9900万人が使っているといわれて、この通信アプリは韓国のネイバーという会社に使用料や広告料を払っている」
長野「考えてみればそういうの、ほとんど海外ですね。価格は先方が決めると」
二木「GoogleもAndroidも日本じゃないですからね。Googleに対して日本の公正取引委員会が『独禁法の違法じゃないの?』と、独禁法違反の命令を出した。もっとバラしなさい、と。Googleはどういう見解かというと、強制はしていません。契約は任意ですから競争を妨げません。スマホの端末もどうぞ自由にしてください、と」
長野「なるほど」
二木「ところがシャープやソニーなどがスマホを出すと『それは困るな』と。なぜ困るかというとGoogleでもAndroidでも初期投資を入れたらスマホの会社はけっこうな額の分配金をもらっていたわけ。GoogleやAndroidなしでスマホを出したら売れないよね、と。だからそういうふうになっている」
長野「ああ……」
二木「じつはアメリカでも巨大IT産業、GAFAに対して独禁法違反だ、分社しろ、と言われる。ただし分社化すると中国の巨大企業が入ってくる。それはいけないとなって結局、黙認、と。ITの巨大産業がいまほど浸透すると逃れられない」
長野「ここまで日本の技術が入っていけなかった、という状況もすごいですよね」
二木「そのことを私は言いたくて。技術立国と呼ばれた日本がなぜ負けたのか、と。世界のデジタルランキング、というのがあって。デジタルを使っている69ヶ国中、日本は(『デジタル技術の習得』で)65位。日本ってデジタル、ダメじゃん、と気がついたのはコロナ禍での給付金。オンライン申請してと言ったら、大混乱でダメだったでしょう」
長野「ほかの国に比べて遅かった」
二木「多くの自治体は結局、郵便で給付しますから、とお手紙で来た。それが2020年。なぜこうなったか。取材して、なるほどと思った。バブルが崩壊して、各企業が赤字になった。どう再建しよう、となったとき大手企業はデジタルの技術部門を切ってしまったんです。成果が出るまで15年ぐらいかかるから」
長野「すぐ成果の出るところを残して、不採算部門みたいに思われてしまったと」
二木「会社を辞めることになった90年代の日本の優秀なソフト技術者が海外へ流れた。バブル崩壊のあとに企業防衛することで、日本の技術が保てなくなった。『失われた30年』というけど、何が失われたかというと、ソフトが失われた、ということだと思います」
「長野智子アップデート」は毎週月曜午後3時~5時、火曜~金曜午後3時~5時35分、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。
※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。
関連記事
この記事の番組情報










