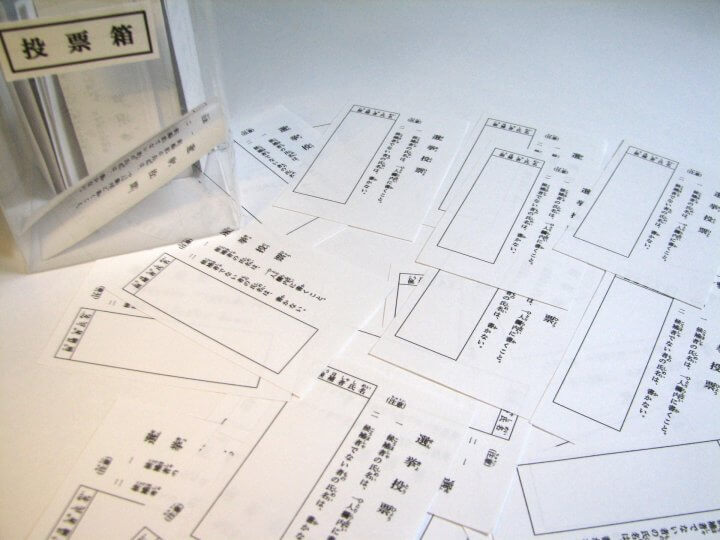カフカの『審判』、現代のアメリカに重なる
ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日15時~17時、火~金曜日15時~17時35分)、10月15日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。「トランプ政権に現れたカフカのディストピア」というテーマで、作家のフランツ・カフカにちなんだ言葉が広まっているという、現在のアメリカについて解説した。
小倉孝保「(作家のカフカについて)『変身』は知っている、という人は多いんですよ(笑)。現在のチェコのプラハに生まれた、ユダヤ系の作家です。ドイツ語で創作をしていました。法学の博士でもあります。最後に書かれた作品が『審判』といい、彼が亡くなった翌年、1925年に発売されました。ちょうど100年になるんです」
長野智子「ご存命のときはそんなに売れていなかった?」
小倉「らしいんです。『審判』なんか、これは絶対にオモテに出すな、という遺言があったと。いや、これは社会的な意義がある、といって友人が出したらしいんです。完成していない、とされていて。初めと終わりだけ書いてあるから、終わっている感じだけど。なんできょう、私がカフカの話をトランプ政権と絡めてしたかったか。このところアメリカのジャーナリズムを読んでいると、カフカの世界が現れてきた、という表現が目につくんです」
長野「あ、記事の中で」
小倉「英語では人名を形容詞的に使うことがけっこうあって。それがカフカエスク。カフカ的。僕もなんとなく『変身』のイメージがあるから、モヤモヤした感じで、カフカ的なものってこうなのかな、というのはあったけど。きのう、イギリス人の友達にカフカエスクについて聞いたんですよ。彼が言うには、非常に難しい英語で。普通の人はなかなか使わないと。友達が言うには簡単に説明すると『なんでもありの世界、という感じだよ』と」
長野「そういう感じですか」
小倉「辞書を調べたら、逮捕されたのに理由なし、説明してもらえない。対応してもらえないのに事態がどんどん進んでいく」
長野「それがまさにカフカ『審判』のストーリーだった」
小倉「そうなんです。彼が最後に書いた『審判』の出だしが、そのシーンです。ある主人公が30歳のときに突然、逮捕されて。なんで逮捕されているか本人がわからない。いろいろなところで聞くけど、答えてくれる人がいない。でも裁判は進んでいく、という話で始まるんです。その世界がいまトランプ政権下のアメリカで起きているんだ、という言い方で」
長野「カフカエスクといわれる」
小倉「カフカエスク、カフカランド(カフカの地)。いま、カフカエスクの世界に入ってしまった。という言い方をしているらしい。人の名前を形容詞に使う、ということがそんなに多いんだ、というのも驚いたし。その人が『日本語でもイギリス人にとって難しい問題があるんだよ』と」
長野「はい」
小倉「たとえば『小倉さん、あなたが書いた“かなえびと”。どういう意味かよくわからないんですよ』。叶える人、という意味で僕がつくった。造語です。日本人だとなんとなく、こんなイメージだ、というのがあるけど。日本語はそういうかたちで言葉をつくっていく。英語はそれを人の名前でつくる。それがいまのアメリカでは、カフカなんです」
「長野智子アップデート」は毎週月曜~金曜午後3時~5時、文化放送(FM91.6MH
※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。
※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。
関連記事
この記事の番組情報