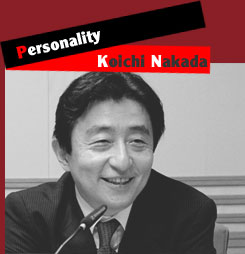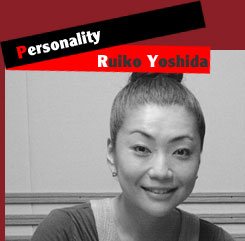第19回 2010.02.25 ON AIR
2010/02/25
『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」。
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田
“法律”の観点から解説します。
____________________________
○注目のニュース
起訴
********************************************
民主党・小沢一郎幹事長の資金管理団体『陸山会』の
土地購入をめぐる事件で、東京地検特捜部は今月4日、
政治資金規正法違反の罪で、衆議院議員・石川知裕容疑者、
元会計責任者で小沢氏の公設第1秘書・大久保隆規容疑者、
元私設秘書・池田光智容疑者の3人を起訴。
小沢氏については、嫌疑不十分で不起訴としました。
********************************************
◆ポイント1 起訴とは
中田 「きょうは、このニュースの内容というよりも
『起訴』というものについてお話します」
「名前の通り訴えを起こすこと。
法に定められた手続きに従って、
裁判所に対して、判決をすることを
求めること――と言われていて、
『起訴』という言葉を使う場合は
『刑事事件』として使われることが一般的です」
____________________________
◆ポイント2 起訴の種類
●公判請求
公開法廷で行われる「公判」手続きを求める請求。
●略式命令を求めるケース
『公判手続き』に対して、簡易裁判所管轄の事件は
『略式手続き』と呼び、
これによる有罪裁判を『略式命令』といいます。
●即決裁判を求めるケース
新しい制度には、
簡易・軽微な事件の場合の即決裁判を求める
『即決手続き』もあります。
中田 「いずれにしても、有罪の判決・裁判を求めて
裁判所に提起するものを『起訴』、
あるいは『公訴の提起』といいます」
____________________________
◆ポイント3 起訴までの流れ
吉田 「どんな経過で行われるんですか?」
●事件を知る(事件の認知)
●捜査がはじまる(捜査の端緒)
●証拠の収集・被疑者の特定
●検察官に送致(=送検)
____________________________
◆ポイント4 『起訴・不起訴』は検察官の裁量で決まる
●起訴独占主義
検察官以外は起訴することができません(原則)
●起訴便宜主義・起訴裁量主義の原則
検察官は、刑事裁判で罪に問わなくていい――と判断した場合
公訴を提起しないこともできます。
中田 「つまり、検察官が一手に引き受けて」
起訴した李起訴しなかったりせんといことを
裁量で決めましょう、という決め方になっているんです」
今回のニュースで、小沢幹事長が不起訴となったのは
起訴独占主義・起訴便宜主義により
検察官が有罪判決を求めて裁判所に公判請求をしなかった
――ということ。
____________________________
◆ポイント5 不起訴の種類
『不起訴』には次のような種類があります。
●捜査の結果、犯罪を構成しないことがわかった場合
『犯罪』は、構成要件に該当した場合、罰せられる――と法に定められています。
◆犯罪が成立する要件を欠く例◆
・窃盗犯が盗んだものが、自分のものだった場合
・刑事未成年(14歳未満)の場合
・心身喪失の状況にあった場合
●訴状条件を欠く場合
・被疑者が死亡していた場合
・公訴時効が完成していた場合
・親告罪に対して告訴がない場合
●嫌疑なし の場合
・犯罪発生は認められながら、
(捜査対象者に)犯人としての嫌疑がない場合
●嫌疑不十分 の場合
・犯人としての嫌疑はありながら
有罪判決のための証拠が集まらなかった場合
吉田 「小沢幹事長の場合はこれですね」
中田 「有罪判決をもらうには、
証拠が足らなかったということですね」
『不起訴』とし場合も
検察官は捜査を再開することができ、
その内容によって、(公訴時効までは)『起訴』することができです。
____________________________
◆ポイント6 検察審査会制度
ポイント4でご紹介した
起訴独占主義、起訴便宜主義(起訴裁量主義)にも例外があります。
検察官には、不起訴にする裁量権があるものの
遺族などから「起訴されるべきだ!」という声が上がることもあり
不起訴にしたことが いいのか悪いのか――について
審査申し立てを受けるのが『検察審査会』。
『検察審査会』は、
管轄する地方裁判所の管轄区域の衆議院選挙人名簿の中から選ばれた
11人の検察審査員で構成されます。
吉田 「我われもその中に入る可能性があるということですね」
検察審査会は“不起訴にした処分が、本当に良かったのか”――と
不服申し立てがあった場合は、審査会議を行い、
次の議決を行うことができます。
1.『起訴相当』(起訴をするべきと認めた場合)
2.『不起訴不当』(起訴しない処分を不当と認めた場合)
3.『不起訴相当』(不起訴処分が妥当だったと認めた場合)
1、2の場合
検察官は再捜査をしなければいけません。
不起訴不当の議決がありながらも、再び『不起訴』となった場合
『検察審査会』は、専門家の弁護士を委嘱し、審査補助員として加え
再び審査をすることができます。(11人+1人)
ここであらためて『起訴相当』となった場合
8人以上の多数で、起訴すべき議決――『起訴議決』ができます。
この『起訴議決』がなされた場合
裁判所が指定した 指定弁護士が
検察官にかわって公訴を提起し、公判が開かれます。
有名な事件には『明石花火大会歩道橋事件』があり
初めて『起訴議決』がなされ、明石警察署 元副署長が起訴されました。
____________________________
(吉田)
「今まで、たくさん聞いてきたことを、
なんとなく整理できた方が多いんじゃないかな、と思いますね」
次回もお楽しみに!
投稿者 senpatsu : 2010年02月25日 21:00