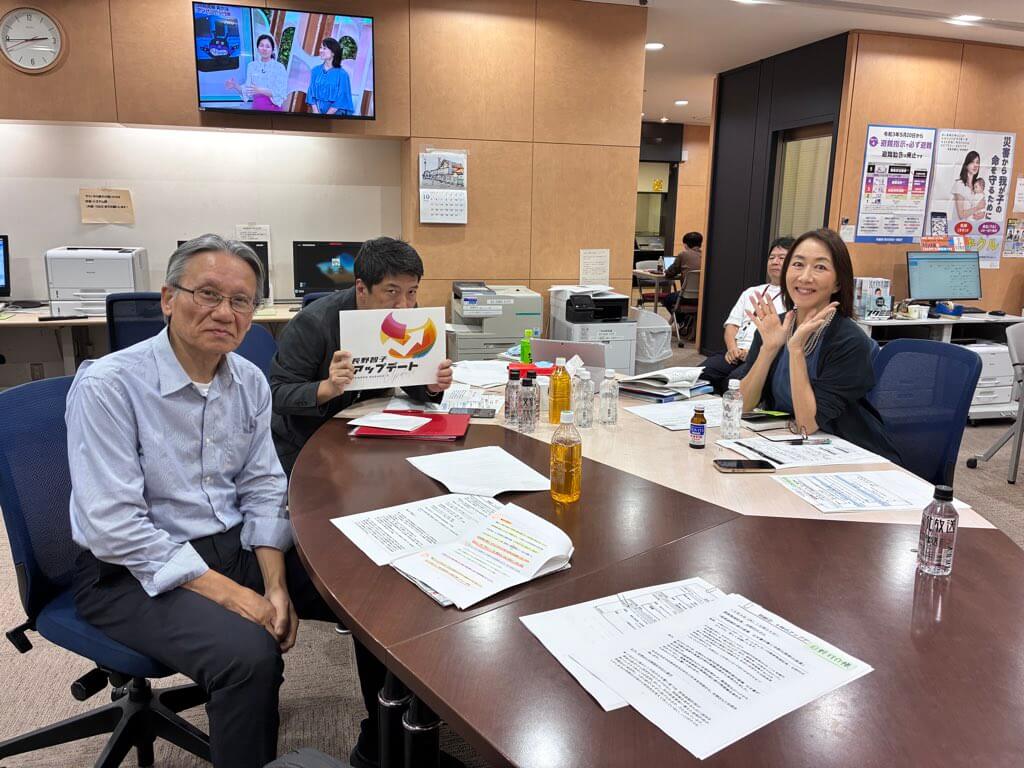
ノーベル賞、受賞ラッシュに日本沸く。一方で心配される科学力
ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日15時~17時、火~金曜日15時~17時35分)、10月9日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。今週、ノーベル生理学・医学賞を坂口志文・大阪大学特任教授が、ノーベル化学賞を北川進・京都大学特別教授が受賞したニュースや、現在の日本の科学力について解説した。
長野智子「まさにノーベルウィークということで。日本人の方々が受賞しています」
久保勇人「ノーベル賞をこれだけとれると誇らしいですね。21世紀に入ってから日本は、複数の受賞者が出る年ってけっこうあるんです。それぐらいとる国として知られています。個人としてはアメリカ国籍の方も入れると30人目、このほかに文学賞のカズオ・イシグロさんもいます。ノーベル賞は1901年から始まっていて、国別で日本は5位です。1位アメリカ、2位イギリス。ドイツ、フランスに日本が続いていると」
長野「がんばっている!」
久保「中国や韓国からも、日本はすごい、という評価がよく出ます。一方で日本は、いま科学研究力が低迷しているといわれています。ひとつの答えとして。文科省が毎年、世界の中での科学研究力の位置づけを調べてまとめています。今年も8月に最新の調査結果が発表されました」
長野「あっ、そうですか」
久保「これを見ると自然科学系の論文の総数は昨年同様世界5位です。つまり何本、自然科学系の論文が発表されたか、という。ところがこの論文を引用して自分の研究に役立てている、非常に注目度が高い論文、と。そういう調査があるんです」
長野「引用された回数が大事なんですよね」
久保「そうなんです。よく『Top10%論文』といわれます。先ほど出した本数は5位と話しました。世界で引用された、注目度の高い論文は13位なんです」
長野「落ちましたね」
久保「いま1位は中国です。アメリカ、イギリス、インド、ドイツ、イタリア、オーストラリア、カナダ、韓国、スペイン、フランス、イランのあとが日本なんです。Top10%論文というのは研究の質の高さも指標のひとつといわれまして。これが現在はそういった状況にある、ということ」
長野「いま連続して受賞している方の研究は30年前とかそういう時期からだから……」
久保「そう。Top10%論文、90年代などには2位や3位でした。どんどん下落していって。21世紀になってから7位、6位、9位、10位、12位と。ひとつの指標ではありますけど、そこら辺が、科学力が低迷しているね、とされる理由で。世界的に見れば論文の総数が多い国は必然的に質の高い論文数も多くなるはずなんです。ところが日本は総数が5位なのにTop10%論文で落ちていると。皆さんが非常に悲観的、なんとかしないといけないね、という状況になっているんですね」
長野「その背景が気になります」
久保「この報告書の中で要因として指摘されていることがいくつかあります。大きくクローズアップされているのは、世界的な物価高騰に対し、研究費の増加が追いついていないこと。それによって資金的にも(厳しく)、人材も離れていく。研究環境が悪化しているんじゃないか、という指摘です」
「長野智子アップデート」は毎週月曜午後3時~5時、火曜~金曜午後3時~5時35分、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。
※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。
関連記事
この記事の番組情報





