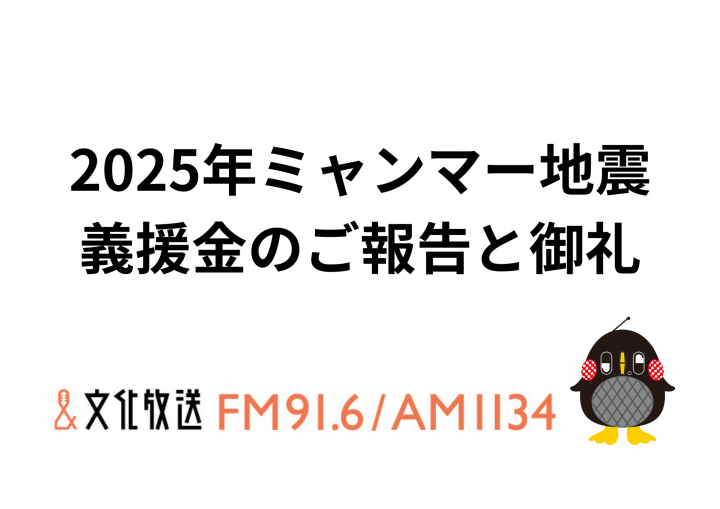命を賭けたドキュメンタリー「ミャンマー・ダイアリーズ」~鈴木BINのニュースな映画
鈴木BINのニュースな映画
文化放送解説委員で映画ペンクラブ会員の鈴木BIN(敏夫)が、気になる映画をご紹介しています
文化放送公式ホームページにて「第5スタジオは礼拝堂」も
- 命を賭けたドキュメンタリー「ミャンマー・ダイアリーズ」

© The Myanmar Film Collective
ミャンマーでは、2021年2月1日に起きた軍によるクーデター以降、一般市民1万人以上が投獄されたり、殺されたりしている。そのミャンマーで映画は撮影された。いずれも匿名の10人のミャンマーの映像作家たちが撮影した映像を持ち寄り、文字通り「命」を賭して完成させた作品だ。
ちなみに今作品には、先日オンライン会見に参加させて頂いたコ・パオ監督のドキュメンタリー「夜明け」の中にも登場した同じ映像が使われていた。それは一般市民が配信していたFacebooki動画で、2021年2月1日の朝、いつものようにエクササイズの模様をライブ配信していたら、向こう側の道路に突然軍が集結し始めたという映像。民主政治が断ち切られ恐怖政治が始まる瞬間を、エクササイズの最中、偶然捉えてしまった歴史的な映像だ。
香港映画との相似点
この「ミャンマー・ダイアリーズ」の制作者は匿名であると書いたが、香港理工大学に立てこもった学生たちが包囲され、民主化デモが鎮圧されてゆく様子を描いた香港のドキュメンタリー映画「理大囲城」も、撮影者自身が安全のため顔を隠して匿名を貫いていた。複数の匿名映画人による共作である点も同じで、抑圧下にあるドキュメンタリー制作の新たな手段として非常に興味深かった。香港の映画人たちも厳しい状況下にあるわけだが、顔がばれたら殺されるという意味においては、ミャンマーの映画人はさらに深刻な環境に置かれていると言えるだろう。
映画の中では、平凡すぎる日常の光景も広がる。昼下がりに煙草をくゆらせる女性。木の上で鳴くカラスたち。ピアノが奏でる「エリーゼのために」。日本と同じ景色。その景色が牧歌的であればあるほど、背後には暴力と不条理と銃声音が隠れているのが見える。彼らもこうした矛盾と暴力のパラレルワールドでずっと暮らしてきたわけではないことが尚更悲しいと思う。少なくともアウンサンスーチー氏が率いていたNLD政権の時代は日本と変わらぬ平和を謳歌していたはずだし、最後のフロンティアとまで呼ばれ世界中の企業が進出し、前途洋洋たる未来が開けていた。それを自己保身と組織保全のために軍が壊した。
天国から地獄へ
「民主主義を」と叫ぶ声が街頭から聴こえてくる。3本指を立てながらデモ行進を行う人達がいる。映画を観ている我々も、彼らにこの後、何が起きるかわかっているので映像を観るのが辛い。銃声が響き渡り、ピアノは演奏を止め、押し入ってきた警察に子どもは「ママを連れて行かないで」と泣き叫ぶ。路上では67歳の女性が逃げも隠れもせぬといった様子で「軍隊が赤い服を着ていただけの女性を撃ち殺した」と悪い奴らに詰め寄り怒りの声を上げ続けていた。「下劣な奴らめ」と。この勇気は多くの日本人にはないであろう。自分にもおそらく無い。恐怖と同時に民衆の強さや勇気を見せつけられる映画でもある。
不服従運動に父が加担したことで恋人にふられ落ち込む女性。家の片隅で寂しげな表情を浮かべる痩せた猫。個人的にもっとも印象に残ったのは、初老の女性を連行するため複数の警官たちが現れたシーンだ。「ママに触らないで」と家の中で抵抗を続ける男の子の声だけが聞こえてくる。カメラは背後から気づかれないように警官隊を撮り続けているのだが、最後尾にいる女性警官2人の様子がどうにも落ち着かない。2人は葛藤や恐怖に怯えているようにも見える。なぜ警察官になってしまったのかと悔いているのかもしれない。
香港のドキュメンタリー映画を観ても、同じようなことを考えるシーンがあった。現場でこん棒を振り下ろす警官たちにも家族はいるだろう。どこで心の琴線を断ち切ってしまったのか。彼ら香港ポリスの中には、ジャッキー・チェンの映画を観て警官を志したものもいるだろうし、習主席に尻尾を振り続ける哀れな行政長官、李家超とは違うはずだ。せめて内面は違っていて欲しいと思う。

- © The Myanmar Film Collective
メタファーなのか、真実なのか
血まみれになった手の映像や袋を被った男性などメタファー的な映像も合間に入る。息をするたびに顔に張り付くビニール袋と、後ろの壁に貼られた種々のメッセージ。息苦しさももちろんだが、自分の顔を見せることができない現実と相まって、実はメタファーでは無いのかもしれない。これが現実なのかも。街の様子を俯瞰した映像も奇妙に静かだが、それが静かであればあるほど重苦しい。
「ミン・アウン・フライン将軍くそったれ」と叫ぶ声がする。ミン・アウン・フラインもまた、定年5ヵ月前にクーデターを起こし、権力を奪って人民を殺し続けている輩たちの首魁だ。彼もまた寝首をかかれるかもしれないという恐怖に怯えているかも知れない。
「助けてください」とベランダから叫ぶ男性がいた。近所の人たちに、「フライパンと鍋を叩いて欲しい」と叫ぶ。これが民衆の抵抗方法だ。扉の前には「やつら」がいるからだ。明日、警察に出頭すると大声を出してももう遅い。家に向かって銃撃音が鳴り響きガラス瓶の割れるような音が続く。夕暮れの町にあかりが灯る中、懸命に鍋を叩いて抗議の意思を示す市民たち。本当に気の毒に思う。のんびり暮らしていたはずの、ごく普通の人間だ。ミャンマー軍や警察の非道にたえかねて、町で平和を訴えていた若者が、銃を手に取り革命軍の兵士へと姿を変えてゆく。これが内戦。市民の家の中のシーンでは、テレビでアメリカのソープオペラが流れていた。ミャンマーは決して北朝鮮のように情報が隔絶された社会ではないことに改めて気が付く。
しかし、そこにはカメラがいる
連行されようとする父親を守ろうと抵抗する市民。令状はあるのかと警官にかみつき、こんなことが許されるのかと泣きながら叫ぶひとたち。声を上げ続ける人たちには女性が多い。夫や父親はすでに連れていかれてしまったのかもしれない。連行された家族は帰って来るのだろうか。市民を装ったものたちによる石と鉄の棒による暴力と拘束も繰り返される。当局に雇われた私服の暴力団だと言う。自国の市民に手をかけるという意味ではロシアのマグネル以上に性質の悪い連中だ。しかしこうした異常な光景を、窓にはめられた鉄格子の陰に隠れて撮影し続けるジャーナリストがいることで我々も真実を知る。
この映画には、レニ・リーフェンシュタールの「オリンピア」や市川崑監督の「東京オリンピック」のような演出的な映像も多く含まれていた。本当の映像なのか?演出なのか?今ミャンマーで起きていることは現実なのか?悪い夢ではないのか?カオスの中に我々をいざなう。そして、映画はあきらめるなというメッセージを添えている。
なお、この映画は、興行収入から映画館配分や経費などを差し引いた併給収益を全て、ミャンマーの避難民支援を行う団体や施設に寄付をすることになっている。映画『ミャンマー・ダイアリーズ』は2023年8月5日(土)から東京のポレポレ東中野ほか全国で順次公開される。
監督・制作:ミャンマー・フィルム・コレクティブ(匿名のミャンマー人監督たちによる制作)
原題:Myanmar Diaries | 2022年 | オランダ ミャンマー ノルウェー | 70分 | ミャンマー語 |カラー | DCP | 5.1ch 配給:株式会社E.x.N
■公式サイト:www.myanmar-diaries.com
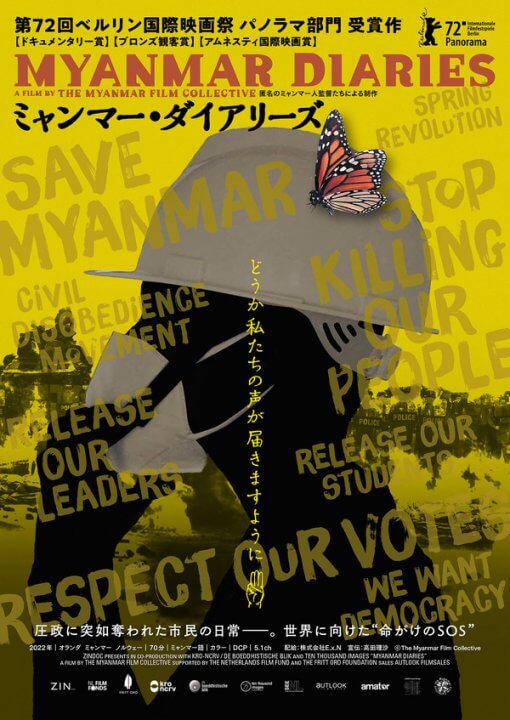
-
Profile
-
1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスク、2023年7月から解説委員。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか